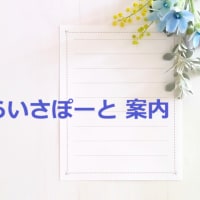小さい時はまだぼやっとした状態で特性自体はあまり目立たなかったように思える。
成長に連れ、家族や他の子どもとの接し方関わり方、
また玩具などへの独特な興味の示し方やぎこちない体の使い方などから、
親は何某らの不安を覚えるようになる。
言葉を発しない、あるいは語彙が広がらない、奇異な声を発する、オウム返し、大人のような話し方、
目が合わない、指差しをしない、まわりが見えていない、興味が偏っている、こだわり、癇癪、多動、
話しかけられることやスキンシップを嫌がる、まわりと共有共感ができないという、
いわゆる氷山の一角が際立つようになる。
次の段階として、子どもの状態を把握するために発達検査を受ける。
何らかの診断がつくと、今の状態が良くなるために何をすればよいのか、
できる限りの情報を探し、子どものために出来る限りのことをしようと親は務める。
その時点では、地域の子どもたちと同じように学校生活を送れるようになってほしいと望む。
それは子どもの将来を心配する親の心情として当然のことでもある。
診断から障害のある子どもだと、我が子の将来の成長をあきらめていいはずはない。
早期の療育で障害が軽減されるのではないか。
認知機能に働きかける学習指導を積み上げていくことで改善がなされるのではないか。
そのような療育は無いのか。
そのような学習支援を地域の教育環境で臨むことが、できないのか。
できないのなら、親が頑張るしかないではないか。
今の時代、検索すれば~学習支援の情報が山のように出てくる中で、
我が子の将来こうなってほしいと望む、
親の気持ちに沿えるような情報に簡単にたどり着くことができる。
そういう時代であるということを認識し、心地よい情報に惑わされてはいけません。