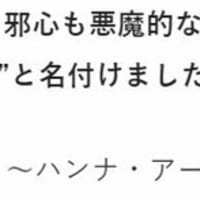「哲学者190人の死に方」という奇妙な本を読んでしまいました。
多くの哲学者が死について語っていることは有名です。 しかし、哲学者がどのように死んだのかを解説している本は、ほとんどありません。死に方として有名な哲学者もあまり多くはなく、裁判にかけられ自ら進んで毒杯を飲んだソクラテスの死、 梅毒で狂気のなかに死んだニーチェくらいしか個人的には知りません。「死」を見つめることで「生」をどのように考察するかについては、すべての哲学者が必ず通る道だと思うけれども、どのように死んだのかということにどれだけの意味があるのかよくわかりません。有名な哲学者たちが 非常に奇妙な死に方をしているのは、事実なのだろうが、一方で非常に多くの哲学者が普通の死に方、例えば、病死をしているというのは 当然のことだと思う。では、なぜ、哲学者の190人もの死に方を、この著者は、根気よく書き続けているのだろうか。<「死ぬことを学ぶこと」ーソクラテス> ここから、哲学が始まるという、だからこそ、「死」についての考察が重要であり、哲学者たちは皆、死を前にして苦悩し考えそして死んでいったのでしょう。しかし、その死に方は、一般の人々と同じ程度に、残酷で滑稽で悲しい。自殺を強要されるもの、自殺するもの、さらし首にされるもの、 梅毒やコレラ、ペストにより死んだもの、動物の糞で窒息死させられたもの、八つ裂きにされたものなど悲惨な例も多い。それでも、読み進んでしまう不思議な本になっている。
20世紀後半以降の哲学者たちの死を初めてこの本で読んだ。ミッシェルフーコー、メルローポンテ、ハンナアーレント、サルトル、ボーボワールなど。しかし、どのように死んだかより、死ぬまでに何をしたかの解説の方が面白かった。ある意味でこの本は哲学の辞書のようなものかもしれない。
<主夫の作る夕食>
コストコのチキンの残りで一品作った。腕が上がったかも!

<思い出の一枚>
受験の春まじか。冬期講習のがんばり。