日時:2月28日
映画館:バルト11
パンフレット:A4横版820円。
マカロニ・ウェスタンの生き神さまと言えば、エンニオ・モリコーネとクリント・イーストウッドである。
マカロニ野郎の半生はイーストウッドの映画人生と重なり、ガンマン人生の節目節目でイーストウッドの映画があったといってもあながち間違いではないだろう。だが、「イーストウッド主演作!」でロードショーされたのも遠い昔。今や、よくてミニシアター、しゃっくりのようにささやかに公開される監督作品。
そんなイーストウッドの最新戦争映画。アカデミー賞効果のおかげで、大規模公開になったのは何より。ストーリーについては、多くのところで語られているので、ここでは省略。
さて、個人的に考えるよく出来た戦争映画とは、戦闘シーンの迫力や出来映えもあるのだが、戦争という巨大なシステムの中で疲弊してあがく人間が描かれている映画だ。
それはお涙頂戴や非人道的で残酷な描写にあるのではなく、真面目で優秀な人間が、真面目で優秀であるがゆえに優れた兵士、殺人マシーンにもなれてしまうという恐ろしいジレンマが描かれているということだ。
この手の映画の話をする時に、必ず引き合いに出してしまうのが、ロシア・イタリア合作の戦争映画「レッド・ストーム/アフガン侵攻」。アフガニスタン撤収間際のソ連軍を描いた映画だが、主人公の小隊長(演じるはマカロニ・マフィアものにもよく出たミケーレ・プラシド)は部下思いで、何とか部下を無傷で故郷に返したいと思っている。
そのためには、通行の安全と引き換えに敵に武器を横流しすることも厭わないし、部下が民間人を誤殺すれば、犠牲者に手りゅう弾を持たせて「ゲリラだった」と言い切る。いざ戦闘となれば、鬼のように活躍してくれる素晴らしい兵士なのだ。その一方で従軍看護婦と関係を持ち、帰国後はウェイターになるのが夢。自分も周囲の人間も生かすには、非情にならなくてはいけない。そのギャップが生々しく、痛々しい。
本作の主人公、クリス・カイルもそんな人間だ。
元々、シールズでスナイパーになれるのは、技術も体力も精神力も信念もすば抜けた人間でなくてはならない。単純に兵隊=無知な人殺しではないのだ。(さらに言うならタイトルこそ「スナイパー」だが、映画では狙撃シーンより最前線で走り回っている方が多い。)
おそらく彼の活動の根源は「困って助けを求める人間がいて、自分が出来ることがあるなら、それをする。」ことなのだろう。別に戦場でなくても、世の中で必要とされ、隣りにいて欲しいのはしたり顔で状況を評するだけの人間ではなく、そんな人間なのだろうが、彼が選んだのは兵隊、しかもエリート中のエリートだった。
しかし、非情な命のやり取りは人間を擦り切らせていく。敵についても同じことが言えて、平時ならオリンピックに出場できる技術と精神力の持ち主が、その才能を全く別の方向で生かすことになる、この悲しさ。
イーストウッドの映画(「チェンジリング」とか「父親たちの星条旗」とか)って、何だか人間の運命を突き放したようなところがあって、悲しさとか痛みを声高に語るのではなく、いつものように淡々と映画は進んでいく。(それでも本作は珍しく、派手な戦闘シーンが多い。)
エンディングに向けて、彼は少しずつ普通の生活になじんでいく。そこが少し食い足りない部分でもあって、映画的には「ハートロッカー」のシリアル棚の前で立ちすくんだり、「大人になると大切なものは1つか2つしか残らない」みたいなぐっとくるところが欲しかった。
主人公を演じるブラッドリー・クーパーは元々線の細い印象があったが、本作では二周りデカくなっての熱演。(不思議なことにイーストウッド映画ではTVシリーズの脇役で活躍した俳優が、ちょこちょこと出てくる。ブラッドリー・クーパーも元々は「エイリアス」なんかに出ていたし、本作も「メンタリスト」のオーウェン・イオマンが顔を出す。)
さて、エンディングでの「続・荒野の1ドル銀貨」のFuneralの使用を初め、何かとマカロニ・ウエスタンとの関係が語られる本作。主人公の父親は「人間には3種類ある。」と名台詞を吐くし、なんと言っても伝説のガンマンが銃稼業からおさらばするのに、砂塵の中、去り行く車両に飛び乗って、ライフルだけが残されているなんて、「ミスター・ノーボディ」のまんまじゃないか。(←世の中のものがすべてマカロニに見える悪いクセ)
ところで、二人目の子どもが生まれたシーンはどうみても赤ちゃんが人形。それとなく指で動かすブラッドリー・クーパーが可笑しいのだが、そんなところが安いマカロニみたいでどうする。(笑)
映画館:バルト11
パンフレット:A4横版820円。
マカロニ・ウェスタンの生き神さまと言えば、エンニオ・モリコーネとクリント・イーストウッドである。
マカロニ野郎の半生はイーストウッドの映画人生と重なり、ガンマン人生の節目節目でイーストウッドの映画があったといってもあながち間違いではないだろう。だが、「イーストウッド主演作!」でロードショーされたのも遠い昔。今や、よくてミニシアター、しゃっくりのようにささやかに公開される監督作品。
そんなイーストウッドの最新戦争映画。アカデミー賞効果のおかげで、大規模公開になったのは何より。ストーリーについては、多くのところで語られているので、ここでは省略。
さて、個人的に考えるよく出来た戦争映画とは、戦闘シーンの迫力や出来映えもあるのだが、戦争という巨大なシステムの中で疲弊してあがく人間が描かれている映画だ。
それはお涙頂戴や非人道的で残酷な描写にあるのではなく、真面目で優秀な人間が、真面目で優秀であるがゆえに優れた兵士、殺人マシーンにもなれてしまうという恐ろしいジレンマが描かれているということだ。
この手の映画の話をする時に、必ず引き合いに出してしまうのが、ロシア・イタリア合作の戦争映画「レッド・ストーム/アフガン侵攻」。アフガニスタン撤収間際のソ連軍を描いた映画だが、主人公の小隊長(演じるはマカロニ・マフィアものにもよく出たミケーレ・プラシド)は部下思いで、何とか部下を無傷で故郷に返したいと思っている。
そのためには、通行の安全と引き換えに敵に武器を横流しすることも厭わないし、部下が民間人を誤殺すれば、犠牲者に手りゅう弾を持たせて「ゲリラだった」と言い切る。いざ戦闘となれば、鬼のように活躍してくれる素晴らしい兵士なのだ。その一方で従軍看護婦と関係を持ち、帰国後はウェイターになるのが夢。自分も周囲の人間も生かすには、非情にならなくてはいけない。そのギャップが生々しく、痛々しい。
本作の主人公、クリス・カイルもそんな人間だ。
元々、シールズでスナイパーになれるのは、技術も体力も精神力も信念もすば抜けた人間でなくてはならない。単純に兵隊=無知な人殺しではないのだ。(さらに言うならタイトルこそ「スナイパー」だが、映画では狙撃シーンより最前線で走り回っている方が多い。)
おそらく彼の活動の根源は「困って助けを求める人間がいて、自分が出来ることがあるなら、それをする。」ことなのだろう。別に戦場でなくても、世の中で必要とされ、隣りにいて欲しいのはしたり顔で状況を評するだけの人間ではなく、そんな人間なのだろうが、彼が選んだのは兵隊、しかもエリート中のエリートだった。
しかし、非情な命のやり取りは人間を擦り切らせていく。敵についても同じことが言えて、平時ならオリンピックに出場できる技術と精神力の持ち主が、その才能を全く別の方向で生かすことになる、この悲しさ。
イーストウッドの映画(「チェンジリング」とか「父親たちの星条旗」とか)って、何だか人間の運命を突き放したようなところがあって、悲しさとか痛みを声高に語るのではなく、いつものように淡々と映画は進んでいく。(それでも本作は珍しく、派手な戦闘シーンが多い。)
エンディングに向けて、彼は少しずつ普通の生活になじんでいく。そこが少し食い足りない部分でもあって、映画的には「ハートロッカー」のシリアル棚の前で立ちすくんだり、「大人になると大切なものは1つか2つしか残らない」みたいなぐっとくるところが欲しかった。
主人公を演じるブラッドリー・クーパーは元々線の細い印象があったが、本作では二周りデカくなっての熱演。(不思議なことにイーストウッド映画ではTVシリーズの脇役で活躍した俳優が、ちょこちょこと出てくる。ブラッドリー・クーパーも元々は「エイリアス」なんかに出ていたし、本作も「メンタリスト」のオーウェン・イオマンが顔を出す。)
さて、エンディングでの「続・荒野の1ドル銀貨」のFuneralの使用を初め、何かとマカロニ・ウエスタンとの関係が語られる本作。主人公の父親は「人間には3種類ある。」と名台詞を吐くし、なんと言っても伝説のガンマンが銃稼業からおさらばするのに、砂塵の中、去り行く車両に飛び乗って、ライフルだけが残されているなんて、「ミスター・ノーボディ」のまんまじゃないか。(←世の中のものがすべてマカロニに見える悪いクセ)
ところで、二人目の子どもが生まれたシーンはどうみても赤ちゃんが人形。それとなく指で動かすブラッドリー・クーパーが可笑しいのだが、そんなところが安いマカロニみたいでどうする。(笑)
| 題名:アメリカン・スナイパー 原題:American Sniper 監督:クリント・イーストウッド 出演:ブラッドリー・クーパー、シエナ・ミラー |











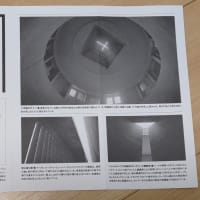














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます