遅くなりましたが、6月議会の報告をします。
6月議会で主に質問したのは原発が事故を起こした際の「避難計画」に実行性があるのか?という問題です。

島根県そして松江市をはじめとする周辺自治体は、島根原発が事故を起こした際の住民の安全を守るために「原発事故避難計画」を策定し、公表しています。また、その避難計画に基づいて、住民が実際に避難する際には、いったいどれくらいの時間がかかってしまうのかを推計した「原子力災害時の避難時間推計」が島根県によって公表されています。今議会では、果たして最悪の事態を想定しても住民の皆さんが被曝をすることなく安全に避難をすることができるのか、避難計画の実効性に関する質問を中心に行いました。
市長は、質問に対して正面から答えようとせず、最悪の事態を想定しても実効性があるかとの質問には「オオカミ少年」とまで言い、福島のような事故はあり得ないかのような答弁をしました。一方では、放射能拡散シミュレーションは必要であると強調していました。
6月議会での主な質問と答弁
★「原発事故避難計画」の実効性に関する質問と答弁(一部割愛)
芦原 他社の規制基準適合性審査書類においては、共通してほぼ1,5時間で圧力容器からの漏洩が始まると解析されている。島根でも同様と考えられるので、およそ2時間もすれば敷地外に漏洩する状態となる。
このような最悪の自体を想定した場合に、5km圏内住民は県の行ったシミュレーション(避難時間推計)通りに2,5時間で5km圏外に出ることができると考えるのか。
市長: どういう根拠に基づいて2時間後にはぱあっと広がってしまうといっているのか、オオカミ少年じゃないけど大変だと言うだけでは説得力がないのではないかと思っています。問題は、放射性物質がどういう形で、どういう方角にどういうスピードで拡散しているのかがある程度わかったうえで議論していく必要があります。今後、県だけでは難しいかもしれませんが、国に対してもそういう要請をやっていきたいと思っています。
芦原: オオカミ少年と言われてきましたが、推進してこられた方には、福島の事故は想定外の事態であったはずです。最初に「最悪の事態を想定しても、なおかつ実効性があるものでないとだめだという観点から質問させていただく」と言いました。中国電力の対策が機能しなかった場合には、短時間で放射性物質が漏れ出す事態になってしまう。その可能性を100%ないと断定することができないと思いますからお聞きしたわけです。
松江高専が福島原発事故後に避難指示から避難を開始するまでの時間について住民アンケートを行っています。だいたい59%の方が1時間から2時間かかると回答されています。事故が起きれば、ほとんどの市民は家族と連絡を取り合い、帰宅を急ぐと思われます。そうなると、そこから渋滞が始まると考える必要がありますから、この2.5時間で脱出だというシミュレーションをされても、非常に甘いと言えます。
30km圏内の住民については、原子力災害対策指針では、2時間で一般人の年間被爆上限の1mシーベルトを超えるほどの放射線量に達すると、数時間内に避難開始だという基準が示されている。
県が公表したシミュレーションでは、3時間40分から19時間15分待機させられた後に、5時間から8時間25分かかって30km圏外に出ることができると想定されている。これでは住民の被曝が避けられない。立地自治体として、このような計画をそのままにしておいていいのか。
市長: シビアアクシデントが出たときに、放射性物質がどういう形で拡散していくのか、やはり国の方としてもきちっと出していただく必要があるんじゃないかと思っています。それによって、住民が放射性物質にさらされるという議論が出てくると思います。
人間ですから、いったん事故が起こった場合にはパニックになると思うんです。そこは冷静に対応していただかないと、中心部の方々が逃げ遅れてしまうという事態があるわけです。放射能拡散シミュレーションが原点になると思います。
*全国原子力発電所立地自治体協議会は、原子力災害対策本部・原子力防災会議合同会議に対して、「UPZ(30km圏内)においては放射性物質の放出後に避難することになるので、低線量被曝について国が国民に説明すること」を求めています。立地自治体は、30km内住民が被曝をする可能性について認識済みです。
芦原: 豪雨などに伴う交通規制や自家用車避難ができなくなる市民が大量発生するなどの考慮がない。シミュレーションはかなりの不備があると思うが、どう考えるか。
防災安全部長: 今回のシミュレーションにつきましては、車両による避難を想定しておりますが、課題を検討する中で、必要があれば再度シミュレーションすることも県に働きかけていきたいと考えています。
6月議会で主に質問したのは原発が事故を起こした際の「避難計画」に実行性があるのか?という問題です。

島根県そして松江市をはじめとする周辺自治体は、島根原発が事故を起こした際の住民の安全を守るために「原発事故避難計画」を策定し、公表しています。また、その避難計画に基づいて、住民が実際に避難する際には、いったいどれくらいの時間がかかってしまうのかを推計した「原子力災害時の避難時間推計」が島根県によって公表されています。今議会では、果たして最悪の事態を想定しても住民の皆さんが被曝をすることなく安全に避難をすることができるのか、避難計画の実効性に関する質問を中心に行いました。
市長は、質問に対して正面から答えようとせず、最悪の事態を想定しても実効性があるかとの質問には「オオカミ少年」とまで言い、福島のような事故はあり得ないかのような答弁をしました。一方では、放射能拡散シミュレーションは必要であると強調していました。
6月議会での主な質問と答弁
★「原発事故避難計画」の実効性に関する質問と答弁(一部割愛)
芦原 他社の規制基準適合性審査書類においては、共通してほぼ1,5時間で圧力容器からの漏洩が始まると解析されている。島根でも同様と考えられるので、およそ2時間もすれば敷地外に漏洩する状態となる。
このような最悪の自体を想定した場合に、5km圏内住民は県の行ったシミュレーション(避難時間推計)通りに2,5時間で5km圏外に出ることができると考えるのか。
市長: どういう根拠に基づいて2時間後にはぱあっと広がってしまうといっているのか、オオカミ少年じゃないけど大変だと言うだけでは説得力がないのではないかと思っています。問題は、放射性物質がどういう形で、どういう方角にどういうスピードで拡散しているのかがある程度わかったうえで議論していく必要があります。今後、県だけでは難しいかもしれませんが、国に対してもそういう要請をやっていきたいと思っています。
芦原: オオカミ少年と言われてきましたが、推進してこられた方には、福島の事故は想定外の事態であったはずです。最初に「最悪の事態を想定しても、なおかつ実効性があるものでないとだめだという観点から質問させていただく」と言いました。中国電力の対策が機能しなかった場合には、短時間で放射性物質が漏れ出す事態になってしまう。その可能性を100%ないと断定することができないと思いますからお聞きしたわけです。
松江高専が福島原発事故後に避難指示から避難を開始するまでの時間について住民アンケートを行っています。だいたい59%の方が1時間から2時間かかると回答されています。事故が起きれば、ほとんどの市民は家族と連絡を取り合い、帰宅を急ぐと思われます。そうなると、そこから渋滞が始まると考える必要がありますから、この2.5時間で脱出だというシミュレーションをされても、非常に甘いと言えます。
30km圏内の住民については、原子力災害対策指針では、2時間で一般人の年間被爆上限の1mシーベルトを超えるほどの放射線量に達すると、数時間内に避難開始だという基準が示されている。
県が公表したシミュレーションでは、3時間40分から19時間15分待機させられた後に、5時間から8時間25分かかって30km圏外に出ることができると想定されている。これでは住民の被曝が避けられない。立地自治体として、このような計画をそのままにしておいていいのか。
市長: シビアアクシデントが出たときに、放射性物質がどういう形で拡散していくのか、やはり国の方としてもきちっと出していただく必要があるんじゃないかと思っています。それによって、住民が放射性物質にさらされるという議論が出てくると思います。
人間ですから、いったん事故が起こった場合にはパニックになると思うんです。そこは冷静に対応していただかないと、中心部の方々が逃げ遅れてしまうという事態があるわけです。放射能拡散シミュレーションが原点になると思います。
*全国原子力発電所立地自治体協議会は、原子力災害対策本部・原子力防災会議合同会議に対して、「UPZ(30km圏内)においては放射性物質の放出後に避難することになるので、低線量被曝について国が国民に説明すること」を求めています。立地自治体は、30km内住民が被曝をする可能性について認識済みです。
芦原: 豪雨などに伴う交通規制や自家用車避難ができなくなる市民が大量発生するなどの考慮がない。シミュレーションはかなりの不備があると思うが、どう考えるか。
防災安全部長: 今回のシミュレーションにつきましては、車両による避難を想定しておりますが、課題を検討する中で、必要があれば再度シミュレーションすることも県に働きかけていきたいと考えています。













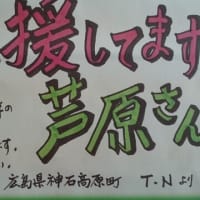
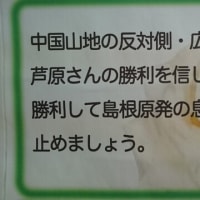
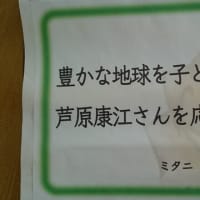
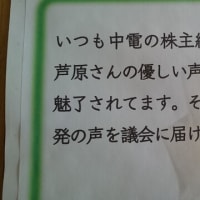
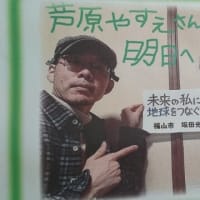


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます