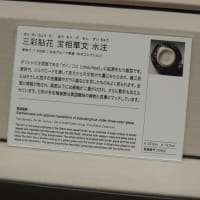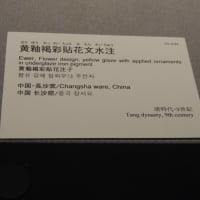「黒楽茶碗 道入」東京国立博物館蔵 1口 道入作 江戸時代・17世紀 高7.7 口径11.6 底径5.4 広田松繁氏寄贈





解説→「道入は樂家三代。ノンコウの俗称で知られ、後世歴代随一の名工とされています。新たな時代に応じた軽やかな装飾性を楽茶碗に取り込みました。薄く削られた口縁、たっぷりとした見込み、かっきりと削り出された高台、流下する光沢のある釉薬などに特色が表れています。 」
(解説高台写真 ColBaseから)
「江戸初期の陶工で、京都楽焼(らくやき)の第3代。吉兵衛(きちべえ)、のち吉左衛門(きちざえもん)、剃髪(ていはつ)後は道入と称す。俗称「のんこう(のんかう)」。初代長次郎の没後、2代目は田中家の宗慶(そうけい)の子、吉左衛門常慶(じょうけい)(1635没)が継ぎ、3代目は常慶の長男の吉兵衛道入が継いだ。「のんこう」の名は、千宗旦(せんのそうたん)が伊勢(いせ)参宮の途次鈴鹿(すずか)の能古(のんこ)茶屋に休み、そのとき付近の竹で花器をつくって「ノンカウ」と銘して道入に贈ったところ、道入がその後いつも花をいけて楽しんだことに由来するといわれる。
初代長次郎と2代常慶の作風が古格を重んじて半筒形茶碗(ちゃわん)に定形をつくりあげ、徹底して没個性の美を追求したのに対し、道入は一転して個性味豊かな作為をあからさまに求め、その達者な技巧で作為巧妙な茶碗をつくり新境地を開拓、楽家歴代中、屈指の名手といわれる。この背景には「綺麗(きれい)さび」を尊んだ時代の風潮と、天下の風流人本阿弥(ほんあみ)光悦との交流から得た個性美への傾斜があった可能性が濃い。その作行きは総体に薄造りで、胴はゆったりと張り、微妙に起伏する曲線が全体の基調となりながら、ところどころに鋭く篦(へら)を入れて緊張感を醸し出している。黒楽・赤楽とも釉(うわぐすり)は強い光沢をもち、白釉(はくゆう)と朱釉が表れて景色をつくる。明るいつややかな美を求める道入の造形精神は、光悦ほど個性に浸りきってはいないが、江戸初期の開放的な茶風をよく反映したものといえよう。高台(こうだい)はときに土見せで軽やかな趣(おもむき)に満ちており、「楽」の印が押される。代表作に、黒楽茶碗では銘「稲妻」「枡(ます)」「桔梗(ききょう)」、赤楽茶碗では「鵺(ぬえ)」「淡雪(あわゆき)」「巴(ともえ)」などがある。[矢部良明]
『林屋晴三編『日本陶磁全集 21 楽代々』(1976・中央公論社)』
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)」
「[生]天正2(1574)
[没]明暦2(1656).2.28. 京都
江戸時代初期の陶工。楽家 (→楽焼 ) の3世。初め吉兵衛,のち吉左衛門,異称「ノンコウ」で知られる。本阿弥光悦の推称を受け,楽家第1の名工とされた。きめ細かな土を用い薄手に仕上げた。楽焼の秘伝とされる朱釉や,口縁部から胴にかけて玉虫色の釉 (うわぐすり) を垂らす幕釉などを創始し,ノンコウ7種ほか多くの名物茶碗を制作した。 」(出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
[没]明暦2(1656).2.28. 京都
江戸時代初期の陶工。楽家 (→楽焼 ) の3世。初め吉兵衛,のち吉左衛門,異称「ノンコウ」で知られる。本阿弥光悦の推称を受け,楽家第1の名工とされた。きめ細かな土を用い薄手に仕上げた。楽焼の秘伝とされる朱釉や,口縁部から胴にかけて玉虫色の釉 (うわぐすり) を垂らす幕釉などを創始し,ノンコウ7種ほか多くの名物茶碗を制作した。 」(出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)