星の世界に魅せられてもう50年になろうとしています。一つの趣味で50年もの間、星を見続けて来ました。
様々な天文現象も体験してきましたが、まだ見たい現象は数多く控えています。メジャーな天文現象はそう毎日
あるものではありませんから、その空白の間を埋めるテーマが必要となってきます。晴れたら毎日できる観測が
変光星というテーマです。近くの比較星と比較して光度を出す単調な作業ながら、実際にやってみると結構癖になります。家の観測所で5センチの双眼鏡と20センチの反射望遠鏡を使い、12等星ぐらいまでの明るい変光星を観測してきました。変光星との付き合いは30年になりますが、延べにして目測数も40011目測に達しました。
飽きっぽい私が、30年も続けられたということも不思議といえば不思議です。何がそうさせたのかは変光星の魅力
でしょう。星も生きているという実感と、私もその星を見て生きていると共通のつながりが見えてきたからこそ継続できたのでしょう。明るさの変化がはっきりわかり予測のできるもの、またその逆で不規則に振るまうもの、
それから予測のできない増光を見せるもの、新星のように忽然と現れるものなど、夜空を眺めていて飽きさせない
体験のできる夜の時間を迎えられることが、1日の最大の至福の時です。
★ これまでの変光星観測の経過
・1989年 142目測
・1990年 264目測
・1991年 137目測
・1992年 1146目測
・1993年 3043目測
・1994年 1425目測
・1995年 854目測
・1996年 500目測
・1997年 524目測
・1998年 1578目測
・1999年 435+996目測(1999年8月までのカウント+以降12月まで集計)
・2000年 2107目測
・2001年 3024目測
・2002年 2650目測
・2003年 1146目測
・2004年 665目測
・2005年 576目測
・2006年 150目測
・2007年 1441目測
・2008年 3276目測
・2009年 2326目測
・2010年 2945目測
・2011年 1741目測
・2012年 415目測
・2013年 1051目測
・2014年 901目測
・2015年 1578目測
・2016年 347目測
・2017年 851目測
・2018年 381目測
・2019年 1378目測
注記)
※8月から開始したので、翌年の8月までを1年間としています。
但し、2000年からは1月より12月末までの合計です。
※総目測数 40011目測 (2019年12月04日現在で)
様々な天文現象も体験してきましたが、まだ見たい現象は数多く控えています。メジャーな天文現象はそう毎日
あるものではありませんから、その空白の間を埋めるテーマが必要となってきます。晴れたら毎日できる観測が
変光星というテーマです。近くの比較星と比較して光度を出す単調な作業ながら、実際にやってみると結構癖になります。家の観測所で5センチの双眼鏡と20センチの反射望遠鏡を使い、12等星ぐらいまでの明るい変光星を観測してきました。変光星との付き合いは30年になりますが、延べにして目測数も40011目測に達しました。
飽きっぽい私が、30年も続けられたということも不思議といえば不思議です。何がそうさせたのかは変光星の魅力
でしょう。星も生きているという実感と、私もその星を見て生きていると共通のつながりが見えてきたからこそ継続できたのでしょう。明るさの変化がはっきりわかり予測のできるもの、またその逆で不規則に振るまうもの、
それから予測のできない増光を見せるもの、新星のように忽然と現れるものなど、夜空を眺めていて飽きさせない
体験のできる夜の時間を迎えられることが、1日の最大の至福の時です。
★ これまでの変光星観測の経過
・1989年 142目測
・1990年 264目測
・1991年 137目測
・1992年 1146目測
・1993年 3043目測
・1994年 1425目測
・1995年 854目測
・1996年 500目測
・1997年 524目測
・1998年 1578目測
・1999年 435+996目測(1999年8月までのカウント+以降12月まで集計)
・2000年 2107目測
・2001年 3024目測
・2002年 2650目測
・2003年 1146目測
・2004年 665目測
・2005年 576目測
・2006年 150目測
・2007年 1441目測
・2008年 3276目測
・2009年 2326目測
・2010年 2945目測
・2011年 1741目測
・2012年 415目測
・2013年 1051目測
・2014年 901目測
・2015年 1578目測
・2016年 347目測
・2017年 851目測
・2018年 381目測
・2019年 1378目測
注記)
※8月から開始したので、翌年の8月までを1年間としています。
但し、2000年からは1月より12月末までの合計です。
※総目測数 40011目測 (2019年12月04日現在で)












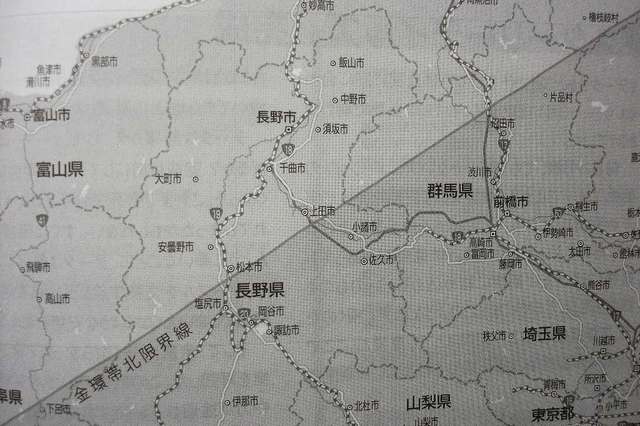
 いつも元気で明るい娘よ、4月から社会人としてがんばってや。父さんも昇格できたし、まだまだがんばるで。
いつも元気で明るい娘よ、4月から社会人としてがんばってや。父さんも昇格できたし、まだまだがんばるで。