宍道湖が気になった。
まず、おもったのは、
「しんじ」
これは、スピカを表している。
しなつ彦をしらべていくと
「しなつ星」=スピカということになり
「真珠星」とも呼ばれるが
福井、若狭地方では
「しんじ星」と呼ばれている。
で、単純に 宍道湖が、=スピカ=しなつ星=しなつ彦
と、考えられる「歴史的背景」に行きあたっていないので
宍道湖が
妙な隠し文字とも思われるので、先に調べてみる。
まず、通常に宍を「しん」と読むかどうか。
宍
発音
音読み
呉音 : ニク
漢音: ジク
訓読み
- しし、しん
しし【▽肉/×宍】
1 人のからだの肉。
2 猪・鹿などの食用肉。
そのほか
にく。み。しし。鳥や獣の切った肉。
身体。人間の身体。肌。
肉付く。肉がつく。
声。歌声。
にく。食用の肉。(日本固有)
にく。物の厚み。太さ。(日本固有)
**********
宍道は「ししみち」
これは、「しし」の身と血ということだろうか?
************
参照する言語?はいろいろあるが、
(ヘブライ語とか、中国語とか・・・)
万葉集などによくみられる
「隠し言葉」(刺す竹などにみられる)に準じて
「日本語」「音霊」「言霊?」の方向で考えてみることにした。
*************
まず、「しんじ」
単純に浮かぶのは 神示
宍道は、神を示しているんだよ。
と、いう仮定で考えてみる。
宍道湖を「しんじこ」と読ませるのは
大熊猫をジャイアント・パンダと読ませるのと
同じような使い方であろう。
宍道は「神を示す」ということになろうということで
これまた、単純に
「しし(肉)と身と血」が神の姿?
いや、「しし」を単純に「鹿・獅子」ととったほうがよいか?
鹿といえば、ナフタリ族 獅子といえばユダ族 (天皇家の中に主導的に入ったと思われる部族)
宍道とは、天皇の身と血・・ともとれる。
**********
宍道の起源(1) 宍道湖(しんじこ) : 蘇える出雲王朝 (exblog.jp)
奈良時代は、「入り海」と呼ばれていますが、中海も「入り海」です。
また出雲風土記(733年)では、ばくぜんと「入り海」と呼ぶ以外に、
野代川の河口付近を「野代の海」と呼ばれていました。
万葉集でも、中海の意宇川の河口付近を「飫宇(おう)の海」と呼ばれている
ところを見ると、宍道湖・中海というような固有名詞は当時はなかったように思われます。
市報松江5月号 (city.matsue.shimane.jp)
 女夫岩遺跡 |
今年は猪年ですので、猪にちなんだ指定文化財を今回紹介します。
天平(てんぴょう)5年(733年)に作られた古代の地誌である『出雲国風土記』の「宍道郷(ししぢのさと)」の条には「(省略)所造天下大神命(あめのしたつくらししおほかみのみこと)の追ひ給ひし猪(しし)の像(かた)、南の山に二つあり。(省略)猪(しし)を追ひし犬の像(かた)、(省略)其の形石(いし)となりて、猪と犬と異なることなし。今に至りても猶あり。故(かれ)、宍道(ししぢ)と云ふ。」(読み下し文・加藤義成『修訂出雲国風土記参究』より)と、「宍道」の地名由来が書かれています。
この『風土記』に記載されている猪像と犬像ではないかという巨石が、宍道町内にあります。
一つは、猪像ではないかとされている「女夫岩(めおといわ)遺跡」(県指定文化財(史跡))です。
この遺跡は山陰自動車道の予定地にありましたが、地元の住民や研究者からの強い要望により、そのまま保存され、山陰自動車道の女夫岩トンネルの上に今も鎮座しています。 もう一つは、猪像、犬像ではないかとされている「犬石猪石」(市指定文化財(史跡))です。
もう一つは、猪像、犬像ではないかとされている「犬石猪石」(市指定文化財(史跡))です。
石宮神社(いしみやじんじゃ)の鳥居の両側には大きな石があり、拝殿の後ろには来待石の柵で囲まれている石があります。この前者が「猪石(ししいし)」、後者が「犬石(いぬいし)」とされています。
ちなみに、江戸時代に、この「宍道」の地名が「宍道湖」の湖名由来となります。
**************
故(かれ)、宍道(ししぢ)と云ふ。
大国主命が犬を連れて猪狩りをした。 二匹の猪(しし)が逃げた猪(しし)の道、すなわち猪道(ししじ)が宍道(ししじ)となりやがて読み方が宍道(しんじ)になった。 これが宍道の地名の由来である。
***********
もうひとつ、考えていたことがある。
宍
と
穴
よく似ているので、調べてきた。
**********
穴
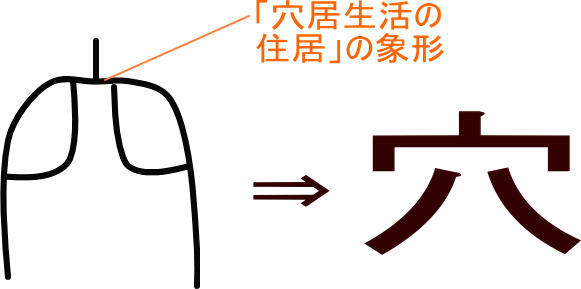 |
象形文字です。「穴居生活の住居」の象形から、「あな」を 意味する「穴」という漢字が成り立ちました。 |
|---|
穴の表す意味と
宍の表す意味がどうも違いすぎる。
*************
一方で、六は「獣」を表す・・・
(また、獣の数字かよ~~~)
*************
穴の意味は
①「あな」
ア:「むろ(物を保存、または育成のために、外気を防ぐように
作った部屋」、「つちむろ」
イ:「死体を土の中に埋める為の穴」
ウ:「地中にある、ある程度以上(普通は人間が入る事ができる
サイズ以上)の大きさの空間」(例:洞穴)
エ:「突き抜けている部分」(例:転んで、ズボンに穴があいた)
オ:「くぼみ」、「へこみ」
カ:「人体の急所(生命に関わる大事な部分)」
以下は、日本のみで用いられる意味
キ:「きず(欠点)」
ク:「損失(失う事)」、「財産や利益などを失う事」
ケ:「隠れ家」、「秘密」
コ:「思ってもいなかったもうけ」、「競馬などの
番狂わせ(予期せぬ出来事)」(例:大穴)
②「あなを開ける」、「あなを掘る」
************
ハは下に広がりがある穴
宍はそのハに「蓋」をして、閉じていると解釈できる。
あるいは、「墓標、墓、目印」をおいてある?
***********
つまり、
穴に「何か」をいれて?
蓋をしたので
宍になったということである。
八幡神=ヤハウェ=八=ハ・・・
と、とれば
ヤハウェに関わるなにかを「いれて」蓋(封印)したとも考えられる。
************
だが、封印してない状態を考えれば
「穴道湖」である。
「穴道」
道
1 人や車が通行する所。みち。
2 人として踏み行うべきみち。道理。特に、仏の教え。
3 道教。道教の教え
あなとうとも読み替えられる。
アナトーあるいはアナト
***********
アナト (‘nt [‘anatu]) は、ウガリット神話に登場する女神で、主神バアルの妹である。愛と戦いの女神であり、狩猟や豊穣の女神でもあると考えられている。
メソポタミア神話の愛と戦いの女神であるイナンナ/イシュタルと起源を同じくすると考えられており、また語源的にその名をイシュタルと同じくするアスタルトと同一視する説もある。 キプロスでは同じ戦いの女神であるアテーナ―(古代ギリシャ語: Ἀνάθ、Ἀθηνᾶ)と同一視されたという例もある。また、こうしたアナトの性質は、民間信仰における移行期、神々の権威が一時的に失墜する時の女性の役割を反映していると考えられている。
*********
ここまでは、こじつけ気味の話に、たまたま、アナトが重なっただけだと思っていた。
**********
ウガリット神話は、シリアの地中海岸にあった古代都市ウガリットに保存されていた粘土板文書に記されていた神話である。
内容は、同じセム系神話として旧約聖書などとも共通する物が多い。
特に重要視されているのは、英雄神バアルの戦いと死、そして再生を描いたものである。
**********
素戔嗚はスサ(国)の王ではなかろうか?
と、調べてきたところに1部分、重なるところがある。
確定できないので、保留しておいて、
古代出雲大社は、スピカを観測していたのではないか・・・
と、考えてみた。
で、どっちゃむきに立っていたのか
スピカの観測点になるかどうか
を、調べてきたが
おおむね、調べられると思う。と、いう言い方しかできない。
と、いうのも
スピカは秋分点の近くにある1等星であるため、しばしば歳差運動の観測に利用されてきた。古代ギリシャの天文学者ヒッパルコスはスピカの位置を観測することで初めて分点の歳差運動を発見した。テーベの神殿は紀元前3200年頃に建てられた時、スピカの方向を向いていた。時代を経るにつれてその歳差運動により、神殿の建設された頃の方位からスピカの方向が異なっていったのである。のちの時代の天文学者コペルニクスも、歳差運動の研究のために、手製の視差定規でスピカを何度も観測している。
スピカ自体が動いてしまう・・という事になる。
実際に、いつごろ建てられたものか。
正直、最初はスピカ観測をしていたとしたら
この建物を建てたのは、いつ頃なのかも判断がつかないが
後に、違う使われ方になったのかもしれない。
つまり、「大国主命の命が、立派な神殿を立ててくれ」
と、いう以前に、古代出雲大社がたっていたことがばれると
大和朝廷の前にちゃんと王朝・天皇?がいたのね。
大和朝廷って、侵略者なんだ・・・
と、いうことをかぎつけられるので
「大国主命が言った」ということにしたんじゃないか?
と、思ったりもするが・・・
しかし・・・わざわざ、大きな建物をたてないと
スピカが見えないとは思えない。
むしろ、何らかの目印だったか
宍道湖から見たらスピカと出雲大社を結ぶ線が直線になる時が
ドンピシャの方向をさしていたとか?
その逆方向になにがあるか
moriheikou.pdf (shimane.lg.jp)
島根の名山をみてきたが・・・
仮に南西方向(7月ごろのスピカ)に出雲大社がみえる山
かつ、宍道湖を通るというパターンになると
山頂に上がって、出雲大社がみえるかどうか・・・
これも保留********
実際、出雲大社は何のために作られたのか?
大国主命を幽閉するため(飛騨口碑)
飛騨王朝が建てた・・・とか。
幽閉される大国主命が自ら願い出たような風であるが・・・
それだけのために、建てるだろうか?
もうしわけない言い方だが
大国主命がそれほどに、優遇?される「うしろ」が見えない。
すると、むしろ、惨殺されたとか、処刑されたとか
その怨念封じであるなら、判らないでもないが・・・
と、いうか、大国主命自体が呪詛したのならば・・だが。
ー人食いを許した罪とあちこちの(部族?)の女を誑し込み
181人の子供がいた。など・・・
正妻をすておいて、腹違いの妹(すせり姫)と駆け落ちしたとか・・・ー
が、奇妙に思ったのが
181人をー八ーと、漢字で書いていたこと。
ハはヤハウェをまつる秦氏を暗示しているかのようである。
********
大国主命は、どこからやってきたのか?
八十神の末弟になっていたのが、因幡の白兎。
改めてウィキ(以前とは違う事が書かれている)
『古事記』・『日本書紀』の異伝や『新撰姓氏録』によると、須佐之男命(すさのおのみこと)の六世の孫、また『日本書紀』の別の一書には七世の孫などとされている。父は天之冬衣神(あめのふゆきぬのかみ)、母は刺国若比売(さしくにわかひめ)。また『日本書紀』正伝によると素戔鳴尊(すさのおのみこと)の息子。日本国を創った神とされている。
須佐之男命の娘である須勢理毘売命(すせりびめのみこと)との婚姻の後にスクナビコナと協力して天下を経営し、禁厭(まじない)、医薬などの道を教え、大物主神(おおものぬしかみ)を祀ることによって葦原中国(あしはらのなかつくに)の国作りを完成させる。だが、高天原(たかあまのはら)からの天照大御神(あまてらすおおみかみ)の使者に国譲りを要請され、対話と武力を交えた交渉の末に幽冥界の主、幽事の主宰者となった。国譲りの際にかつて須佐之男命から賜って建立した「富足る天の御巣の如き」大きな宮殿(出雲大社)を修復してほしいと条件を出したことに天津神(あまつかみ)が同意したことにより、このときの名を杵築大神(きづきのおおかみ)ともいう。
大国主神を扱った話として、因幡の白兎の話、根の国訪問の話、沼河比売への妻問いの話が『古事記』に、国作り、国譲り等の神話が『古事記』と『日本書紀』に記載されている(但し、『日本書紀』では「大国主神」という神名ではない)。『出雲国風土記』においても多くの説話に登場し、例えば意宇郡母里郷(現在の島根県安来市)の条には「越八口」を大穴持命が平定し、その帰りに国譲りの宣言をしたという説話がある。 また山陰、四国、近畿、三遠信、北陸、関東など広範囲における地方伝承にも度々登場する。
*********
素戔嗚が建てた・・・とすることで、
飛騨王朝を消し去ったともとれる。
が、スサノオ(出雲王朝は25代と聞く)がたてたのなら、
別の目的があったと思われるので
もう一度、出雲大社に戻る。
きになったのが、復元図の設計の時にひかれていた線がピラミッドにみえたこと。
そこで、出雲大社―ピラミッドでググる。
***********
矢口壹琅 の ONE LOVE:ギザの大ピラミッドと出雲大社の不思議な一致 - livedoor Blog(ブログ)
上古代の大社本殿の復元図を最初に見た瞬間から
『あれ?』っと思った。
なんかに似ている。。。
みたことあるな。。。
そして、あるとき、
その何かに気付いてしまった。
エジプト、ギザにある大ピラミッドの内部にある大回廊と、それは、とてもよく似てるのである。
重力拡散の間の作りが大社の本殿(屋根まである)。そして大回廊が本殿へと続く長い回廊。。。
調べた結果、
なんと!
実は、大ピラミッドの王の間と大回廊の構造は、古代の出雲大社の神殿の大きさや高さ、それに至る回廊と、
古代出雲大社の本殿の高さと、大ピラミッドの玄室及び重力拡散の間の高さが
同じである!という事実。
しかも、玄室へ続く大回廊の長さと角度が、出雲大社の本殿へ続く長い階段と同じなのである。
これは、どう考えてもあきらかに、大ピラミッド建造にかかわった建築士が、日本まで来たか、
あるいは、その逆、日本の出雲大社を作った人々が、エジプトに行ってピラミッドを作ったか。のどちらかしかない。
実は、エジプトにはピラミッド建造について、古くから言い伝えが残っている。
それは、紀元前300年ごろ実在した神官マネトが残したとされる記録で、こんな一節があったという。
「不思議な方法によって、東方から訪れた高貴な人々が、エジプトにピラミッドを残して去っていった」
いまだ、建造方法や目的が謎に包まれているギザの三大ピラミッドを建設したのは、古代エジプト人ではなく、東方からやってきた人々であるというのだ。
そして、スフィンクスが顔を向ける真東の遥か延長線上に、日本がある。。。
古代の歴史浪漫というか、超古代には不思議な話がいっぱいあって、
それはなんだか隠された真実と繋がってる気がするんだよね。
**********
ウガヤフキアエズ王朝実在論さまの記事の中では、
前方後円墳は
死者が「星」に帰るための「船?」の滑走路(ワープ?)で
帰る星の方向を向いている。
(なので、いろんな星の方向になっている)
************
やはり、しんじ(湖)ーしんじ(星)ーしなつ(星)ースピカ
を、目指すようなルート(滑走ルート?)があったのだろうか?
島根の36名山のなかにも、
「星を見るための山」
「修験道?の山-スサノオの足跡在り}
などもある。
もしかすると、出雲大社が見える見えないは関係ないかもしれない。
但し、宍道湖が、「ししじ湖」から「しんじ湖」となったのは、
もっと、あとのことのようなので、
無関係と考えるべきかもしれない。
ただ、宍道湖の名前の由来と石宮神社
別途、考えさせられる。
天平五年(七三三年)に記された古代出雲の地誌「出雲国風土記」には、宍道町の地名の由来となった犬石、猪石の物語が取り上げてあります。
これを現代ふうにすると、「出雲の国の治めておられた大穴持命(大国主命)が犬を使って猪狩りをされました。
この追われていた二匹の猪と犬は石となって今も南の山に残っている。この故事より(猪のとおった道と言う意味から)この地域を猪の道=宍道(ししじ)と呼ぶようになりました。」というものです。
鳥居の両側に巨石を猪石に、神社拝殿後ろの石(ご神体)を犬石にあてる説があります。
また猪石については他に女夫岩(宍道町白石)をあてる説もあります。
ーなんで、石になるーという素朴な疑問。
で、なんで、その(犬)石をご神体にしている?
ま、これも、星座関係?
ーシリウスー
おおいぬ座(大犬座)は、 猟犬 の姿を表した星座です。冬の夜空で、ひときわ青白く輝く星、おおいぬの口元にある α 星シリウスは、古代には神としてもあがめられました。
ー南斗六星ー
いて座(射手座)は、半人半馬のケンタウルス族が弓を引く姿を表した、夏を代表する星座の1つです。6つの明るい星がひしゃくの形に並んだ南斗六星が目印です。
ーいのしし座ー
ケンタウルス座 ( ケンタウルスざ 、 ( ラテン語: Centaurus)は、トレミーの48星座の1つ。 ... 紀元前3千年紀後半にはイノシシ (the Wild Boar) に変化した。
獅子座ー猪は獅子座?
α星は、全天21の1等星の1つであり、レグルスと呼ばれる。β星のデネボラが、うしかい座のα星アークトゥルス、おとめ座のα星スピカと形作る三角形は春の大三角と呼ばれる[1]。λ、ε、μ、ζ、γ、η、レグルスを繋ぐことでできる特徴的な「?」形を裏返した星の並びを、「ししの大鎌」と呼ぶ[2]。日本ではこれを「樋掛け星(といかけぼし)」と呼ぶ地方がある。
********
結局、結論が出ないまま終わる・・・


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます