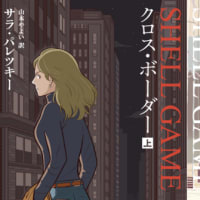小さな村で起きた凄惨な殺人事件。
小さな村で起きた凄惨な殺人事件。いったいどうして?
なぜこんな殺され方をしないといけないのか?
そういう疑問を突きつけられ、
懸命に捜査に乗り出すイースタ警察署の刑事たち。
時は1990年の年明け。
スウェーデンのバルト海に面した港町の冬のできごと。
 ブルガリアの友人が送ってくれたマリア・カラスのオペラを
ブルガリアの友人が送ってくれたマリア・カラスのオペラを 深夜まで聴いてベッドに入ったクルト・ヴァランダーは、
明け方に警察署からの電話でたたき起こされた。
ちょうど、褐色の肌の女との強烈にエロチックな夢を見ていたときだ。
シャワーも浴びずに着替えて家を出た。
ヴァランダーは妻が出て行ったことで苦しんでいる。
クリスマスの2日前に離婚手続きの書類が郵送されてきたばかり。
「死ぬのも生きることのうち」
これはヴァランダーの箴言。
生まれ故郷のマルメの町で、まだ若い警官だったときに
ナイフで心臓のすぐ側を刺され
死にかけたエピソードが さりげなく挟まれる。
 こうして本の冒頭の10ページのなかに、
こうして本の冒頭の10ページのなかに、 読者を後に引けない気分にさせる要素が
これでもかと詰め込まれる。
もう読み進むしかない。
 凄腕の作家ヘニング・マンケルが描いた警察小説。
凄腕の作家ヘニング・マンケルが描いた警察小説。 捜査は二転三転する。
警察署長はスペインで休暇中。
ヴァランダーは署長代理を務めており、
記者会見を開く立場。 テレビのインタビューも受ける。
そのヴァランダーを中心に
イースタ警察署の刑事たちがチームで動いているところがいい。
誰もが役割を与えられ、
その任務を忠実にこなしていく。
 泥臭いアクション。
泥臭いアクション。 同時進行の事件の犯人をみつけ追跡中。
建物の入り口で体を伏せたとたんに、
石の階段に頭をぶつけ、
ひたいのこぶが裂けて血が流れだす。
そのこぶはイースタの移民逗留所の火事から
人を助け出すために奮闘したとき
できたものだったのだけど。
そして、足場を上って犯人を確認したのだが、
引き返そうとしたときに高い足場から落下した。
すんでのところで足が足場の板と板のあいだに挟まり 逆さ吊りに。
そうでなければ死んでいたのだから、助かったのだけど…
でも、足一本で逆さづりだよ。
なんかダサい気も少し…。
けれどすごい。
その状態からなんとか脱出したが、
場面描写があまりに真に迫っていて、
大変そうで、気の毒でもあり…
なんか、口元が笑っちゃいそうで共感が膨れ上がるのだ。
同じイースタ署のガンで死にかけている
老刑事 リードベリとの交流は心にしみる。
リードベリは捜査を正しい方向に導く優れものの刑事。
ひとり暮らしのリューマチ持ち。
ヴァランダーはしばしば夜にリードベリの家を訪ね、
薄暗いベランダでウィスキーを飲みながら
捜査について話しこむ。
そのリードベリと語り合うシーンは秀逸!
 人生を余すところなく描き切ろうとする著者の気迫が
人生を余すところなく描き切ろうとする著者の気迫が
透徹した雰囲気を作り出し、
読者の心をさりげなくわしづかみにする。