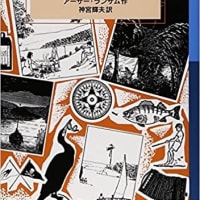●ツバメ号・ウォーカー兄弟のモデルとなった5人兄弟の父親は、「ランサムのツバメ号シリーズが生まれたのは、一部分は自分の手柄だ」と主張できるか?
 そもそも『アーサー・ランサムの生涯』(ヒュー・ブローガン著・筑摩書房)という評伝を読むまで、ウォーカー兄弟にモデルがいたことを知らなかった。
そもそも『アーサー・ランサムの生涯』(ヒュー・ブローガン著・筑摩書房)という評伝を読むまで、ウォーカー兄弟にモデルがいたことを知らなかった。
自伝の中ではツバメ号シリーズについてはほとんど語られていないし、『ツバメ号とアマゾン号』の前書きやあとがきにも、そういう記述はない。
『不思議の国のアリス』が実在の少女アリスに触発されたように、『くまのプーさん』のクリストファー・ロビンは、作者A・A・ミルン自身の息子がモデルであるように、ツバメ号の子どもたちにモデルがいた。
それなら、もっと有名な話となってもよさそうなものだ。
しかし、イギリスではともかく、日本ではその話は、あまり知られていない。
評伝から察するに、ランサムがモデルの件に関して、だんだん頑なな態度をとるようになったのが、原因と思われる。 ウォーカー兄弟のモデルとされているのは、ランサムが青年時代から家族同様に親しみ、豊かな愛情の恩恵にあずかったコリングウッド家の、娘ドーラの子どもたちである。
ウォーカー兄弟のモデルとされているのは、ランサムが青年時代から家族同様に親しみ、豊かな愛情の恩恵にあずかったコリングウッド家の、娘ドーラの子どもたちである。
「1928年4月、アルツンヤン夫妻、アーネストとドーラが、長期滞在のために、シリアからもどって、レインヘッドの下手のバンク・グランド農場に落ち着いた。夫妻には5人の子どもがいた。タクィ、スージー、メイヴィス(ティティでとおっている)、ロジャ、ブリジッドである。
一家は、ふだん、アーネストと父親が病院を経営しているアレッポに住んでいるのだか、数年ごとにコニストンを訪ねていた。…」
このとき、アルツンヤンとランサムが半額ずつ出し合って、ディンキー2隻を購入した。2隻は「メイヴィス号」「ツバメ号」と命名された。ランサムはその夏、子どもたちとディンキーのレースをしたり、ピール島まで帆走し、ピクニックをして食事をするなど、愉快に過ごした。
秋がきて、冬となり、翌年の1929年1月、アルツンヤン一家がシリアに戻るときがきた。子どもたちランサムの家にやってきて、たまたまランサムの誕生日が昨日だったこともあり、「とてもきれいなトルコ製のスリッパ」をプレゼントする。
その行為に心から喜んだランサムの頭に、「…ツバメ号の本を書こう。そうすれば、子どもたちははるか離れた砂漠とラクダと蚊の国にいてもそれが読める、という着想が浮かんだ」(伝記)
つづく3月24日、ランサムはこの年はじめてツバメ号をウィンダミア湖に浮かべ、なぎの中をセーリングしながら思索にふけった。そして
「彼は、アルツンヤンの子どもたちとツバメ号で走ったときのことを思い出した。ドーラやアーネストとはじめて知り合ったときのことも思い出した。そうだ、ピール島でキャンプ地をつくってお茶をわかしたことがあったな。それから、あの赤い帽子の二人の女の子。『家に帰り着く前に、頭の中では、物語のはじまりの部分ができていた。そこで、私は、紙を1枚とると、できごとのいくつかを書きはじめた』…」(評伝『』中はランサムの言葉) 「ツバメ号」の書きはじめについて、ランサムは次のように語っている。
「ツバメ号」の書きはじめについて、ランサムは次のように語っている。
「私は、(釣りとセーリング以外)ほかになにをする気にもなれず、古い納屋の二階に逃げ込んでいた。(雨防ぎにセメントで穴をふさいだため、フクロウたちを追い出してしまったのだが、彼らはいちばん大きなイチイの木にまで引越ししただけなのでほっとした。そして、一羽は夜になると鳴いて、作品づくりに貢献してくれた)。
古い納屋の二階で、私はいつも、なにがどんなふうにおこるのかと思案していた。そして、書いていると、さまざまなことが紙上にひょいひょいとあらわれてくるので、私がほかの人たちのために物語を書いているのではなく、だれかが私に物語をきかせてくれるような気がして、立ち上がって部屋を歩きまわりながらくすくす笑うのだった」
ランサムは子どもの頃から、コニストン湖や湖沼地方に思い出を積み重ねてきた。つねに心を解き放たれ、癒される場所でもあった。
その地を舞台に、文学で生きようと志した17歳のころから念願だった子どもの物語を書きはじめたのだ。
ツバメ号のシリーズは、国際的に人気を博す大ヒットシリーズとなった。 さて、そこで父親のアルツンヤンの名前が上がってくる。
さて、そこで父親のアルツンヤンの名前が上がってくる。
1961年ごろ、ランサムは「アーネスト・アルツンヤンが『ツバメ号とアマゾン号』誕生に果した自分の役割を過大に言い立てていると信じこんだ」。
1962年にアルツンヤンは亡くなったのだが、「タイムズ」の死亡記事が、ランサムには問題だった。
「それには、アーネストの子供たちがツバメ号の4人のモデルだとあり、アーサーの疑いの目には、だからランサム・シリーズの名誉のいくぶんかは、子どもたちの父親のものだと述べてあるようにすら写った」(評伝) どうでもいいじゃない、と言いたくなるが、ランサムは自分が描いた、自分と緊密に結びついた物語の中の子どもたちと、現実のアルツンヤンの子どもたちは、まったく別の存在だと認識していた。
どうでもいいじゃない、と言いたくなるが、ランサムは自分が描いた、自分と緊密に結びついた物語の中の子どもたちと、現実のアルツンヤンの子どもたちは、まったく別の存在だと認識していた。
想像のなかの物事というのは、現実とは違うのだ。イメージの中に存在するだけである。
イメージと現実。その仕組み、境界線が曖昧なため、人は翻弄される。
モデルはモデルであっても、登場人物とイコールではまったくない。言わばまったくの他人である。そのズレをちゃんと認識しないと、混乱が生まれる。 そして、アルツンヤン氏。
そして、アルツンヤン氏。
いいじゃないか、自慢ぐらいしても。自分の子どもがツバメ号が生まれるきっかけとなったのだ。すばらしい物語である。シリーズの中には“本を読む喜び”が散りばめられている。
ランサムにとっては、当然のようにツバメ号シリーズが主だけれど、アルツンヤン自身の人生にとっては、自分と自分の子どもが「主役」で、ランサムやツバメ号シリーズは、あくまで「脇役」でしかない。
どんなにツバメ号のシリーズの存在が大きくても、その図式には変わりがない。
だから、アルツンヤンは、自分の子どもたちがモデルになったことを大いに自慢していい。
ランサムは、むしろ、自慢に思ってくれたことについて、喜ぶべきである。
喜べないにしても、自分の書いた物語が、そんなことくらいどうってことないほど、素敵な物語であることを自覚し、その物語を生み出した自分を誇りに思えばいい。 いずれにしても、読者にはどうでもいいことである。読者が知り合いになるのは、アルツンヤンの子どもたちではなく、物語の中の子どもたちなのだから。
いずれにしても、読者にはどうでもいいことである。読者が知り合いになるのは、アルツンヤンの子どもたちではなく、物語の中の子どもたちなのだから。
モデルがいたというのなら、現実との接点が見えて、物語の世界が膨らむだけのことである。
最近の「アーサー・ランサム」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ジブリノート(2)
- ハル文庫(100)
- 三津田さん(42)
- ロビンソン・クルーソー新聞(28)
- ミステリー(49)
- 物語の缶詰め(88)
- 鈴木ショウの物語眼鏡(21)
- 『赤毛のアン』のキーワードBOOK(10)
- 上橋菜穂子の世界(16)
- 森について(5)
- よかったら暇つぶしに(5)
- 星の王子さま&サン=テグジュペリ(8)
- 物語とは?──物語論(20)
- キャロル・オコンネル(8)
- MOSHIMO(5)
- 『秘密の花園』&バーネット(9)
- サラモード(189)
- メアリー・ポピンズの神話(12)
- ムーミン(8)
- クリスマス・ブック(13)
- 芝居は楽しい(27)
- 最近みた映画・ドラマ(27)
- 宝島(6)
- 猫の話(31)
- 赤毛のアンへの誘い(48)
- 年中行事 by井垣利英年中行事学(27)
- アーサー・ランサム(21)
- 小澤俊夫 昔話へのご招待(3)
- 若草物語☆オルコット(8)
バックナンバー
人気記事