自然栽培米田んぼ。
いよいよ種籾の準備も始まりました♪
まずは種籾の『泥水処理』です。
種籾を病気から守る目的で行います。
一般的には農薬での消毒をしますが、私の自然栽培米作りでは農薬は使用しません。
農薬を使用しない場合、温湯消毒という方法も有ります。
これは種籾をお湯に一定時間浸けて、熱で病原菌を殺菌するという方法です。
私も以前はこの方法をやっていましたが、なかなか手間が掛かるのでやめました。
泥水処理は本で見つけた方法を参考に行っています。
田んぼの土で泥水を作りその中に種籾を浸けて、土の中の微生物の働きで種籾を病原菌から守るという理屈です。
それでは作業の様子です!
まず、自然栽培米田んぼに行って土を取ってきます。
田んぼの畦にはタンポポが咲き始めていました♪


まず、田んぼの表層の土を削り取ります。
表層には植物残渣や種が多いので。

土を掘っていきます。

だいたいこのくらいですかね。

土と水を混ぜて泥水を作ります。
少しずつバケツで砕いて混ぜながら桶に移します。


泥水が出来たらしばらく置いておきます。
すると草の種やゴミが浮いてくるので、すくい取ります。


種籾を催芽機並べて入れ、泥水を入れていきます。
私は魚の水替えポンプを利用しています。



催芽機は『浸種モード』で20℃に設定し、一日循環させます。


20℃で循環させるところも、この温度で良いのかまだはっきりわかりません。
本で読んだものを参考にそのままやっています。
泥水処理をやり始めた最初の頃は温度はかけず冷たい水で行っていましたが、その頃に比べると結果が良い感じがします。
翌日、
種籾の泥を洗い流し、浸種開始します。
この後6日程水に浸けて十分に水分を吸わせて、その後30℃ほどの温度の水に一日浸けて芽を出させます!
泥水処理。
実際に泥水が効果を発揮しているのかは正直なところ不明です。
以前に実験で、無消毒、温湯消毒、泥水処理の3種類を比較しましたが、結果、病気の発生はばか苗病が多少見られた程度でどれもほぼ無かったです。
病気の予防と言うよりは、種の内から田んぼの微生物と触れ合う事で早く共生関係が生まれるのではないかという目的で行っております。
無消毒で全然病気が出ないという方も居るようなので、何もしなくても良いかもですね。
やらなければならない事。やった方が良い事。やらなくても良い事。やらない方が良い事。
まだまだ研究!!
それではまた☆
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
「無農薬・無肥料 自然栽培米」栽培の様子をまとめましたのでどうぞご覧くださいm(__)m
2022(令和4年)
2021(令和3年)
2020(令和2年)
2019年度(平成31年・令和元年)
2018年度(平成30年)
2017年度(平成29年)
2016年度(平成28年)
2015年度(平成27年)
2014年度(平成26年)
2013年度(平成25年)
2012年度(平成24年)
いよいよ種籾の準備も始まりました♪
まずは種籾の『泥水処理』です。
種籾を病気から守る目的で行います。
一般的には農薬での消毒をしますが、私の自然栽培米作りでは農薬は使用しません。
農薬を使用しない場合、温湯消毒という方法も有ります。
これは種籾をお湯に一定時間浸けて、熱で病原菌を殺菌するという方法です。
私も以前はこの方法をやっていましたが、なかなか手間が掛かるのでやめました。
泥水処理は本で見つけた方法を参考に行っています。
田んぼの土で泥水を作りその中に種籾を浸けて、土の中の微生物の働きで種籾を病原菌から守るという理屈です。
それでは作業の様子です!
まず、自然栽培米田んぼに行って土を取ってきます。
田んぼの畦にはタンポポが咲き始めていました♪


まず、田んぼの表層の土を削り取ります。
表層には植物残渣や種が多いので。

土を掘っていきます。

だいたいこのくらいですかね。

土と水を混ぜて泥水を作ります。
少しずつバケツで砕いて混ぜながら桶に移します。


泥水が出来たらしばらく置いておきます。
すると草の種やゴミが浮いてくるので、すくい取ります。


種籾を催芽機並べて入れ、泥水を入れていきます。
私は魚の水替えポンプを利用しています。



催芽機は『浸種モード』で20℃に設定し、一日循環させます。


20℃で循環させるところも、この温度で良いのかまだはっきりわかりません。
本で読んだものを参考にそのままやっています。
泥水処理をやり始めた最初の頃は温度はかけず冷たい水で行っていましたが、その頃に比べると結果が良い感じがします。
翌日、
種籾の泥を洗い流し、浸種開始します。
この後6日程水に浸けて十分に水分を吸わせて、その後30℃ほどの温度の水に一日浸けて芽を出させます!
泥水処理。
実際に泥水が効果を発揮しているのかは正直なところ不明です。
以前に実験で、無消毒、温湯消毒、泥水処理の3種類を比較しましたが、結果、病気の発生はばか苗病が多少見られた程度でどれもほぼ無かったです。
病気の予防と言うよりは、種の内から田んぼの微生物と触れ合う事で早く共生関係が生まれるのではないかという目的で行っております。
無消毒で全然病気が出ないという方も居るようなので、何もしなくても良いかもですね。
やらなければならない事。やった方が良い事。やらなくても良い事。やらない方が良い事。
まだまだ研究!!
それではまた☆
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
「無農薬・無肥料 自然栽培米」栽培の様子をまとめましたのでどうぞご覧くださいm(__)m
2022(令和4年)
2021(令和3年)
2020(令和2年)
2019年度(平成31年・令和元年)
2018年度(平成30年)
2017年度(平成29年)
2016年度(平成28年)
2015年度(平成27年)
2014年度(平成26年)
2013年度(平成25年)
2012年度(平成24年)











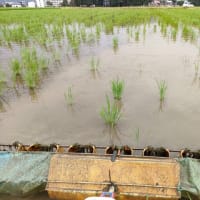








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます