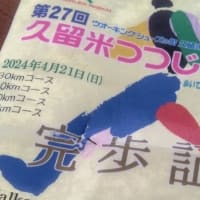久留米地方は、薄っすらと雪に覆われる朝を迎えた。
私はと言えば、相も変わらず、高良山へ山ジョグに向かう。
だがしかし、
途中で、コロッと気が変わる。
高良川沿いから、筑後川河川敷の適当な所までのジョギングに切り替えた。
だって、見上げると高良山は真っ白なんだもん。
寒そうじゃないか。

タッタッタッタ
あと少しで筑後川河川敷という場所まで来ると、所謂『ハコモノ』がある。
これが、筑後川をテーマにしたものである事は、薄々聞いている。
15年以上前からあった筈だが、未だに訪れた事は無い。
ふーん。
またしても、コロッと気が変わった。
定見の無さが、我ながら半端ではない。
どうしようか。
覗いてみるか。
これだから暇人は恐ろしい。

なんですと⁉️
無料ですと!
ジョギング中止決定。

無人の受付を通り、中に入る。
ガラーン
何しろ、動くものは私一人である。
おずおずと先に進む。
先ずは、筑後川の歴史についてのパネル展示である。
結構興味を引くものも展示されている。
有明海海岸線の年代ごとの変化や、アオ取水のパネル展示などは、特に興味深い。
どちらも、九州の古代史を紐解く場合、重要な鍵となるものだ。
もっと研究されてしかるべきなのだが。
長くなるので止める。

『筑後川は、徳川幕府の防衛上の政策として、橋は無く、瀬渡し船があるのみでした』
と、ある。
でも、その事より、日田から有明海までの、輸送の大動脈であり続けた事が、その事の大きな原因である。
巨大な材木を積んだ筏が、行き来していたのだ。
橋など作れるはずがない。
聞くところによると、河口の大川はたいそう羽振りが良く、筏人夫専門の女郎屋まであったらしい。
大正時代になってようやく、こんな粗末な橋がかけられたことが分かる。

パネルコーナーの他には、筑後川に住む淡水魚を集めたミニ水族館もある。
赤い上着を着たお姉さんは、ここの職員である。
ここまで来て、ようやく動いているものに出会う。

これはあの向井千秋さんが、宇宙で孵化させたメダカの子孫との事。
久留米人だって、だーれも知らんぞ!
宝の持ち腐れとは、この事である。

私には元々、淡水魚飼育の趣味がある。
こういうアクアリウムやテラリウムを見ると、今でも胸がときめく。
自宅と会社には、熱帯魚水槽を置いてたし、展示場に池を作って、メダカやタナゴを飼育していた。

この日本バラタナゴは池に入れていた。
産卵前の発色する姿は、熱帯魚にはない、上品な美しさがある。
私が引退するまでは、か細くも命脈を保っていた筈だが、その後どうなったかは知らぬ。
ここでようやく、この施設名の由来が分かった。
この日本を代表するタナゴの学名こそが「ナンチャラ・カンチャラ・くるめうす」と言うらしいのだ。
久留米でとれたタナゴが、基準となる標本になったからだとか。
これももう少し、どうにかならんのかねえ。
淡水魚専門誌なんかにそんな事、一言も載ってなかったが。
もう一度言う。
久留米人だって、だーれも知らんぞ。

子供連れのご婦人が居た。
これで、この日は二組の来場者は確定したようだ。
頑張れ、くるめウス!!

これは、昭和28年の大水害の時に、筑後川の川底から引き揚げられた、樹齢200年の楠木なんだとか。
帰りは、立派なコンクリート製の橋になった、現在の豆津橋経由で、自宅までジョギングである。