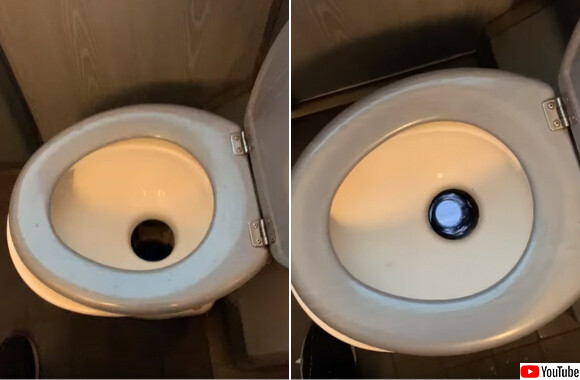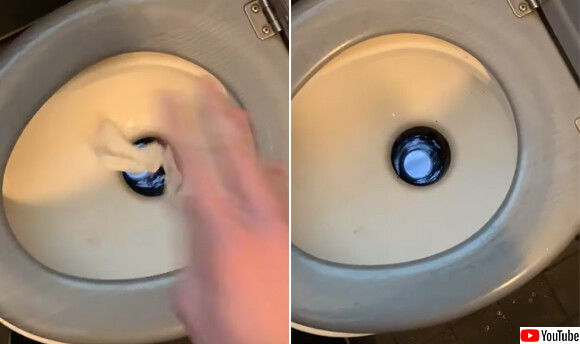雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?
MLMではない格安副業です。
100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。
↑ ↑ ↑
クリックしてね!

今から約1万1500年前、狩猟採集民族が現在のトルコに建設したと言われている巨大神殿ギョベクリ・テペは、人類最古の神殿である可能性が高く、新石器時代研究にとって極めて重要な発見のひとつだ。
神殿が建てられた当時、人類は狩猟生活を送っていたが、移住する彼らが一つの場所に巨大な建造物を作ったことは、考古学の不思議と言われていた。
今回の発見は考古学者をさらに驚かせた。イスラエル・テルアビブ大学と同国考古学庁の研究者たちが構造解析を行ったところ、ギョベクリ・テペの円形構造物と、無数にある石灰岩の巨大な柱のレイアウトに幾何学の知識が使われてることがわかったという。
ギョベクリ・テペの遺跡には円形の囲い最大直径20メートルのものを含め、円形の囲いが3つあるが、これらは後から継ぎ足して適当に作られたのではなく、最初から、ひとつの計画のもとに建てられたものだという。
その根拠は、この3つの円の中心を結ぶときれいな正三角形になることらしい。つまり、この建設を指揮した者は、幾何学的知識を持っていたことになる。
イスラエル考古学庁のギル・ハックリー氏ら研究者たちは、コンピューターアルゴリズムを使って、この新石器時代の遺跡の中にある、これら円形建造物の建築設計プロセスを追跡してみた。

1994年にドイツ人考古学者クラウス・シュミッツ博士によって発見されたギョベクリ・テペは、考古学界に熱い議論を生み出してきた。
このような新石器時代初期の遺跡については、集中的に研究されてきたが、この時代の建築計画の問題や文化的な影響はまだそれほど研究されていない。
研究者の多くは、ギョベクリ・テペ遺跡の円形の囲いは、長い時間をかけて徐々に建設されたと主張しているが、ハックリー氏らは3つの囲いが、最初から幾何学模様を折りこんだ単一プロジェクトとして計画されたものだと言っている。
The World's Oldest Temple Was Built Along A Grand Geometric Plan
これまでは、幾何学を使ったり、間取り図を作成するといった建築計画能力や実行力は、ギョベクリ・テペが建設された時代よりも遥かに後の時代に出てきたものとされてきた。
つまり、狩猟採集民族が、食料を自ら生産する農耕民族へと移行した1万500年前のことだというのだ。おもしろいのは、初期の農耕民族の特徴のひとつとして、彼らが四角形の建造物を使っていたことがあげられる。
ハックリー氏はこう語る。
ハックリー氏らは次回、レヴァント諸国のほかの新石器時代の建築遺跡を調査する予定だという。
この発見は、学術誌『Cambridge Archaeological Journal』(5月)に掲載された。
References:aftau / eurekalert/
☆最近こういう話題には慣れてきた!
雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?
MLMではない格安副業です。
100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。
↑ ↑ ↑
クリックしてね!
MLMではない格安副業です。
100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。
↑ ↑ ↑
クリックしてね!

ギョベクリ・テペの円形の囲い image by:Cambridge Archaeological Journal
今から約1万1500年前、狩猟採集民族が現在のトルコに建設したと言われている巨大神殿ギョベクリ・テペは、人類最古の神殿である可能性が高く、新石器時代研究にとって極めて重要な発見のひとつだ。
神殿が建てられた当時、人類は狩猟生活を送っていたが、移住する彼らが一つの場所に巨大な建造物を作ったことは、考古学の不思議と言われていた。
今回の発見は考古学者をさらに驚かせた。イスラエル・テルアビブ大学と同国考古学庁の研究者たちが構造解析を行ったところ、ギョベクリ・テペの円形構造物と、無数にある石灰岩の巨大な柱のレイアウトに幾何学の知識が使われてることがわかったという。
遺跡の3つの円形の囲いを結ぶと正三角形に
ギョベクリ・テペの遺跡には円形の囲い最大直径20メートルのものを含め、円形の囲いが3つあるが、これらは後から継ぎ足して適当に作られたのではなく、最初から、ひとつの計画のもとに建てられたものだという。
その根拠は、この3つの円の中心を結ぶときれいな正三角形になることらしい。つまり、この建設を指揮した者は、幾何学的知識を持っていたことになる。
イスラエル考古学庁のギル・ハックリー氏ら研究者たちは、コンピューターアルゴリズムを使って、この新石器時代の遺跡の中にある、これら円形建造物の建築設計プロセスを追跡してみた。

ギョベクリ・テペの遺跡 image by:Teomancimit/Wikipedia commons
考古学の不思議、ギョベクリ・テペ
ギョベクリ・テペは、まさに考古学の不思議です。1万1500年から1万1000年の間の新石器時代に建造されたもので、巨大な円形の石の構造物や、高さ5.5メートルもある石柱が無数に見られます。
当時はまだ、農耕や家畜の飼育はなかった時代なので、狩猟採集民族が建てたとしか思えないのですが、動物を追って生活する彼らは定住していなかったはずです。
ひとところにこのような複雑で巨大な建築物を作ることは、あまり考えられないことなのです(ギル・ハックリー氏)
1994年にドイツ人考古学者クラウス・シュミッツ博士によって発見されたギョベクリ・テペは、考古学界に熱い議論を生み出してきた。
このような新石器時代初期の遺跡については、集中的に研究されてきたが、この時代の建築計画の問題や文化的な影響はまだそれほど研究されていない。
研究者の多くは、ギョベクリ・テペ遺跡の円形の囲いは、長い時間をかけて徐々に建設されたと主張しているが、ハックリー氏らは3つの囲いが、最初から幾何学模様を折りこんだ単一プロジェクトとして計画されたものだと言っている。
The World's Oldest Temple Was Built Along A Grand Geometric Plan
この建造物のレイアウトは、精神世界や社会構造の変化を反映した空間的、象徴的な階層によって特徴づけられています。
わたしたちの研究では、標準偏差マッピングに基づいたアルゴリズムという分析ツールを使って、設計を調整する目に見えない幾何学模様を特定しました。
この研究は、レヴァント(地中海東部の沿岸諸国)世界で計画された初期の建築開発について、重要な情報をもたらしてくれます。この発掘現場の、とくに擬人化された巨大な柱の特徴についての新たな解釈の扉を開くものなのです(ギル・ハックリー氏)
新石器時代始めの劇的な文化革新の表れか
これまでは、幾何学を使ったり、間取り図を作成するといった建築計画能力や実行力は、ギョベクリ・テペが建設された時代よりも遥かに後の時代に出てきたものとされてきた。
つまり、狩猟採集民族が、食料を自ら生産する農耕民族へと移行した1万500年前のことだというのだ。おもしろいのは、初期の農耕民族の特徴のひとつとして、彼らが四角形の建造物を使っていたことがあげられる。
ハックリー氏はこう語る。
人類初期の建築計画であるこのケースは、新石器時代始めの文化の劇的な変化のひとつの例かもしれません。
我々の発見は、四角い建造物への移行のようなこの時代の建築の大きな変遷は、専門知識のある者による知識ベースに基づいて、トップダウンというやり方で実行されたのではないかということを示しています
建築計画のもっとも重要で基本的な手法は、後期亜旧石器時代(旧石器時代末期と中石器時代初頭)のレヴァント地域で、ナトゥフ文化(中石器文化)の一部として考案され、新石器時代の初期を通して続きました。
この新しい研究からは、大規模な建築計画、抽象デザインの利用、整然とした模様が、人類の歴史のこんな早い形成期にすでに活用されていたことがわかります
ハックリー氏らは次回、レヴァント諸国のほかの新石器時代の建築遺跡を調査する予定だという。
この発見は、学術誌『Cambridge Archaeological Journal』(5月)に掲載された。
References:aftau / eurekalert/
☆最近こういう話題には慣れてきた!
雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?
MLMではない格安副業です。
100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。
↑ ↑ ↑
クリックしてね!