
今日・ある方のブログの記事で
吾妻山の雪ウサギ伝説・・・のある事を知りました。(ゆうゆう大王さん、勝手に使用することをお許し下さい。)
福島に春を告げる
浄土平のすぐ近く、福島市内から見ると西部に位置する吾妻小富士。
この名前は福島市内から眺めた形が富士山に似ていることから呼ばれている。
早春、福島に桃の花が咲く頃・・・山の積雪も少しずつ解け始め
北方斜面に「種まきウサギ」又は「雪ウサギ」と呼ばれる雪形が残るようになる。
昔から地元の農民はこの「ウサギ」を見ることによって春の訪れを知り
苗代に種まきを始めたともいわれ、
現在では福島地方の早春のシンボルとして一般に親しまれている。
また、吾妻小富士の下の残雪がうさぎ形に見られる頃になると
晩霜の心配がないという福島市飯坂地区に伝わる天気ことわざもあって
吾妻小富士の麓にうさぎ形の残雪が見られるようになると
晩霜の心配はしなくとも良いと言う言い伝え。
これは吾妻小富士は海抜1700メートルくらいなので、雪が解け出すために
10℃以上の気温になったとすれば、福島市では20℃以上の気温になるためと言われています。
種まきウサギ伝説
① 雪ウサギ」が…昔、日照りが続いて困っていたとき
トンビが可愛がっていたウサギを掴んで西へと飛んでいった。
行き先を見れば吾妻山に雪うさぎが現れていた。
そこで吾妻山に登り雨乞い祈願して戻ったところ、
家の岩室より水が湧き出していた。
この水を田に引いて種子を蒔くことができたので
秋には豊作となった…こんな民話も語られています。
②昔、田沢村(現在の福島市蓬莱町田沢)の兎田(うさぎでん)に身なし子がいたど、
山の奥さ小さな田畑を作って暮らしていた。
ある日、山で親子の兎を拾って可愛がっていた。
このころ、このあたりでは、日照りが続いて田植えができないひどい不作の年だった。
村人は田沢の貝沼(皆沼)は、西山の雷沼(東屋沼)の底とつながっていて、
吾妻権現がまつられていたので、ここで雨乞いしたが、さっぱりききめがなかった。
そこで村人は山伏の先達(あんない)で大勢雨笠、蓑着て
吾妻山さ登って雷沼に「雨たもんたれ龍王やーい」といったが、一粒の雨も降らなかった。
身なし子も裏山さ登って拝んでいると、二羽のトンビが天高く飛んでいた。
「トンビ ぴいひょろろ目まわしてみせろ」と言うと、
トンビは急に谷へおりていって白いものをわしづかみにかっさらって西山の方さとんでいってしまったど。
飛んでいった先をみると、たまげた。
吾妻小富士の横はらに、親子うさぎの雪形がありありとあらわれていた。
トンビにさらわれた親子うさぎは実は山神になっていたんだと。
そこで小富士の神に「雨たもんたれ龍王やーい」
・・・と拝んで山を降りてみると、びっくりした。
家の前の岩室から、水がこんこんわいて川さ流れていたど。
「これはありがたい」と田んぼに水をひき、種をまいた。
村人にも教えたら、秋になって村中、万年豊作になって、
みんなも福しく(裕福)なり、その子は大きくなると長者様になったど。
それから、その田を「兎田」(うさぎでん)・・・と
吾妻山の雪形を「種まき兎」と呼ぶようになり
以来種まき、蚕の掃立(はきたて)の目安となって村は栄えもうしたど。
(福島市蓬莱町にある種まき兎伝説発祥の地・説明板より抜粋)
・・・とありました。
吾妻山の雪ウサギ伝説・・・のある事を知りました。(ゆうゆう大王さん、勝手に使用することをお許し下さい。)
福島に春を告げる
浄土平のすぐ近く、福島市内から見ると西部に位置する吾妻小富士。
この名前は福島市内から眺めた形が富士山に似ていることから呼ばれている。
早春、福島に桃の花が咲く頃・・・山の積雪も少しずつ解け始め
北方斜面に「種まきウサギ」又は「雪ウサギ」と呼ばれる雪形が残るようになる。
昔から地元の農民はこの「ウサギ」を見ることによって春の訪れを知り
苗代に種まきを始めたともいわれ、
現在では福島地方の早春のシンボルとして一般に親しまれている。
また、吾妻小富士の下の残雪がうさぎ形に見られる頃になると
晩霜の心配がないという福島市飯坂地区に伝わる天気ことわざもあって
吾妻小富士の麓にうさぎ形の残雪が見られるようになると
晩霜の心配はしなくとも良いと言う言い伝え。
これは吾妻小富士は海抜1700メートルくらいなので、雪が解け出すために
10℃以上の気温になったとすれば、福島市では20℃以上の気温になるためと言われています。
種まきウサギ伝説
① 雪ウサギ」が…昔、日照りが続いて困っていたとき
トンビが可愛がっていたウサギを掴んで西へと飛んでいった。
行き先を見れば吾妻山に雪うさぎが現れていた。
そこで吾妻山に登り雨乞い祈願して戻ったところ、
家の岩室より水が湧き出していた。
この水を田に引いて種子を蒔くことができたので
秋には豊作となった…こんな民話も語られています。
②昔、田沢村(現在の福島市蓬莱町田沢)の兎田(うさぎでん)に身なし子がいたど、
山の奥さ小さな田畑を作って暮らしていた。
ある日、山で親子の兎を拾って可愛がっていた。
このころ、このあたりでは、日照りが続いて田植えができないひどい不作の年だった。
村人は田沢の貝沼(皆沼)は、西山の雷沼(東屋沼)の底とつながっていて、
吾妻権現がまつられていたので、ここで雨乞いしたが、さっぱりききめがなかった。
そこで村人は山伏の先達(あんない)で大勢雨笠、蓑着て
吾妻山さ登って雷沼に「雨たもんたれ龍王やーい」といったが、一粒の雨も降らなかった。
身なし子も裏山さ登って拝んでいると、二羽のトンビが天高く飛んでいた。
「トンビ ぴいひょろろ目まわしてみせろ」と言うと、
トンビは急に谷へおりていって白いものをわしづかみにかっさらって西山の方さとんでいってしまったど。
飛んでいった先をみると、たまげた。
吾妻小富士の横はらに、親子うさぎの雪形がありありとあらわれていた。
トンビにさらわれた親子うさぎは実は山神になっていたんだと。
そこで小富士の神に「雨たもんたれ龍王やーい」
・・・と拝んで山を降りてみると、びっくりした。
家の前の岩室から、水がこんこんわいて川さ流れていたど。
「これはありがたい」と田んぼに水をひき、種をまいた。
村人にも教えたら、秋になって村中、万年豊作になって、
みんなも福しく(裕福)なり、その子は大きくなると長者様になったど。
それから、その田を「兎田」(うさぎでん)・・・と
吾妻山の雪形を「種まき兎」と呼ぶようになり
以来種まき、蚕の掃立(はきたて)の目安となって村は栄えもうしたど。
(福島市蓬莱町にある種まき兎伝説発祥の地・説明板より抜粋)
・・・とありました。











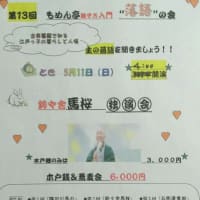









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます