9 環境設定をする
・黒板の周りや中に余計な物を貼らない。掲示物など、貼り過ぎず、
シンプルにする。
※ 発達障害や知的障害がある場合,「選択注視」が難しい。選択注視とは,
多くの中から,自分の必要な情報だけに注目する力である。
※ 多くのものがべたべた貼ってあると,余計な物に注意が取られ,
「ここを見なさい」という所に注目することができず,場合によっては騒いだり,
動き出したりし,授業が成立しなくなってしまう。
※ 金魚の水槽を黒板脇などに置くのも検討が必要である。集中がそがれる。
聴覚に注意欠陥が現れる子どもで,金魚の水槽のブクブクの音に気持ちを取られ,
全く授業にのれない子がいた。視覚的にも聴覚的にも,環境設定で配慮が必要である。
10 発達段階に応じた対応をする
・RPDCAの基本であり,実態把握の重要性である。実態を把握し,発達の段階を見て,
適切な教材を与える必要がある。また,適切な言葉かけ,支援が必要となる。全く
見当違いな支援をしていては,成長するどころか,成長を止めてしまう恐れさえある。
※ 例えば,太田ステージでステージⅡの子どもに,言葉だけの指示は通じない。その
ことを理解せず,いつまでも,言葉だけで「早く靴を履きなさい」と言い続けていて
はダメである。視覚的は提示,指さし,補助が必ず必要となる。
※ 言葉の理解のない段階の子どもも,「靴を履きなさい」と言い続けていると,
言葉を理解したかのようにできるようになる場合がある。しかし,それは,言葉を理解
して動いているのではなく,「感覚運動的」に身に付いているのである。同じような場所で,
同じような動作,言葉をかけていると,その場ではできるようになってくる。これは感覚運動
である。言葉の理解のない子は感覚運動でもいろいろ身に付けていくことが,生活の自立に
つながるといわれるので,それはよい。しかし,だからといって,「言葉を理解している」
「言葉が分かるのよ」として,他の行動も同様に扱うと,指導は息づまる。
・黒板の周りや中に余計な物を貼らない。掲示物など、貼り過ぎず、
シンプルにする。
※ 発達障害や知的障害がある場合,「選択注視」が難しい。選択注視とは,
多くの中から,自分の必要な情報だけに注目する力である。
※ 多くのものがべたべた貼ってあると,余計な物に注意が取られ,
「ここを見なさい」という所に注目することができず,場合によっては騒いだり,
動き出したりし,授業が成立しなくなってしまう。
※ 金魚の水槽を黒板脇などに置くのも検討が必要である。集中がそがれる。
聴覚に注意欠陥が現れる子どもで,金魚の水槽のブクブクの音に気持ちを取られ,
全く授業にのれない子がいた。視覚的にも聴覚的にも,環境設定で配慮が必要である。
10 発達段階に応じた対応をする
・RPDCAの基本であり,実態把握の重要性である。実態を把握し,発達の段階を見て,
適切な教材を与える必要がある。また,適切な言葉かけ,支援が必要となる。全く
見当違いな支援をしていては,成長するどころか,成長を止めてしまう恐れさえある。
※ 例えば,太田ステージでステージⅡの子どもに,言葉だけの指示は通じない。その
ことを理解せず,いつまでも,言葉だけで「早く靴を履きなさい」と言い続けていて
はダメである。視覚的は提示,指さし,補助が必ず必要となる。
※ 言葉の理解のない段階の子どもも,「靴を履きなさい」と言い続けていると,
言葉を理解したかのようにできるようになる場合がある。しかし,それは,言葉を理解
して動いているのではなく,「感覚運動的」に身に付いているのである。同じような場所で,
同じような動作,言葉をかけていると,その場ではできるようになってくる。これは感覚運動
である。言葉の理解のない子は感覚運動でもいろいろ身に付けていくことが,生活の自立に
つながるといわれるので,それはよい。しかし,だからといって,「言葉を理解している」
「言葉が分かるのよ」として,他の行動も同様に扱うと,指導は息づまる。













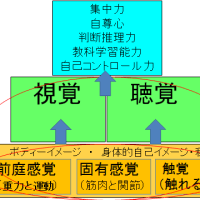






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます