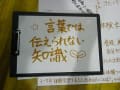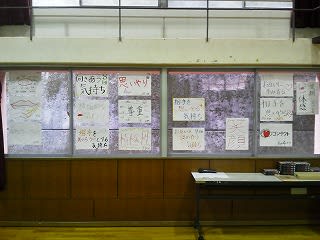都市公園が抱える課題(内包する問題)は多い。
特に近隣住民や利用者との関係において発生する事案は、それぞれの思いや社会、所属する地域コミュニティーが抱える問題が交差し複雑化する傾向を見せている。
このように複雑化した課題に対応するには、公園管理者が公園を含む地域を俯瞰し、公園ルールを明確にしたうえで、個人の立場ではなく公園として対応することが大切になる。
また、公園ルールを明確にしたうえで、問題の背景や社会的な動きについて考えて(理解して)おく必要もあると思う。
事案の解決は容易いからと強硬に行い、その後にトラブルを残しては意味がない。
最近の公園運営では運営者目線という中だけの視点ではなく、公園周辺や利用者を含む視点がいま求められている。
公園を取り巻く地域(公園を軸とした地域)を含めどの様なコミュニティーを公園として形成したいのかを考えることが求められている。
しかし、多くの公園では日常管理の重要さから質の維持が求められているが、質の維持を堅持するあまり、変化しないことが常態化ているのではないかとさえ思えてしまうことがある。
結果、問題があったとしても顕在化(具現化)するまで先送りになるのではないかと。
たとえば、公園に多い禁止看板。
看板を見かけるが、積極的な対話が行われている様子は粗見ない。
対応の多くは、対処療法的な当事者への注意のみであり、極端にいえば見つけなければ対応しない。
本当にそれでいいのだろうか?
見ようとするのか、目に入るのかは同じようで全く違うのだが…。
特に、施設管理者(行政)が苦手な事案に倫理が絡むものが多い。
これらの解決には、日常のコミュニケーションと問題に対する思考の構築(考え方)が大切になる。
しかし、問題解決の基礎となるはずの日常のコミュニケーションを苦手とし、公園ルールを掛け軸のように管理し、未確認なまま運用している管理者が多いのではないか。
また、このような体制は、職員ごとに異なる対応をする要因となる。
最近のドラマから言葉を借りれば、「ならぬものは、ならぬものです」を言えない管理者が非常に多いと思っている。
そのため同じ行為であっても、ダメと言われる人と、言われない人(暗黙の許可)が存在してしまう。
結果、ノラネコへの餌やり、ゴミの投棄、植栽の盗掘、花の枝折り、エサ台の設置など個人の思惑による行為が公園ルールが認識しづらいために発生し、継続されやすくなる。
「これぐらい(このぐらい)」「きれいだったから」「どうせ、枯らすだけでしょ」「いいことしているのだら」

個人的な倫理観は本当に正しいのだろうか?
また、倫理観は個々で違うことはないのだろうか?
倫理観に換わる判断基準は何なのか。
個人の範疇でなく、公的な立場での判断とはどうあるべきか。
公園管理者の養成には、複雑化する課題に対応できるような資質の形成が求められている。
そのため、一般的な維持管理の手法だけでなく、運営面を考え論理的思考術や倫理についての学びが必要と考えている。
公園とは何なのか、これからの公園の役割とは、職員は何者なのかを考えることを通して学ぶことが重要だと思っている。
どうだろうか?
正直な話し、公園を利用する市民にも様々な事例を通じて倫理について考える機会が必要なのだと思っている。
どの様にして、そのような機会を公園管理者として作り出していくのか。
地域の中の公園になるためには、園内だけを考えていても仕方ないのかもしれない。