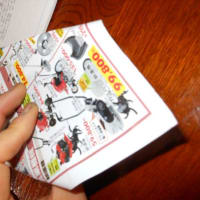ここから数秘学も交えて、このリンパ(7つの主要内分泌腺・チャクラ)の人間の進化に及ぼす影響について考えてみたいと思います。
と、その前に今日フト考えたのが、私もそうですが、世間一般に ”体に良い” と宣伝されたり、考えるモノはついつい使い過ぎてしまう傾向があると思います。 健康食品しかり、運動しかり、セラピーしかり。
しかし、ケイシーにしろひふみ神示にしろ、中庸と申しますか、各個人の適量というものをものスゴく重視しています。 良いモノも使い過ぎれば、多過ぎれば毒となる。 コレはマクロバイオティクスの基本理念のひとつです。
あの大森先生ですらも、この事を理解し過ぎるぐらい理解されているのに、やり過ぎて失敗した経験を何回もお持ちでした。 ですから、一般の方がこの事を理解するのも難しいし、ましてや身に付けるのもかなりの困難を要すると思います。
私自身も、頭ではある程度理解しているのに、ついつい多目に使ってしまう傾向があります。 こちらに関しても今後の人生課題としたいと思っています。
『 “中庸” をもって徳とせよ』
でしょうか。
さて、では前回からの続きに入りたいと思います。 まだあまり上手く頭の中でマトメ切っていないので、筆の赴くままに書いてゆきますので、読み苦しい点に関しては適当にご自分で補って下さい。
【エメラルド・タブレット 〔真理の探求〕】
東洋古代の大聖は、一つなる宇宙意識によって、凡てのことを知ることが出来た。
トス(ヘルメス)が言った。 『創造的能力は、第三の眼を開くと活動する.創造的能力は第三の眼を開く訓練の結果として現れるものである』
人間は第三の眼が、自分のドコにあるかも知らない。 第三の眼というのは、眉間に隠れている粘液腺のことで、今日の学者はこれを脳下垂体という。 しかしそれが創造能力の秘密を蔵しているのだということは知られていない。
第三の眼を開くには、まず自分の内なる太陽を見なければならぬ。 この太陽の出る処は心臓の中心、アナハタ・チャクラである。 解剖学では胸腺というが、胸腺がどんな機能をもっているかということは、まだ知られていない。
~~~~~~~(抜粋ここまで)~~~~~~~~~~~~~
前回最後に書きましたが、上記にあります、皆異なる個性を持つ人間を、個々の正しい進化の方面に導く最高位のチャクラ 「脳下垂体(Pituitary Gland)」 ですが、こちらは占星学では大吉祥星の ”木星(Jupiter)” に照応し、数秘学の奇数展開では “3(Three)” 、可視光線では ”青(Blue)” に対応します。
そして、上記に採り上げられているもう一つのチャクラ “胸腺(Thymus Gland)” ですが、こちらは占星学では愛と美と調和・平和を司る ”金星(Venus)” に照応し、数秘学では “6(Six)” 、可視光線では ”藍色(Cyan)” に対応するようです。
そう、今まで何回も書いていますが、“3(Three)” という数は “1(One)・太陽(Sun)・橙(Orange)” と ”2(Two)・月(Moon)・紫(Violet)” という基数が分裂して、再び結合した最初の数であり、最も強い結合を表すと述べられています。
これから以後の数は(4~∞)いくら数が膨張して見えようとも、この3つの数(1,2,3)の複雑な組み合わせに過ぎないというニュアンスが読み取れます。
で、この “3(Three)” という数を倍化した数字が ”6(Six)” であり、関係が深い。
ここで、少しばかりケイシー・リーディングより抜粋しますと、
One, then, the whole number - divisible by that of the various parts as may be taken up to make the whole. One always being, then, a basis for a start - for division - for building - or for disintegration; shown by the relationship of other numbers as respecting same, as may always be seen that when one and one are two - TWO then the weaker number. ALWAYS, in the division, the even numbers - as two, four, six, eight - are the weaker, while the odd numbers are the strength - each having its variation from the vibrations as are naturally created by such. One, then, the Unit.
Two the division, and ready for a change.
Three, again with strength, with the activity of both one and two.
Six again showing a weakness, or a strength again - the multiple of three, strength - yet showing either weakness OR strength, dependent upon the relationship of the day, month, or year, or stock - according to the conditions as are added in same.
ONE is the beginning, to be sure. Before ONE is nothing. After ONE is nothing, if all be IN ONE - as ONE God, ONE Son, ONE Spirit. This, then, the ESSENCE of ALL force, ALL manners of energies. All activities EMANATE from the ONE.
TWO - the COMBINATION, and begins a division of the whole, or the One. While TWO makes for strength, it ALSO makes for weakness. This is ILLUSTRATED in that of your music, of your paintings, of your metals, of WHATEVER element we may consider!
THREE - again a combination of One and Two; this making for strength, making for - in division - that ability of Two AGAINST One, or One against Two. In THIS strength is seen, as in the Godhead, and is as a greater strength in the whole of combinations.
SIX - again makes for the BEAUTY and the symmetrical forces of ALL NUMBERS, making for strength;
NUMBERS of same! But best study as you would your own A.B.C's. One - the all power. Two - divided. Three - the strength of One and the weakness of Two. Four - the greater weakness in all its associations and powers. Five - a change imminent, ever, in the activities of whatever influence with which it may be associated. Six - the strength of a Three, with a helpful influence. Seven - the spiritual forces that are activative or will be the activative influences in the associations of such an influence. Eight - a money number. Nine - the change. Ten - back to One again. These in their correlated influences as you will find in your own experience, and we will see these are but signs. Study in some of these, but turn most to the influence of the force of the One within self.
~~~~~~(抜粋ここまで)~~~~~~~~~~~~~
ここまで試行錯誤しながら研究していて、フト直感から思い浮かんだ有名な中国の諺が 『青は藍より出て藍より青し』 でした。
下に抜粋して次回に続きます。
〔青は藍より出でて藍より青し〕
染め物の一種に、藍染めというのがある。染料の藍玉は青味は帯びて
いるものの、どちらかと言うと黒い色だ。この藍玉を溶かした藍瓶に、
反物を入れて引き上げると、最初は緑がかった色が見る見る青くなる。
この素朴な驚きは今も昔も変わらない。
中国の儒家 筍況(B.C.300~240頃) の言葉
学は、もって已むべからず。
青は藍より出でて藍より青く、
氷は 水これを為して、水よりも寒し。(「荀子」勧学篇)
学問はいつまでも止まると云う事はないし、
弛んではならない。
青がもとの藍よりも青いように、
氷がもとの水よりも冷徹なように、
師を凌ぐ学の深さを持った弟子も現れるものだ・ ・ ・
ここから弟子が師よりも優ることを、この言葉で表すようになった。
「出藍」とか、「出藍の誉れ」というのもここから来ている。
南北朝時代の北朝に李謐という人物が居た、李謐は初め孔潘に就いて
学んでいたが、その進歩はめざましかった。数年の後、孔潘は李謐の方
が自分より学問が進んだと考え、自ら進んで李謐の弟子になった。この
時、同門のものは筍況のこの言葉を引用して、李謐の優秀さと孔潘の実
直さを褒め称えている。
近年の師と仰がれる人々で、筍況のこの言葉を真に理解している人は
少ない。弟子はいつまで経っても弟子であり、一人前或いは自分と同等
と認めても、その弟子の「弟子」になることが出来ない。
将に「学は、もって已むべからず」である。この「青は藍より出て藍
より青し」に触れたら、この事も思い出して欲しい。
「過ちては、則ち改めるに憚ること勿れ」