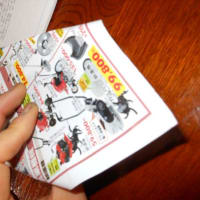ここんトコ、冷えますね~。 昨日も雪降る下露天風呂に浸かって宇宙の神秘を考えていました。 朝の散歩では星を見ながらの、特に黄道十二宮のSaggitrariusからScorpio、そして北斗七星を見ながらいろいろと考えています。
さて、これだけ雪が降ったり、寒かったりするとホントにCO2が原因で温暖化してるのか?と疑問をもちたくなります。 昔はこのプロパガンダに関していろいろと調べましたが、私の直感の総てを納得させてくれるような答えは得られていないのがホントのとこです。
さてそこで、ケイシー・リーディングより現在問題となっているこちら(温暖化)に関するひとつの考える角度と思われるようなリーディングを本厄・・・じゃなくって翻訳本より抜粋してみたいと思います。
【エドガー・ケイシー 驚異の波動健康法 〔第一章 水の神秘的な治癒力〕】
~海~
海は、あまり私たちが自分との関係を考えずにいる水の世界です。 ところが、リーディングは、私たちが海に影響を及ぼし、勿論、海も私たちに影響を及ぼしていると指摘しています。 最初のリーディングは、私たちが海の活動をどう使うかによって、その成分に変化が出てくると述べています。
〔問5〕:「海の塩は、人間の血中の塩と同じでしょうか?」
〔答5〕:必ずしも同じではない。 同じ時もまたある。 血の塩に最も近い組織である。 だが、熱さや寒さ、食物の違いによって人体の血が絶えず変化しているように、海中の塩、塩の位置も周囲の活動の使い方によって変化してくる。」(R658-15)
次の抜粋は、人口密度と太陽活動が組み合わさって、海の海流の中に変化を作り出すと語っています。 これが、ついには気象にも影響するのです。
〔Cayce夫人〕:あなたの前には、ハーバート・ジャンプリン・ブラウンによる1926年1月15日の長期予報の報告書があります。 あなたは、この報告書と、その基礎となっている太陽理論に関して私が質問することにお答えになります。」
〔Cayce〕:よろしい。 我々の前には、ここにプリントされた報告書がある。 この中には、冷静な分析からというよりも、むしろ、予測的な性質の状況が多々見られる。 いつの時代にもあったと思われるような状況が多数予測されるだろうが、このレポートの中では、それらが陸や海の状態というより、太陽のそれに関係させようとの試みがなされている。 だが、我々は黒点による太陽の放射率よりも、人口密度が太陽の状態と結合し合って、海や海流にある変動を起こすのだと強調したい。」(R195-29)
リーディングは、この経過をハッキリと説明しています。 熱は地球から放出されますが、人間がいろいろな物質を燃焼させるために、その放出量には変化が出てきます。 人口が多ければ、それだけ沢山の熱が放出されます。 この熱が 「大気中の反射」、 つまり太陽熱に関係してくるのです。 二つの結合した熱が地球に戻り、海流を変化させます。 それによって海辺が温暖になる地域もあれば、寒くなる地域も出てきます。
〔Q1〕:ブラウンの理論は正しいでしょうか? つまり、太陽の放射活動とそれが海流に働きかける作用を測定することによって、気象は何年も前から予測可能という説ですが・・・・・・」
〔A1〕:「先にも暗示したことをこれらが考慮に入れていないなら、正しいことにはなりえない.というのも、”放出されたものは返ってくる” というのが宇宙の法則である。 地球上のあちこちで熱さ寒さが大気中に放出され、それが大気中の反射と結びついて、海流を変化させる作用を生み出すのだ。こうして、海があちこちの岸辺に熱を運んだり、寒さを運んだりするのである。」(R195‐29)
リーデングは、遠い昔に使われていた霊泉の源が今も復興できると言いました。 これはバハマ諸島にあるビミニの井戸で、アトランティスの時代に使われていたものであるとのことです。 その周辺の水にも生命力があって、若返らせる力を持っているとのことです。
〔問5〕:「ビミニの井戸は再建できるのでしょうか?」
〔答5〕:「 アトランティス時代にあったその特別な場所をどう開発すべきかについては、この源から沢山述べてきた。 そこは二つの目的のためのセンターとなるだろう。 一つは(その泉ばかりか周辺にもある生命力によって)ある種の病気をもつ人たちを再生させるためと、もう一つは考古学的調査の為の拠点である。 そして、この仕事が着手されるならば、海の下から、これまで世界に産出したより多くの金が発見されるであろう」(R578-4)