防災カレンダー
兵庫県西脇市

兵庫県西脇市

第一ステップは
・その場にいない人の陰口悪口を言わない
でした。
それまでの私は本当に、自分で無自覚にいろいろな人の陰口悪口を相当言っていた人間だったと思います。が、本人は無自覚なので覚えていません。
ただ一つ覚えているのは「まるぞうさん、そろそろそういう人の悪口を言うのはやめてもらえませんか」と友人から指摘を受けたということでした。
もう20年近くも前のことですが、はっきり覚えています。
それほど、私はいつも「無自覚に」誰かの陰口悪口を放言していたのでしょう。
でも社員からすると、私が社外の取引先や、その場にいない社員の悪口を言っているのを聞くのはさぞかし辛いことであったと思います。
そのため、私は「その場にいない人の陰口悪口は言わない」と心に決めました。
第二ステップは
・社会の批判や愚痴を言わない
ということです。
これは別に「言わない」と決めたわけではなく、第一ステップの習慣を続けていたら、自然とそうなっていた。ということです。
・社会が悪い
・政府が悪い
・業界が悪い
・テレビが悪い
・マスコミが悪い
・〇〇国が悪い
・近頃〇〇な人が増えた。
・近頃〇〇な若者が増えた。
・近頃〇〇な老人が増えた。
etc etc...
いつの間にかそういう話題を私が口にすることはなくなりました。
相手がそういう話題になっても、「でも〇〇って良い面もあるよね」と話題を良い方向に持っていくか、あるいは、「そうねえ…」と流すか、反応せずただニコニコと黙っているか。
これは、その方が自分の気持ちが良いからです。
別に道徳的に「正しくあれ」と主張する意図ではなく、本当にそれが自分の気持ちが良いからなのです。
テーブルの上に食べ散らかしたゴミが残っていたら、そっと集めてゴミ箱に入れます。でもそれは道徳ではなく、私が気持ちが良いからです。
第三ステップは
・自分の主張を説得させる欲望がなくなって
・相手を肯定して喜んでもらうのが嬉しい
という変化です。
これも特に決心したわけでなく、第一ステップと第二ステップの延長で私に起きた変化です。
もちろん
・仕事として必要な指示や報告
・安全や健康のリスクに関する話題
については、きちんと主張します。
でも、本当にそういうことは年に数回もありません。
99.9%は、別に私が相手に無理に自分の主張を通す必要はない。それより相手の主張を肯定して「そうですね」と認めて、相手が喜んでくれる方が私は嬉しいし気持ちがいいのです。
個人的な趣味としては
・8割はどうかな?
・でも2割は良いかな
という場合は、その2割の「相手の主張を肯定する」話題として膨らませます。
相手が「どうしたらいいだろうか?」と質問をする時は、
本当にこちらの知見が役に立つ場合は、できる限りの相談にのりますが、
でも大抵は「自分の意見を肯定して欲しい」ということがほとんどなので、
・仕事として必要な指示や報告
・生活の安全や健康のリスクに関する話題
以外は、相手の意見を肯定する。そういう会話になります。
この第三ステップについては、異議のある方もいらっしゃるでしょう。
それで良いと思います。
あるいは「ああ、そういう気持ちわかる」という方もいらっしゃるでしょう。
それで良いと思います。
そこまでして、自分の意見をおさえて媚びへつらえばそりゃ相手も気持ち良いでしょうよ。というご意見もそれで良いと思います。
ただし私は、ご機嫌とりのために媚びているわけではなく、またぐっと自分の意見を抑えつけているのではないのです。
あるいは「ああ、そういう気持ちわかる」という方も少なからずいらっしゃるでしょう。
そう。そういう風景です。
自分の主張を相手に認めさせたいという欲が本当に少なくなりました。(仕事上の決断や生活の安全や健康のリスクに関する話題を除く)
それより、相手を肯定して、相手が喜ぶ顔が、こちらも気持ちが良いのです。
おまけ(読者の方によって教えて頂いたこと)
==========
薫兄者さん
・・・
京極夏彦氏の小説『姑獲鳥の夏』では、床に転がっている人間の〇体が「見えない」というシーンが出てきますね。見たくない、信じたくないという想いが、〇体を見えなくしてしまう。読んだときは「ほんまかいな!?」と思いましたが、人間確かに「見たいものを、見たいようにしか見ていない」ものだな、というのはよく実感します。
彼が見ている世界、彼女が見ている世界と私が見ている世界は似て非なるもの。
黒澤明の映画『羅生門』はそんな人間の性(さが)のようなものを、物語的に上手く描いています。世代を越えて、一見の価値ある映画です。
人は基本、己の「目」に映るものしか信じない。でも「本当」の世界は、己の「目」に見えることを越えて、「目」の前に広がっているのだろう。
なんてことを、つらつら思う今日この頃。
なんといいますか
面白いね。
→ 私もかつては
・自分の思い込みが正しい
という世界で生きておりました。
今は「半分は間違っているかも」という補正を実感いたしまして、は随分私を助けてくれたと思います。それでもやはり半分は「私の思い込み」の中で生きております。
==========
ようこさん
・・・
私は今はパモキサン錠を冷蔵庫野菜室に備えてあります。
==========
菜の花♪さん
・・・
わたしも最近ですが、お店の方に「ごちそうさまでした」「美味しかったです」と素直に伝える事ができる様になりました。
「ごちそうさまでした」はいつも言っていましたが、「美味しかった」と伝えるのは少し緊張します。
でも、満面の笑みと「ありがとうございます」と返して頂いて、心が充電されて暖かい気持ちになりました。
とても素敵な事ですね!
これからも続けたいと思っています。
→ そうなんです。こちらが「ご馳走様でした。美味しかったです。」とお伝えして、相手が喜んでくださる笑顔がこちらにまた幸せな気持ちにさせてくれるのです。(^o^)/
ありがとうございます。
==========
話し変わって、今も忘れられない人がいます。私が横断歩道を渡ろうとした時、道の真ん中に穴があり、そこに爪先を引っかけて派手にダイブしたことがありまして。痛かった!そのとき反対側の歩道にいた女性が、私に手を差し伸べている光景が視界に入った。
あっちとこっちで届くわけがないのですが。それを見た。激しく身体を打撲して痛かったけど、私はその人の咄嗟にして下さったお姿を今もはっきり記憶しています。おもいだすたびに胸がポッと温かくなるのです。観音様のお姉さん有り難うございます。
→ 投稿くださってありがとうございます。そして観音様のお姉さん、ありがとうございます。(^^)
==========
SHO_KOさん
・・・
ハワイの言葉ですが、また書いてしまってすみませんが、
“マラマ・アイナ”は(愛し守る・土地)という意味で
愛して、守るということは同じことなんだなと思いました。それは、愛する気持ちだけじゃなくて、
愛することは守ること。守ることは愛すること。なのだということを連想し、印象に残りました。
私の心はいうのです。「愛するだけじゃ片手落ち」
愛すること、守っていくことができて両輪になる。
それぞれがバランスして両輪が動くのだと。両輪ができて永遠につながる。そう感じました。
そして、なんとなく思ったのは、縄文人は愛することはできたはずだけど、なぜ滅びたのだろうか?(正確には純粋から混血人種になった?)
愛することや感謝すること「今」を楽しむのは得意だったけれど、守る事は遺伝子として存在し続けることが叶わなかったのだろうか?
より何かと混じり合うことで、「今」をより良く生きるために新しい生き方、何かを選択したのだろうか。
そんなことを夢想しました。
→ 縄文人は滅んだとも言えるかもしれませんが、溶け込んだとも言えるかもしれません。
創造→調和→破壊→創造→・・・
螺旋を描きながら新しい風景を生み出すリズム。123の三拍子です。
==========
==========
薫兄者さん
・・・
京極夏彦氏の小説『姑獲鳥の夏』では、床に転がっている人間の〇体が「見えない」というシーンが出てきますね。見たくない、信じたくないという想いが、〇体を見えなくしてしまう。読んだときは「ほんまかいな!?」と思いましたが、人間確かに「見たいものを、見たいようにしか見ていない」ものだな、というのはよく実感します。
彼が見ている世界、彼女が見ている世界と私が見ている世界は似て非なるもの。
黒澤明の映画『羅生門』はそんな人間の性(さが)のようなものを、物語的に上手く描いています。世代を越えて、一見の価値ある映画です。
人は基本、己の「目」に映るものしか信じない。でも「本当」の世界は、己の「目」に見えることを越えて、「目」の前に広がっているのだろう。
なんてことを、つらつら思う今日この頃。
なんといいますか
面白いね。
→ 私もかつては
・自分の思い込みが正しい
という世界で生きておりました。
今は「半分は間違っているかも」という補正を実感いたしまして、は随分私を助けてくれたと思います。それでもやはり半分は「私の思い込み」の中で生きております。
==========
ようこさん
・・・
私は今はパモキサン錠を冷蔵庫野菜室に備えてあります。
==========
菜の花♪さん
・・・
わたしも最近ですが、お店の方に「ごちそうさまでした」「美味しかったです」と素直に伝える事ができる様になりました。
「ごちそうさまでした」はいつも言っていましたが、「美味しかった」と伝えるのは少し緊張します。
でも、満面の笑みと「ありがとうございます」と返して頂いて、心が充電されて暖かい気持ちになりました。
とても素敵な事ですね!
これからも続けたいと思っています。
→ そうなんです。こちらが「ご馳走様でした。美味しかったです。」とお伝えして、相手が喜んでくださる笑顔がこちらにまた幸せな気持ちにさせてくれるのです。(^o^)/
ありがとうございます。
==========
話し変わって、今も忘れられない人がいます。私が横断歩道を渡ろうとした時、道の真ん中に穴があり、そこに爪先を引っかけて派手にダイブしたことがありまして。痛かった!そのとき反対側の歩道にいた女性が、私に手を差し伸べている光景が視界に入った。
あっちとこっちで届くわけがないのですが。それを見た。激しく身体を打撲して痛かったけど、私はその人の咄嗟にして下さったお姿を今もはっきり記憶しています。おもいだすたびに胸がポッと温かくなるのです。観音様のお姉さん有り難うございます。
→ 投稿くださってありがとうございます。そして観音様のお姉さん、ありがとうございます。(^^)
==========
SHO_KOさん
・・・
ハワイの言葉ですが、また書いてしまってすみませんが、
“マラマ・アイナ”は(愛し守る・土地)という意味で
愛して、守るということは同じことなんだなと思いました。それは、愛する気持ちだけじゃなくて、
愛することは守ること。守ることは愛すること。なのだということを連想し、印象に残りました。
私の心はいうのです。「愛するだけじゃ片手落ち」
愛すること、守っていくことができて両輪になる。
それぞれがバランスして両輪が動くのだと。両輪ができて永遠につながる。そう感じました。
そして、なんとなく思ったのは、縄文人は愛することはできたはずだけど、なぜ滅びたのだろうか?(正確には純粋から混血人種になった?)
愛することや感謝すること「今」を楽しむのは得意だったけれど、守る事は遺伝子として存在し続けることが叶わなかったのだろうか?
より何かと混じり合うことで、「今」をより良く生きるために新しい生き方、何かを選択したのだろうか。
そんなことを夢想しました。
→ 縄文人は滅んだとも言えるかもしれませんが、溶け込んだとも言えるかもしれません。
創造→調和→破壊→創造→・・・
螺旋を描きながら新しい風景を生み出すリズム。123の三拍子です。
==========
まる(=・3・=)ぞうのネタ帳。
今後記事にするかもしれないししないかもしれない。気になる情報は、とりあえずここに放り込んであります。
https://twitter.com/J5F6eZXx6YgJP2x
防災意識カレンダー。
Twitterで要注意日の朝6時ごろ配信しております。
https://twitter.com/ohisama_maruzo
本ブログに共感される方はクリックのほどよろしくお願いいたします。
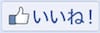
にほんブログ村ランキング
■ブックマーク
備忘録検索(β版)
ゆっくり解説(Youtube)
ゆっくりまるぞう動画(YouTube)
■防災意識リマインダー
防災に注意が必要な期間は、メールやTwitterで防災意識リマインダーを受け取ることができます。詳しくはこちら
■地震雲写真投稿方法
地震雲(飛行機雲のように短時間で消えない立ち上がる雲)を目撃された方は、雲の御写真と目撃情報を下記のメールアドレスにお送り頂ければ幸いです。
ohisama.maruzo@gmail.com
御写真とともに送って頂きたい情報
・目撃された日時(何日何時頃など)
・目撃された場所(県名や地名など)
・目撃された方向(可能なら)
地震雲かわからない方は地震雲の見分け方をご参考になさってください。
(個人情報は厳重に管理し、私以外の第三者に投稿者のメールアドレスなどの個人情報を開示することはありません。また御写真の画像情報や機種情報は消去いたします。人物が特定できる映り込みなどのぼかし加工もこちらで対応いたします。なおお送り頂いた御写真と目撃情報は関連サイトにも掲載させて頂くことがあります。)
■非掲載希望のコメントについて
1.公開を希望しないコメントは投稿しないでください。基本的に投稿されたものは他の読者の方の目にもふれるとお考えください。
2,どうしても公開されたくないメッセージを送りたい方はメールでお願いします。
ohisama.maruzo@gmail.com
3,ただしメールでお送り頂いた内容に対し、私はメールで返信をお送りすることは一切ありません。一方通行となります。
4,上記のようにコメントは原則公開ですが、炎上つながる場合や個人情報が含まれている場合、読者間での私信コメントは、私の判断で非公開とする場合があります。
■引用転載について
本ブログは引用元をあきらかにしていただければ、ブログやSNSでの拡散は許可いたします。















ありがとうございます^ ^
スマホにアマゾンの2段階認証のメールが届かない件、原因はいまだ不明です。たった2日前、買い物できたのに。
アカウントサービスに連絡しようにも肝心のログインができないので弱りました。
しかたないので直接電話できることはできないかと探してやっとアマゾンに電話してなおりました。
(着信拒否などはしていないのです。携帯電話の会社にも電話してみましたが、シムカードをいちどはずして入れなおせといわれた。)
その電話番号ですが、最初にアマゾンにログインするときに、パスワード等を入力する画面が出ます。
その下に<お困りですかと小さく書かれた文字が出ます。そこをクリックすると案内されて出てきます。
カード会社にも電話しましたが、不正利用はありませんでした。
もうひとつ、2段階認証しても詐欺が増えてるようなので
https://www.youtube.com/watch?v=ry6YUeY3Zp4
<amazonで二段階認証を突破される未だかつてない不正利用が急増!その手口とは…?
皆様の参考になれば幸いです。何せ年寄でIT音痴なので。
それより、相手を肯定して、相手が喜ぶ顔が、こちらも気持ちが良いのです。
奥様とパンケーキのお店に行かれた記事でもそうでしたよね。
別に奥様の機嫌を取るとかそういう理由ではなく、相手を尊重した方が気楽という感覚は、別に第3段階とかいう話ではなくて、もともとそういう人ってけっこう多いと思います。(女の人は特に)
でも、リーダータイプの男の人だと、それをするのも最終段階の3段階目になるのかあ、と思いました。なるほどね~。
あ、でも、これから新な4段階目のお話が出てくるのかもしれないですよね☆
☆進化は続くよどこまでも☆
人生にやさしいことは沢山ありました。小さい頃、夜遅くまで留守番してる私のことを近所の皆さん知っててくれました。地震があって停電したら大家さんはすぐに懐中電灯を2つ持ってきてくれました。商店街のおばさんもお菓子を持って見に来てくれました。
床屋のおばさんはいつも私の髪を結ってくれたしな。近所のお医者さんは、お腹が痛くなったらすぐ来なさい、お母さんがいなくてもみてあげると言ってくれました。私は皆さんに見守られ幸せだったんだ。
そんな話をしたら、あなたもそうしなさいよと目上の人から言われました。そうですよね。優しくなりたいです。
→そうですよねー。議論して打ち勝ったとしても、特に自分にとってメリットはないので、その考え方は基本的によく分かります。
ただ、相手が何かを批判していて、自分も相手を肯定すると「相手と同じように、対象物を批判」しなくてはならない時って、ありませんか?その時は、流す感じでしょうか?
例えば、今だと政治家の裏金問題。私はそれほど問題とは思っていないのですが、周りは割と怒っています。
「こんなんだから自民党はダメだ。だから、◯◯党に頑張ってもらって、政権を明け渡してもらわないとと思う。あなたは、どう思う?」と聞かれた時に、同じように自民党批判をして相手の意見に同調するのか、自民党を批判せず擁護するのか。
自分は政治を批判したくないと思っていても、相手に合わせると批判しなくてはならない場面で、まるぞうさんならどう対処されるのか、知りたいです。
学生の頃であれば、「んー難しいことはわかんなーい」とはぐらかして済ませることも出来ますが、社会人の場合はそういう訳にもいかないのかなと思いまして。
この前からの社会の潤滑剤シリーズ、そして今日のお話も大変興味深く拝見しております。
今日のお話の「第2のステップ」ですが、これは私がまさにできないことで耳が痛いです。
私の話になってしまうのですが、例えば自分より年上の人の考え方が幼かったり、若者があまりにも芯が無くしっかりしてないのを見ると「全く世も末だわ、どいつもこいつも…」という具合になってしまうのです。そして「戦争に負けたから教育が云々」「そもそも私らの親世代が云々」とか旦那に絡んでしまいます。大変良くないです。しかも口が悪い上素面で絡むのでタチが悪い。
要は自分の中で年上の方はこうあってほしい、若者もこうあってほしいと理想を押し付けているだけに過ぎず、現実はそうではないから吠えてるだけなのですが…。まるぞうさんはこのような場合の心の折り合いをどんな風に上手くつけていますか?
もしよろしければ教えて頂きたいです…。
ちなみに私は不惑の年齢です。
「戦争が〜」と吠えてしまいますが、それは先の大戦で亡くなった方々に対して現代の我々は恥ずかしい生き方をしているように感じてるからです。
だって今の人々は老いも若きもスマホばかり、先祖に手も合わせず絶対に人間として退化してると思うのです。
怒りん坊な私に何か一言、良い心の持ち方をどうぞよろしくお願い致します。
また、参拝する理由って、ぶっちゃけ何ですか?
そして、参拝させて良かったと思うところって、どんなことですか?
お返事ありがとうございます。
そうですね。そして、その土地は求めたのかも知れません。
その土地が愛しているものたちをたとえ失ったとしても、変わっていくことをその姿を夢見たかった。
その土地が許した。そんな気もしました。