
お彼岸の供物といえば「おはぎ」
今では年中食することができますが、小豆の収穫に合わせた秋が旬といえます。
おはぎは、四季で名前が変わります。
季節の花から、春は牡丹餅
夏と冬は、おはぎを作るときにすりこぎを使い、お餅のように杵でぺったん、ぺったんとつきません。
餅をつかないことから「つき知らず」という言葉遊びとして名前があります。
夏の暗い夜に船が着いても、いつ着いたのか気づかない「着き知らず」から「夜船」
冬の北窓からは月が見えませんから「月知らず」というわけで「北窓」
夏も冬も季節の花から名前が付いていれば、すっと入ってきそうですが、船と窓では知らなければクイズなら答えは絶対に出ませんね。
おはぎは、表面を覆う小豆が萩の花に似ていることから「萩の花」と呼ばれ、転じておはぎとなったようです。
この言葉は室町時代の宮中に仕える女官たちの間で使われた隠語のひとつで女房詞(にょうぼうことば)と呼ばれます。
頭に「お」がつく言葉はその代表的なものです。
「おかず」「おなか」「おにぎり」「おでん」と他にも随分あります。
なんとなく上品ですよね。
日本語も変化をしてきました。
こうした古い言葉も残り、外国語も柔軟に取り入れ、新語も続々出てきています。
リモートワークも直接会わないで話す新しいスタイルですので言葉も変わってきそうな気がします。










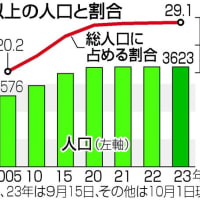
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます