10月1日(水)ハーゲン・クァルテット
~トッパンホール8周年バースデーコンサートシリーズ~
トッパンホール
【曲目】
1.ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調Op.135
2.ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調Op.95「セリオーソ」

3.ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調op.131
これまでに何度か聴いているハーゲン弦楽四重奏団の印象はしなやかさ、柔らかく落ち着きのある音色、それにヨーロッバ的と言いたくなる自然な呼吸など。今回久しぶりにこのカルテットを聴いてそうした印象を再認識したのと同時に、新たな発見というか、しばらく聴かなかった間にまた素晴らしい成長を遂げているのを感じ、本物のアーティストというのはいつまでも同じ場所に安住するものではないと思い知った。
まず感心するのはアンサンブルの緻密さ。息が合っているとか、音色が溶け合っているといった弦楽四重奏に求められる基本のような次元を凌駕した一体感。もちろん各プレーヤーならではの持ち味はある。1曲目のベートーヴェン最後のカルテット出だしの意味深長なヴィオラの問いかけ、ヴェロニカの湿感のある深いヴィオラの響きは聴衆全てがはっとするような印象的なものだが、それに他の3声が唱和してもそのヴェロニカのヴィオラの印象がそのまま持続するのを聴くと、「これがハーゲンQの演奏か」ということになる。第3楽章の前半、4人が一緒のハーモニーを奏でる場面などはひとりのプレーヤーが重音で弾いているかのような一体感。
この作品135はこの世から離れて彼岸にあるような崇高で孤高な音楽と言われ、実際そういう音楽だと思う。簡潔な印象で演奏時間も短いが、そうした特別な音楽であるために演奏会ではプログラムの最後に置かれることも珍しくないが、ハーゲンQはプログラムの冒頭に持ってきた。ハーゲン・クァルテットの演奏するこの曲を聴いていて、浮世離れした演奏ではなく地に足が着いた演奏という印象を持った。
例えば2楽章、4人が一丸となってズンズン進んで行く迫力と臨場感は生き生きとした命が宿る「この世の」音楽だったし、あの天に放たれるような最後の和音をハーゲンは天にではなく、大地にしっかりと足跡を残すようにして終わらせた。全曲を通してハーゲンQが演奏するこの曲は聴く者と同じ大地を踏みしめているような「現実味」を感じた。
それに対して、「セリオーソ」の第2楽章や、最後に演奏したOp.131の第4楽章などからは実に崇高で気高い精神性が伝わってくる。これは、Op.135を天の高みから現実に下ろすことで、血気盛んな「セリオーソ」や嬰ハ短調の曲にもある「崇高さ」の存在を訴えかけているようにも思えた。
但しそうした崇高さだけではなく、「セリオーソ」にしても嬰ハ短調にしても、ハーゲンQはこれらの曲と真摯に対峙して、そこから人間ベートーヴェンの本物の生き様を見い出して提示しているという印象も強く持った。例えば「セリオーソ」では、そこに込められたというベートーヴェンの失恋の痛手の気持ちは、相手への敬意と痛手を乗り越えて先へと進もうとする力強い意思を感じた。
嬰ハ短調では消化不良の演奏も時々見受けられるが、ハーゲンQはこの一見多様でつかみどころのはっきりしない音楽を現世のものとしてしっかりと咀嚼して、全曲を通して明確な定旋律を響かせていた。そのことでこの曲の真の「大きさ」が見えたような気がする。そんなところにもハーゲンQの「成長」を感じ、白状すればこの曲を聴いてまだ本当の感動までは至れていない未熟な自分を高みへと引き上げてくれるかも、とこの先への更なる期待が膨らむ。
~トッパンホール8周年バースデーコンサートシリーズ~
トッパンホール
【曲目】
1.ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調Op.135

2.ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第11番 ヘ短調Op.95「セリオーソ」


3.ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調op.131

これまでに何度か聴いているハーゲン弦楽四重奏団の印象はしなやかさ、柔らかく落ち着きのある音色、それにヨーロッバ的と言いたくなる自然な呼吸など。今回久しぶりにこのカルテットを聴いてそうした印象を再認識したのと同時に、新たな発見というか、しばらく聴かなかった間にまた素晴らしい成長を遂げているのを感じ、本物のアーティストというのはいつまでも同じ場所に安住するものではないと思い知った。
まず感心するのはアンサンブルの緻密さ。息が合っているとか、音色が溶け合っているといった弦楽四重奏に求められる基本のような次元を凌駕した一体感。もちろん各プレーヤーならではの持ち味はある。1曲目のベートーヴェン最後のカルテット出だしの意味深長なヴィオラの問いかけ、ヴェロニカの湿感のある深いヴィオラの響きは聴衆全てがはっとするような印象的なものだが、それに他の3声が唱和してもそのヴェロニカのヴィオラの印象がそのまま持続するのを聴くと、「これがハーゲンQの演奏か」ということになる。第3楽章の前半、4人が一緒のハーモニーを奏でる場面などはひとりのプレーヤーが重音で弾いているかのような一体感。
この作品135はこの世から離れて彼岸にあるような崇高で孤高な音楽と言われ、実際そういう音楽だと思う。簡潔な印象で演奏時間も短いが、そうした特別な音楽であるために演奏会ではプログラムの最後に置かれることも珍しくないが、ハーゲンQはプログラムの冒頭に持ってきた。ハーゲン・クァルテットの演奏するこの曲を聴いていて、浮世離れした演奏ではなく地に足が着いた演奏という印象を持った。
例えば2楽章、4人が一丸となってズンズン進んで行く迫力と臨場感は生き生きとした命が宿る「この世の」音楽だったし、あの天に放たれるような最後の和音をハーゲンは天にではなく、大地にしっかりと足跡を残すようにして終わらせた。全曲を通してハーゲンQが演奏するこの曲は聴く者と同じ大地を踏みしめているような「現実味」を感じた。
それに対して、「セリオーソ」の第2楽章や、最後に演奏したOp.131の第4楽章などからは実に崇高で気高い精神性が伝わってくる。これは、Op.135を天の高みから現実に下ろすことで、血気盛んな「セリオーソ」や嬰ハ短調の曲にもある「崇高さ」の存在を訴えかけているようにも思えた。
但しそうした崇高さだけではなく、「セリオーソ」にしても嬰ハ短調にしても、ハーゲンQはこれらの曲と真摯に対峙して、そこから人間ベートーヴェンの本物の生き様を見い出して提示しているという印象も強く持った。例えば「セリオーソ」では、そこに込められたというベートーヴェンの失恋の痛手の気持ちは、相手への敬意と痛手を乗り越えて先へと進もうとする力強い意思を感じた。
嬰ハ短調では消化不良の演奏も時々見受けられるが、ハーゲンQはこの一見多様でつかみどころのはっきりしない音楽を現世のものとしてしっかりと咀嚼して、全曲を通して明確な定旋律を響かせていた。そのことでこの曲の真の「大きさ」が見えたような気がする。そんなところにもハーゲンQの「成長」を感じ、白状すればこの曲を聴いてまだ本当の感動までは至れていない未熟な自分を高みへと引き上げてくれるかも、とこの先への更なる期待が膨らむ。
















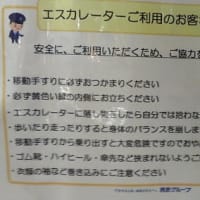









ハーゲンQ大好きなのですが今年は聴きにいけず、拝読して色々想像しました。
ヴェロニカの深い音色、羨ましいです。出産で代役アイリスさんが来日した時以降、聴きに行けていないので。
ベートーヴェンの言及もとても興味深く拝読しました。op125までルートヴィヒ君はまさに「本物の生き様」を見出すべくゴリゴリ頑張ってきたと思うのですが、op126からはだんだんと達観したように内省へ向かう、という印象を持っています。
pocknさんのセリオーソ→131→135のご感想が私のイメージに近くとても共感しました。