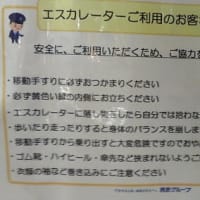5月23日(土)ウィーン国立歌劇場オペラ公演
ウィーン・シュターツオーパー
【演目】
チャイコフスキー/歌劇「エフゲニー・オネーギン」


【配役】
ラリーナ:アウラ・ツワロフスカ Aura Twarowska(MS)/タチヤーナ:タマール・イヴェリ(S)/オリガ:エリザベト・クルマン(MS)/フィリッピェヴナ:マルガレータ・ヒンターマイアー(MS)/エフゲニー・オネーギン:シモン・キーンリーサイド(Bar)/レンスキー:マリウス・ブレンチウ(T)/グレーミン侯爵:アイン・アンガー(B)/サレツキー:マルクス・ペルツ(B)/トリケ:アレクサンダー・カイムバッハー(T) 他
【演出】ファルク・リヒター
【舞台】カトリン・ホフマン 【衣装】マーティン・クレーマー 【照明】カールステン・サンダー
【演奏】
小澤征爾指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団/ウィーン国立歌劇場合唱団

小澤がウィーン国立歌劇場のプルトに立つ姿、これも一度は見ておきたかった。その小澤征爾の指揮でチャイコフスキーの名作オペラ「エフゲニー・オネーギン」を観た。これも初めて観るオペラ。あらかじめあらすじとリブレットの対訳を読んでおき公演に臨んだ。
ベルリン・ドイツオペラでは日本式にステージ上方に字幕が投影されており、字幕システムは今や世界のオペラ劇場でも必須アイテム化している。
大きな拍手に迎えられて小澤がウィーン・シュターツオーパーのオケピットに登場した時はやっぱり感慨深かった。そして始まったオケの前奏、粘り気を含んでたっぷり熱く歌う弦の響きが、この物語の世界に一気に誘ってくれる。このオーケストラの響き、雄弁な語り口とテンションの高さにはまたつくづく感嘆。小澤は日本で聴くとき以上に熱く歌い、軽快に踊り、デリケートに音を織り上げてゆき、この激しいエモーショナルなオペラを鮮やかに形作って行った。
歌手たちの充実ぶりもすごい。最初に登場したラーリナ役のアウラ・ツワロフスカ(Aura Twarowska)とフィリッピェヴナ役のヒンターマイヤーの歌があまりに存在感たっぷりだったので、主役のタチヤーナとオリガと勘違いしてしまったほど。こうして脇役までが主役級の歌を聴かせてしまうところが、ウィーン・シュターツ・オーパーのすごいところだ。
主役たちはもちろん素晴らしい。高鳴る感情を輝かしい声でしなやかに歌ったレンスキー役のブレンチウ、「手紙の場」から聴衆を魅了し続けたタチヤーナ役のイヴェリは、あこがれ、焦燥、熱い思いと次々に湧き出る感情を見事に歌い分け、凛とした芯の通った強さで貫かれていた。
キーンリーサイドの一種近寄り難い威光を放つオネーギンも素晴らしい。幕切れの切迫感と迫力あるタチヤーナとのやり取りや最後の叫びは、聴き手の心を最高潮へと導いた。グレーミン侯爵役のアンガーは貫禄と人間味に溢れる歌、3幕のアリア「誰でも一度は恋をして」は人生の総決算のような立派な歌だった。
ファルク・リヒターの演出はすっきりと焦点の定まった舞台を見せてくれた。この舞台で視覚的に印象付けられたのは、黒が基調の舞台に蛍光色に浮かび上がるオブジェ。これは大きさや配置を変えながら全幕を通していろいろな用途で使われる。そして舞台後方で降りしきる雪。第1幕全部、第2幕での決闘の場、そして第3幕のタチヤーナとオネーギンの最終場で、細かい雪片が後から後から降り続ける情景は、このオペラの「冬」という設定を印象づけるだけでなく、冷たい感情とか、逆に燃え上がる気持ちへの警鐘とか、或いは3幕では過ぎし日への恋慕の情などが呼び覚まされるように感じた。
第1幕と2幕のパーティーではバレエ団を投入してサーカスのアクロバットのような華やいだはじけるような賑やかさを演出したのに対し、第3幕では華やかな音楽とは裏腹に、舞台は極端に動きを抑え、時の経過を印象づけていた。
そのほか視覚的に訴えたのは抱擁しあう何組もの男女の姿。第1幕でオネーギンがタチヤーナの求愛を断る場面では、抱擁しあう男女の男の方が女から次々に離れて行く。ちょっと見え見えの演出だったが、3幕ではそれまで抱擁し合っていたのは若い男女だったのが、どれもが年齢を重ねた姿のカップルに変わっていた。これは実際の時間の経過以上に決定的な隔たりがオネーギンの前に立ちはだかっていることの暗示だろうか。1幕と2幕が休憩なしに上演され、3幕との間で休憩が入ったのもそのためだろう(休憩の場所はそれともこれが定石なのかな?)。
一番ショッキングだったのは決闘の場面。オネーギンがピストルを撃つ直前にリンスキーは自分の拳銃をテーブルに置いてしまった。決闘することが決まり、自分の運命を悟っていることは自ら歌ってもいるが、最初からレンスキーはオネーギンを撃つ気はなかったわけだ…
初めて接するオペラをこうした充実し切った公演で体験できた意味は自分にとっても大きいが、終幕後、ほぼ満席の会場も大いに沸いた。タチヤーナ役のイヴェリが人一倍のブラボーを浴び、レンスキー役のブレンチウは一発ブーイングを食らっていたが、やはり大きなブラボーコール。そして我らが小澤はこの素晴らしい公演をまとめ上げた功績に値するに十分のブラボーを受けていた。日本で出没する「小澤のオペラにブーイングを浴びせ隊」はさすがにウィーンまでは来れないようでホッとしたが、もしこいつらが来てブーを浴びせたら、「ブラヴィッシモーッ!!!」と叫んでやるところだった。
こうした大舞台でスタンディングオヴェージョンで大喝采を受ける小澤の公演を体験でき、大いに満足した!
PS この公演にはセーラー服姿の日本の女子高生達がGalerie席を中心に大勢陣取っていた。学校の旅行でウィーンに来るなんて金持ち!ウィーン少年合唱団と間違えられなかっただろうか…?という冗談はさておき、この高校生達の胸にもきっと感動が刻まれたことだろう。

ウィーン・シュターツオーパー
【演目】
チャイコフスキー/歌劇「エフゲニー・オネーギン」



【配役】
ラリーナ:アウラ・ツワロフスカ Aura Twarowska(MS)/タチヤーナ:タマール・イヴェリ(S)/オリガ:エリザベト・クルマン(MS)/フィリッピェヴナ:マルガレータ・ヒンターマイアー(MS)/エフゲニー・オネーギン:シモン・キーンリーサイド(Bar)/レンスキー:マリウス・ブレンチウ(T)/グレーミン侯爵:アイン・アンガー(B)/サレツキー:マルクス・ペルツ(B)/トリケ:アレクサンダー・カイムバッハー(T) 他
【演出】ファルク・リヒター
【舞台】カトリン・ホフマン 【衣装】マーティン・クレーマー 【照明】カールステン・サンダー
【演奏】
小澤征爾指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団/ウィーン国立歌劇場合唱団

小澤がウィーン国立歌劇場のプルトに立つ姿、これも一度は見ておきたかった。その小澤征爾の指揮でチャイコフスキーの名作オペラ「エフゲニー・オネーギン」を観た。これも初めて観るオペラ。あらかじめあらすじとリブレットの対訳を読んでおき公演に臨んだ。
ウィーン国立歌劇場には前回訪れたとき(2002年)からそれぞれの客席の前に個人用の液晶小型モニターが備え付けられ、ドイツ語の字幕が出るのでとても助かる。 ちなみにドイツ語上演の「ラインの黄金」のときもちゃんと字幕(ドイツ語)が出ていた。 |  |
ベルリン・ドイツオペラでは日本式にステージ上方に字幕が投影されており、字幕システムは今や世界のオペラ劇場でも必須アイテム化している。
大きな拍手に迎えられて小澤がウィーン・シュターツオーパーのオケピットに登場した時はやっぱり感慨深かった。そして始まったオケの前奏、粘り気を含んでたっぷり熱く歌う弦の響きが、この物語の世界に一気に誘ってくれる。このオーケストラの響き、雄弁な語り口とテンションの高さにはまたつくづく感嘆。小澤は日本で聴くとき以上に熱く歌い、軽快に踊り、デリケートに音を織り上げてゆき、この激しいエモーショナルなオペラを鮮やかに形作って行った。
歌手たちの充実ぶりもすごい。最初に登場したラーリナ役のアウラ・ツワロフスカ(Aura Twarowska)とフィリッピェヴナ役のヒンターマイヤーの歌があまりに存在感たっぷりだったので、主役のタチヤーナとオリガと勘違いしてしまったほど。こうして脇役までが主役級の歌を聴かせてしまうところが、ウィーン・シュターツ・オーパーのすごいところだ。
主役たちはもちろん素晴らしい。高鳴る感情を輝かしい声でしなやかに歌ったレンスキー役のブレンチウ、「手紙の場」から聴衆を魅了し続けたタチヤーナ役のイヴェリは、あこがれ、焦燥、熱い思いと次々に湧き出る感情を見事に歌い分け、凛とした芯の通った強さで貫かれていた。
キーンリーサイドの一種近寄り難い威光を放つオネーギンも素晴らしい。幕切れの切迫感と迫力あるタチヤーナとのやり取りや最後の叫びは、聴き手の心を最高潮へと導いた。グレーミン侯爵役のアンガーは貫禄と人間味に溢れる歌、3幕のアリア「誰でも一度は恋をして」は人生の総決算のような立派な歌だった。
ファルク・リヒターの演出はすっきりと焦点の定まった舞台を見せてくれた。この舞台で視覚的に印象付けられたのは、黒が基調の舞台に蛍光色に浮かび上がるオブジェ。これは大きさや配置を変えながら全幕を通していろいろな用途で使われる。そして舞台後方で降りしきる雪。第1幕全部、第2幕での決闘の場、そして第3幕のタチヤーナとオネーギンの最終場で、細かい雪片が後から後から降り続ける情景は、このオペラの「冬」という設定を印象づけるだけでなく、冷たい感情とか、逆に燃え上がる気持ちへの警鐘とか、或いは3幕では過ぎし日への恋慕の情などが呼び覚まされるように感じた。
第1幕と2幕のパーティーではバレエ団を投入してサーカスのアクロバットのような華やいだはじけるような賑やかさを演出したのに対し、第3幕では華やかな音楽とは裏腹に、舞台は極端に動きを抑え、時の経過を印象づけていた。
そのほか視覚的に訴えたのは抱擁しあう何組もの男女の姿。第1幕でオネーギンがタチヤーナの求愛を断る場面では、抱擁しあう男女の男の方が女から次々に離れて行く。ちょっと見え見えの演出だったが、3幕ではそれまで抱擁し合っていたのは若い男女だったのが、どれもが年齢を重ねた姿のカップルに変わっていた。これは実際の時間の経過以上に決定的な隔たりがオネーギンの前に立ちはだかっていることの暗示だろうか。1幕と2幕が休憩なしに上演され、3幕との間で休憩が入ったのもそのためだろう(休憩の場所はそれともこれが定石なのかな?)。
一番ショッキングだったのは決闘の場面。オネーギンがピストルを撃つ直前にリンスキーは自分の拳銃をテーブルに置いてしまった。決闘することが決まり、自分の運命を悟っていることは自ら歌ってもいるが、最初からレンスキーはオネーギンを撃つ気はなかったわけだ…
初めて接するオペラをこうした充実し切った公演で体験できた意味は自分にとっても大きいが、終幕後、ほぼ満席の会場も大いに沸いた。タチヤーナ役のイヴェリが人一倍のブラボーを浴び、レンスキー役のブレンチウは一発ブーイングを食らっていたが、やはり大きなブラボーコール。そして我らが小澤はこの素晴らしい公演をまとめ上げた功績に値するに十分のブラボーを受けていた。日本で出没する「小澤のオペラにブーイングを浴びせ隊」はさすがにウィーンまでは来れないようでホッとしたが、もしこいつらが来てブーを浴びせたら、「ブラヴィッシモーッ!!!」と叫んでやるところだった。
こうした大舞台でスタンディングオヴェージョンで大喝采を受ける小澤の公演を体験でき、大いに満足した!
PS この公演にはセーラー服姿の日本の女子高生達がGalerie席を中心に大勢陣取っていた。学校の旅行でウィーンに来るなんて金持ち!ウィーン少年合唱団と間違えられなかっただろうか…?という冗談はさておき、この高校生達の胸にもきっと感動が刻まれたことだろう。