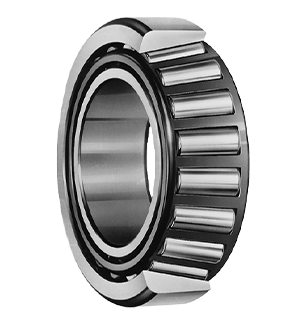さて、本日の記事は・・・自作のタイヤチェンジャーですよ


動画を載せることが出来ればすごく単純に伝わるんですが、ブログの醍醐味?はやっぱり写真なのかな?という事で、かなり多めの写真を載せる事にしました。
まず全容

軽トラの荷台の上に載せた状態で作業がしやすい高さに合わせて制作しました。
ざっと説明しますと、厚さ3㎜・幅300㎜高さ50㎜長さ2000㎜の軽量鉄骨平梁の上にメインポスト(高さ800㎜)とホイールのターンテーブルを配置してあります。
大雑把に(目を細めて)見れば?普及型の一般的なものと似ています。

要所の接写をズラッと貼っておきますよ。

土台にスライドガイドを溶接してあります。蝶ネジで固定できるようにしてあり、軽トラのタイヤサイズにも合うようにマルチな位置で固定できます。
この簡易チェンジャーの肝となるマウントヘッド周りの接写。↓

↑マウントヘッドが写ってますが、これは普通のタイヤチェンジャーにも使う普及型?の物です。
・・・・・何故かアヒルのようなカタチ↓ですが、多分偶然だと思うんですが見れば見るほどアヒルです、ほんとうにありがとうございました。

ヤフオク!で1,980円(送料900円別)でした。

これはターンテーブル?・・・・手動です。

たぶんこの手の回転台は作り出すのは無理だと思い、今回タイヤチェンジャーを自作するにあたって倉庫に放置してあったミニクレーン↓から外して使用しました。

↑の製品の土台部分を使っていますが、意外に精巧な出来でローラーベアリングが奢ってありました。
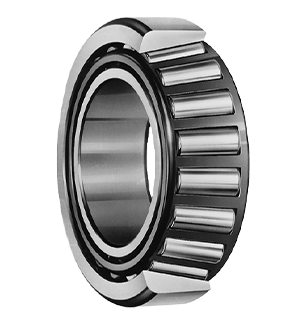
回転は結構スムーズ

※左クリックで動画に飛びます
ホイールの固定方法には悩みまして、自作するなら一番無難なボルトにホイールナットという組み合わせで。

↓マウントヘッドをガッチリと固定する、その上簡単にスイングアップさせるような構造ってのがいまいち判らなかったので、差し当って作りながら様子を見ようという事で、追加のパーツも付けられるような余裕は持たせてあります。

※2022年12月に改修した画像を貼っておきます

改修した結果、アーム固定時のガタツキが解消された。


※2022年12月改修内容→アームを7㎝程度延長。

改修により2㎝程度だったメインマストとタイヤトレッド面のクリアランスが確保された。
このクリアランスはある程度広くないと、外したタイヤがメインマストとホイールの間で逃げが無い。
ここからは作業工程の様子ですよ。
↓既にビード落とし済みのホイール&タイヤをセットしました。

↓大雑把な位置決めが済んだら、アームを固定する蝶ネジを締め込み固定。

セッティングする際の目安がこの隙間でしょうか?ガッチガチに固めたヘッドマウントですが、作業中はホイールに接触する場面も出てくるので、3㎜程度~

↓マウントヘッドの位置が決まったら、回転台も固定します。

↓スポンジでビードワックスを手が届く範囲に塗り込みますが、ビード保護とスムーズな作業の為にはスプレー式のタイプが有ればベスト。

スプレー式のビードクリーム・・・クリームか? とは思いますが
※下記写真を左クリックで楽天の売り場に飛びます

↓ナイロン製のビードヘルパーを嵌めておきます。ホイールのクビレにビードを落とした位置で固定できるので、以降の作業がとても楽になるのです。


↓ヘッドの通称「アヒルの嘴」に沿わせてタイヤレバーを差し込み

↓アヒルの頭にビードを乗せれば大方の作業は終わりって感じです。

↓時計回りにタイヤを回していくんですが、重い・・・

↓アウトサイド側が外れ、インサイド側のビードを浮かせながらレバーでアヒル頭に載せる準備

↓アウトサイド側とは違いインサイド側は、そのまま回してもビードは乗ってこないので絶妙な形の木片を挟み、ビード落ち止めとして使用


↓はい、終わりです~

さて、ここからは組付け作業になります。
準備するものが予め決まっているわけではないのですが、新品のバルブは最低限準備します。専用の工具があるので、あっと言う間に交換完了です。

ホイールのリムやマウントヘッドに接触する部分には入念にビードワックスを塗りつけます。

↓タイヤ交換の動画を観てると、インサイド側は揺すりながら押し付けていくとヌルッと入っちゃうのは有ります。
BSの55扁平ではそう簡単でもないのですがビードクリーム多めで充分滑る状態にしておけば、外す時に比べるとあっけないほど簡単に嵌るのです。

※新品タイヤに付いてる黄色いマーク(軽点)をバルブ位置と合せて組むようにはしてますが、中古だとかすれて見えない事もあり、気休め程度のものと思って良いです。詳しく説明してくれるサイト→https://tire-navigator.com/archives/9944
アウトサイド側の嵌め込み。
外す時に使ったビードヘルパーを嵌め、ホイールのクビレにビードを落としてあります。バルブの内側が痛まないように色々考えながら手探りの作業・・

とてもスムーズに作業終了です。外す時はビードクリームが上手く塗布できてない部分があり滑りが悪く難儀しましたが、嵌めるのはあっと言う間でした。

遂に組み込み作業が終わり、後はビード上げです。虫ゴムを外した状態で普通にエアーを入れていくと、じわりじわりとビードがリムに寄ってきて、最後は「バンッ!」って音と共にビードが上がります。

これで一本完成・・・・約5分ほどの作業時間が掛るんですが、体力が結構要るので、休み休みですよ。
※2022/12/7追記
ビード上げ作業の様子を約1分にまとめた動画
クリックでyoutubeに飛びます。

ざっと画像だけ貼りましたが、なるべく早めに作業のポイントなどを書き込んでいくので、興味が有る方は後日再度この記事を見てみてください。
ではっ
次の関連記事↓
※1/4追記
組み終わってから一週間程経ち、エアーチェックしてみて漏れがない事は確認できました。
バランス取りは、当初スタンドにでも持って行ってやってもらおうと思ってたのですが、まあここまでやるなら自分でやってみようか?という事で、簡易バランサー買おうと思います。
高速でブレないように出来れば差し当って合格なんだろうか?
※3/20追記
春到来で道路もほぼ出たので、真冬用の新しいスタッドレスを外して、上記で組んだ7年落ちGZを今現在履いています。
バランスを簡易バランサーで見てみたのですが、4本とも古いウエイトを全部剥がした状態で気泡がセンターから外れてなかったので、そのまま走ってみましたよ。
振動は感じられません・・・・1○○㎞/hまで出してみましたが、全ての速度域でも振動は無し。
偶然それほどバランスが崩れていなかったんでしょうかね?
※2020/8/21追記
夏タイヤの交換時期だったので、追記しますが・・・・ポテンザのS001を外そうとした結果、残念ながらビードが上手くマウントヘッドに乗らなくて、ギブアップ。



一応セオリー通りビード落とし・ホイールのくびれに行くようにヘルパーも3つ噛ましたんですが、アヒルの頭にビードが乗らない。チープなレバーが曲がって曲がってもうね、全然作業が進みませんでした。
結局、外すのはスタンドでやってもらって、この度購入したプレイズのPX 205/55/16を自力で履かせるという作業です。
今回は動画を撮ったので貼っておきます※画像をクリックでyoutubeに飛びます。

関連記事
あと、令和4年追加の見た事が無いタイプのビードブレーカー製作過程
※画像クリックで当該記事に飛びます

自作ビードブレーカーの作動状況動画
※画像クリックで当該記事に飛びます

※令和3年10月31日追記
最近のyoutubeやヤフオクで見かける事が多くなったギアレンチを利用したアダプターに興味津々!
うちにもギアレンチは有るので、アマゾンで6,000円出して新品買うか持ってるのを使うか悩みます。
今のところ、大抵のアダプター商品に付いてくるのは この手。
この手。

アマゾンで5,170円で購入可能。→https://www.amazon.co.jp/dp/B01MRFJMQE
例えば、これをウチのあまり見た事のないタイプのチェンジャーに使うとしたら、ターンテーブル(笑)に大きいホールソーのような形状の下向きギアを付けて、横方向からギアレンチで回す・・・的な使い方が考えられますが、このギアレンチってのが58倍とかなので、手で回すとするととても大変。
ただし、イメージというか発想の転換的なものは頂けました。

 の油圧ジャッキを使ってるようです。
の油圧ジャッキを使ってるようです。