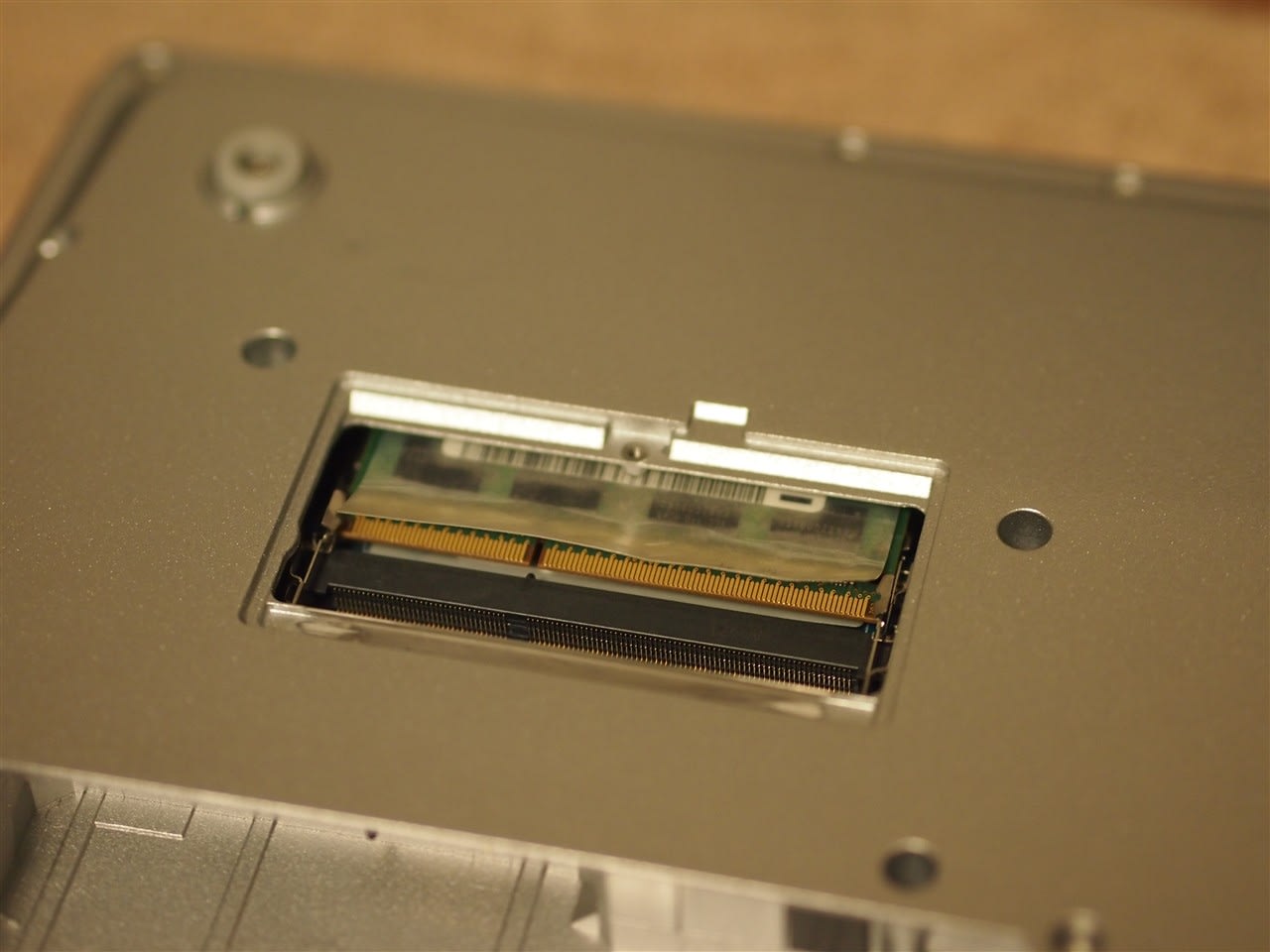22.12.11 NHK New Web記事: 「月着陸船」ロケットから分離 世界初“民間”で月目指す
2022年12月11日 19時33分
NHK 総合午後7時のトップニュースとして,本記事内容が流されましたので,記録しておきます.
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221211/k10013919911000.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
世界初の民間による月面着陸を目指す東京のベンチャー企業が開発した月着陸船を搭載したアメリカのロケットが日本時間の11日夕方打ち上げられました。月着陸船は47分後にロケットから切り離され、打ち上げは成功しました。
民間による月面着陸を目指しているのは、東京のベンチャー企業「ispace」(アイ・スペース)です。
自社で開発した無人の月着陸船をアメリカの民間企業「スペースX」のロケットに搭載し、日本時間の11日午後4時38分にフロリダ州の発射場から打ち上げられました。
月着陸船は47分後にロケットから切り離され、打ち上げは成功しました。
計画では地球から38万キロ離れた月に向かって航行し、来年4月末に月への着陸に挑む予定で、成功すれば、世界で初めて民間だけで月面着陸を成し遂げることになります。
月着陸船には、JAXA=宇宙航空研究開発機構などが開発した小型ロボットなどが搭載され、月面探査をはじめ、さまざまな技術の実証が行われる予定です。
月は近年、水の存在を示す研究論文が相次いで発表されるなど、人類が宇宙での活動領域を広げる上で拠点となる場所に位置づけられ、アメリカが進める国際的月探査プロジェクト「アルテミス計画」など国家間の競争が激化しています。
これに伴って、民間企業の間でも地球周辺にとどまっていた宇宙の商業利用を拡大しようとする動きが見られ、今回の打ち上げが、月を舞台にした新たなビジネスの布石となるか注目されます。
関係者など約60人が配信映像を見守る
東京 日本橋の会場には、月着陸船を開発した「ispace」の関係者などおよそ60人が集まり、配信される映像で、打ち上げを見守りました。
そして、午後4時38分、月着陸船を搭載したロケットが打ち上がると拍手したり肩を組み合ったりして喜んでいました。
さらに、その47分後、月着陸船がロケットから切り離された映像が流れると、会場からは大きな歓声があがり、ガッツポーズしたり、拍手したりする姿も見られました。
開発した企業の代表「美しい打ち上げ」
月着陸船を開発した「ispace」代表、袴田武史CEOは、アメリカ・フロリダ州からオンラインで会見し、「スペースXのロケット打ち上げを間近で見ることができ、非常に美しかった。月面着陸までの間、1つ1つ学びながら次のミッションなどに反映させていきたい」と話していました。
月着陸船の構造 開発したベンチャー企業「ispace」とは
【月着陸船の構造】
今回打ち上げられた月着陸船は、底面と上面が八角形の「八角柱」に近い形をしていて、着陸時に衝撃を緩和する機能が付いた細い支柱4脚で支えます。高さはおよそ2.3メートル、幅はおよそ2.6メートルで、重さは燃料を入れない状態で340キロほど。推進装置が底面を中心に装着されていて、方向転換や姿勢制御のほか、着陸の時などにも使用されます。側面には、太陽光パネルが貼り付けられているほか、放射線のダメージを防ぐとともに氷点下170度から110度まで耐えられる設計です。上面には通信機器やカメラが設置されていますが、積み荷は最大30キロまで搭載可能です。
【搭載されている荷物は7つ】
月着陸船には、JAXAなどが開発した月面で走行し、画像データを取る変形可能な小型ロボットのほか、発火のリスクが低く、低温や高温の環境でも動く電池など7つの荷物が搭載されています。
【「ispace」とは】
月着陸船を開発したのは、東京に本社を置くベンチャー企業「ispace」で2010年9月に設立しました。アメリカのIT企業、グーグルなどが開いた民間で競う「月面探査レース」にチーム「HAKUTO」として出場し、月面探査車を開発。最終選考まで残りました。その後、無人の月面探査車とともに月に送り込むための着陸船の開発計画を引き継ぎ、今回の打ち上げを成功させ、月面への到達を足がかりに宇宙の商業利用を拡大し、ビジネスにつなげたいねらいです。
【スピード感重視の開発体制】
月面着陸を成功させるうえで、着陸船の向きや姿勢を自動で制御できるシステムはなくてはならない技術の1つです。ところが、JAXAをはじめ日本はこれまで探査機を月面に降り立たせた実績がなく、すべてを純国産で開発するには多くの時間と費用がかかることが予想されます。代表の袴田武史CEOは、かつて出場した「月面探査レース」などでの経験を踏まえ、「アポロ計画」で実績のあるアメリカの研究機関とともに開発を進めてきました。すでに確立された技術を活用することで、民間ならではのスピードとコストを優先した開発体制を整えながら、今回の打ち上げにこぎ着けました。
【売上総額100億円に】
企業は、今回の月着陸船の打ち上げに加え再来年には月面を走行する探査車を着陸船に搭載して、ロケットで打ち上げる計画です。さらに2025年には、アメリカの研究機関などと共同で月面に荷物を運ぶサービス自体をNASAに提供する予定で、これらの売り上げは合わせて100億円ほどだということで、今回のミッションなどを通じて、技術の実証や事業モデルの確立を図りたい考えです。
打ち上げに使われたロケット「ファルコン9」とは
東京のベンチャー企業が開発した「月着陸船」は、アメリカの民間企業、「スペースX」の商業用ロケット、「ファルコン9」で打ち上げられました。
【ロケット諸元】
「ファルコン9」は全長70メートル、直径3メートル70センチある2段式のロケットです。燃料は、家庭の暖房でも使われる灯油の一種「ケロシン」で、液体酸素とともに燃焼させます。大きな特徴は、「再使用できる」点です。打ち上げ後に切り離した1段目ロケットを着地点に誘導し、垂直に着陸。商業衛星のほか、国際宇宙ステーションへの有人宇宙船や補給船の打ち上げで実績を積み重ねています。
【月探査の打ち上げ実績あり】
このうち、月探査に関係するものとしては、2019年2月にイスラエルの民間団体が開発した月面探査機や、ことし8月に韓国の宇宙機関が開発した月を周回する探査機を打ち上げています。
【過去の失敗は2回】
文部科学省によりますと、「ファルコン9」はことし9月までに175回打ち上げられ、173回が成功しています。過去に失敗したのは2回で、2015年6月、打ち上げから2分後にロケットが爆発したほか、2016年9月には、打ち上げ2日前、エンジンの燃焼試験中に爆発し搭載していた人工衛星が失われたケースです。
ロケット分離から月着陸までの流れ
月着陸船は「ファルコン9」に搭載され、日本時間の11日午後4時38分に、アメリカ・フロリダ州の発射場から打ち上げられました。
【ロケットから分離後の流れ】
打ち上げのおよそ47分後にロケットから切り離され、その後、地上との通信を確立。姿勢が安定しているかや電源が供給されているかなどを確認します。月着陸船から送信された電波はヨーロッパの宇宙機関が運用する地上のアンテナで受信したあと、東京・日本橋にある「ispace」の管制室に送信されます。管制室で運用を担当するのは海外の宇宙機関出身のエンジニアなどで、月着陸船の状況を確認し必要な操作を行います。
【燃料節約のため“遠回り”】
月は、地球のまわりを回る衛星で、およそ38万キロ離れていますが月着陸船は直接月には向かわず、いったん地球からおよそ150万キロのエリアまで遠ざかります。これは燃料を極力節約するためで、この間、安定した飛行ができるかも確認する予定です。そして、打ち上げのおよそ3か月後、今度は太陽の重力を利用しながら月に近づき、打ち上げのおよそ4か月後に月を周回する軌道に入り、月面着陸の準備に入ります。
【着陸方法は】
ここまでミッションが順調に進めば、いよいよ月に着陸します。ガスを噴射して速度を落としながら徐々に月面に接近。月面に対して垂直になるよう姿勢を調整し、最終的には4つの脚で着地の衝撃を緩和させながら降り立つ計画です。着陸を想定しているのは、月の北半球にある「氷の海」と呼ばれる場所の近くで、月面で通信と電力の供給を確かめた後、搭載した機器の技術実証などを行う予定です。
月探査 国や民間の競争が激化
月は近年、水の存在を示す研究論文が相次いで発表されるなど、人類が宇宙での活動領域を広げるうえで拠点となる場所に位置づけられたことで、月探査をめぐる国や民間の競争が激しくなっています。
【欧米日の月探査】
月探査に向けた動きの1つが、アメリカが日本やヨーロッパなどと進める国際プロジェクト「アルテミス計画」です。先月16日に、月を周回する無人の宇宙船を大型ロケットで打ち上げ、計画の第1段階に入りました。2025年には、水が氷の状態で存在すると指摘されている月の南極付近に宇宙飛行士を降り立たせ、燃料として利用できるかを探る予定です。日本ではこのほか、JAXAの無人探査機「OMOTENASHI」が日本初の月面着陸を目指すも成し遂げられず、来年度、「SLIM」という探査機で月を目指します。
【中国とロシア】
また、中国はおととし、月の岩石などを地球に持ち帰ることに成功し、今後はロシアとともに月面などでの研究拠点の建設に向けた取り組みを行うとしています。
【民間も機運高まる】
国家間の競争激化に伴って、民間企業の間でも月をビジネスの舞台とする機運が高まり、2019年にはイスラエルの民間団体が月面着陸に挑みましたが、失敗に終わりました。ほかにもアメリカの複数の企業が月着陸船の打ち上げを計画していて、東京のベンチャー企業「ダイモン」が開発した小型の月面探査ロボットも搭載されることになっているなど、民間の動きも活発化しています。
【月ビジネスの市場規模は】
月面や月周辺での経済活動について、「PwCコンサルティング合同会社」は、2030年ごろから建設やインフラ整備、農業、エネルギー分野などの事業が増えると予測しています。そのうえで、月探査に関連する経済活動の市場規模は2040年までに合わせて1700億ドル、日本円でおよそ23兆円に成長する可能性があるとしています。
【ビジネスの舞台になるか】
一方で、宇宙の商業利用を月にまで拡大するには、技術的にも経済的にもさまざまなハードルを乗り越える必要があります。月の重力は地球のおよそ6分の1ですが、小惑星に比べると大きく、これまで民間の力だけで探査機を月面着陸させた例はありません。月探査は事業としての不確実性が大きく、月で新たなビジネスを展開するには、国も民間も商業利用についてのビジョンを明確化するとともに、開発コストをどう確保するかが課題となります。