私たちは、「玉造温泉(たまつくりおんせん)」の旅館の一つ「佳翠苑皆美(かすいえんみなみ)」というところに二泊しました。
玉造温泉とは、玉湯川の両脇にいくつも立ち並ぶ旅館の温泉のことです。
川の水は当然のこと冷たいですが、囲われた中に温かい(熱い?)足湯とかあります。旅館を出て近くを散策したいなあというときには、足ふきタオルを忘れずに。私はハンカチで拭いちゃった(笑)
父は、同じことを何回も言うくせがありますが、佳翠苑皆美は、いくつもある旅館のうち、口コミで1番らしいです。やったぜ☆☆☆☆☆(確かに、すごく丁寧な旅館だった。)
宿にあった、温泉ものがたりというのを引用して説明します。
1.昔むかし、玉造に猟師の湯乃助さんという人がおりまして雪の日に、山の中でまっ白に輝く鹿からお告げを聞いたそうです。翌日、お告げのとおり家の近くの一カ所だけ雪の積もっていないところがあり、そこを掘っていくと熱い湯がこんこんと湧き出しました。これが、玉造温泉のはじまりです。
2.今から約千三百年前、奈良時代に書かれた書物「出雲国風土記」に「神の湯」として玉造温泉のことが記されています。老若男女が集まり、にぎやかに湯浴みをする様子が生き生きと描かれ、また、温泉の美肌効果、健康増進効果が名調子で謳いあげられています。
佳翠苑皆美の源泉「神の湯」↓↓
あっついタオルをしぼって顔を拭きます。
クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

3.平安時代になると玉造温泉の名は京の都にも伝わり、清少納言の「枕草子」にも、玉造温泉の名があらわれています。わが国を代表する温泉として、
「湯は七久里の湯、有馬の湯、玉造の湯」
と記されています。
※七久里の湯は現在はどの温泉か諸説あり、はっきりとはわかりません。
(4以降は省略します。)
佳翠苑皆美には、1階と、別館9階に温泉があります。
料理がめちゃくちゃ美味しいです。
どっちかというと海の幸です。
「十六島海苔」の「十六島」ってなんて読むと思いますか? 「うっぷるい」って読むんです。アイヌ語または朝鮮語らしいです。
また、「あごのつみれ」もありました。
「車海老のグリル」もありました。
「鮭のグラタン」もありました。
「蜆すまし(2日目)」も、
「蜆ちゃづけ(1日目)」も、ありました。
「蜆」は「シジミ」と読むんですよ。
ただ、茶碗蒸しは得意じゃないみたいでした。
(私は茶碗蒸しオタクです(笑))
旅館で働くのが仕事としている人が多いのか、玉造温泉駅近く・玉湯川沿いには、ランドセル背負った小学生がけっこういました。
川辺の足湯↓↓
ベジアイスを食べながら。
クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

こういうスポットもあります↓↓
クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

佳翠苑皆美の朝ごはんのバイキング。(バイキング以外に和定食もあります。)
自分でよそうココナッツアイスがあって超感激。
シジミのお味噌汁をよそってくださるこのみち25年のおばあさん↓↓
クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

2日目と1日目では、お菓子箱の中もがらっと変わっていました。
薔薇の花を浮かせるハーブティーもあります。
では、玉造温泉編は終わります。
玉造温泉とは、玉湯川の両脇にいくつも立ち並ぶ旅館の温泉のことです。
川の水は当然のこと冷たいですが、囲われた中に温かい(熱い?)足湯とかあります。旅館を出て近くを散策したいなあというときには、足ふきタオルを忘れずに。私はハンカチで拭いちゃった(笑)
父は、同じことを何回も言うくせがありますが、佳翠苑皆美は、いくつもある旅館のうち、口コミで1番らしいです。やったぜ☆☆☆☆☆(確かに、すごく丁寧な旅館だった。)
宿にあった、温泉ものがたりというのを引用して説明します。
1.昔むかし、玉造に猟師の湯乃助さんという人がおりまして雪の日に、山の中でまっ白に輝く鹿からお告げを聞いたそうです。翌日、お告げのとおり家の近くの一カ所だけ雪の積もっていないところがあり、そこを掘っていくと熱い湯がこんこんと湧き出しました。これが、玉造温泉のはじまりです。
2.今から約千三百年前、奈良時代に書かれた書物「出雲国風土記」に「神の湯」として玉造温泉のことが記されています。老若男女が集まり、にぎやかに湯浴みをする様子が生き生きと描かれ、また、温泉の美肌効果、健康増進効果が名調子で謳いあげられています。
佳翠苑皆美の源泉「神の湯」↓↓
あっついタオルをしぼって顔を拭きます。
クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

3.平安時代になると玉造温泉の名は京の都にも伝わり、清少納言の「枕草子」にも、玉造温泉の名があらわれています。わが国を代表する温泉として、
「湯は七久里の湯、有馬の湯、玉造の湯」
と記されています。
※七久里の湯は現在はどの温泉か諸説あり、はっきりとはわかりません。
(4以降は省略します。)
佳翠苑皆美には、1階と、別館9階に温泉があります。
料理がめちゃくちゃ美味しいです。
どっちかというと海の幸です。
「十六島海苔」の「十六島」ってなんて読むと思いますか? 「うっぷるい」って読むんです。アイヌ語または朝鮮語らしいです。
また、「あごのつみれ」もありました。
「車海老のグリル」もありました。
「鮭のグラタン」もありました。
「蜆すまし(2日目)」も、
「蜆ちゃづけ(1日目)」も、ありました。
「蜆」は「シジミ」と読むんですよ。
ただ、茶碗蒸しは得意じゃないみたいでした。
(私は茶碗蒸しオタクです(笑))
旅館で働くのが仕事としている人が多いのか、玉造温泉駅近く・玉湯川沿いには、ランドセル背負った小学生がけっこういました。
川辺の足湯↓↓
ベジアイスを食べながら。
クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

こういうスポットもあります↓↓
クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

佳翠苑皆美の朝ごはんのバイキング。(バイキング以外に和定食もあります。)
自分でよそうココナッツアイスがあって超感激。
シジミのお味噌汁をよそってくださるこのみち25年のおばあさん↓↓
クリックで拡大↓(戻るときは×を押さないで戻る矢印← を押してね)

2日目と1日目では、お菓子箱の中もがらっと変わっていました。
薔薇の花を浮かせるハーブティーもあります。
では、玉造温泉編は終わります。















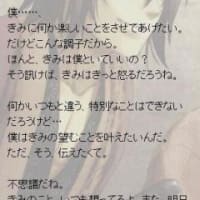

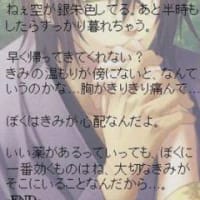

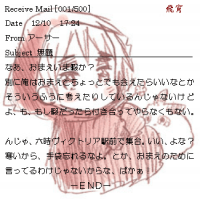

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます