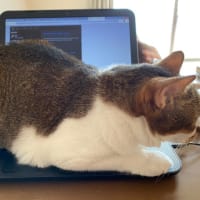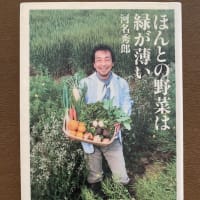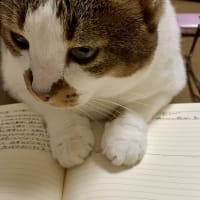今日の岡山城です。岡山城は大規模改修中の休館中です。それに伴って、つい最近まで天守は足場で囲われていて見えなくなっておりましたが、近頃その囲いも取り払われて「烏城」と言われたその漆黒の姿を見せてくれています。
昔の書物で読んだのですが、この辺りには「三つの山」があってそれぞれ、「天神山」「石山」「岡山」という名で呼ばれていたそうです。始まりは豊臣家の五大老の一人である宇喜多秀家の父の直家が「石山」にあった城に入城し改修、その後、秀家が「石山」の隣の「岡山」に城を築いたのが岡山城の始まりとされています。関ヶ原の後、宇喜多氏は改易され、小早川家、そして維新まで池田家を城主としてこの地は繁栄します。
その岡山城ですが、天守は今から77年前の1945年(昭和20年)6月29日の午前2時43分から午前4時7分にかけての米軍機による岡山大空襲で焼失します。以前近くの喫茶店でお会いした90歳のご老人から当時のことをお聞きしたことがあります。「火が天守に燃え移って、あれはさながら“落城”という感じだったよ。」とおっしゃっていました。
米軍の空襲リストには全国180カ所の都市が記載されています。岡山はその31番目でした。空襲では市街地の約73%が焼け野原となり、1,737人 の方々が亡くなられました。
掲載の写真は旭川にかかる相生橋からの眺めです。向かって右側の木々の奥が日本三名園のひとつの後楽園です。写真のちょうど真ん中辺りになるかと思いますが、岡山城を望む旭川の岸に昭和天皇の歌碑が建っています。
きしちかく烏城そびえて旭川ながれゆたかに春たけむとす
昭和42年、岡山県の植樹祭に天皇・皇后おそろいでご臨席の際に旭川を詠われたお歌です。その前年の昭和41年に岡山城は再建されました。御製からは、岡山城を再び目にされた昭和天皇の感慨とお喜びが伝わってくるようです。