3回目を最前列で観て、思い切って千秋楽を観に行って(17列目下手)その後いろいろなことを考えておりました。
演技や台詞から次々に湧き出てくるインスピレーション…それは連想であり、空想や推測でもあり、東京公演が終わった後も私の脳内ではクリスチャンの音楽や歌とともに『無伴奏ソナタ』の世界が途切れなく続いているような不思議な感覚でした。
一場面の芝居に含まれてる(と感じた)情報がとにかく多くて、一人の台詞や演技の奥に見えない物語がいくつもある気がします。多分キャラメルボックスならではの原作潤色や役者さんの個性も相まって、私の目に映る『実写化・無伴奏ソナタ』の世界がより鮮やかで豊かになっていたのかもしれません。シーンごとに心に浮かんだことを書き出していくと、とんでもない長さになりそうですが(苦笑)ゆっくり記憶の書庫を歩き回りながら書き綴って行きたいと思います。

『無伴奏ソナタ』 総括 その1
われわれが自由でありうるために、
われわれ全員が法律の奴隷となる。
(マルクス・トゥッリウス・キケロ)
暗転の中に響くオープニングの鐘の音。ドイツ滞在中に朝夕親しんでいる「あの音」と同じだ、と気づく。教会から高らかに鳴らされる鐘は、時に祝福であったり、時に哀悼であったり…日々の暮らしに空気のように寄り添って「時」を告げていく。
ひんやりとした夜明け前を思わせる、暗く青い照明に浮かび上がる舞台。黒一色の衣装を着た人物の影。まるで墓地に佇む会葬者だ。あたかも「誰かの葬送」に私自身が立ち会っているかのような錯覚に陥った。
これは…ひょっとしたら、クリスチャン・ハロルドセンの葬送なのかもしれない。
まだ物語は始まってもいないのに、彼の人生に起きてゆく出来事を「何もかも分かっている」観客――私はそう思った。
鐘の音が消えていく。青白い光の中で黒い人影がひとり、またひとりとベルを鳴らす。水滴の落ちるような澄んだ音色。ひときわ高い音のベルは、クリスチャンの手に握られている。周囲で鳴り響く澄んだベルの音は、先ほどまでの葬送のイメージとは真逆に、クリスチャンの「誕生」を告げているようにも聞こえてくる。
間近で見るクリスチャン(=多田さん)、初回で私は正直「この人の演技のイメージが根底から変わった!」と衝撃を受けた。本当に圧倒的だった。この瞬間、たった数メートルの距離で、どこか生命を感じさせないようなふわりとした存在感の彼を見て、逆にゾクリとするほどの迫力を感じた。何かが憑依している…役者が「演じて」いるんじゃない、今ここにいる彼は「クリスチャン・ハロルドセン」だとしか思えない。これまで観た3本の作品のどれとも違う。完全に「生きて」存在していた。私は文字通り目が離せなかった。
人影がクリスチャンを取り囲み、周囲を巡り、迫り、去っていく。
舞台前方に歩を進めるクリスチャン。
下手に立つ長身の人影は、沈黙したまま「見守っている」。
チリーン…
一人佇み、どこか寂しげにベルを鳴らすクリスチャンの背中を見送ると、「人影」が大きく腕を振り上げた。バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ」――この物語の主題が流れ始める。
陳腐な言い方かもしれないが、「運命の輪が廻り始める」この瞬間がとても好きだ。
そしてここから始まるクリスチャンの人生を思い返し、早くも胸が詰まった。
☆
≪音合わせ≫
やっぱり近くで観ると違う!何でも前方列が良いというものではないが、やっぱり声や動きの伝わり方は(生身なだけに)迫力がある。父の決断も、母の愛も、政府の人間の傲慢さや葛藤までも、手のひらに掬い取れそうな細やかさとリアルさでひたひた伝わってくる。短いシーンなのに全ての人間にちゃんと背後のストーリーがある。原作では「時系列で事実(とSF的世界観)を淡々と述べていく」あの部分が、こんなにも人間同士の生臭いぶつかり合いになるということに、改めて驚く。
ハロルドセン夫妻の職業は「プレイヤー(演奏者)」である。父がヴァイオリニスト、母はピアニストという設定だ。この「条件」が、クリスチャンの波瀾に満ちた人生の中で形を変えながら何度も顔を出す。このあたりも脚本・演出ともに「上手いなあ」と唸った。
クリスチャンの父親・リチャードの配役が石橋さん=「ウォッチャー」であることがまた暗示的だと思う。リチャードの登場場面はここだけだが、彼は姿を消しても物語の中で基調音のひとつとして存在し続ける。「父性」…それを最終局面の「ウォッチャー」の中に見出した時、あれほど驚愕し同時に涙した理由は、私の中にこの冒頭場面のリチャードがちゃんと残っていたからに他ならない。
クリスチャンの母親・カレン(=大森さん)が必死に政府の女性検査官・ジャニス(=岡田さん)に食い下がるシーンは、女性・イコール・母性でないことを面白いほどに見せつけてくる。自らのミッションに忠実、冷静かつ理論的なジャニスのほうが、観ている私には「より理解できる」存在だ。彼女の言うことは「正しい」。非の打ちどころ無く正しく、クリスチャンが「幸せになるために」何が最も必要で、何に最上の価値を置くべきなのか、全くブレていない。だからと言って我を忘れて取り乱すカレンが愚かに見えるかというと、決してそうではない。カレンの姿に「理屈ではない」人間の、そして母親の愛情を私は見ていた。父親と同じように、母カレンの面影は別の形でクリスチャンの意識と無意識の中で生き続ける。←台詞だけでなく後述の「ある場面」で気づいてまた打ちのめされた…。
一歩控えて彼女たちを見つめる検査官・ギルバート(=左東さん)の、仕事とはいえやるせない悲しみやカレンへの同情を隠しきれない表情が、その時の私の感情にモロにシンクロする。きっと「メイカー」と認定された子どもの親たちの歓喜や愁嘆を見続けてきたのだろうと、ふと彼の背景にまで想いをめぐらしてしまうほどに。
クリスチャン本人が登場しない場面で、もっと言うなら全員が「キャラメルボックス版オリジナルキャラクター」であるにも関わらず、これほどに濃いものができるのか!と。原作を知らなくても、もちろん素晴らしい舞台だと思うが、原作既読だからこそ、新鮮な驚きに(話の筋とは別に)ワクワクさせられる。
ちなみにここまでの短い間にもちゃーんと笑いのネタを仕込んでくるのが、いかにもキャラメルボックスらしい。過剰だと原作の雰囲気を損なうので、私的にはこのくらいで十分!淡々とした物語の程よいスパイスになっていたと思う。
☆
≪第一楽章≫
語り手は「ハウスキーパー」のオリヴィア(=岡内さん)。いささかハウスキーパーらしからぬ性格設定で戸惑うが、観客視点に近い立場として「メイカー」の特殊性や、クリスチャンがいかに一般市民の生活とはかけ離れた「ルール」の中で生きているのかを説明するには、あのくらいでないと「足りない」のかもしれない。
ここでようやく主役登場、30歳になったクリスチャンが目の前に現れた。
随分若く見える。友人が「年齢不詳」と評したのも頷ける。
冒頭の浮世離れした「無生物感」とは真逆の、ちょっと頼りなげな線の細い青年。
音楽の天才と言っても、彼の心はおそらく「無垢な子どものまま」…世俗との関わりの一切を断たれ(それを疑問に思った時期はあったにしても)自らの才能に絶対の自信を持ち「特権階級としての恩恵」を受け入れている。疑うこと、嘘をつくこと、誰かを欺くことなど思いも寄らない、素直な笑顔がとても愛らしい。およそ負の感情と無縁に生きて来たであろう彼の存在感は一種独特で、世の中にこんな人間がいるのだろうか?というオリヴィアの思いを私も客席で共有していた。
不思議な「楽器(Instrumentと原文には表現されている)」で不思議な「曲」を奏でるクリスチャンの表情は嬉々として、時に恍惚とした喜びさえ浮かべて、子どもが無心に玩具と戯れる姿にも似ていた。青い背景に銀色の五線譜が光り、クリスチャンと「楽器」の足元には、曲調に合わせて様々な色の光の輪やきらめきが生まれ、消えていく。劇場に芝居を観に来たはずなのに、どこかのホールで音楽を聴いているような浮揚感。その間にも、オリヴィアは彼女の目から見たクリスチャンを語っていたが、私の目はクリスチャンに引き寄せられたままだった。
★
第一楽章ではもう一人のキャラクターが、実は私のお気に入りである。政府職員で「メイカー」の管理者・ポール(=畑中さん)。前の場面に出てきた政府職員たちとは雰囲気を異にする、エリート臭さはあっても底抜けに明るくて、ちょっとお調子者の好青年。クリスチャンとは5年の付き合いだと言っているが、外の世界を知っているせいか?彼よりはやや年上にも見える。音楽という伴侶があったとはいえ、孤独な生活を送るクリスチャンにとっては「(前任のハウスキーパーを除いて)唯一の友だち」であり、どこか兄のように思える存在だったかもしれない。
ピシリと着こなしたスーツ姿で、オリヴィアに悪童めいた揶揄を投げかけ、クリスチャンの体調を滑稽なほど真剣に心配し、音楽を聞いて軽やかに踊り出す。何とも人懐っこい愛嬌のカタマリで、クリスチャンの「本人の意識しない部分での可愛らしさ」と好一対、どうにも憎めない。舞台上で楽しげに動き回る姿を見ていると、愛らしさに思わず頬が緩む。だが、やはり彼もまた「法律」の守り手であり、その「仕事」に対しての考えもまた、ラストで明かされるのだが。
彼らは原作にはここまでの「設定」を伴って登場しない。オリヴィアは相当の脚色、ポールは存在そのものが完全に舞台オリジナルだ。とても人間臭く、とても我々に近い。だからこそ「特別な者」としてのクリスチャンが一人になった時に見せる苦悩が際立つのだろうか。
★
クリスチャンの「幸せな日々」に混乱と終焉をもたらす「リスナー」の男(=小多田さん)、彼が手渡したバッハの録音は、クリスチャンの母カレンによると、奇しくも両親が学生時代に知り合うきっかけとなった曲(=「無伴奏ソナタ」)だった。ヴァイオリニストの父リチャードは、クリスチャンと過ごした僅か2年の間に、家でその曲を弾いただろうか?クリスチャンの記憶の奥底に、母のかぼちゃスープの味と同じように、父のヴァイオリンも、残っていたのだろうか。
ところでこの「リスナー」…彼は1年間ずっと森に通いクリスチャンの音楽を聴いていた、と語った。彼の音楽に魅入られ、熱狂し、それだけでは飽き足らず、禁を犯してクリスチャンに話しかけ、あろうことか「他人の音楽」を聞かせようとする。他の「リスナー」たちは「メイカーの音楽を評価する」本来の仕事に忠実だったが、この男だけは全く違う。狂気に似た情熱でクリスチャンの才能に関わろうとする。
バレなければいい。分からなければいい。模倣しなければいい。
バッハを聴けば「君に欠けているものが分かるはず」だ、と彼は言った。
彼は一体…何がしたかったのだろうか?
クリスチャンの才能を愛するあまりに、「足りない」ことが許せなくなった?
それを自分が直接に関わることで「クリスチャンの音楽を完璧にしたかった」?
だとしたら何という傲慢さだろう。しかし、私は「リスナー」だけを責めることはできなかった。どうするか決めるのはクリスチャン自身。かつて父が母にそう諭したように。閉ざされた森という名の楽園で、人の形をした蛇がバッハという林檎を持ってきても、その誘惑に堪えることができるか、できないか…クリスチャンの音楽への欲望は、きっと耐えられない。話の筋が分かっていても、私は胸の痛みとともに「楽器」に向かい呻吟するクリスチャンを見ていた。
「君の才能はこんなものじゃない。君はもっと先へ行ける」
欲望や好奇心と自制の狭間で苦悩する天才を描くこの場面は、皮肉なほど美しい。青い床に落ちた白い光と窓枠の十字の影が、憔悴しきったクリスチャンの上に落ちる。その中で跪きバッハを聴く彼の姿は、どこか懺悔の祈りを捧げているようにも見えた。
★
そして運命の日、ポールとともに「ウォッチャー」がやって来る。あの黒衣の姿を見るだけで劇場内の気温がすうっと下がる気がする。原作では盲目であり盲導犬を連れている設定だが、さすがに舞台に動物は出せないので、左手で白杖ならぬ「黒杖」を持っている。右手はポケットに入れられたままだが、その理由も後から明かされる。←この辺、原作にはない脚本の妙!
石橋さん演じる「ウォッチャー」の身体的なアドバンテージと、そこから生み出される存在感や、造形に関して、この第一楽章でのインパクトはまさに「想像通りで、想像以上」――おそらく私が持っていた「原作のイメージ」に一番近い。監視者としての威圧感、そして得体のしれない冷ややかな雰囲気、絶対的な威厳と深く気品のある声音、全てが「本物のウォッチャーだ…!」としか思えなかった。
重ねて言うなら『無伴奏ソナタ』は主役のハマりっぷりもさりながら、陰陽のようなクリスチャンとウォッチャーの関係性が凄い。
禁を犯したクリスチャンは楽園を追われる。だが、この場面でのクリスチャンの哀れさは「メイカーでいられなくなること」ではない、と私は思った。「音楽を禁じられること」ですらない、と思った。何が一番哀れに思えたか、それはクリスチャンが「自分の身に何が起こるのか、全く分かっていなかった」こと…オリヴィアに「僕は傲慢だった。少しくらい法律を破っても、僕だけは許されると思っていた」と寂しそうに微笑んで告白するクリスチャンの表情は、悪戯をして叱られた子どもとさして変わらない。その無垢な純粋さが、観ているのが辛くなるほど痛かった。そしてこの何ともやりきれない痛みや哀しみを、舞台上のオリヴィアとポールは「分かって」くれていた。
「そんなの絶対に無理よ!音楽を奪われたら、クリスチャンはきっと生きて行けない!」
ウォッチャーの手前、それまで(いつもの軽さを封印して)一人称も「私」になり、ビジネスライクな態度を崩さなかったポールが「そんなことは分かってる!」とオリヴィアに怒鳴り返すシーンが、私はものすごく好きだ。彼の「法の番人」としての立場は「クリスチャンの友だち」であり続けることを許さなかった。その矛盾を越えて「僕は5年も彼と一緒にいた。彼は僕の友だちだったんだ!」と叫ぶポールの姿はクリスチャンへの愛情と激しい怒りと、深い悲しみに満ちていて胸を打つ。クリスチャンの苦しみとはまた別の次元で、ポールも苦しんでいたに違いない。天才の苦悩は凡人の私には想像の付かない世界だろうが、ポールの苦しみは「自分にも理解できる世界のものだから」余計に近しく思ったのかもしれない。
「ぼくたちの生活と幸せは法によって守られている」
「法を犯すことは許されない。法律は守らなければならない」
この言葉は、後々の場面で何度も「別の人物によって」語られる。
クリスチャンの「たった一人の友だち」であった「彼」と同じ、あの声で――。
台詞とは真逆に、苦しそうに唇を噛み、身を翻すポール。
その後姿に向かって「大バカ野郎!!」と怒鳴りたいのを堪え、私は黙って涙を流した。
※このシーンのBGMは『最後の晩餐』(by DEPAPEPE)…それを知って聞くと、余計に切ない。
★
繰り返し考えた。自分の行為がきっかけとなり、クリスチャンが「メイカー」としての地位も名声も全て失ったことを、あの「リスナー」の男は知ったのだろうか?知ったとして、彼は何を思っただろうか?
悲しみ?失望?
それとも他の感情?
あの男もまた法を犯したとして処罰されたのだろうか。事件後、政府はきっとクリスチャンの創造性の「汚染」の原因を突き止めようとしたに違いない。恐らくは彼もまた職を失い、本来あるべき「幸せな」人生を失ったのではないか…?
それにしても。クリスチャンが自分の欲望(彼自身は「不安」と言っていたが)に抗えず負けたように、あの男もまた自分の「リスナー」としての本性に忠実であったに過ぎないのだろう。それによって引き起こされる不都合を想像するよりも、クリスチャンの音楽への執着と関与を選んだのかもしれない。
クリスチャンの「原罪」を生み出した蛇の末路は、誰も知らない。
(続く)
※≪第二楽章≫~≪喝采≫までは後日追記予定です。
≪おまけ≫
サンシャイン劇場 階段シアター♪




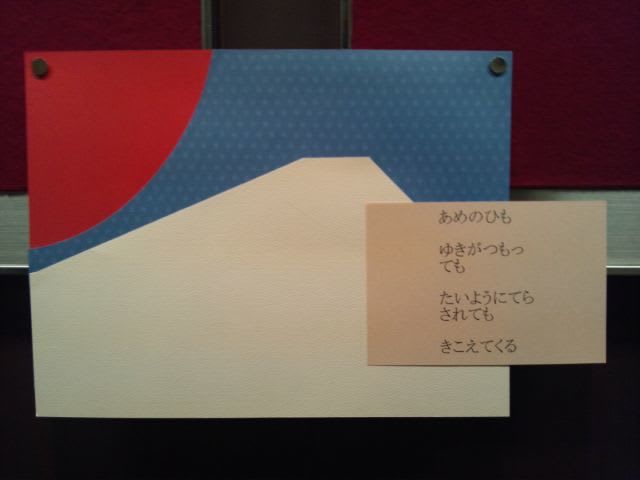

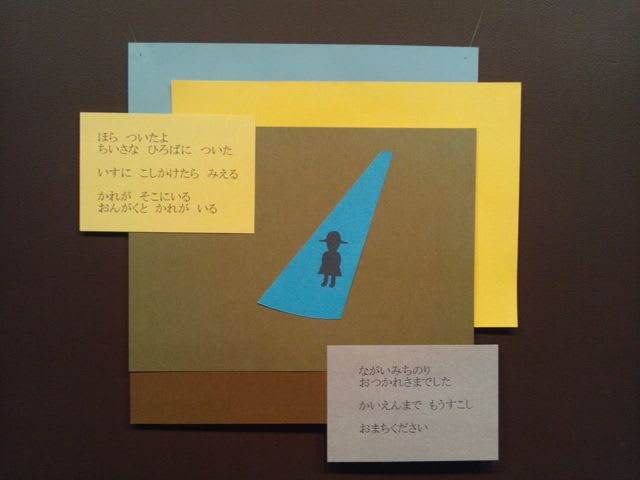
最後、上りきったところの1枚を見て「これは反則…!」と思いました。
許されるならもらって帰りたかった!(笑)
演技や台詞から次々に湧き出てくるインスピレーション…それは連想であり、空想や推測でもあり、東京公演が終わった後も私の脳内ではクリスチャンの音楽や歌とともに『無伴奏ソナタ』の世界が途切れなく続いているような不思議な感覚でした。
一場面の芝居に含まれてる(と感じた)情報がとにかく多くて、一人の台詞や演技の奥に見えない物語がいくつもある気がします。多分キャラメルボックスならではの原作潤色や役者さんの個性も相まって、私の目に映る『実写化・無伴奏ソナタ』の世界がより鮮やかで豊かになっていたのかもしれません。シーンごとに心に浮かんだことを書き出していくと、とんでもない長さになりそうですが(苦笑)ゆっくり記憶の書庫を歩き回りながら書き綴って行きたいと思います。

『無伴奏ソナタ』 総括 その1
われわれが自由でありうるために、
われわれ全員が法律の奴隷となる。
(マルクス・トゥッリウス・キケロ)
暗転の中に響くオープニングの鐘の音。ドイツ滞在中に朝夕親しんでいる「あの音」と同じだ、と気づく。教会から高らかに鳴らされる鐘は、時に祝福であったり、時に哀悼であったり…日々の暮らしに空気のように寄り添って「時」を告げていく。
ひんやりとした夜明け前を思わせる、暗く青い照明に浮かび上がる舞台。黒一色の衣装を着た人物の影。まるで墓地に佇む会葬者だ。あたかも「誰かの葬送」に私自身が立ち会っているかのような錯覚に陥った。
これは…ひょっとしたら、クリスチャン・ハロルドセンの葬送なのかもしれない。
まだ物語は始まってもいないのに、彼の人生に起きてゆく出来事を「何もかも分かっている」観客――私はそう思った。
鐘の音が消えていく。青白い光の中で黒い人影がひとり、またひとりとベルを鳴らす。水滴の落ちるような澄んだ音色。ひときわ高い音のベルは、クリスチャンの手に握られている。周囲で鳴り響く澄んだベルの音は、先ほどまでの葬送のイメージとは真逆に、クリスチャンの「誕生」を告げているようにも聞こえてくる。
間近で見るクリスチャン(=多田さん)、初回で私は正直「この人の演技のイメージが根底から変わった!」と衝撃を受けた。本当に圧倒的だった。この瞬間、たった数メートルの距離で、どこか生命を感じさせないようなふわりとした存在感の彼を見て、逆にゾクリとするほどの迫力を感じた。何かが憑依している…役者が「演じて」いるんじゃない、今ここにいる彼は「クリスチャン・ハロルドセン」だとしか思えない。これまで観た3本の作品のどれとも違う。完全に「生きて」存在していた。私は文字通り目が離せなかった。
人影がクリスチャンを取り囲み、周囲を巡り、迫り、去っていく。
舞台前方に歩を進めるクリスチャン。
下手に立つ長身の人影は、沈黙したまま「見守っている」。
チリーン…
一人佇み、どこか寂しげにベルを鳴らすクリスチャンの背中を見送ると、「人影」が大きく腕を振り上げた。バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ」――この物語の主題が流れ始める。
陳腐な言い方かもしれないが、「運命の輪が廻り始める」この瞬間がとても好きだ。
そしてここから始まるクリスチャンの人生を思い返し、早くも胸が詰まった。
☆
≪音合わせ≫
やっぱり近くで観ると違う!何でも前方列が良いというものではないが、やっぱり声や動きの伝わり方は(生身なだけに)迫力がある。父の決断も、母の愛も、政府の人間の傲慢さや葛藤までも、手のひらに掬い取れそうな細やかさとリアルさでひたひた伝わってくる。短いシーンなのに全ての人間にちゃんと背後のストーリーがある。原作では「時系列で事実(とSF的世界観)を淡々と述べていく」あの部分が、こんなにも人間同士の生臭いぶつかり合いになるということに、改めて驚く。
ハロルドセン夫妻の職業は「プレイヤー(演奏者)」である。父がヴァイオリニスト、母はピアニストという設定だ。この「条件」が、クリスチャンの波瀾に満ちた人生の中で形を変えながら何度も顔を出す。このあたりも脚本・演出ともに「上手いなあ」と唸った。
クリスチャンの父親・リチャードの配役が石橋さん=「ウォッチャー」であることがまた暗示的だと思う。リチャードの登場場面はここだけだが、彼は姿を消しても物語の中で基調音のひとつとして存在し続ける。「父性」…それを最終局面の「ウォッチャー」の中に見出した時、あれほど驚愕し同時に涙した理由は、私の中にこの冒頭場面のリチャードがちゃんと残っていたからに他ならない。
クリスチャンの母親・カレン(=大森さん)が必死に政府の女性検査官・ジャニス(=岡田さん)に食い下がるシーンは、女性・イコール・母性でないことを面白いほどに見せつけてくる。自らのミッションに忠実、冷静かつ理論的なジャニスのほうが、観ている私には「より理解できる」存在だ。彼女の言うことは「正しい」。非の打ちどころ無く正しく、クリスチャンが「幸せになるために」何が最も必要で、何に最上の価値を置くべきなのか、全くブレていない。だからと言って我を忘れて取り乱すカレンが愚かに見えるかというと、決してそうではない。カレンの姿に「理屈ではない」人間の、そして母親の愛情を私は見ていた。父親と同じように、母カレンの面影は別の形でクリスチャンの意識と無意識の中で生き続ける。←台詞だけでなく後述の「ある場面」で気づいてまた打ちのめされた…。
一歩控えて彼女たちを見つめる検査官・ギルバート(=左東さん)の、仕事とはいえやるせない悲しみやカレンへの同情を隠しきれない表情が、その時の私の感情にモロにシンクロする。きっと「メイカー」と認定された子どもの親たちの歓喜や愁嘆を見続けてきたのだろうと、ふと彼の背景にまで想いをめぐらしてしまうほどに。
クリスチャン本人が登場しない場面で、もっと言うなら全員が「キャラメルボックス版オリジナルキャラクター」であるにも関わらず、これほどに濃いものができるのか!と。原作を知らなくても、もちろん素晴らしい舞台だと思うが、原作既読だからこそ、新鮮な驚きに(話の筋とは別に)ワクワクさせられる。
ちなみにここまでの短い間にもちゃーんと笑いのネタを仕込んでくるのが、いかにもキャラメルボックスらしい。過剰だと原作の雰囲気を損なうので、私的にはこのくらいで十分!淡々とした物語の程よいスパイスになっていたと思う。
☆
≪第一楽章≫
語り手は「ハウスキーパー」のオリヴィア(=岡内さん)。いささかハウスキーパーらしからぬ性格設定で戸惑うが、観客視点に近い立場として「メイカー」の特殊性や、クリスチャンがいかに一般市民の生活とはかけ離れた「ルール」の中で生きているのかを説明するには、あのくらいでないと「足りない」のかもしれない。
ここでようやく主役登場、30歳になったクリスチャンが目の前に現れた。
随分若く見える。友人が「年齢不詳」と評したのも頷ける。
冒頭の浮世離れした「無生物感」とは真逆の、ちょっと頼りなげな線の細い青年。
音楽の天才と言っても、彼の心はおそらく「無垢な子どものまま」…世俗との関わりの一切を断たれ(それを疑問に思った時期はあったにしても)自らの才能に絶対の自信を持ち「特権階級としての恩恵」を受け入れている。疑うこと、嘘をつくこと、誰かを欺くことなど思いも寄らない、素直な笑顔がとても愛らしい。およそ負の感情と無縁に生きて来たであろう彼の存在感は一種独特で、世の中にこんな人間がいるのだろうか?というオリヴィアの思いを私も客席で共有していた。
不思議な「楽器(Instrumentと原文には表現されている)」で不思議な「曲」を奏でるクリスチャンの表情は嬉々として、時に恍惚とした喜びさえ浮かべて、子どもが無心に玩具と戯れる姿にも似ていた。青い背景に銀色の五線譜が光り、クリスチャンと「楽器」の足元には、曲調に合わせて様々な色の光の輪やきらめきが生まれ、消えていく。劇場に芝居を観に来たはずなのに、どこかのホールで音楽を聴いているような浮揚感。その間にも、オリヴィアは彼女の目から見たクリスチャンを語っていたが、私の目はクリスチャンに引き寄せられたままだった。
★
第一楽章ではもう一人のキャラクターが、実は私のお気に入りである。政府職員で「メイカー」の管理者・ポール(=畑中さん)。前の場面に出てきた政府職員たちとは雰囲気を異にする、エリート臭さはあっても底抜けに明るくて、ちょっとお調子者の好青年。クリスチャンとは5年の付き合いだと言っているが、外の世界を知っているせいか?彼よりはやや年上にも見える。音楽という伴侶があったとはいえ、孤独な生活を送るクリスチャンにとっては「(前任のハウスキーパーを除いて)唯一の友だち」であり、どこか兄のように思える存在だったかもしれない。
ピシリと着こなしたスーツ姿で、オリヴィアに悪童めいた揶揄を投げかけ、クリスチャンの体調を滑稽なほど真剣に心配し、音楽を聞いて軽やかに踊り出す。何とも人懐っこい愛嬌のカタマリで、クリスチャンの「本人の意識しない部分での可愛らしさ」と好一対、どうにも憎めない。舞台上で楽しげに動き回る姿を見ていると、愛らしさに思わず頬が緩む。だが、やはり彼もまた「法律」の守り手であり、その「仕事」に対しての考えもまた、ラストで明かされるのだが。
彼らは原作にはここまでの「設定」を伴って登場しない。オリヴィアは相当の脚色、ポールは存在そのものが完全に舞台オリジナルだ。とても人間臭く、とても我々に近い。だからこそ「特別な者」としてのクリスチャンが一人になった時に見せる苦悩が際立つのだろうか。
★
クリスチャンの「幸せな日々」に混乱と終焉をもたらす「リスナー」の男(=小多田さん)、彼が手渡したバッハの録音は、クリスチャンの母カレンによると、奇しくも両親が学生時代に知り合うきっかけとなった曲(=「無伴奏ソナタ」)だった。ヴァイオリニストの父リチャードは、クリスチャンと過ごした僅か2年の間に、家でその曲を弾いただろうか?クリスチャンの記憶の奥底に、母のかぼちゃスープの味と同じように、父のヴァイオリンも、残っていたのだろうか。
ところでこの「リスナー」…彼は1年間ずっと森に通いクリスチャンの音楽を聴いていた、と語った。彼の音楽に魅入られ、熱狂し、それだけでは飽き足らず、禁を犯してクリスチャンに話しかけ、あろうことか「他人の音楽」を聞かせようとする。他の「リスナー」たちは「メイカーの音楽を評価する」本来の仕事に忠実だったが、この男だけは全く違う。狂気に似た情熱でクリスチャンの才能に関わろうとする。
バレなければいい。分からなければいい。模倣しなければいい。
バッハを聴けば「君に欠けているものが分かるはず」だ、と彼は言った。
彼は一体…何がしたかったのだろうか?
クリスチャンの才能を愛するあまりに、「足りない」ことが許せなくなった?
それを自分が直接に関わることで「クリスチャンの音楽を完璧にしたかった」?
だとしたら何という傲慢さだろう。しかし、私は「リスナー」だけを責めることはできなかった。どうするか決めるのはクリスチャン自身。かつて父が母にそう諭したように。閉ざされた森という名の楽園で、人の形をした蛇がバッハという林檎を持ってきても、その誘惑に堪えることができるか、できないか…クリスチャンの音楽への欲望は、きっと耐えられない。話の筋が分かっていても、私は胸の痛みとともに「楽器」に向かい呻吟するクリスチャンを見ていた。
「君の才能はこんなものじゃない。君はもっと先へ行ける」
欲望や好奇心と自制の狭間で苦悩する天才を描くこの場面は、皮肉なほど美しい。青い床に落ちた白い光と窓枠の十字の影が、憔悴しきったクリスチャンの上に落ちる。その中で跪きバッハを聴く彼の姿は、どこか懺悔の祈りを捧げているようにも見えた。
★
そして運命の日、ポールとともに「ウォッチャー」がやって来る。あの黒衣の姿を見るだけで劇場内の気温がすうっと下がる気がする。原作では盲目であり盲導犬を連れている設定だが、さすがに舞台に動物は出せないので、左手で白杖ならぬ「黒杖」を持っている。右手はポケットに入れられたままだが、その理由も後から明かされる。←この辺、原作にはない脚本の妙!
石橋さん演じる「ウォッチャー」の身体的なアドバンテージと、そこから生み出される存在感や、造形に関して、この第一楽章でのインパクトはまさに「想像通りで、想像以上」――おそらく私が持っていた「原作のイメージ」に一番近い。監視者としての威圧感、そして得体のしれない冷ややかな雰囲気、絶対的な威厳と深く気品のある声音、全てが「本物のウォッチャーだ…!」としか思えなかった。
重ねて言うなら『無伴奏ソナタ』は主役のハマりっぷりもさりながら、陰陽のようなクリスチャンとウォッチャーの関係性が凄い。
禁を犯したクリスチャンは楽園を追われる。だが、この場面でのクリスチャンの哀れさは「メイカーでいられなくなること」ではない、と私は思った。「音楽を禁じられること」ですらない、と思った。何が一番哀れに思えたか、それはクリスチャンが「自分の身に何が起こるのか、全く分かっていなかった」こと…オリヴィアに「僕は傲慢だった。少しくらい法律を破っても、僕だけは許されると思っていた」と寂しそうに微笑んで告白するクリスチャンの表情は、悪戯をして叱られた子どもとさして変わらない。その無垢な純粋さが、観ているのが辛くなるほど痛かった。そしてこの何ともやりきれない痛みや哀しみを、舞台上のオリヴィアとポールは「分かって」くれていた。
「そんなの絶対に無理よ!音楽を奪われたら、クリスチャンはきっと生きて行けない!」
ウォッチャーの手前、それまで(いつもの軽さを封印して)一人称も「私」になり、ビジネスライクな態度を崩さなかったポールが「そんなことは分かってる!」とオリヴィアに怒鳴り返すシーンが、私はものすごく好きだ。彼の「法の番人」としての立場は「クリスチャンの友だち」であり続けることを許さなかった。その矛盾を越えて「僕は5年も彼と一緒にいた。彼は僕の友だちだったんだ!」と叫ぶポールの姿はクリスチャンへの愛情と激しい怒りと、深い悲しみに満ちていて胸を打つ。クリスチャンの苦しみとはまた別の次元で、ポールも苦しんでいたに違いない。天才の苦悩は凡人の私には想像の付かない世界だろうが、ポールの苦しみは「自分にも理解できる世界のものだから」余計に近しく思ったのかもしれない。
「ぼくたちの生活と幸せは法によって守られている」
「法を犯すことは許されない。法律は守らなければならない」
この言葉は、後々の場面で何度も「別の人物によって」語られる。
クリスチャンの「たった一人の友だち」であった「彼」と同じ、あの声で――。
台詞とは真逆に、苦しそうに唇を噛み、身を翻すポール。
その後姿に向かって「大バカ野郎!!」と怒鳴りたいのを堪え、私は黙って涙を流した。
※このシーンのBGMは『最後の晩餐』(by DEPAPEPE)…それを知って聞くと、余計に切ない。
★
繰り返し考えた。自分の行為がきっかけとなり、クリスチャンが「メイカー」としての地位も名声も全て失ったことを、あの「リスナー」の男は知ったのだろうか?知ったとして、彼は何を思っただろうか?
悲しみ?失望?
それとも他の感情?
あの男もまた法を犯したとして処罰されたのだろうか。事件後、政府はきっとクリスチャンの創造性の「汚染」の原因を突き止めようとしたに違いない。恐らくは彼もまた職を失い、本来あるべき「幸せな」人生を失ったのではないか…?
それにしても。クリスチャンが自分の欲望(彼自身は「不安」と言っていたが)に抗えず負けたように、あの男もまた自分の「リスナー」としての本性に忠実であったに過ぎないのだろう。それによって引き起こされる不都合を想像するよりも、クリスチャンの音楽への執着と関与を選んだのかもしれない。
クリスチャンの「原罪」を生み出した蛇の末路は、誰も知らない。
(続く)
※≪第二楽章≫~≪喝采≫までは後日追記予定です。
≪おまけ≫
サンシャイン劇場 階段シアター♪




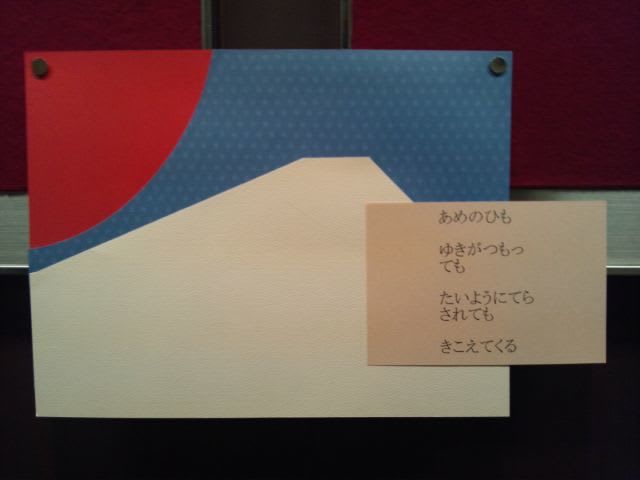

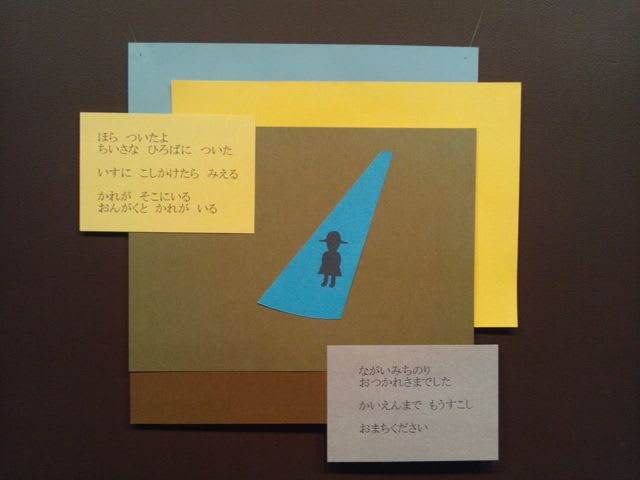
最後、上りきったところの1枚を見て「これは反則…!」と思いました。
許されるならもらって帰りたかった!(笑)









