最近、すっかりラーメンブログになりつつある…(汗)
(「えー。ラーメンブログじゃん」っていう突っ込みはなしで、、、)
これまでラーメンの論文を二つ書いて、三本目の構想を考えている。三作目は、「ラーメン屋店主の学びに多大な影響を与えるラーメンフリークの存在の解明」がテーマ。いよいよ、教育学的ラーメン論文の革新部分に触れることになる(大げさだな~)。
ラーメン界における大きな特徴は、「ラーメンフリーク」と呼ばれる強力なラーメン屋のパートナーが存在する、という点だ。ラーメンフリークは、一般的には「オタク」の範疇に入るものと考えられているが、オタクという概念では説明できない要素を多分に含んでいる。オタクは、作り手に間接的に影響を与える可能性をもっているが、直接的に作り手に関与することは難しい。ラーメンフリークは、ラーメン店主とのパートナーシップを生きる場合が多く、直接作り手に影響を与えているケースが多い。
ラーメン屋店主も、ラーメンフリークの評価に対してそれなりの関心をもっており、HPやブログやSNSの評価を一通り把握している。なかには、心ない書き手の文章に傷ついたり、腹を立てたりする場合もあるし、逆にあることないことを書いて、誹謗中傷に近い厳しいコメントを残す書き手もいる。いずれにしても、ラーメンというジャンルほど、食べ手が作り手のラーメンについて熱く語る料理はないはずである。カレーもそれなりに人気があるが、ラーメンブログほどの量はない。
では、いったいラーメンフリークとはいったいどんな人間で、どんな特徴があり、どんな活動をし、どのような影響をラーメン店主に与えているのか。また、そのラーメンフリークについて、ラーメン店主はどう思っているのか。この辺をリサーチして、インタビューして、文献を大量に読みこんで、書いていきたいなって思う。
で、僕的には、「よき食べ手」(よき受容者)という概念を使って、ラーメン文化の最大の特徴を浮き彫りにしたいと思う(大げさだ~~)。善き受容者が多いこと、それがラーメン界を盛り上げることにつながっている、と。ラーメンフリークは、概して平和な人が多い。それは武内さんもかつて語っていた。仕事もそれなりにやって、プライベートはラーメンで充実させる。さらには、ラーメンフリーク独自のコミュニティーがあり、あらゆる世代の人々が休日のプライベートを満喫している。
この「ラーメンフリーク」を解明することで、逆に、趣味のない人間、趣味ともいえない趣味に走る人間も浮き彫りになるだろう。「ラーメンにはまること」と「覚せい剤にはまること」には全然違うニュアンスがある。何にはまるかも、その人の生きる背景によって基礎づけられているのでは、と思うのだ。平和な人間は覚せい剤にははまらない。逆に、平和でない人間はラーメンフリークにはならない。なぜか。そこに、何か大きな問題が隠れているようにも思えるのだ。
また、学校問題と関連させていえば、「よき受容者」が不在であることが、教育界の大きな問題なのではないか、と問題提起したいのである。教育を心から愛し、教育のことを日々考える「教育フリーク」はどれだけいるのだろうか。教育学者は、そういう意味では、「教育フリーク」でなければならないはずなのに、そこまでの愛情を感じる学者はあまりいないように思う。僕の尊敬するとある大学院の先生はものすごい「教育フリーク」だった。10000校以上の学校を見たと言っていた(凄い!)
「よき受容者」ではない、「わるい受容者」が増えると、その文化はねじ曲がっていく。わるい受容者の代表が、モンスターペアレントやクレーマーと言われる人だ。彼らも少なからず、その分野に精通している。よく勉強している人も少なくない。ただ、その分野そのものをよくしよう、という気持ちが欠如している。逆に、その分野の存続を危うくさせるのだ。建設的な批判ではなく、ただ作り手の悪いところだけを弾叫する。それはフリークの批判ではない。
…なんてことを論じられたら面白いかな、と





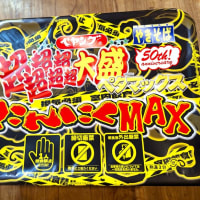



![ローソン[盛りすぎチャレンジ]47%増量でお値段そのまま!「盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり」が凄かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0c/22/ce1c21831fa593422e72ccc820e09ca4.jpg)
![McDonald's マクドナルド 期間限定[メキシカンチーズチキン]はまさにメキシカンスパイシーチリテイスト!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/10/c61d1e12ecfc56a4cb6816a43a3b333c.jpg)







