NHK東京児童合唱団の「テ・ルーキス・アンテ」リハーサル…NHKにて。早い時期はまだ中身に言及する段階では無いだろうと思い、28日(水)に立ち会う。
原宿駅から渋谷のNHK西口へ近道を行こうと思ったら、代々木公園のグラウンドに入り込んでしまい、引き返すがNHK内の通りが柵で閉められていて大周りをして本館から入った。そこから西館に行くのが複雑で本館の*階に行ってしまい、通りすがりの職員さんに聞くと5階に渡り廊下があるとの事で、新人アナウンサーが廊下でニュース原稿を暗唱しているのを横目で見つつ、西館*階の児童合唱事務室に到着…リハ開始時刻の2分前。
常任指揮者の加藤氏がリハーサル室に案内して下さった。まだ前の曲をやっていた。走ったせいで汗だく。
指揮者は金田典子氏。しかしその横で大谷研二氏がむしろメインになって僕に質問し、団員に指示を出して下さった。
まずプロではあり得ない、団員達の演奏姿に感激した。それが何かは本番まで伏せておこう。
もちろん、歌が上手いこと以外は普通の子供たちだ。僕の曲のリハの時間になってもしばらくは集中できず、だらだらした空気はあった。
けれど一通り歌って頂いて、何かないかと指揮者に訊かれ、冒頭の音程を自ら歌って示し、あとは後半のテンポだけ、と伝えると集中力はぐんと増した。
団員は丁度40人ほど。ただし4等分ではなく、ソプラノⅠが12人、Ⅱが7人らしい。「もっと増やしてくれないか」とソプラノⅡのパートリーダーらしき子がぼやいていた。
各パート1人ずつ(計4人)、小さな女の子が混じっていた。歌うというより周りを聴きながら熱心に楽譜に書き込みをしていた子も。
金田氏によると、この音楽内容なら大人の声の方が良いかと思い、一度中学3年以上の編成でやってみたが、どうも違うと感じ、小学2年生も混ぜたのだそうだ。
正味40分ほどリハを行い、何か無いかとまだ訊かれるので、「何も無い、素晴らしい、幸せだ」と答えた。
僕への質問という事で、ダンテの「神曲」は読んだのか、とアルトの中学生に聞かれた。なぜ煉獄編を選んだのか、本当に初演なのか、と金田さんからも訊かれた。
帰り際、伴奏者の前田氏が、僕が右手のピアノ曲を自演した時のコンサートで彼も他の曲を弾いたピアニスト、という事を明かしてくれた。
帰り支度の際、スチール製の筆箱を鞄に入れ損ね、テーブルに垂直に叩きつけてしまい、まるでアイスホッケーのように吹っ飛んだ。そばにいたソロ担当の?中学生が床に散乱した筆記具を一緒にせっせと拾ってくれた。
合唱団は「夕焼けこやけ」を歌っていた。
![]()
28日のリハでは技術的な問題など一切無かった事に驚き、満足していたが、1日経ち、2日経つうちに、作曲していた際中の熱い記憶がよみがえり、3箇所ほど直すべき点が明らかになった。
1月31日(土)(本番前日)のリハは前回より狭く、アップライトピアノの*04室。
15時過ぎから拙作。大谷氏も同席して下さる。休憩中メンバーの入れ替えでごたごたしている時を見計らい、金田さんに切り出した。
1つ目は「テ・ルーキス・アンテ」の発音について。これは意味と共に僕が団員たちに直接説明することになった。
2つ目はソプラノⅡが少ない事への局部的な解決策。
3つ目はクライマックスへの持って行き方のより効果的なダイナミックスの変更。すべて即座に改善された。言わばこれは作曲家のお土産。
次に大谷氏が斬新なアイデアを色々提案して下さった。声色、ピッチ、持続音の質に関して、超一流の感覚を持っているのに舌を巻く。
次々に繰り広げられる試行錯誤を目の当たりにするのは、むしろ本番よりも価値がある。
金田さんは大谷氏や団の子供らから「カネゴン」と呼ばれていた。僕が小学生のころ教えて頂いたソルフェージュの女の先生に面影がよく似ていらっしゃる。
16時から前回と同じ、グランドピアノのある広い*06室に移動し、ゲネプロ的に3曲通し。僕の曲は小さい子が増え、今日は45人ほどだった。
歌が終わり、拍手の後、解放されて散らばった子供らは口々に「マリアの懐から…」を歌い出し、しばらく鼻歌のさざ波に包まれた。
ピアニストには音量をお願いしたが、やや欲求不満になる。「もっと出してくんねえかなあ…」と帰宅後、家のピアノを叩きまくったら弦が切れた!![]()











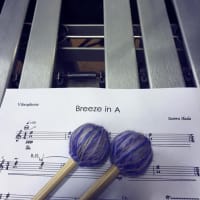

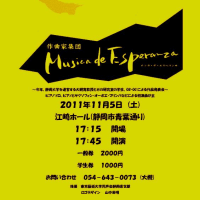
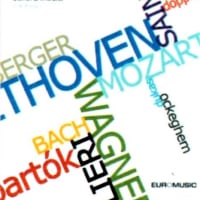

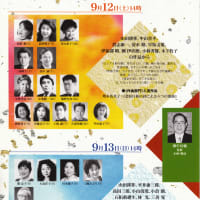
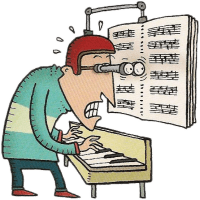

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます