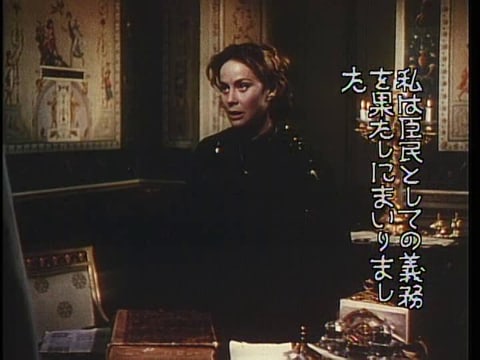イノセント』 - L'INNOCENTE -
1975年 124分 イタリア
監督 ルキノ・ヴィスコンティ LUCHINO VISCONTI
製作 ジョヴァンニ・ベルトルッチ GIOVANNI BERTOLUCCI
原作 ガブリエレ・ダヌンツィオ GABRIELE D'NNUNZIO
脚本 スーゾ・チェッキ・ダミーコ SUSO CECCHI D'AMICO
エンリコ・メディオーリ ENRICO MEDIOLI
ルキノ・ヴィスコンティ LUCHINO VISCONTI
美術 マリオ・ガルブリア MARIO GARBUGLIA
撮影 パスクァリーノ・デ・サンティス PASQUALINO DE SANTIS
音楽 フランコ・マンニーノ FRANCO MANNINO
出演
ジャンカルロ・ジャンニーニ GIANCARLO GIANNINI
ラウラ・アントネッリ LAURA ANTONELLI
ディディエ・オードパン DIDIER HAUDEPIN
RUNA MOREKKLLI
MASSIMO GIROTTI
MARIE DUBOIS
ROBERTA PALADINI
CLAUDE MANN
ジェニファー・オニール JENNIFER O'NEILL
マルク・ポレル MARC POREL

わがまま【我が儘】[大辞林より]
(1)他人のことを考えず、自分の都合だけを考えて行動すること。また、そのさま。身勝手。自分勝手。
(連語)自分の意のままであること。
-----------------------------------------
決闘、相手のことを考えず、自分にとって邪魔な者を殺すこと.
二人の男は、もめ事の元になった女の気持ちを考えることなく決闘に及んだ、女は勝った方のものという我が儘な考え方による決闘だった.が、そのもめ事の元を質せば女の我が儘であり、さらに付け加えればこの女、自分が元で決闘をすることになった、その決闘の最中に居なくなってしまったらしい.全くどうしようもない我が儘な女である.
主人公のこの男、浮気をするにも一見もっともらしい理由を並べたけれど、全く妻の気持ちを考えない、妻に耐えることだけを如いた我が儘な言い訳だった.
「当家の金で洗礼を受けさせてやる」この言葉からは、この男が子供を自分の子供として育てる気持ちだった、少なくとも、つもりであったのが分かる.無心論者のこの男、わざわざ教会に出かけ、洗礼の儀式を陰から見ていた.妻と同じように夜中に子供を見に行っていたらしく、この男、決して子供を殺すつもりはなかったと思われるのだけど.
彼が殺意を抱いたのは、妻の子供を嫌いだと言う言葉を聞いたからであり、つまり、彼は妻の気持ちを考えて殺人に及んだのであって、彼にしてみれば、我が儘とは反対の行動であったのだけど.けれども、新婚当時のようにSEXをする妻が、自分の意のままであると思い込んでいた、妻が自分に嘘をつくとは思っても見なかった、その思い込みが我が儘な思い込みであり、自分の犯した殺人により妻は去って行く事によって、殺人という行為が我が儘な行為である、邪魔だから殺すという行為は、正に我が儘な行為に他ならないことを、彼は思い知ることになった.
彼は自殺をする.自殺とは我が儘な死に方と言えるのだけど、その死に方が、彼の我が儘な生き方の、それに対する責任の取り方でもあったと言えるのでしょうか.
他方の女は、男が自殺した屋敷から逃げ出した.先の自分が元で決闘になった、その決闘をほったらかして勝手に居なくなってしまった例を考えると、この女はめんどうなことは避けて通ること、言い換えれば、自分のしたことに何ら責任を負わないことが生き方らしい.
「男に惑わされる生き方は、そろそろ止めようと思う」と、この女は言ったけれど、この女が二人の男を惑わしたから決闘になったのであり、「男に惑わされる生き方は、そろそろ止めようと思う」、つまり、我が儘な男と付き合うのはよそうと思う、と言いたいらしいけれど、この言葉自体が、我が儘な言いぐさと言える.
-----------------------------------------
この男の死に様は、孤独であった.振り返れば、夫が浮気をすると言いはり、いつ戻るか分からない旅行に出てしまった.そして、残された妻は孤独であった.我が儘は、孤独をもたらし、そして、人を不安にさせる行為である.
赤ちゃんは人の話し声がした方が、安心してよく眠るという.一人残された妻もまた、作家の言葉を聞いて眠りに就いた.言い換えれば、彼女は作家の言葉に安らぎを求め、作家の言葉が彼女に安らぎを与えたからこそ、二人は関係を持ったと言ってよいのでしょう.
イノセント=インノセント=『罪無き者よ』
-----------------------------------------
妊娠3か月目のジュリアナは、ベットの上で刺繍をしていた.
夫は彼女に、医者を手配するから、堕胎すように言う.
彼は、話をしながらジュリアナの着物を脱がせ、布団をまくって、そして、寝間着をたくし上げると、彼女、その下には何も身につけていなかった.
「いいか」、彼は、妻の着物を、はぎ取るようにした.
「僕は無心論者だが」、言い終わった時には、ジュリアナは全裸.おっぱいも、あそこのお毛けも見えてる.
「善悪は、自分なりに、意識している」、こう言いながら、全裸の彼女を愛撫する.
「神にさばきを任せはしない」「責任だけはとるつもりだ」、きゃ、もっと見せて、スケベ.
-----------------------------------------
スケベなシーンを観客は真剣に観てくれるはず、ヴィスコンティはこう考えて、スケベなシンーンを背景にして、大切な言葉を、描き込んでいるらしい.
(もっとも、日本人が観ると、女の子の裸の方へ目が行ってしまい、字幕を読むのはおろそかになってしまうかも?)
「神にさばきを任せはしない.責任だけはとるつもりだ」
つまり、夫は自分は自分で裁くと言い、その言葉の通り、彼は自分を自分で裁いた.子供を殺した罪を、自殺することで償ったのだが、女は、男が自殺した屋敷から逃げ出した.
さて、この女、誰から裁きを受けるのか?
『罪無き者よ』= 自らも含め、誰からも裁きを受けることのない者.


1975年 124分 イタリア
監督 ルキノ・ヴィスコンティ LUCHINO VISCONTI
製作 ジョヴァンニ・ベルトルッチ GIOVANNI BERTOLUCCI
原作 ガブリエレ・ダヌンツィオ GABRIELE D'NNUNZIO
脚本 スーゾ・チェッキ・ダミーコ SUSO CECCHI D'AMICO
エンリコ・メディオーリ ENRICO MEDIOLI
ルキノ・ヴィスコンティ LUCHINO VISCONTI
美術 マリオ・ガルブリア MARIO GARBUGLIA
撮影 パスクァリーノ・デ・サンティス PASQUALINO DE SANTIS
音楽 フランコ・マンニーノ FRANCO MANNINO
出演
ジャンカルロ・ジャンニーニ GIANCARLO GIANNINI
ラウラ・アントネッリ LAURA ANTONELLI
ディディエ・オードパン DIDIER HAUDEPIN
RUNA MOREKKLLI
MASSIMO GIROTTI
MARIE DUBOIS
ROBERTA PALADINI
CLAUDE MANN
ジェニファー・オニール JENNIFER O'NEILL
マルク・ポレル MARC POREL

わがまま【我が儘】[大辞林より]
(1)他人のことを考えず、自分の都合だけを考えて行動すること。また、そのさま。身勝手。自分勝手。
(連語)自分の意のままであること。
-----------------------------------------
決闘、相手のことを考えず、自分にとって邪魔な者を殺すこと.
二人の男は、もめ事の元になった女の気持ちを考えることなく決闘に及んだ、女は勝った方のものという我が儘な考え方による決闘だった.が、そのもめ事の元を質せば女の我が儘であり、さらに付け加えればこの女、自分が元で決闘をすることになった、その決闘の最中に居なくなってしまったらしい.全くどうしようもない我が儘な女である.
主人公のこの男、浮気をするにも一見もっともらしい理由を並べたけれど、全く妻の気持ちを考えない、妻に耐えることだけを如いた我が儘な言い訳だった.
「当家の金で洗礼を受けさせてやる」この言葉からは、この男が子供を自分の子供として育てる気持ちだった、少なくとも、つもりであったのが分かる.無心論者のこの男、わざわざ教会に出かけ、洗礼の儀式を陰から見ていた.妻と同じように夜中に子供を見に行っていたらしく、この男、決して子供を殺すつもりはなかったと思われるのだけど.
彼が殺意を抱いたのは、妻の子供を嫌いだと言う言葉を聞いたからであり、つまり、彼は妻の気持ちを考えて殺人に及んだのであって、彼にしてみれば、我が儘とは反対の行動であったのだけど.けれども、新婚当時のようにSEXをする妻が、自分の意のままであると思い込んでいた、妻が自分に嘘をつくとは思っても見なかった、その思い込みが我が儘な思い込みであり、自分の犯した殺人により妻は去って行く事によって、殺人という行為が我が儘な行為である、邪魔だから殺すという行為は、正に我が儘な行為に他ならないことを、彼は思い知ることになった.
彼は自殺をする.自殺とは我が儘な死に方と言えるのだけど、その死に方が、彼の我が儘な生き方の、それに対する責任の取り方でもあったと言えるのでしょうか.
他方の女は、男が自殺した屋敷から逃げ出した.先の自分が元で決闘になった、その決闘をほったらかして勝手に居なくなってしまった例を考えると、この女はめんどうなことは避けて通ること、言い換えれば、自分のしたことに何ら責任を負わないことが生き方らしい.
「男に惑わされる生き方は、そろそろ止めようと思う」と、この女は言ったけれど、この女が二人の男を惑わしたから決闘になったのであり、「男に惑わされる生き方は、そろそろ止めようと思う」、つまり、我が儘な男と付き合うのはよそうと思う、と言いたいらしいけれど、この言葉自体が、我が儘な言いぐさと言える.
-----------------------------------------
この男の死に様は、孤独であった.振り返れば、夫が浮気をすると言いはり、いつ戻るか分からない旅行に出てしまった.そして、残された妻は孤独であった.我が儘は、孤独をもたらし、そして、人を不安にさせる行為である.
赤ちゃんは人の話し声がした方が、安心してよく眠るという.一人残された妻もまた、作家の言葉を聞いて眠りに就いた.言い換えれば、彼女は作家の言葉に安らぎを求め、作家の言葉が彼女に安らぎを与えたからこそ、二人は関係を持ったと言ってよいのでしょう.
イノセント=インノセント=『罪無き者よ』
-----------------------------------------
妊娠3か月目のジュリアナは、ベットの上で刺繍をしていた.
夫は彼女に、医者を手配するから、堕胎すように言う.
彼は、話をしながらジュリアナの着物を脱がせ、布団をまくって、そして、寝間着をたくし上げると、彼女、その下には何も身につけていなかった.
「いいか」、彼は、妻の着物を、はぎ取るようにした.
「僕は無心論者だが」、言い終わった時には、ジュリアナは全裸.おっぱいも、あそこのお毛けも見えてる.
「善悪は、自分なりに、意識している」、こう言いながら、全裸の彼女を愛撫する.
「神にさばきを任せはしない」「責任だけはとるつもりだ」、きゃ、もっと見せて、スケベ.
-----------------------------------------
スケベなシーンを観客は真剣に観てくれるはず、ヴィスコンティはこう考えて、スケベなシンーンを背景にして、大切な言葉を、描き込んでいるらしい.
(もっとも、日本人が観ると、女の子の裸の方へ目が行ってしまい、字幕を読むのはおろそかになってしまうかも?)
「神にさばきを任せはしない.責任だけはとるつもりだ」
つまり、夫は自分は自分で裁くと言い、その言葉の通り、彼は自分を自分で裁いた.子供を殺した罪を、自殺することで償ったのだが、女は、男が自殺した屋敷から逃げ出した.
さて、この女、誰から裁きを受けるのか?
『罪無き者よ』= 自らも含め、誰からも裁きを受けることのない者.