
GW(いつのはなsry)中に行ってきたフランスの芸術家ソフィ・カルの展覧会です。
初めての原美術館、カフェも楽しめる美術館ランキングで堂々の1位を獲得した美術館で品川にあります。
中庭が良いとか書いてありましたが、正直思っていたよりも心地よくはなかったです。
メニューはとても洗練されていたと思いますけど!
しかし、何より問題なのは駅から 結 構 遠 い ということですね笑
駅直通の国立新美術館を見習ってほしいぜよ!若いってなんなんだr
んで、その国立新美術館は2位。
確かにあの吹きぬけの空間でコーヒー飲めたら幸せかもしれん。
ただ一杯1000円近いというね(^q^)
東京戻ったら社会人の特権で飲んでやるぜ!
とまあ、そんなくだらないことはさておき。
行って参りました「ソフィ・カル―最後のとき/最初のとき―」!
最初の動機はカフェだったのですが、展示そのものもなかなかどうして面白かったです。
「人の視覚体験」を扱った作品群で、とても新しい内容の展示でした。
副題でもある「最後のとき/最初のとき」の字義通り、最初の視覚体験と最後の視覚体験をビデオや手紙などのメディアに収め、展示していました。
いわゆる「美的体験」によらないコンセプチュアルアートの一種ですね。
どちらかというと「感性的感覚」というべきエステティックな展示だったと言えますね。
まず、「最初のとき」に関してですが、これを端的に示した作品は《海を見る》という名前の作品です。
この作品のコンセプトは、トルコの内陸部に居て一度も海を見たことない人々を、海の街イスタンブールに招き、その反応を1人ずつ記録するといったものです。
海を見た「最初のとき」をビデオというメディアに委ねた作品ですね。
子どもは無邪気にはしゃぎますが、年を重ねるにつれて圧倒される反応が多くなっているようでした。
自分が失ってしまった「初めての体験」を他人を通して体験するという作品は、自分の感覚と相手の体を同期するというプロセスを伴っているのではないか、ということを「考えさせられ」ました。
自己と他者を同期する、ということは同じ空間に存在せしめるということ。
そして、同じ空間に存在せしめる、というのはビデオの役割。
メディアの身体拡張ということは随分と前から言われていることですが、それを地で感じるような作品でしたね。
そして「最後のとき」は、《最後に見たもの》というスナップと手紙のメディアの作品に現れています。
失明した人のスナップの横に、失明した際に最後に見たものの記憶を説明した文章を載せるといったものです。
これは「現在のスナップ」と「過去を説明した文章」を併置させるという手法ですね。
ここから鑑賞者が辿るプロセスとは、この併置された両者から当時の状況を「想像」するということです。
先ほどの、身体を同期させるという現在性とは大きく異なるプロセスですね。
むしろ、真逆とも言って良い。
「身体の同期」というものがメディアの空間拡張につながっているとしたら、この「想像力」というものはメディアの時間拡張を感じさせるものがありますね。
同じ館内にありながら、鑑賞者には異なる知覚プロセスを求める点が非常に面白い展示でした。
「最初/最後」の副題に示されるように、二元論で攻めると理解がしやすくなるかもしれません。
hona-☆
初めての原美術館、カフェも楽しめる美術館ランキングで堂々の1位を獲得した美術館で品川にあります。
中庭が良いとか書いてありましたが、正直思っていたよりも心地よくはなかったです。
メニューはとても洗練されていたと思いますけど!
しかし、何より問題なのは駅から 結 構 遠 い ということですね笑
駅直通の国立新美術館を見習ってほしいぜよ!若いってなんなんだr
んで、その国立新美術館は2位。
確かにあの吹きぬけの空間でコーヒー飲めたら幸せかもしれん。
ただ一杯1000円近いというね(^q^)
東京戻ったら社会人の特権で飲んでやるぜ!
とまあ、そんなくだらないことはさておき。
行って参りました「ソフィ・カル―最後のとき/最初のとき―」!
最初の動機はカフェだったのですが、展示そのものもなかなかどうして面白かったです。
「人の視覚体験」を扱った作品群で、とても新しい内容の展示でした。
副題でもある「最後のとき/最初のとき」の字義通り、最初の視覚体験と最後の視覚体験をビデオや手紙などのメディアに収め、展示していました。
いわゆる「美的体験」によらないコンセプチュアルアートの一種ですね。
どちらかというと「感性的感覚」というべきエステティックな展示だったと言えますね。
まず、「最初のとき」に関してですが、これを端的に示した作品は《海を見る》という名前の作品です。
この作品のコンセプトは、トルコの内陸部に居て一度も海を見たことない人々を、海の街イスタンブールに招き、その反応を1人ずつ記録するといったものです。
海を見た「最初のとき」をビデオというメディアに委ねた作品ですね。
子どもは無邪気にはしゃぎますが、年を重ねるにつれて圧倒される反応が多くなっているようでした。
自分が失ってしまった「初めての体験」を他人を通して体験するという作品は、自分の感覚と相手の体を同期するというプロセスを伴っているのではないか、ということを「考えさせられ」ました。
自己と他者を同期する、ということは同じ空間に存在せしめるということ。
そして、同じ空間に存在せしめる、というのはビデオの役割。
メディアの身体拡張ということは随分と前から言われていることですが、それを地で感じるような作品でしたね。
そして「最後のとき」は、《最後に見たもの》というスナップと手紙のメディアの作品に現れています。
失明した人のスナップの横に、失明した際に最後に見たものの記憶を説明した文章を載せるといったものです。
これは「現在のスナップ」と「過去を説明した文章」を併置させるという手法ですね。
ここから鑑賞者が辿るプロセスとは、この併置された両者から当時の状況を「想像」するということです。
先ほどの、身体を同期させるという現在性とは大きく異なるプロセスですね。
むしろ、真逆とも言って良い。
「身体の同期」というものがメディアの空間拡張につながっているとしたら、この「想像力」というものはメディアの時間拡張を感じさせるものがありますね。
同じ館内にありながら、鑑賞者には異なる知覚プロセスを求める点が非常に面白い展示でした。
「最初/最後」の副題に示されるように、二元論で攻めると理解がしやすくなるかもしれません。
hona-☆










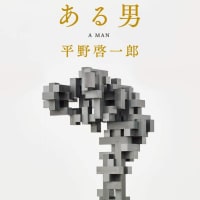









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます