前回に引き続き、クストリッツァ監督の作品で更新です。久しぶりに最高の映画体験をしました、というのが1995年にカンヌでパルムドールを受賞した『アンダーグラウンド』です。個人的に人生のベスト5に入る作品です!
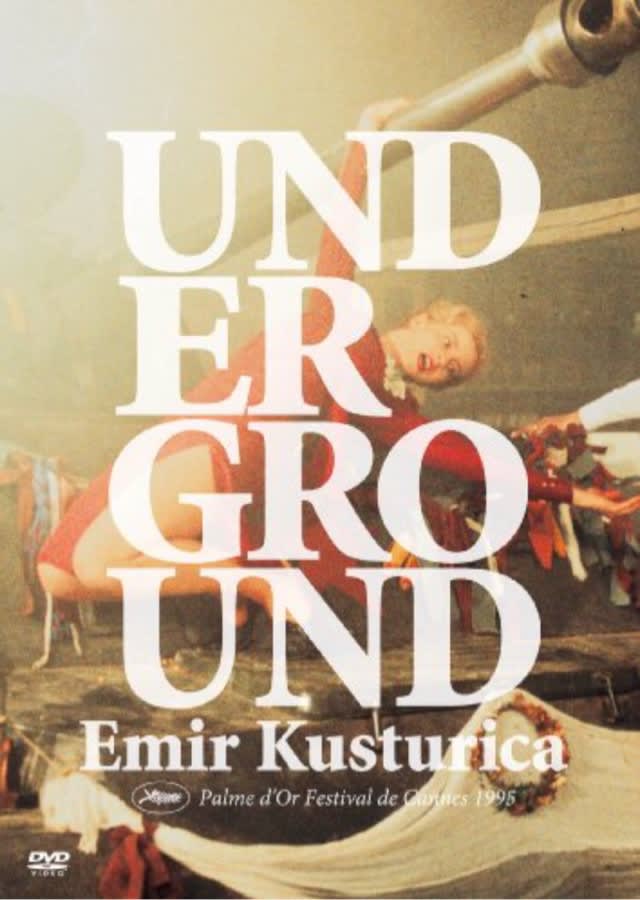
<Story>
1941年、ナチスに侵攻されたセルビア。パルチザンのマルコ(ミキ・マノイロヴィッチ)は地下室に弟のイヴァン(スラヴコ・スティマチ)や仲間のクロ(ラザル・リストフスキー)らをかくまい、武器を製造させることにする。英雄となったマルコは地下生活を続ける仲間たちには第2次世界大戦が続いていると思い込ませる一方、新政府の重要人物としてのし上がっていくが……。(Yahoo!映画より)
言葉では表現できないと言ってしまえばそれまでですが、この映画のスゴさはもう本当に観なければ伝わりません。ユーゴスラヴィアという国の興亡史というスケールの大きさだけではなく、ジプシーブラスによる祝祭的雰囲気、ブラックユーモアによる批判的姿勢など、色々な要素が詰まった映画なのです。

ヨヴァンとエレナ夫妻の結婚式
ユーゴスラヴィア解体に対する批判的姿勢とパルチザン賛美的な描写から、大セルビア主義に近いと非難を受けてもいたようですが、それはさて置き、『ジプシーのとき』でもテーマとなっていた「帰属意識」という問題が本作ではより直接的に取り上げられています。
ユーゴスラヴィアという帰属意識
『七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家』と表現されるユーゴスラヴィア。監督自身はセルビア人の父とムスリム人の母の元に生まれ、帰属意識はユーゴスラヴィアに在りました。
複雑な国でありながらも、そのアイデンティティはユーゴスラヴィアに存する、という考え方には確かに大セルビア主義と非難されるのにも納得ですが、それは「ユーゴスラヴィア」という個別の事象に目を向けた場合の話です。
この構造をより普遍的な問題として捉えるのであれば、それは「有名無実でも帰属意識は成立しうる」ということでしょう。それは何もユーゴスラヴィアに限った話ではありません。例えば、それは国を持たない民族であるユダヤ人やクルド人などにも当てはまるでしょう。(ユーゴスラヴィアが単一民族ではないという指摘はごもっともですが!)
そこでクストリッツァが媒介としたのがジプシーという存在です。彼らもまた「放浪する民族」でしかなく、固定の国を持たない集団。しかし文化もあれば帰属意識もある、その在り方に自身の境遇を重ねて表現しているのです。

要所で登場するジプシーブラス隊
天国(ユートピア)としての帰属意識
それではクストリッツァは普遍的な帰属意識をどのようにして表現したのか。ラストシーンで登場する天国の島が不滅の帰属意識を象徴しています。
共産党員として活躍したクロとマルコ、ヒロインのナタリア、クロの息子ヨヴァンなど、作中では死んでしまった主要人物たちがドナウ河沿いのある半島(=ユーゴスラヴィア的ユートピア)で宴を広げているシーンが最後に映写されます。直前まで戦火の場面であったのも相まり、突然映し出される牧歌的な映像と祝祭的なジプシーブラスの音楽は平和を象徴する天国のようです。
そこでは足の不自由なナタリアの弟バタは歩けるようになり、マルコの吃音症の弟イヴァンも流暢に話すことができる、正に不可能が可能になるユートピア的な空間として描写されます。
"Underground - Finale"
半島は陸地から分離し、遠くへと揺蕩っていくのですが、島上にある準共同体は一個体の生命のように一体となって祝祭を楽しみ続けます。それはさながらユーゴスラヴィアという共同体の彼岸のようでもあるわけです。
最後に墓標のように添えられるイヴァンの言葉は、共同体の普遍的な帰属意識を訴えかけているかのようです。
「苦痛と悲しみと喜びなしでは、子供たちにこう伝えられない。『むかし、あるところに国があった』、と」

クロとマルコとナタリア
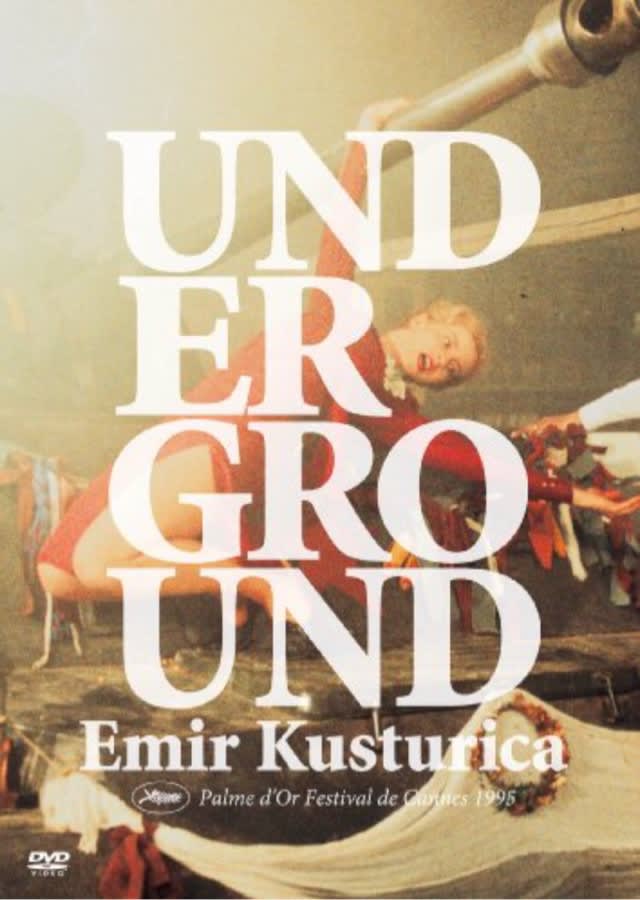
<Story>
1941年、ナチスに侵攻されたセルビア。パルチザンのマルコ(ミキ・マノイロヴィッチ)は地下室に弟のイヴァン(スラヴコ・スティマチ)や仲間のクロ(ラザル・リストフスキー)らをかくまい、武器を製造させることにする。英雄となったマルコは地下生活を続ける仲間たちには第2次世界大戦が続いていると思い込ませる一方、新政府の重要人物としてのし上がっていくが……。(Yahoo!映画より)
言葉では表現できないと言ってしまえばそれまでですが、この映画のスゴさはもう本当に観なければ伝わりません。ユーゴスラヴィアという国の興亡史というスケールの大きさだけではなく、ジプシーブラスによる祝祭的雰囲気、ブラックユーモアによる批判的姿勢など、色々な要素が詰まった映画なのです。

ヨヴァンとエレナ夫妻の結婚式
ユーゴスラヴィア解体に対する批判的姿勢とパルチザン賛美的な描写から、大セルビア主義に近いと非難を受けてもいたようですが、それはさて置き、『ジプシーのとき』でもテーマとなっていた「帰属意識」という問題が本作ではより直接的に取り上げられています。
ユーゴスラヴィアという帰属意識
『七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家』と表現されるユーゴスラヴィア。監督自身はセルビア人の父とムスリム人の母の元に生まれ、帰属意識はユーゴスラヴィアに在りました。
複雑な国でありながらも、そのアイデンティティはユーゴスラヴィアに存する、という考え方には確かに大セルビア主義と非難されるのにも納得ですが、それは「ユーゴスラヴィア」という個別の事象に目を向けた場合の話です。
この構造をより普遍的な問題として捉えるのであれば、それは「有名無実でも帰属意識は成立しうる」ということでしょう。それは何もユーゴスラヴィアに限った話ではありません。例えば、それは国を持たない民族であるユダヤ人やクルド人などにも当てはまるでしょう。(ユーゴスラヴィアが単一民族ではないという指摘はごもっともですが!)
そこでクストリッツァが媒介としたのがジプシーという存在です。彼らもまた「放浪する民族」でしかなく、固定の国を持たない集団。しかし文化もあれば帰属意識もある、その在り方に自身の境遇を重ねて表現しているのです。

要所で登場するジプシーブラス隊
天国(ユートピア)としての帰属意識
それではクストリッツァは普遍的な帰属意識をどのようにして表現したのか。ラストシーンで登場する天国の島が不滅の帰属意識を象徴しています。
共産党員として活躍したクロとマルコ、ヒロインのナタリア、クロの息子ヨヴァンなど、作中では死んでしまった主要人物たちがドナウ河沿いのある半島(=ユーゴスラヴィア的ユートピア)で宴を広げているシーンが最後に映写されます。直前まで戦火の場面であったのも相まり、突然映し出される牧歌的な映像と祝祭的なジプシーブラスの音楽は平和を象徴する天国のようです。
そこでは足の不自由なナタリアの弟バタは歩けるようになり、マルコの吃音症の弟イヴァンも流暢に話すことができる、正に不可能が可能になるユートピア的な空間として描写されます。
"Underground - Finale"
半島は陸地から分離し、遠くへと揺蕩っていくのですが、島上にある準共同体は一個体の生命のように一体となって祝祭を楽しみ続けます。それはさながらユーゴスラヴィアという共同体の彼岸のようでもあるわけです。
最後に墓標のように添えられるイヴァンの言葉は、共同体の普遍的な帰属意識を訴えかけているかのようです。
「苦痛と悲しみと喜びなしでは、子供たちにこう伝えられない。『むかし、あるところに国があった』、と」

クロとマルコとナタリア




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます