
こんにちは。最近更新がんばってますただけーまです。
さて、11連休という神のようなGWが始まりました。
長過ぎるが故に連休明け会社に行きたくない思いが募りまくりそう(笑)ですが、まあ今月は個人的にがんばった(当社比)つもりなので思いっきり羽を伸ばします。とりあえず、友人らと行く潮干狩りと屋久島トリップの楽しみみがやばみです。
さて、またまた映画になってしまいますが、レビューという名の感想文を提出したいと思います。本当は小説とか美術とか漫画とかネタは溜まっているのですが、なかなか文章に起こすのが億劫で放置中。そのうち内容忘れて永遠に書かないんじゃないかとさえ思います。※去年は闇に葬られた映画が多々あり。(『そして父になる』とか『東ベルリンから来た女』とか『ゼロ・ダーク・サーティ』とか……キャスリン・ビグローは書きたいなあ……)
そういえば『ローン・サバイバー』もまだ記事にしてないな……ラストシーンでぼろぼろ泣いてしまったので、こいつもいずれ書きたいが恐らく闇逝きの可能性が高くして云々……
ええと、気を取り直して。
今回はジョシュア・オッペンハイマー監督の『アクト・オブ・キリング』を観てきたので、その感想を下記につらつらと述べていきたいと思います。テイストとしては、結構昔に話題になった『華氏911』に近い(?)メッセージ性()の強いドキュメンタリー映画。内容よりもコンセプトが先行して制作された感じの映画で、だからもうシナリオの芸術的構成とか美的なロングショットの全くない、個人的には好きじゃないタイプの映画でした。※私が卒論で扱ったテーマは記録映画ですが……
正直、偶然から生じる美的価値というものは個人的には「在る」と思いますし、実際に今回の映画でも美的なシーンというのは在りましたが、どうにもやはり人工的に計算され尽くした美には敵わないというのが私的見解。美術とは即ち人の手による技術:アルスが根源であるという美学史的な観点からも、この考え方はある種妥当性があるような気もします。まあ、そうは言っても結局は「自然美」の孕む崇高的な価値(サブライム)に勝るものはないと個人的には思いますが……いかに第六感を刺激するかという点に於いて広大な自然に勝るものは在りますまい。
まあ、そんなことはさて置き。この映画はとにかく「凄く気持ち悪い」です。いや、もちろん良い意味で。個人的に好きじゃないタイプの映画でしたが、名作というのには大いに賛同できるような映画です。アイヒマン実験を思わせる心理学の実験のような映画で、なんというか部分的にではあれ「人の心の可視化」に若干成功したような映画で、可視化された人間の心の悍ましさに「気持ち悪さ」というものを感じてしまいました。
それでは、具体的に何が気持ち悪いのか考察(=感想)に移っていきます。
※以下、多分にネタばれなので「観るかも……」という方は左上の[戻る]ボタンをクリック!
[あらすじ]
1960年代のインドネシアで行われていた大量虐殺。その実行者たちは100万近くもの人々を殺した身でありながら、現在に至るまで国民的英雄としてたたえられていた。そんな彼らに、どのように虐殺を行っていたのかを再演してもらうことに。まるで映画スターにでもなったかのように、カメラの前で殺人の様子を意気揚々と身振り手振りで説明し、再演していく男たち。だが、そうした異様な再演劇が彼らに思いがけない変化をもたらしていく。
現在もインドネシアではプレマンと呼ばれる民兵団(ギャングやならず者の集団)が政局を左右するほどの非常に大きい力を持っています。プレマンの語源は「Free Man」で、アメリカ自由主義の思想を継承した集団でもある(作中ではしきりに自由が謳われていた)のですが、彼らは戦後のアメリカとソ連の対立構造の中で、共産主義者を次々と殺害し自由を勝ち取った英雄……として同国内では認知されています。しかしその実、無抵抗な共産主義者の残酷な処刑や華僑からの資金搾取など、やっていることはギャングそのもの。そんな連中が街を牛耳っている実情に、オッペンハイマーはカメラを向け、インドネシアの真実とは何かという具体的な事実を曝すことで、自由の行末とは何か、悪とは何か、といった人類普遍の問題にまで言及すうことに成功しています。
1.「アクト・オブ・キリング」という手法
広告の文句でも謳われている「これが悪の正体なのか」という文言からもわかる通り、この作品は基本的に悪者中心(国内では英雄として偽装されていますが)でストーリーが進んでいきます。無邪気に嘗ての処刑方法を説明して演じてみせたり、新聞会社と結託して無実の人を処刑したと笑いながら語ったり、華僑から当然のように金をゆすったり(寧ろ生かしている分善人だと言わんばかりの様子)といった典型的な「悪」のシーンが多く映写されます。
ジョシュアはこうした公的に認められた「悪」に対してどのような手法をとったのか。それが本作のタイトルでもある「殺戮の演技(=アクト・オブ・キリング)」をプレマンの指導者的立場にあったアンウォー・コンゴにさせるといったものになります。この手法の本質は一体何であったのか、監督は実際に何を狙っていたのか、というところは非常に気になるところですが、この手法が物語を揺らした機能は以下2つではないかと個人的には思われます。
(1)過去の再現
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という諺がありますが、彼らが無邪気に過去の悪事を話すことができるのは、それが既に過去の産物だからなのではないか、という疑問がどうしても残ってしまいます。記憶が褪せていくのは生きている以上仕方のないことですが、その喉元を過ぎてしまった悪事を「再び喉元に持ってきたらどうなるのか」という実験的機能がこの手法にはあるわけです。果たして彼らはこれまで通り悪事を嬉々として語ることができるのか、それとも何か変化が起きるのか……

撮影現場の指揮をするアンウォー・コンゴ
(2)立場の反転
そして、個人的にはこれが最も物語の根幹を揺さぶった、悪とは何かという命題に対する1つの成果を導いた要因だと感じているわけですけれども、この手法の中で非常に面白い(←語弊がある)のは殺戮者が被害者の役を演じる部分があるところです。演技ではあれ、嘗ての加害者が被害者へと反転する。これが殺戮者の良心を見事に呼び起こしているように感じました。この機能は最終的に良心の呵責が殺戮者を追い詰めるという結末へとつながっていきます。

被害者の役を演じるアンウォー・コンゴ
この映画の最後に悪の心がくじける(責任転嫁の思いと良心の呵責のせめぎ合い?)瞬間は、この映画の粋とも言うべきか、本作の実験的手法の成果を示す実に印象的なシーンです。「俺は悪いことをしたのか……?」と涙ぐみながら殺戮者が話すシーンには、非常に考えさせられる部分が多かったですね。
※以下、どうでもいいこと
①良心の呵責を呼び起こして自身の罪に気づかせるのって『ねじまきカギュー』という漫画での復讐手法にかなり似てますね。
②「殺戮の演技」……「殺戮縁起」って敵が『べるぜバブ』に出てたなあ。
2.自由主義の失敗
アンウォー・コンゴを始めとする殺戮者がしばしば語るのは、嘗てはそれが当たり前だった、生きていくには仕方がなかった、金を稼ぐにはそれしかなかった……といったような自身の大量殺人を正当化するような台詞です。この「悪事の責任転嫁」という人間の本能的な性質には、かの有名なアイヒマン実験を思い出さずにはいられませんでした。
自由主義に託けて行われた大量殺人はプレマンの中で罪悪感無く消化されていったものの、実際に殺戮シーンを再現する(自身が被殺害者となる)ことで喉元まで上がってきた罪への意識は、最早何にも託けることのできないものになっています。そこで「俺は悪いことをしたのか……?」という自問につながっていくわけですね。監督がここまで意図していたのかはわかりませんが、ここでの主役の心境の変化には目を見張るものがあります。
まだプレマンたちが覇権を握っていない時代、それは自由主義に属しているが故に自身で責任を取ることなく共産主義者たちを殺害することが出来た時代でした。そのような事象はインドネシアに限ったことではなく、所謂「赤狩り」というものが当たり前に行われていた、ある種時代の風潮という側面さえあった時代のように推測されます。
しかし、今回再現された疑似殺戮が撮影された時代、それは自由主義かさも当然かのように「蔓延」している時代になるわけです。(本質的云々はさて置き)サルトルの「人間は自由という刑に処せられている」という有名な言葉がありますが、まさにその通りで、あらゆる行為に責任が伴ってくる時代に於いてジョシュアの行ったこの「アクト・オブ・キリング」という実験的手法は「自由とは何か」「正義とは何か」「人間とは何か」といった人文学的な人類普遍の命題に一石を投じることが出来たのではないでしょうか。
キャストのほとんど全員が"anonymous"と表記されたエンドロールが流れるのを見て、果たして自由とは何なのかと考えずにはいられません。平和な時代、平和な場所に生まれてこれてよかったと感じるとともに、自身のドメスティックな姿勢を是正しなければいかんとも思いましたね。
hona-☆
さて、11連休という神のようなGWが始まりました。
長過ぎるが故に連休明け会社に行きたくない思いが募りまくりそう(笑)ですが、まあ今月は個人的にがんばった(当社比)つもりなので思いっきり羽を伸ばします。とりあえず、友人らと行く潮干狩りと屋久島トリップの楽しみみがやばみです。
さて、またまた映画になってしまいますが、レビューという名の感想文を提出したいと思います。本当は小説とか美術とか漫画とかネタは溜まっているのですが、なかなか文章に起こすのが億劫で放置中。そのうち内容忘れて永遠に書かないんじゃないかとさえ思います。※去年は闇に葬られた映画が多々あり。(『そして父になる』とか『東ベルリンから来た女』とか『ゼロ・ダーク・サーティ』とか……キャスリン・ビグローは書きたいなあ……)
そういえば『ローン・サバイバー』もまだ記事にしてないな……ラストシーンでぼろぼろ泣いてしまったので、こいつもいずれ書きたいが恐らく闇逝きの可能性が高くして云々……
ええと、気を取り直して。
今回はジョシュア・オッペンハイマー監督の『アクト・オブ・キリング』を観てきたので、その感想を下記につらつらと述べていきたいと思います。テイストとしては、結構昔に話題になった『華氏911』に近い(?)メッセージ性()の強いドキュメンタリー映画。内容よりもコンセプトが先行して制作された感じの映画で、だからもうシナリオの芸術的構成とか美的なロングショットの全くない、個人的には好きじゃないタイプの映画でした。※私が卒論で扱ったテーマは記録映画ですが……
正直、偶然から生じる美的価値というものは個人的には「在る」と思いますし、実際に今回の映画でも美的なシーンというのは在りましたが、どうにもやはり人工的に計算され尽くした美には敵わないというのが私的見解。美術とは即ち人の手による技術:アルスが根源であるという美学史的な観点からも、この考え方はある種妥当性があるような気もします。まあ、そうは言っても結局は「自然美」の孕む崇高的な価値(サブライム)に勝るものはないと個人的には思いますが……いかに第六感を刺激するかという点に於いて広大な自然に勝るものは在りますまい。
まあ、そんなことはさて置き。この映画はとにかく「凄く気持ち悪い」です。いや、もちろん良い意味で。個人的に好きじゃないタイプの映画でしたが、名作というのには大いに賛同できるような映画です。アイヒマン実験を思わせる心理学の実験のような映画で、なんというか部分的にではあれ「人の心の可視化」に若干成功したような映画で、可視化された人間の心の悍ましさに「気持ち悪さ」というものを感じてしまいました。
それでは、具体的に何が気持ち悪いのか考察(=感想)に移っていきます。
※以下、多分にネタばれなので「観るかも……」という方は左上の[戻る]ボタンをクリック!
[あらすじ]
1960年代のインドネシアで行われていた大量虐殺。その実行者たちは100万近くもの人々を殺した身でありながら、現在に至るまで国民的英雄としてたたえられていた。そんな彼らに、どのように虐殺を行っていたのかを再演してもらうことに。まるで映画スターにでもなったかのように、カメラの前で殺人の様子を意気揚々と身振り手振りで説明し、再演していく男たち。だが、そうした異様な再演劇が彼らに思いがけない変化をもたらしていく。
現在もインドネシアではプレマンと呼ばれる民兵団(ギャングやならず者の集団)が政局を左右するほどの非常に大きい力を持っています。プレマンの語源は「Free Man」で、アメリカ自由主義の思想を継承した集団でもある(作中ではしきりに自由が謳われていた)のですが、彼らは戦後のアメリカとソ連の対立構造の中で、共産主義者を次々と殺害し自由を勝ち取った英雄……として同国内では認知されています。しかしその実、無抵抗な共産主義者の残酷な処刑や華僑からの資金搾取など、やっていることはギャングそのもの。そんな連中が街を牛耳っている実情に、オッペンハイマーはカメラを向け、インドネシアの真実とは何かという具体的な事実を曝すことで、自由の行末とは何か、悪とは何か、といった人類普遍の問題にまで言及すうことに成功しています。
1.「アクト・オブ・キリング」という手法
広告の文句でも謳われている「これが悪の正体なのか」という文言からもわかる通り、この作品は基本的に悪者中心(国内では英雄として偽装されていますが)でストーリーが進んでいきます。無邪気に嘗ての処刑方法を説明して演じてみせたり、新聞会社と結託して無実の人を処刑したと笑いながら語ったり、華僑から当然のように金をゆすったり(寧ろ生かしている分善人だと言わんばかりの様子)といった典型的な「悪」のシーンが多く映写されます。
ジョシュアはこうした公的に認められた「悪」に対してどのような手法をとったのか。それが本作のタイトルでもある「殺戮の演技(=アクト・オブ・キリング)」をプレマンの指導者的立場にあったアンウォー・コンゴにさせるといったものになります。この手法の本質は一体何であったのか、監督は実際に何を狙っていたのか、というところは非常に気になるところですが、この手法が物語を揺らした機能は以下2つではないかと個人的には思われます。
(1)過去の再現
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という諺がありますが、彼らが無邪気に過去の悪事を話すことができるのは、それが既に過去の産物だからなのではないか、という疑問がどうしても残ってしまいます。記憶が褪せていくのは生きている以上仕方のないことですが、その喉元を過ぎてしまった悪事を「再び喉元に持ってきたらどうなるのか」という実験的機能がこの手法にはあるわけです。果たして彼らはこれまで通り悪事を嬉々として語ることができるのか、それとも何か変化が起きるのか……

撮影現場の指揮をするアンウォー・コンゴ
(2)立場の反転
そして、個人的にはこれが最も物語の根幹を揺さぶった、悪とは何かという命題に対する1つの成果を導いた要因だと感じているわけですけれども、この手法の中で非常に面白い(←語弊がある)のは殺戮者が被害者の役を演じる部分があるところです。演技ではあれ、嘗ての加害者が被害者へと反転する。これが殺戮者の良心を見事に呼び起こしているように感じました。この機能は最終的に良心の呵責が殺戮者を追い詰めるという結末へとつながっていきます。

被害者の役を演じるアンウォー・コンゴ
この映画の最後に悪の心がくじける(責任転嫁の思いと良心の呵責のせめぎ合い?)瞬間は、この映画の粋とも言うべきか、本作の実験的手法の成果を示す実に印象的なシーンです。「俺は悪いことをしたのか……?」と涙ぐみながら殺戮者が話すシーンには、非常に考えさせられる部分が多かったですね。
※以下、どうでもいいこと
①良心の呵責を呼び起こして自身の罪に気づかせるのって『ねじまきカギュー』という漫画での復讐手法にかなり似てますね。
②「殺戮の演技」……「殺戮縁起」って敵が『べるぜバブ』に出てたなあ。
2.自由主義の失敗
アンウォー・コンゴを始めとする殺戮者がしばしば語るのは、嘗てはそれが当たり前だった、生きていくには仕方がなかった、金を稼ぐにはそれしかなかった……といったような自身の大量殺人を正当化するような台詞です。この「悪事の責任転嫁」という人間の本能的な性質には、かの有名なアイヒマン実験を思い出さずにはいられませんでした。
自由主義に託けて行われた大量殺人はプレマンの中で罪悪感無く消化されていったものの、実際に殺戮シーンを再現する(自身が被殺害者となる)ことで喉元まで上がってきた罪への意識は、最早何にも託けることのできないものになっています。そこで「俺は悪いことをしたのか……?」という自問につながっていくわけですね。監督がここまで意図していたのかはわかりませんが、ここでの主役の心境の変化には目を見張るものがあります。
まだプレマンたちが覇権を握っていない時代、それは自由主義に属しているが故に自身で責任を取ることなく共産主義者たちを殺害することが出来た時代でした。そのような事象はインドネシアに限ったことではなく、所謂「赤狩り」というものが当たり前に行われていた、ある種時代の風潮という側面さえあった時代のように推測されます。
しかし、今回再現された疑似殺戮が撮影された時代、それは自由主義かさも当然かのように「蔓延」している時代になるわけです。(本質的云々はさて置き)サルトルの「人間は自由という刑に処せられている」という有名な言葉がありますが、まさにその通りで、あらゆる行為に責任が伴ってくる時代に於いてジョシュアの行ったこの「アクト・オブ・キリング」という実験的手法は「自由とは何か」「正義とは何か」「人間とは何か」といった人文学的な人類普遍の命題に一石を投じることが出来たのではないでしょうか。
キャストのほとんど全員が"anonymous"と表記されたエンドロールが流れるのを見て、果たして自由とは何なのかと考えずにはいられません。平和な時代、平和な場所に生まれてこれてよかったと感じるとともに、自身のドメスティックな姿勢を是正しなければいかんとも思いましたね。
hona-☆










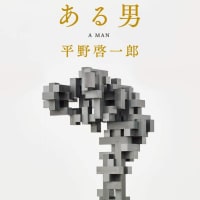









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます