おはようございます。ようやく暖かくなってきましたね。落ち着いたら誰かお花見でも行きましょう。
桜庭一樹さんの『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』を読みました。

映画化された桜庭一樹さんの『私の男』は観ましたが、小説は初めて読みます。こういう口語調のライトな小説を読むのは久しぶりでしたが、扱っているテーマが重く心にずっしりくる内容。救えない結末がなんとも哀しい物語ですが、横行している児童虐待の問題に正面から向き合った作品です。
母子家庭で生活を支える山田なぎさと元芸能人の父親海野雅愛から虐待を受ける海野藻屑、形は違えど現状に問題があるふたりの少女の物語です。
構造としては、ふたりが出会ってから徐々に心を通わせていく過去のシーンと、なぎさが兄の友彦とともに行方知れずとなった藻屑を探しに山を登る現在のシーンが交互に展開されます。
冒頭から美少女のバラバラ殺人死体というバッドエンドが予告されているせいなのか、緩やかに、不器用に育まれていく友情は、定期的に挿入される現在のシーン(藻屑の悲劇を詳らかにするシーン)によって、より儚さが強調されるようです。
父権的構図
男女間の問題を作者が盛り込もうとしたのかは定かではありませんが、花名島による過剰な暴力シーンや藻屑の身体に残る虐待の傷痕からはそうした「男性の恐ろしさ」のようなものも感じられます。
「クラス内の男子」のアイコンである花名島が割って入れないふたりの関係性にはエスのような尊さも感じさせつつ、花名島と海野雅愛による父権的暴力によって、女性(或いは子供)の脆さが対比されているようです。
神的存在
そして少し特殊なのがなぎさの兄である友彦の存在。本文中でも神が宿っていると表現される友彦は、全能的な第三者の視点から詰まりそうな物語をうまく流していく役割を担っています。
こうした「物語から一線を画す存在」というのは割と昔からあって、パッと思いつくところで言うと『ボリス・ゴドゥノフ』の乞食とか、『アンダーグラウンド』の吃音症患者なんかがそれにあたります。彼らに共通しているのは権力に与していないという点。権力は、神的役割を付与しやすいのかもしれませんね。
砂糖菓子の弾丸
タイトルにもなり、かつ文中にも頻出する「弾丸」とは一体何か。それは「現状を打開する力」のようなものです。
なぎさはニートの兄と母子家庭を支えるために、若くから収入を得られる自衛隊という実弾を得ようとする。その一方で、藻屑は現実を打開するのではなく空想に逃げようとする、いわば何も撃ち抜けない「砂糖菓子の弾丸」を求めるわけです。現状の課題に対するふたりの対称的な考え方が伺えます。
私は人魚だから陸地の空気に汚染されてると身体中の痣を説明し、引きずる足も人魚だから上手く歩けないと言う藻屑は、結局虐待の果てに命を落としてしまう。
虐待を庇うのは何故か。それは虐待されても、父親しか頼れなかった子供の現実があるからです。虐待されている子供は、親に依存する傾向が強いのは、闘うための実弾を持たないからなんでしょう。子供にとっての実弾は結局親でしかないのです。
子供の頃は本当に世界が狭くて、何もできないと思っていて、大人になったら自由になれるなんて考えもつかなくて…だから、急に実弾を持たされても、どう闘ったら良いかわからない大人たちも多いのです。
桜庭一樹さんの『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』を読みました。

映画化された桜庭一樹さんの『私の男』は観ましたが、小説は初めて読みます。こういう口語調のライトな小説を読むのは久しぶりでしたが、扱っているテーマが重く心にずっしりくる内容。救えない結末がなんとも哀しい物語ですが、横行している児童虐待の問題に正面から向き合った作品です。
母子家庭で生活を支える山田なぎさと元芸能人の父親海野雅愛から虐待を受ける海野藻屑、形は違えど現状に問題があるふたりの少女の物語です。
構造としては、ふたりが出会ってから徐々に心を通わせていく過去のシーンと、なぎさが兄の友彦とともに行方知れずとなった藻屑を探しに山を登る現在のシーンが交互に展開されます。
冒頭から美少女のバラバラ殺人死体というバッドエンドが予告されているせいなのか、緩やかに、不器用に育まれていく友情は、定期的に挿入される現在のシーン(藻屑の悲劇を詳らかにするシーン)によって、より儚さが強調されるようです。
父権的構図
男女間の問題を作者が盛り込もうとしたのかは定かではありませんが、花名島による過剰な暴力シーンや藻屑の身体に残る虐待の傷痕からはそうした「男性の恐ろしさ」のようなものも感じられます。
「クラス内の男子」のアイコンである花名島が割って入れないふたりの関係性にはエスのような尊さも感じさせつつ、花名島と海野雅愛による父権的暴力によって、女性(或いは子供)の脆さが対比されているようです。
神的存在
そして少し特殊なのがなぎさの兄である友彦の存在。本文中でも神が宿っていると表現される友彦は、全能的な第三者の視点から詰まりそうな物語をうまく流していく役割を担っています。
こうした「物語から一線を画す存在」というのは割と昔からあって、パッと思いつくところで言うと『ボリス・ゴドゥノフ』の乞食とか、『アンダーグラウンド』の吃音症患者なんかがそれにあたります。彼らに共通しているのは権力に与していないという点。権力は、神的役割を付与しやすいのかもしれませんね。
砂糖菓子の弾丸
タイトルにもなり、かつ文中にも頻出する「弾丸」とは一体何か。それは「現状を打開する力」のようなものです。
なぎさはニートの兄と母子家庭を支えるために、若くから収入を得られる自衛隊という実弾を得ようとする。その一方で、藻屑は現実を打開するのではなく空想に逃げようとする、いわば何も撃ち抜けない「砂糖菓子の弾丸」を求めるわけです。現状の課題に対するふたりの対称的な考え方が伺えます。
私は人魚だから陸地の空気に汚染されてると身体中の痣を説明し、引きずる足も人魚だから上手く歩けないと言う藻屑は、結局虐待の果てに命を落としてしまう。
虐待を庇うのは何故か。それは虐待されても、父親しか頼れなかった子供の現実があるからです。虐待されている子供は、親に依存する傾向が強いのは、闘うための実弾を持たないからなんでしょう。子供にとっての実弾は結局親でしかないのです。
子供の頃は本当に世界が狭くて、何もできないと思っていて、大人になったら自由になれるなんて考えもつかなくて…だから、急に実弾を持たされても、どう闘ったら良いかわからない大人たちも多いのです。










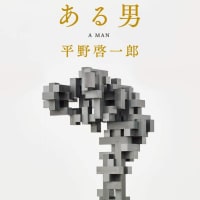









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます