京大の小出准教授や西川福井県知事は、原発の利益を受けてきた都市部に建てるべきだ。
多摩大学の田坂教授は、沖縄を除く、各都道府県が協議・協力して作るべきだ。大阪の橋下市長は、安全性が確保されるならばと言う条件付で、大阪で受け入れる可能性もある。と発言されています。
私は、事故やテロ、ミサイルの危険性を考えると、余りにも使用済み核燃料を集中して保管するのは、現実的ではないと思われますし、都市部では危険性が高くなると思われます。施設が大きくなればなるほど、事故などが起こったときの危険性は高くなります。その点では、できるだけ分散したほうがいいと思いますが、あまりに分散しすぎるのも、管理や警備がやっかいになりそうですし、建設の同意を得なければいけない人々の数が増えすぎるのも、かえって建設が困難になりそうでもあります。
田坂教授の提言、「依存型民主主義」を脱し「参加型民主主義」へ
田坂教授は、政府に対して、近い時期に「法律的枠組み」の議論を始めることを提言しています。 すなわち、すべての国民に使用済み核燃料の貯蔵と処分の問題を考えることを促すための「法律的枠組み」です。まず、その議論を始めること、具体的には、「すべての都道府県が、過去に恩恵に浴した原発電力量に相当する使用済み核燃料の長期貯蔵を引き受ける」という法律を検討すべきでしょう。そうした法律が実際に成立するか否かは、難しい問題ですが、まず、すべての国民が、この問題を「自分たち一人ひとりの問題」として真剣に考える状況を生み出すことが、政府の役割として重要でしょう。 もとより、すべての都道府県に使用済み核燃料の長期貯蔵施設を建設することは、現実的ではありません。
従って、この法律には、上記の条項に加えて「各都道府県が協議・協力して集中貯蔵施設を建設することを、政府は全面的に支援する」という条項を入れるべきでしょう 本当に、そうした法律が上程され得るか否か以前に、この問題を「法律的枠組み」の問題として国民に提起し、メディアも含めた国民的討議を促すことに、極めて重要な意義があると思います。 なぜなら、これまでの原子力政策は、「原子力村が、密室で進めてきた」という批判がある一方で、国民の側にも、「政府と電力会社に任せておけば、原発の問題も、うまくやってくれる」という無意識の依存心理があったのも事実だからです。 すなわち、これから原発問題やエネルギー問題を正しく解決していくためには、まず、国民全体が、こうした「依存型民主主義」の意識を脱し、国民一人ひとりが、この問題を「自らの問題」として受け止め、議論し、政策決定に参画していく「参加型民主主義」の意識へと成熟していくことが求められているのです。とのべられています。
しかし、どこに作るにしても、建設するまでに、時間がかかってしまい、核燃料プールにある核燃料は、危険に晒され続けることになります。
2014年7月19日 「脱原発四日市市民の集い」2014年度第3回原発シンポジウム 園田淳










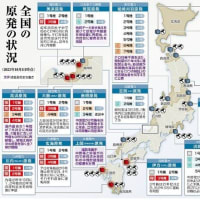


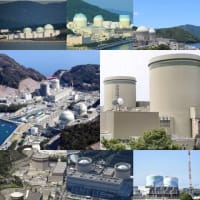






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます