今日、書店を歩いていて、
以前から思っていたいこととともに
感じたことがあります。
教育の場に行かなかった自分がいうのも難ですが、
教育者って、信念は持ってないといけませんが、
それを具現化するための、
「いろいろな」引き出しを持たないといけないんだろうな、
ということです。
「いろいろな」というのがミソなんですよね。
というか、教育の「全て」がここに凝縮されていると思います。
「いろいろな」人間がいるという前提に立つこと、
これに尽きるんじゃないかと思ったりします。
「教育は斯くあるべきだ」という話を聞くと、
正直、「いい加減にしろ」と思います。
斯くあるべきという場合は、
斯くあるべき方向に導くための手段を沢山持たないといけない、
そう思っています。
結局、何が腹立たしくて書いているかというと、
某ヨットスクールのように、
一つの方法しか持たない人間が、
教育についてのたまっているのを見る時です。
あれは、自分が「一つの方法しか持てない無能な教育者」であることを
自白していることになるのに、
分からないのかなと思います。
いろいろな人間がいるという前提に立てば、
同じことをしても、それで良い人とダメな人がいます。
ダメな人の場合は、別の方法を試さないといけない。
前のヨットスクールの例に立てば、
そこの一通りのやり方で全ての子供を矯正できるという。
「有り得ない」でしょう。
人間は、肉体的、精神的に、
個体差があります。
とりわけ精神面においては、
体力の様に、見た目や数値に表れない分、
非常に誤解されやすいです。
「頑張るな」という最近の行き過ぎた風潮はどうかと思いますが、
「頑張れば何とかなる」というのは明らかな間違いです。
頑張ることにも、個体差があるのです。
勘違いして欲しくないのは、
ここを決して「逃げ道」にしてはいけないのですが、
個体差を認めることは、極めて重要なことだということです。
先も書いたとおり、
通り一遍の教育論で、一つの方向性で、
全ての子供を何とかできると思ったら、
それは間違いなく大いなる驕りだと思います。
右も左も関係なく、
それだけが、本当に腹が立つんですよね。
「教育再生会議」のメンバーに対して、
僕自身が偏見を持つのも、
今まで書いたこととどこかしら矛盾するので、
それは控えないとと思うのですが、
百歩譲って、在るべき姿とやらに向かわせる場合に、
在るべき姿の前には、
その人数だけの個体数があることを認識して欲しい、
そう思います。
長くなりました。。。ごめんなさい。。。













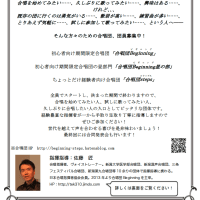





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます