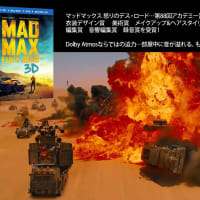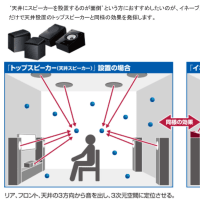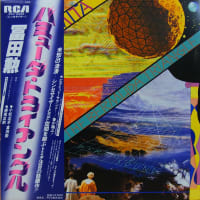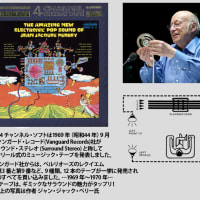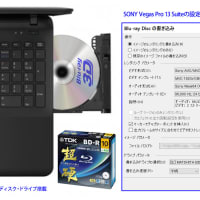JVC KENWOOD GS-TD1-B で3D撮影に興じて早くも8ヶ月になります。
2011年11月11日に購入...その後に2012年5月15日に追加購入しました。
現在...この GS-TD1-B が Amazon で何と 45,420円なんです。
実に驚異的な安値です。 もう1台欲しくなりました。
私が何故... GS-TD1-B に熱中しているのかと申しますと...
1. 高画質...色調が実に整っている。特に「黒と白の表現」が良い。
2. 内臓ステレオ・マイクが高音質...楽器音の収録にも使える。
3. インテリジェントオート...旅行と屋外での撮影がラクチン。
4. マニュアル機能が充実...特にホワイト・バランスの調整がし易い。
5. インテリジェントオートとマニュアルの切り替えが簡易。
しかし、欠点も幾つかあります。ひとつは「ファイルの細分化」。
「MP4(MVC・フレームシーケンシャル)/TXP画質」の長時間連続撮影では
録画ファイルが「3.89GBごと(約16分20秒間)」に細分化されます。
各録画ファイルを連結すると画像は途切れずに繋がりますが
「繋ぎの箇所で音声が一瞬途切れる」という重大な欠陥があります。
従ってコンサートなどの収録では別途に音質の良いステレオ・マイクと
メモリー・レコーダーで「途切れなく録音」しておくことが大切。
もうひとつの欠陥は「MP4(MVC・フレームシーケンシャル)」と
「AVCHD 3D(MVC・フレームシーケンシャル)」のファイルは
Vegas Pro 11のタイムラインに載せても「3Dにならない」のです。
これは実に厄介なことです。
「AVCHD 3D(MVC・フレームシーケンシャル)」は SONY HDR-TD10/20 の
「MVC(SONY 独自規格)」と同じ形式のものではないようです。
従って、「MP4(MVC・フレームシーケンシャル)/TXP画質」で撮影し
CyberLink PowerDirector 10 で「H.264 AVC」の
「サイド バイ サイド フル幅(L/R)AVCHD 1920 x 1080/60i[Double]」または
「サイド バイ サイド ハーフ幅(L/R)AVCHD 1920 x 1080/60i」...
「H.264 マルチ ビュー コーディング AVCHD 1920 x 1080/60i」に変換して
Vegas Pro 11のタイムラインに載せて編集を行っています。

★ 3Dビデオ収録は音声にも気配りが大切 ★
私は元々...“オーディオ・マニア”。中学生の頃からステレオ・アンプや
音質の良いスピーカー・システムの探究と自作に熱中していました。
55年前...お小遣いを貯めて完成させたステレオ再生システムは音楽好きの
祖父が絶賛してくれた高音質なものでした。
新宿の中古レコード店で買い求めた米国RCAのステレオ・レコード...
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団「新世界(ドボルジャーク)」が
素晴らしい立体音響で鳴り響いた感動が今も記憶に残っています。
1960年代になるとステレオ・レコードが数多く発売されるようになりました。
私が最も愛聴したのが英国デッカの「ロンドン・フェイズ4シリーズ」。
特にスタンリー・ブラック指揮ロンドン・フェスティバル管弦楽団と
ビッグ・バンド...テッド・ヒース楽団のステレオ・レコード。次いで...
米国マーキュリー・レコードの「35mmマグネチック・フィルム・シリーズ」。
2000年...超高音質と銘打った「スーパー・オーディオCD」が登場して
我がオーディオ・ライフを一層充実させてくれました。
特に米国RCAの名演奏・名録音盤(1957~1960)が
スーパー・オーディオCDで復刻されたことが嬉しい限りです。
“オーディオ・マニア”には「ふたつの派」があります。
「再生音探究派」と「生録派」です。前者はレコード再生を主としたもので
後者は自ら録音して楽しむ人です。1970年代のことですねぇ。
高級オーディオ機器メーカーが「生録コンサート」を開催したこともありました。
ホールの客席に大きな録音機とステレオ・マイクを持ち込み
ヘッドホンでモニターしながら「VUメーター」の監視に熱中するのです。
私は主催者側の依頼による「総合司会と録音の指導」を受け持っていました。
何故なら、私は当時オーディオ専門誌で連載記事を執筆していたからです。
その後、「生録」は衰退しました。録音派はFMステレオ放送のエア・チェックに
熱中するようになったのです。当然ながら...レコード製造と販売業界は
音楽著作権協会と歩調を合わせ、この事態に猛反発。
私のビデオ収録と編集は「高品位な音質の探究」です。しかも...
「なるべくコストを掛けない」ということに徹しています。
吹奏楽と管弦楽の収録においてはホールの常備されている
「三点吊りステレオ・マイク」を基本的に活用していますが
それが「高品位な音質」とは言えない場合が多々ありました。

私は ZOOM H2n というサラウンド・マイクを独自に改良を加えたものを使用。
雄大な低音を響かせる大太鼓、耳を圧するブラスのテュッティ、切ない音色の
オーボエやユーフォニアム、そしてホールの響きと盛大な拍手...これらを
臨場感豊かに伝える5.1チャンネル・サラウンドに仕上げています。

ビデオカメラに内臓されたステレオ・マイクと音声収録回路は
実にチープなもので、決して良質な音ではありません。
特に自動録音レベルは最悪...突然の大きな音で全体の音量が下がったり
静かな雰囲気なのに音量が大きくなったり、不自然極まります。
SONY HDR-TD10 は録音レベルを「低」にしても歪みがちです。
JVC KENWOOD GS-TD1-B は「-1~-2」に設定するとコンサートや
イベントのPAスピーカーが発する大音量でも歪みません。
逆に野鳥の声や虫の音を収録する際は「+1~+2」に設定すると自然です。
そして、「3Dサウンド」に設定すると普通のステレオ・スピーカーでも
サラウンド感豊かな再生音が楽しめます。旅のスナップやイベントなどを
「3Dサウンド」で収録すると再生時に臨場感が満喫できます。

JVCが1970年代に開発した「バイフォニック技術」を使っています。
上図は JVC KENWOOD GS-TD1 の「3Dサウンド」を解説しているページを参考にしました。
「バイフォニック」は人間の頭部を模した形状の「両耳部」がマイクになっています。
GS-TD1 のマイクは「耳の形状(耳介...耳たぶ)」を想定したものとのことです。
なんとも実に素晴らしいアイデアです。
これは、スピーカーで聴いている音声が、ヘッドホンのように
Lchに記録された音声は左耳だけで、Rchに記録された音声は右耳だけで
聴くことができ、音の広がり感の再現が可能になるわけです。
これを記録の段階で行っており、アーカイブ先の再生環境で3Dサウンド効果が得られる...
というわけですが、ヘッドホンではなくステレオ・スピーカーで聴くことが原則。
JVC 3Dサウンドのデモ
映像作家・幻 彩のホームページ