依存症の治療において「マトリックスモデル」という外来治療を基本としたモデルが注目されている。
これまで我が国のアルコール依存症などの治療は底付き体験を重視し、治療継続性を重視していなかった。
コントロールを失った飲酒行動により身体的にもボロボロになり、社会的信用や家族の信用などを失い、このままでは死んでしまう、しかし自分一人ではやめられないと思い知るいわゆる「底付き体験」を経て断酒を決心し断酒の3本柱(断酒会、通院、嫌酒薬)をつづけながら一日一日断酒を継続することが治療の中心であった。
結果として外来は投薬と短いカウンセリングのみであとは自助グループまかせというスタンスになりがちであった。
一方、入院型、入所型のアルコール依存症の専門病院でも他の精神障害の合併などがあり、プログラムの型にはまらない患者は対象外として放置されてきた。また退院後の十分なフォローができず治療が継続できない人が多かった。
しかしアルコール依存症は糖尿病や高血圧、タバコ、がんなどと同様の慢性疾患であると考えると、それぞれの地域で継続した治療を受けなければすぐに再発するのは当然だ。
マトリックスモデルにおいでは依存症治療の最終目標は、断酒・断薬ではなく、依存症と言う病を生き延びることができるように援助することだと考える。
マトリックスモデルでは外来ベースの初期回復プログラム、再発予防プログラム、家族教育プログラム、社会支援プログラムなど様々な治療プログラムが用意され、入院は急性増悪時のみに限る。
何度も失敗を繰り返し乱用がとまらない患者にはうんざりし患者の責任にかえしてしまいたくなるが、「治療継続性を重視」し、乱用がとまらない責任は患者ではなく援助者側にあると考える。
一律に断酒、断酒を目標として患者に押し付ける治療は早期の治療中断をもたらしやすい。
患者の中には節酒に戻ることが可能な群もいる。
治療継続性が予後に関連するので、とにかく来続けてもらうことを重視し「動機付け面接」を繰り返す。
すぐに嗜癖がとまらなくても、病識が不十分でも争わず、通院継続をねぎらう受容的な態度で接する。
再乱用時(スリップ時)にも突き放すのではなく援助を継続する。
嗜癖行動が、本人にとってメリットになっていた側面とデメリットになっていた面を客観的に把握してもらう認知への介入をおこなう。
細かなスケジューリングで暇な時間をなくす、HALT (Hungry,Angry,Lonely,and Tired)などトリガーとなるものを確認し対処行動を学んでもらうなど行動へも介入する。
プログラムではお菓子やコーヒーなども提供し、明るく受容的な雰囲気を重視し、ワークブックを用いて具体的にやめ方を学ぶ。
治療的な「場」が治療を促進すると言う考え方だ。
(東洋医学の外経絡・褥創のラップ療法みたく。)
現代社会においてギャンブルや買い物、リストカットやひきこもり、摂食障害、ボーダーラインパーソナリティ障害など依存症モデルとしてとらえることのできる精神疾患は多い。
嗜癖行動の行動変容にはマトリックスモデルのように場の力を利用したサポーテッド ピア サポート(Supported Peer Support)が鍵となる。
身体疾患でも多職種による継続的、多面的援助で心理的サポートを重視し行動変容を期待する藤沢町民病院の健康増進外来なども注目されているが、これもそういう時代の流れなのであろう。
これまで我が国のアルコール依存症などの治療は底付き体験を重視し、治療継続性を重視していなかった。
コントロールを失った飲酒行動により身体的にもボロボロになり、社会的信用や家族の信用などを失い、このままでは死んでしまう、しかし自分一人ではやめられないと思い知るいわゆる「底付き体験」を経て断酒を決心し断酒の3本柱(断酒会、通院、嫌酒薬)をつづけながら一日一日断酒を継続することが治療の中心であった。
結果として外来は投薬と短いカウンセリングのみであとは自助グループまかせというスタンスになりがちであった。
一方、入院型、入所型のアルコール依存症の専門病院でも他の精神障害の合併などがあり、プログラムの型にはまらない患者は対象外として放置されてきた。また退院後の十分なフォローができず治療が継続できない人が多かった。
しかしアルコール依存症は糖尿病や高血圧、タバコ、がんなどと同様の慢性疾患であると考えると、それぞれの地域で継続した治療を受けなければすぐに再発するのは当然だ。
マトリックスモデルにおいでは依存症治療の最終目標は、断酒・断薬ではなく、依存症と言う病を生き延びることができるように援助することだと考える。
マトリックスモデルでは外来ベースの初期回復プログラム、再発予防プログラム、家族教育プログラム、社会支援プログラムなど様々な治療プログラムが用意され、入院は急性増悪時のみに限る。
何度も失敗を繰り返し乱用がとまらない患者にはうんざりし患者の責任にかえしてしまいたくなるが、「治療継続性を重視」し、乱用がとまらない責任は患者ではなく援助者側にあると考える。
一律に断酒、断酒を目標として患者に押し付ける治療は早期の治療中断をもたらしやすい。
患者の中には節酒に戻ることが可能な群もいる。
治療継続性が予後に関連するので、とにかく来続けてもらうことを重視し「動機付け面接」を繰り返す。
すぐに嗜癖がとまらなくても、病識が不十分でも争わず、通院継続をねぎらう受容的な態度で接する。
再乱用時(スリップ時)にも突き放すのではなく援助を継続する。
嗜癖行動が、本人にとってメリットになっていた側面とデメリットになっていた面を客観的に把握してもらう認知への介入をおこなう。
細かなスケジューリングで暇な時間をなくす、HALT (Hungry,Angry,Lonely,and Tired)などトリガーとなるものを確認し対処行動を学んでもらうなど行動へも介入する。
プログラムではお菓子やコーヒーなども提供し、明るく受容的な雰囲気を重視し、ワークブックを用いて具体的にやめ方を学ぶ。
治療的な「場」が治療を促進すると言う考え方だ。
(東洋医学の外経絡・褥創のラップ療法みたく。)
現代社会においてギャンブルや買い物、リストカットやひきこもり、摂食障害、ボーダーラインパーソナリティ障害など依存症モデルとしてとらえることのできる精神疾患は多い。
嗜癖行動の行動変容にはマトリックスモデルのように場の力を利用したサポーテッド ピア サポート(Supported Peer Support)が鍵となる。
身体疾患でも多職種による継続的、多面的援助で心理的サポートを重視し行動変容を期待する藤沢町民病院の健康増進外来なども注目されているが、これもそういう時代の流れなのであろう。










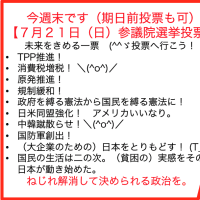
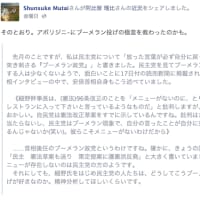




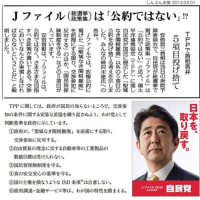

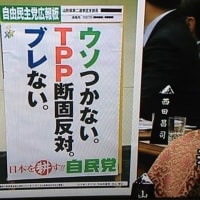

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます