ひさびさの更新。
先日、京都でACT-Kという取り組みをされている高木俊介先生の講演を聴く機会があった。
ACT(Assertive Community Treatment) と は、重い精神障害を抱えた人が住む慣れた場所で安心して暮らしていけるように、様々な職種の専門家から構成されるチームが支援を提供するプログラムのことだ。
包括型地域生活支援プログラムと訳される。
ACTのような方式がこれからの精神福祉の中心となっていくことは間違いない。
我らが地域にもということで今回は松本地区の精神障害者の当事者の会アンダンテの会が主催。
病院の同僚やいつもお仕事をさせていただいている支援者、当事者や患者家族の方もたくさん参加。
支援者、当事者、家族がそろって勉強するこういう講演会もいいものだ。
「統合失調症」という病名の名付け親でもある高木先生は精神障害者の苦難の歴史からACTがうまれたの必然までユーモアと辛口をまぜながらお話しであった。
ACTを理解するためには、まずは歴史的背景が必要とのことで歴史の話から・・・。
かつて日本では多くの精神障害者は地域に混じって暮らしていたという。
座敷牢で私的監禁というケースも確かにあったが、統合失調症ののおババも調子が悪くなるとブツブツいって神経の方に神が乗り移ったなどと言われつつもそれなりに尊重されていたのだ。
そして太平洋戦争~終戦、石炭から石油へとエネルギーの主役が代わり、産業の主役は林業や農業などの第一次産業から第2次、第3次産業へと移った。
日本が工業国として栄えつつあった高度成長期、内陸部から臨海部への若者の人口移動があった。
そんな流れの中で高齢者や障害者は「生産阻害因子」とよばれ、どこかで集めて面倒を見ましょうということになった。
そして精神病者は病気なんだからちゃんと治さないとということで人里はなれた精神病院にあつめられた。
英、仏、米、伊で地域精神保健が動き出し精神病院の解体がはじまろうとしていた1960年代、医療金融公庫による融資で民間精神病院が大濫造されていった。
国の政策で医療スタッフも少しでよいということで民間の精神病院がものすごい勢いで増えていった。
患者を集めるために往診がおこなわれ浮浪者などをどんどんあつめ、黄色い救急車がさらっていくという都市伝説がどこでも聞かれた。
高度経済成長の波の中で、障害者は捨て石となった。
ボロボロの病院も経済成長のおこぼれできれいになり皆が幸せになるといわれた。
20年かけてリンチで患者を死亡させた宇都宮病院事件や、レイプ事件、ポチとよばれた男事件などでそれはウソだということがわかったのだが・・。
そして気づいた時には日本は障害者収容列島となっていた。
しかし障害者は病院や施設へ入れていたらいいという時代はおわった。
それは一つには人権の問題。
そしてもう一つは経済的余裕の問題。
たしかに昔は施設化すると安上がりだった。
障害者を収容所のような劣悪な施設に入れておくことでコストもかからず、家族も高収入の得られる仕事にいけた。
しかし高度成長がおわってみると仕事がない
施設ケアもちゃんとやると人件費がかかり、施設の建て替えにもお金がかかる。
その一方で地域化は施設ケアと比べてもコストがかからず、長期入院の患者が地域へ移行することで35万人の消費者、35万部屋の利用がうまれる。
巨大民間精神病院がすいとっていた患者の年金や生活保護が地域で回るようになる。
働ける人は働いて、働けないくらい重い人も幸せになって消費しましょう。
脱施設化をすすめるしかない。ということである。
「精神障害者福祉のこれから」という厚生労働省の答申もこの方向である。
当事者も家族もこれからはこの方向でものを言っていけばいいのである。
地域で重度の精神障害者が暮らしていくために重要なのは、訪問の充実、そして家族の支援である。
日本でもいろんな職種のチームが重度の人を地域でささえるACTモデルでやりましょうということになった。
(つづく)
ACT-K 精神障害者の地域移行は必然
ACT-Kこころの医療宅配便
ACT-K 専門性の時代
先日、京都でACT-Kという取り組みをされている高木俊介先生の講演を聴く機会があった。
ACT(Assertive Community Treatment) と は、重い精神障害を抱えた人が住む慣れた場所で安心して暮らしていけるように、様々な職種の専門家から構成されるチームが支援を提供するプログラムのことだ。
包括型地域生活支援プログラムと訳される。
ACTのような方式がこれからの精神福祉の中心となっていくことは間違いない。
我らが地域にもということで今回は松本地区の精神障害者の当事者の会アンダンテの会が主催。
病院の同僚やいつもお仕事をさせていただいている支援者、当事者や患者家族の方もたくさん参加。
支援者、当事者、家族がそろって勉強するこういう講演会もいいものだ。
「統合失調症」という病名の名付け親でもある高木先生は精神障害者の苦難の歴史からACTがうまれたの必然までユーモアと辛口をまぜながらお話しであった。
ACTを理解するためには、まずは歴史的背景が必要とのことで歴史の話から・・・。
かつて日本では多くの精神障害者は地域に混じって暮らしていたという。
座敷牢で私的監禁というケースも確かにあったが、統合失調症ののおババも調子が悪くなるとブツブツいって神経の方に神が乗り移ったなどと言われつつもそれなりに尊重されていたのだ。
そして太平洋戦争~終戦、石炭から石油へとエネルギーの主役が代わり、産業の主役は林業や農業などの第一次産業から第2次、第3次産業へと移った。
日本が工業国として栄えつつあった高度成長期、内陸部から臨海部への若者の人口移動があった。
そんな流れの中で高齢者や障害者は「生産阻害因子」とよばれ、どこかで集めて面倒を見ましょうということになった。
そして精神病者は病気なんだからちゃんと治さないとということで人里はなれた精神病院にあつめられた。
英、仏、米、伊で地域精神保健が動き出し精神病院の解体がはじまろうとしていた1960年代、医療金融公庫による融資で民間精神病院が大濫造されていった。
国の政策で医療スタッフも少しでよいということで民間の精神病院がものすごい勢いで増えていった。
患者を集めるために往診がおこなわれ浮浪者などをどんどんあつめ、黄色い救急車がさらっていくという都市伝説がどこでも聞かれた。
高度経済成長の波の中で、障害者は捨て石となった。
ボロボロの病院も経済成長のおこぼれできれいになり皆が幸せになるといわれた。
20年かけてリンチで患者を死亡させた宇都宮病院事件や、レイプ事件、ポチとよばれた男事件などでそれはウソだということがわかったのだが・・。
そして気づいた時には日本は障害者収容列島となっていた。
しかし障害者は病院や施設へ入れていたらいいという時代はおわった。
それは一つには人権の問題。
そしてもう一つは経済的余裕の問題。
たしかに昔は施設化すると安上がりだった。
障害者を収容所のような劣悪な施設に入れておくことでコストもかからず、家族も高収入の得られる仕事にいけた。
しかし高度成長がおわってみると仕事がない
施設ケアもちゃんとやると人件費がかかり、施設の建て替えにもお金がかかる。
その一方で地域化は施設ケアと比べてもコストがかからず、長期入院の患者が地域へ移行することで35万人の消費者、35万部屋の利用がうまれる。
巨大民間精神病院がすいとっていた患者の年金や生活保護が地域で回るようになる。
働ける人は働いて、働けないくらい重い人も幸せになって消費しましょう。
脱施設化をすすめるしかない。ということである。
「精神障害者福祉のこれから」という厚生労働省の答申もこの方向である。
当事者も家族もこれからはこの方向でものを言っていけばいいのである。
地域で重度の精神障害者が暮らしていくために重要なのは、訪問の充実、そして家族の支援である。
日本でもいろんな職種のチームが重度の人を地域でささえるACTモデルでやりましょうということになった。
(つづく)
ACT-K 精神障害者の地域移行は必然
ACT-Kこころの医療宅配便
ACT-K 専門性の時代
 | ACT‐Kの挑戦―ACTがひらく精神医療・福祉の未来 (Psycho Critique) 高木 俊介 批評社 このアイテムの詳細を見る |










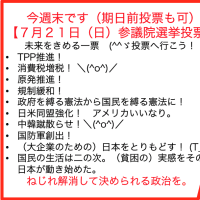
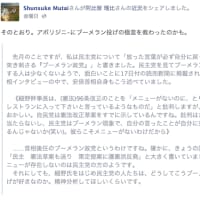




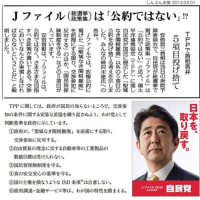

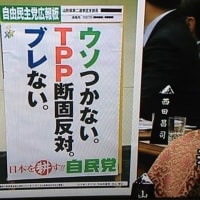

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます