社会の矛盾や混乱は弱者にまず影響し、弱者は駆け込み寺である医療に集まる。そういった意味で病院はあらゆる社会矛盾ののバッファー、安全装置といえる。
医療は教育や環境と同じく社会共通資本なのである。みんなで大切にまもり育てなくてはいけない。
しかし、その医療を資本主義経済におけるサービス業の一つであるという認識でとらえる人が増えてきたことにより危機に瀕している。
現在、日本の医療機関は二つの強い圧力にさらされている。医療費抑制と安全要求である。この二つは相矛盾する。相矛盾する圧力のために、労働環境が悪化し医師が病院から離れ始めた。現状はきわめて深刻である。医療機関の外から思われているよりはるかに危機的である。(「医療崩壊 立ち去り型サボタージュとは何か?」小松 秀樹 より)
医療システムや制度の不備は、病院内のささいなルールや手続き(煩雑化したアリバイ的な書類等)などミクロのことであれ、医療行政や社会制度などのマクロのことであれ、いったんは医師に降りかかる。悪い結果となればたとえ不可避のことであっても訴訟の被告や犯罪者にされる危険性すらある。 医師自ら状況を変化させるような手立てとれるのならよいのだが、状況を変化させることが出来ず、ひずみの状態が続くと医師たちの疲弊を引き起こし、医療ミスを誘発したり、医師の離職(立ち去り型サボタージュ)、転職につながり医療崩壊を引き起こす。そして最終的には患者や地域住民の不利益となるのだが、その構造はなかなか気づかれないようだ。
炭鉱で有毒ガスがでていると、カゴのカナリアがさえずるのをやめて死んでいき、鉱夫に危険を知らせる。医師はさしずめ医療現場におけるカナリアだ。医師は患者の命や生活に責任をおうという役割を負っており、それはつまり患者や住民の生活を人質にとられていることに他ならず、どんなに自分がつらくても体調が悪くても逃げることは許されず良心的な医師であればあるほどまず自らを疲弊させ燃え尽きていくからだ。
周りを見ると医師たちには余裕がなく、みな疲れた顔をしているのが気にかかる。しかしカナリアたちが弱っていることを、鉱夫は気づいていないか無視しているようだ。悲しいかなカナリアたちは団結することも、戦略的にシステムに対するアプローチすることも知らず、またその余裕もなく、状況の悪化に打つ手を見出せずただただ疲弊しているように思われる。
カナリアよ!逃げ出す前に、あるいは倒れて死ぬ前に最期の力を振り絞って鳴き、鉱夫たちに危機を伝えよう。鉱夫たちの団結を引き起こし、炭鉱(やま)の外にも危機をつたえ、状況を改善させる以外にカナリアたち(そして鉱夫たち)の生き残る道は無いのだから。
現在、日本の医療機関は二つの強い圧力にさらされている。医療費抑制と安全要求である。この二つは相矛盾する。相矛盾する圧力のために、労働環境が悪化し医師が病院から離れ始めた。現状はきわめて深刻である。医療機関の外から思われているよりはるかに危機的である。(「医療崩壊 立ち去り型サボタージュとは何か?」小松 秀樹 より)
医療システムや制度の不備は、病院内のささいなルールや手続き(煩雑化したアリバイ的な書類等)などミクロのことであれ、医療行政や社会制度などのマクロのことであれ、いったんは医師に降りかかる。悪い結果となればたとえ不可避のことであっても訴訟の被告や犯罪者にされる危険性すらある。 医師自ら状況を変化させるような手立てとれるのならよいのだが、状況を変化させることが出来ず、ひずみの状態が続くと医師たちの疲弊を引き起こし、医療ミスを誘発したり、医師の離職(立ち去り型サボタージュ)、転職につながり医療崩壊を引き起こす。そして最終的には患者や地域住民の不利益となるのだが、その構造はなかなか気づかれないようだ。
炭鉱で有毒ガスがでていると、カゴのカナリアがさえずるのをやめて死んでいき、鉱夫に危険を知らせる。医師はさしずめ医療現場におけるカナリアだ。医師は患者の命や生活に責任をおうという役割を負っており、それはつまり患者や住民の生活を人質にとられていることに他ならず、どんなに自分がつらくても体調が悪くても逃げることは許されず良心的な医師であればあるほどまず自らを疲弊させ燃え尽きていくからだ。
周りを見ると医師たちには余裕がなく、みな疲れた顔をしているのが気にかかる。しかしカナリアたちが弱っていることを、鉱夫は気づいていないか無視しているようだ。悲しいかなカナリアたちは団結することも、戦略的にシステムに対するアプローチすることも知らず、またその余裕もなく、状況の悪化に打つ手を見出せずただただ疲弊しているように思われる。
カナリアよ!逃げ出す前に、あるいは倒れて死ぬ前に最期の力を振り絞って鳴き、鉱夫たちに危機を伝えよう。鉱夫たちの団結を引き起こし、炭鉱(やま)の外にも危機をつたえ、状況を改善させる以外にカナリアたち(そして鉱夫たち)の生き残る道は無いのだから。










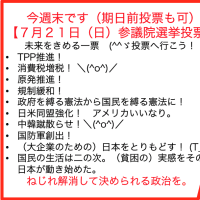
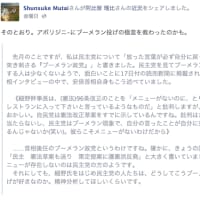




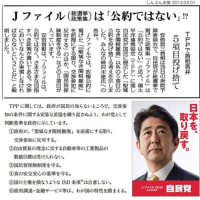

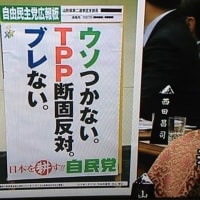

逃げ出すカナリヤが何を言っても、残された鉱夫たちには負け惜しみのようにしか聞こえませんね。
かくして静かに立ち去るのみです。
やはり伝わらないようですねー。
結局、お任せ、依存型、ではなくパートナーシップ型の医療がいかにできるかということでしょうか?
医療の有用性と限界を医療従事者と非医療従事者がいかに共有できるかという視点に立った運動を展開してくことだと思います。
医師の役割を突き詰めれば医療資源、社会資源のトリアージなわけで・・。診断がそのトリアージタッグなわけです。
社会における医師は技術の利用において社会に責任をもつ立場です。その役割として政治家や裁判官と同様に公的な立場にたたねばなりません。
(住民のわがままをただ聞くのが政治ではないのと同じことです。)
医師自身が、そこに自覚的でなく、ビジネスの視点やマーケットの視点のみをいれるとおかしなことになるとおもいます。医療政策などについても現場からもっと発言、提案し、市民にもわかる言葉で伝えていくことが肝要でしょう。
もちろんグラウンドデザインや計画策定においては政治・経済など他の専門科の力が必要です。