つづいて、鹿児島のナカノ在宅医療クリニックの中野一司先生の講演。
初めてお会いしたが、いい感じに力の抜けた先生で、ML(メーリングリスト)を主催し、NQネットワーク指数は相当高い方だ。
ペーパーだが薬剤師でもあり夕張で活躍されている村上智彦先生同様のヤクザ医師であるそうだ。
情熱的でありながら分かりやすい講演で自分の問題意識と重なり視点論点が整理できた。
中野先生は、もともと大学病院で10億円の予算で医療情報システムを構築した実績があり、今は「過労死したくない。楽して楽しく!赤ひげの要らない、医師が働かないシステム」を作るために診療所をベースに鹿児島を舞台に地域をラボにして壮大な実験を行っていると言う。
抱え込まない。働きすぎない。賢くはたらく。楽をするために知恵を絞る。
「失敗したらやめます!」というノリでいかにも楽しんで仕事をされている様子がうかがえた。
これぞ、まさに「はたらく」だ。
・はやく
・たのしく
・らくになるように
・くふうする。
楽しそうに振る舞うことで仲間を増やすトムソーヤ方式でMLを通じて仲間をどんどん増やし在宅医療を全国に広める中心となっており、MLではどんなことでもレスを返し、いい場の維持につとめているそうだ。
そしてそのML等のICT (Information Communication Technology)を通じたネットワークをフル活用し、多職種の在宅医療学会も実行委員もつくらず低コストで鹿児島で開催してしまった。
講演の中で一番主張されていたのは「我々はキュアからケアへのパダダイムシフト、医療で言えば病院医療から在宅医療へのシフトというのムーブメントのまっただ中にいる」ということだ。
これは、イリイチの言う「脱病院化社会」ともつながるだろう。
客観的な治癒(キュア)、主観的な願いや価値観が反映された(ケア)のずれが苦しみになる。
これまで医療も政治もキュアに大きく片寄っていたが、これからはよりケアをベースとした対人援助を行わなければならないという。
超高齢化社会が到来し、増えているのは病気ではなく障害である。障害は病院で治療(キュア)するよりも地域でケアしていく方がQOLも上がればお金もかからない。
もちろんキュアを目指す医療の役割は存在しキュアを否定する訳ではない。
キュアとケアの比率が8:2くらいでキュアに片寄っている現状からせめて5:5くらいまでにすることを目指したいということだそうだ。
在宅医療は落ちこぼれの医療なのだろうか?
否、最先端の医療であると言う。
在宅医療は手抜きの医療ではあるが、どこを手抜きするかを見極めるには何かあるときにしっかり対応できる知識や経験は必要である。
またキュアはできなくても予後や経過を予測するのは医師の大切な仕事だ。
キュア主体の病院の専門医師にはなかなか理解されないことであるが、定期的な訪問診療の重要性は「病状」だけではなく「生活や思いを把握する」ことにある。それが結果として緊急の往診時に良い対応、ケースによっては自宅での看取りにつながる。
結果として低コストになる場合が多いが、それは目的ではない。
病院は病気をみつけ、検査をし、治療をする場所だ。
そこは患者から生活や人生をはぎ取り条件を同一にし、生物学的に疾病だけを診るのに特化した作りになっている。
場所的に看取りはできない。
しかし死んじゃう患者は返せない。
結果、満足死が実現できず、死因が病院としか言いようがないケースも多いのは実感として感じるところだ。
しかし在宅医療は、患者を中心に考えて検査や治療もしない、結果として看とる選択肢もとりうる。
よけいな医療介入をしない方が結果として長生きできる場合もある。
リラックスできる家と言う環境がもっとも良い薬になる場合も多い。
なにしろ家は自分を元気にする気が満ちている場所(東洋医学的に外経絡(がいけいらく)という考え方だ。)なのだから当然だ。
医療崩壊が問題とされるが、医療崩壊とは病院医療の崩壊であり、在宅の側から見れば在宅医療再生だという。
在宅医療はチーム医療である。
チーム医療実践のための条件として、連携のコストを安くし、各職種スタッフが優秀なことが大事でありそれにはITのフル活用が鍵となる。
もちろん顔の見える関係あってこそのICTだ。
これは、千葉県東金地区での平井愛山先生らの「わかしおネットワーク」の実践でも強調されていたことだ。
日本福祉大学の二木立氏はかつて地域包括ケアはネットワーク型ではコストがかかりすぎ質が悪くなり、むしろ一つの保健医療福祉の複合体が抱え込むモデルの方が良いと主張していたそうであるが、それはICTの発展を見逃していた考え方であった。
確かに二木の言う一つの良質な複合体を中心とした囲い込みの医療で、良質な医療福祉を提供しているところは南佐久地域をはじめとして全国に散見される。
しかし、地域には様々なリソースが存在し、それをフル活用するためには、囲い込んだらうまくいかずネットワークを作り、それを有機的に結びつけるのが重要だという。
お互いに足りないところを暴露して、協同作業や勉強会などを通じて相互にレベルアップを目指すことが大事だそうだ。
これは自分も日頃実感していることであるが、多職種でチームで医療を行うことで相互に技術移転がおこる。
細菌やウィルスの間で薬剤耐性の遺伝子などプラスミドなどを通じて移転するのは困ったことだが、こういう技術の移転は大歓迎だ。
ナカノ在宅クリニックでリハビリスタッフ(PT,OT)が配属されているのは看護職他にリハビリの教育を行うことが主目的であるという。
そして、医師と看護師が訪問診療に同行するのも同様の狙いがあるのだろう。
つまり看護師は医師から、医学的なキュアの視点やアセスメントや治療技術を学び医師は看護師からケアの視点や技術を学ぶことができる。
そして頻繁に開催されるミーティングやカンファレンスこそ教育だという。
クリニックでは電子メールで患者の情報をやり取りし(実質、電子カルテになっている)、病院に来る前にすでにMLで情報が共有できており、それらの情報に目を通した状態でスタッフミーティングに望む。
だからそれは申し送りではなくディスカッションになるのだそうだ。
これは回復期リハビリテーション病棟のモデルルームである初台リハビリテーション病院での電子システムの活用やカンファレンスのあり方と全く同じである。
自分の病院でも情報共有ではいつもバタバタしてなかなかそこまではいっていない。
情報をいちいち開かないと見ることができない、できあいの電子カルテシステムの使いづらさにもあるが、カンファレンスやミーティング、ケア会議をもっと盛り上げるような仕掛けを導入しなければならないだろう。
そして病院に入院したときなどには退院前カンファレンスを大事にして、こういう人でも在宅できるのだという実例を示すことで病院スタッフへの在宅医療の啓蒙(営業活動)の意味もあるそうだ。
こういったことを通じて医師の頭の中でキュアからケアのパラダイムシフトを促進することが今後の医療福祉のあり方の鍵の一つになるであろう。
(これは次の洪先生の在宅医療支援病棟の話にもつながる。)
中野先生が主張されていたのは事務仕事に忙殺されているケアマネージャーに情報がしっかり入るようにして、モニタリングなどのケアマネジメントに専念できるようにするということである。
もうひとつ、教育の割に活用されていない職種である薬剤師をもっと活躍させるべきだと言う主張。これにも強く同感できた。
最期に褥創のラップ療法を紹介。
ラップ療法の普及こそキュアからケアのパラダイムシフトの一部ともいえる。
学会では認めたがらない人もいまだに多いラップ療法であるが、効果は確実だ。
コンセプトは傷を治すのではなく、傷が治るもの、人がやることはその環境を整えるだけということだ。
これはまさに東洋医学的な考え方だ。
貧乏な在宅ではいかに安くするかがポイントである、
水道水とオムツとポリ袋で低コストでできるラップ療法は従来の治療法の200分の1のコストでできる。そしてホームヘルパーでもできる。
人は貧しい時代はまず物、ついでエネルギー、そして情報をもとめててきた。
そしてこれからは時間を大切にするようになるだろう。
民主党のいうコンクリートから人への転換にもつながる。
IT時代とはお金があまり価値をもたない時代であると言う。
そんな時代に、こころの豊かさとはどうやって手に入れるものなのだろうか。
その答えが「ケア」にあるのだろう。
地域循環型の医療連携
初台リハビリテーション病院
初めてお会いしたが、いい感じに力の抜けた先生で、ML(メーリングリスト)を主催し、NQネットワーク指数は相当高い方だ。
ペーパーだが薬剤師でもあり夕張で活躍されている村上智彦先生同様のヤクザ医師であるそうだ。
情熱的でありながら分かりやすい講演で自分の問題意識と重なり視点論点が整理できた。
中野先生は、もともと大学病院で10億円の予算で医療情報システムを構築した実績があり、今は「過労死したくない。楽して楽しく!赤ひげの要らない、医師が働かないシステム」を作るために診療所をベースに鹿児島を舞台に地域をラボにして壮大な実験を行っていると言う。
抱え込まない。働きすぎない。賢くはたらく。楽をするために知恵を絞る。
「失敗したらやめます!」というノリでいかにも楽しんで仕事をされている様子がうかがえた。
これぞ、まさに「はたらく」だ。
・はやく
・たのしく
・らくになるように
・くふうする。
楽しそうに振る舞うことで仲間を増やすトムソーヤ方式でMLを通じて仲間をどんどん増やし在宅医療を全国に広める中心となっており、MLではどんなことでもレスを返し、いい場の維持につとめているそうだ。
そしてそのML等のICT (Information Communication Technology)を通じたネットワークをフル活用し、多職種の在宅医療学会も実行委員もつくらず低コストで鹿児島で開催してしまった。
講演の中で一番主張されていたのは「我々はキュアからケアへのパダダイムシフト、医療で言えば病院医療から在宅医療へのシフトというのムーブメントのまっただ中にいる」ということだ。
これは、イリイチの言う「脱病院化社会」ともつながるだろう。
客観的な治癒(キュア)、主観的な願いや価値観が反映された(ケア)のずれが苦しみになる。
これまで医療も政治もキュアに大きく片寄っていたが、これからはよりケアをベースとした対人援助を行わなければならないという。
超高齢化社会が到来し、増えているのは病気ではなく障害である。障害は病院で治療(キュア)するよりも地域でケアしていく方がQOLも上がればお金もかからない。
もちろんキュアを目指す医療の役割は存在しキュアを否定する訳ではない。
キュアとケアの比率が8:2くらいでキュアに片寄っている現状からせめて5:5くらいまでにすることを目指したいということだそうだ。
在宅医療は落ちこぼれの医療なのだろうか?
否、最先端の医療であると言う。
在宅医療は手抜きの医療ではあるが、どこを手抜きするかを見極めるには何かあるときにしっかり対応できる知識や経験は必要である。
またキュアはできなくても予後や経過を予測するのは医師の大切な仕事だ。
キュア主体の病院の専門医師にはなかなか理解されないことであるが、定期的な訪問診療の重要性は「病状」だけではなく「生活や思いを把握する」ことにある。それが結果として緊急の往診時に良い対応、ケースによっては自宅での看取りにつながる。
結果として低コストになる場合が多いが、それは目的ではない。
病院は病気をみつけ、検査をし、治療をする場所だ。
そこは患者から生活や人生をはぎ取り条件を同一にし、生物学的に疾病だけを診るのに特化した作りになっている。
場所的に看取りはできない。
しかし死んじゃう患者は返せない。
結果、満足死が実現できず、死因が病院としか言いようがないケースも多いのは実感として感じるところだ。
しかし在宅医療は、患者を中心に考えて検査や治療もしない、結果として看とる選択肢もとりうる。
よけいな医療介入をしない方が結果として長生きできる場合もある。
リラックスできる家と言う環境がもっとも良い薬になる場合も多い。
なにしろ家は自分を元気にする気が満ちている場所(東洋医学的に外経絡(がいけいらく)という考え方だ。)なのだから当然だ。
医療崩壊が問題とされるが、医療崩壊とは病院医療の崩壊であり、在宅の側から見れば在宅医療再生だという。
在宅医療はチーム医療である。
チーム医療実践のための条件として、連携のコストを安くし、各職種スタッフが優秀なことが大事でありそれにはITのフル活用が鍵となる。
もちろん顔の見える関係あってこそのICTだ。
これは、千葉県東金地区での平井愛山先生らの「わかしおネットワーク」の実践でも強調されていたことだ。
日本福祉大学の二木立氏はかつて地域包括ケアはネットワーク型ではコストがかかりすぎ質が悪くなり、むしろ一つの保健医療福祉の複合体が抱え込むモデルの方が良いと主張していたそうであるが、それはICTの発展を見逃していた考え方であった。
確かに二木の言う一つの良質な複合体を中心とした囲い込みの医療で、良質な医療福祉を提供しているところは南佐久地域をはじめとして全国に散見される。
しかし、地域には様々なリソースが存在し、それをフル活用するためには、囲い込んだらうまくいかずネットワークを作り、それを有機的に結びつけるのが重要だという。
お互いに足りないところを暴露して、協同作業や勉強会などを通じて相互にレベルアップを目指すことが大事だそうだ。
これは自分も日頃実感していることであるが、多職種でチームで医療を行うことで相互に技術移転がおこる。
細菌やウィルスの間で薬剤耐性の遺伝子などプラスミドなどを通じて移転するのは困ったことだが、こういう技術の移転は大歓迎だ。
ナカノ在宅クリニックでリハビリスタッフ(PT,OT)が配属されているのは看護職他にリハビリの教育を行うことが主目的であるという。
そして、医師と看護師が訪問診療に同行するのも同様の狙いがあるのだろう。
つまり看護師は医師から、医学的なキュアの視点やアセスメントや治療技術を学び医師は看護師からケアの視点や技術を学ぶことができる。
そして頻繁に開催されるミーティングやカンファレンスこそ教育だという。
クリニックでは電子メールで患者の情報をやり取りし(実質、電子カルテになっている)、病院に来る前にすでにMLで情報が共有できており、それらの情報に目を通した状態でスタッフミーティングに望む。
だからそれは申し送りではなくディスカッションになるのだそうだ。
これは回復期リハビリテーション病棟のモデルルームである初台リハビリテーション病院での電子システムの活用やカンファレンスのあり方と全く同じである。
自分の病院でも情報共有ではいつもバタバタしてなかなかそこまではいっていない。
情報をいちいち開かないと見ることができない、できあいの電子カルテシステムの使いづらさにもあるが、カンファレンスやミーティング、ケア会議をもっと盛り上げるような仕掛けを導入しなければならないだろう。
そして病院に入院したときなどには退院前カンファレンスを大事にして、こういう人でも在宅できるのだという実例を示すことで病院スタッフへの在宅医療の啓蒙(営業活動)の意味もあるそうだ。
こういったことを通じて医師の頭の中でキュアからケアのパラダイムシフトを促進することが今後の医療福祉のあり方の鍵の一つになるであろう。
(これは次の洪先生の在宅医療支援病棟の話にもつながる。)
中野先生が主張されていたのは事務仕事に忙殺されているケアマネージャーに情報がしっかり入るようにして、モニタリングなどのケアマネジメントに専念できるようにするということである。
もうひとつ、教育の割に活用されていない職種である薬剤師をもっと活躍させるべきだと言う主張。これにも強く同感できた。
最期に褥創のラップ療法を紹介。
ラップ療法の普及こそキュアからケアのパラダイムシフトの一部ともいえる。
学会では認めたがらない人もいまだに多いラップ療法であるが、効果は確実だ。
コンセプトは傷を治すのではなく、傷が治るもの、人がやることはその環境を整えるだけということだ。
これはまさに東洋医学的な考え方だ。
貧乏な在宅ではいかに安くするかがポイントである、
水道水とオムツとポリ袋で低コストでできるラップ療法は従来の治療法の200分の1のコストでできる。そしてホームヘルパーでもできる。
人は貧しい時代はまず物、ついでエネルギー、そして情報をもとめててきた。
そしてこれからは時間を大切にするようになるだろう。
民主党のいうコンクリートから人への転換にもつながる。
IT時代とはお金があまり価値をもたない時代であると言う。
そんな時代に、こころの豊かさとはどうやって手に入れるものなのだろうか。
その答えが「ケア」にあるのだろう。
地域循環型の医療連携
初台リハビリテーション病院










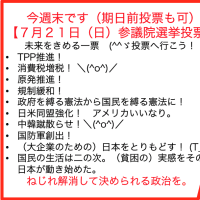
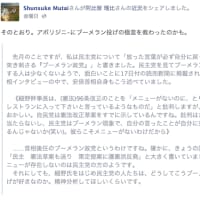




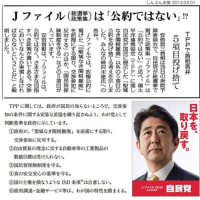

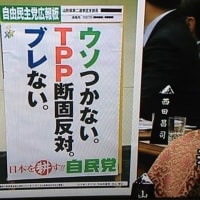

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます