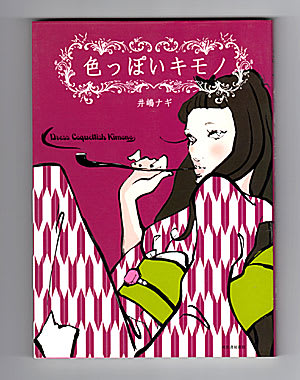
ぼーっと本棚を見ていて、しばらく目を通してないなーと、取り出しました。
タイトルもすごいでしょ「色っぽいキモノ」。著者は井嶋ナギさんというライターの方です。
1973年のお生まれだそうですから、今年41歳、この本は2006年発行ですので、
お書きになったころは30代ですね。
この本の「はじめに」には、
「実は姐さんなテイストが好き!」
「品のいい着物だけじゃ、物足りない!」
「とにかく、着物で色気を漂わせたい!」
そんな風に思っている方、いらっしゃいませんか?
私は、ずっと昔からそう思っていました。
と、あります。すでにちょとカゲキな空気が…。
元々そう思ったのは、大学生の時に見た映画で、岩下志麻さんの鬼気迫る縁起の時に衣装と風情…
それを見て「これだ」と思ったのだそうですが、いわゆる苦界の女性や裏社会の女性たちの着物の選び方着方は、
さすがに本がありませんよね。それでご自身で書くことになさったのだそうです。
実はこういうのって「粋」とか「艶」と言い表されることが多いのですが、
一番漠然としてわかりにくい…見ると「あっ粋だねぇ」とか「仇っぽいね」とか言えるのですが。
この本は、そういうことを実にうまく、着物の歴史などの説明とともに表しています。
この本には芸者、花魁、はたまた小説に出てくる妖艶な女性など、たくさん出てきます。
写真も豊富で、浮世絵のほかに「アコガレの極妻ファッション、岩下さん」の写真も。
元々江戸文学を専攻されていた方で、泉鏡花から任侠映画まで…。
これだけ書くと、同じ着物のお話でも、私たち「シロウト」さんには縁のないお話のように聞こえますが、
実はそうでもありません。
以前にも書きましたが、まず着物の形や着方で、今に近い原型が整ったのが江戸時代です。
その江戸時代のファッション・リーダーは「芸者・役者・花魁」です。
彼らや彼女たちの使う化粧品や、着物の色柄、着方、帯の締め方など、
いろいろなものが真似られ、庶民のものとなっていきました。
もちろん、なんでもそのままではありません。それを取り入れる方も、ちゃんとアレンジを考えていました。
職業に貴賤なし、それは私もそう思いますが、昔はただ身分差別や仕事による差別が
あっただけではなく、なんといいますか「だから理解する」みたいなところもあったのですね。
以前「ゆかたはじゅばんも着ず、足袋も履かないですむ、1年の内でもっとも開放的な姿でいられるから、
湯上り着から、日が落ちてからの外出着として女性に歓迎された」と書きましたが、
それは元々、一般の女性(ある程度の暮らしの人)は「長じゅばんを着て、着物を着て、
その上からきっちり帯を締める。足袋を履く」というのがふつうだったから。
逆に花魁や女郎さん、彼女たちの「職業用衣装」は長じゅばんで、帯は前で結び、
着物は打掛のようにして羽織り、冬場でも足袋は履かないのがふつうだった…ということから、
一般の人はそれをしなかったし、花魁さんたちも「職業上の意地」で、足袋は履かなかったと言われています。
それを着なくていい、履かなくていい…となった時の解放感は、今私たちがゆかたを着るときよりも、
ずっと大きく楽しいことだったと思います。
なにかカセがかかると、それから解放さることは、とてもいいものです。
何々してはいけない、何々でなければならない、そういう縛りの中でこそ生まれた、
職業婦人の着物、一般庶民の着物、その色柄、着方…。
ただマネするだけでなく、いかに自分の立場で、それを楽しめるようにアレンジできるか。
それがおしゃれの醍醐味だと思います。
さすがに真っ赤な蹴だしを付けようとは思いませんが、ぼんやりしたボカシのじゅばんだの、
重箱背負ったようなつまんないお太鼓だの…そんなものからちょっと自由になりたいな、と思ったら、
この本は面白いです。ポーズの色っぽい決め方、なんて項目もありますよ。
別に、男に媚びるための艶めいたことをしましょう、なんて言っている本ではありません。
今はすっかり影をひそめてしまった「昔の女性の着物に対する執念」、
それを覗き見ることで、自分の着姿をもっと楽しいものにしたいなぁと、そんなことを思う本です。
アマゾンではこちら。
 |
色っぽいキモノ |
| クリエーター情報なし | |
| 河出書房新社 |




























一般的な着物の本と違う視点で書かれているのが、とても面白かった~。筆者とは年齢も近いので、共感するところもあったりしまして。
とにかく徹底して「色っぽい」という観点で書いてあるのが、潔くて好きです(笑)。
なんとなくタイトルが気になって買ったものです。
それまでの堅苦しい着物本と違って、面白い本でした。
最近は書店に行っても、着物本を買うことが少なくなりました。
あまりにも私の日常とかけ離れていて「参考にもならない・・・」とため息が出てしまうのです。
お風呂掃除が出来る着物っ!!!なんてタイトルの本が出たら、飛びついて買うんですけど…
着物の切り口もいろいろあるんだなあと改めて感心いたしました。
今度読んでみたいですね。
ああ、読もうと思いつつそのままになっている本が一杯だあ(笑)。
違う視点というのが、新鮮ですよね。
目の前に色っぽい女性がちらちら浮かびながらで
読んでました。
取り入れることはできないテクでも、
あぁそうよね、と言えることが多くてむ、
楽しい本ですよね。
「着物で風呂掃除」、その着方を
書いてみたいと思ってはいるのですが…。
私もいつ買ったっけ…の本がいっぱいです。
この本は、切り口の違いが歴然で、
それでいてきっぱりで、面白いですよ。
着物を着ない人にもたのしめるかもの本です。