今回の東京行きの理由。
八ヶ岳リードオルガン美術館所有のハーモニウムの貸し出しです。
僕自身ハーモニウム、ハルモニウムと未だに呼び方が不統一です。
ハーモニウムは英語及び口語ドイツ語読みで、日本での動きとしてはこちらに統一する方向のようです。
ハルモニウムはずっと今まで日本で言い習わされて来た表記で、今はまだ多数派のようです。
実際の発音に近いハーモニウムの方が好ましいとは思いつつも、ハルモニウムの方が日本では通りが良いので、僕もハルモ~で発音することが多いのです。
実は僕も最近知ったのですが、「r」音を「ル」と発音、表記するのは「舞台ドイツ語」と言うんだってね。
19世紀末に造られた標準発音で、ドイツでは20世紀半ば頃、日本では末まで「正しい」発音として認知されていたそうです。
僕もドイツ人と仕事をすることは多かったけれど、r音をル、しかも巻き舌音で発音する人には会ったことが無かったので、ずっと気にはなっていたのです。
わかったときはすっきりしたなあ。
さて、話を戻して。
八ヶ岳リードオルガン美術館のハーモニウムはフランスのミュステル社製で、足踏み送風式ハーモニウムとしては最上級モデルです。
2段鍵盤ペダル(足鍵盤)付きの楽器も存在しますが、この足踏み送風は表現力の要なのです。
送風機が無いとかいう消極的な理由での足踏みではないのです。
手鍵盤を1段に集約し、足鍵盤を切り捨てるという取捨選択がこの楽器を形作っているのです。
現役楽器としての使い勝手を良くするため、オーナーと相談の上、ピッチをa=435Hzから現代のクラシックオーケストラの標準である(もちろん例外はある)442Hzに変更しました。
参照記事 貸出可能なハーモニウムは日本では(世界的にも)非常に稀少です。
もう一台、八ヶ岳リードオルガン美術館には小さいハーモニウムがあります。こちらも貸出可です。
いずれも僕が修復したもので、その後の管理もしているのです。
19世紀末から20世紀初頭にはかなり流行った楽器で、作曲家がストップの使い方(レジストレーション)まで指示した楽譜もあります。
そういった楽譜をその通りに再現するためには一定の規模以上のハーモニウムを使わなければなりません。
今回はそういった時代楽器(ピリオド楽器)を使った演奏なのです。
厳密に言えば、ピッチはa=435Hzであるべきなのですが、そこは良いようです。
コンサートは5月18日東京にて。ご都合の合う方はお出かけください。















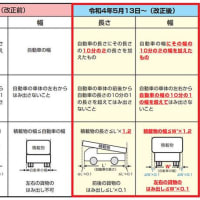




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます