芝刈りと柴刈りは違うのよ。
今日は月曜ですが、先週の土曜が学校行事で登校だったので娘は休みです。
そこで一緒に薪を取りに行くことにしました。
大きい丸太を現地でチェーンソーで玉切りにしたものの他、枯れ枝も確保します。
昔話で「おじいさんは山に柴刈りに行きました…」というヤツです。
柴は特定の植物の名前ですが、小径木や枝の総称でもあります。
火力の立ちあがりと火持ちのバランスがなかなかに優れています。
柴も昭和30年代くらいまでは重要な燃料であったといいます。
昔の人にとって山は貴重な資源の供給源です。昔は自然が豊かで動物も多かったとステレオタイプ
に言われますが、実際どうだったんでしょうね?
かつては山の木の実、どんぐりや栃の実なんかは人間にとっても非常に重要な食料で、縄文人に至っては
主食級の重要度だったらしい。
少ないとはいえ、複数の集落を築けるほどの人口が木の実で生きて行くというのは信じがたいことです。
どんぐりの類はかなりの確率でゾウムシの卵が産みつけられているので、少しでも早く確保して火を通して殺す
のと発芽を防ぐことをしないと長期保存は出来ません。
わずかな期間に一年分の集落の主食を採集するというものすごいテンションです。
クマとは真っ向から対立関係にあったわけです。
この季節、葉の落ちた木に柿の実がなっている風景は良いものですが、それも昔は極めて限られた風景だったのでしょう。
みんな取っちゃうからね。
シカやいのししだってこの上ない貴重なタンパク源だったわけで、それらを求める気持ちは今より遥かに強かったと思われます。
木そのもの、きのこや木の実、薪、落ち葉、シカ、いのしし、クマ…、山の資源に一番無頓着なのは現代人でしょう。
入会地を巡って近隣の村人が血を流したりというのももはや過去の話です。
一部地域ではまだちょっと残っているけどね。
まあ、お陰で僕たちは山から木を伐って来て薪ストーブを使ったり出来るわけです。
皆がそれをしだしたらあっという間に枯渇してしまいますから。
人々の価値観の隙間で助かっているのです。
自分ががんばらないと、自分自身や大切な人達が飢えてしまうとか、寒さに凍えてしまうという昔の人が常に感じていた
であろう危機感や使命感の欠片を実感出来るわけです。
もちろん、それは現代社会でも同じなのですが、貨幣というすばらしく便利なツールを仲立ちとすることで、素朴で直接的な
実感からは遠ざかってしまうのは仕方がないところでしょう。
家族が一緒に働くというのは楽しいものです。
な、ケツデカ星人。
その立派なケツは女の子だからじゃなくて大臀筋!すまん、ワシからの遺伝じゃ。
だけどね、君がいずれ誰かに裏切られたり、辛い目にあったりしても、そのフトモモとケツは決して君を裏切らない。
おやつをたくさん持ってきていたんだね、りーちゃん。
「こういうところで食べるおやつは最高ですなあ」
ああ、その通りだ!















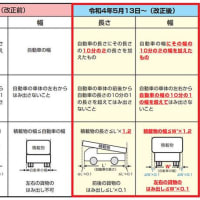




ものすごく共感させてもらうわけですが、そこまでキチンと言葉にする事が僕にはまだ出来ません。
カッコよすぎます。
参りました、兄さん。
これからも、兄さんお世界を楽しみにしています。
過分にお褒めいただき恐れ入ります。
でも僕も思うことをうまく言葉に出来なくて苛立ちを感じています。
都会で暮らす人達の空想する自然は美しく脆弱なものなのでしょうね。
山で暮らせば、自然と闘わなければならないことも多く、その手強さも身にしみてわかるのですが。
「事件は現場で起きているんだッ」
とかいうドラマを共感しながら視ている人達が、現実の山に来ることなく自然を語っていたりするわけです。
この空想世界の住人のみなさんにはぜひ自然に触れて実感して欲しいと思います。