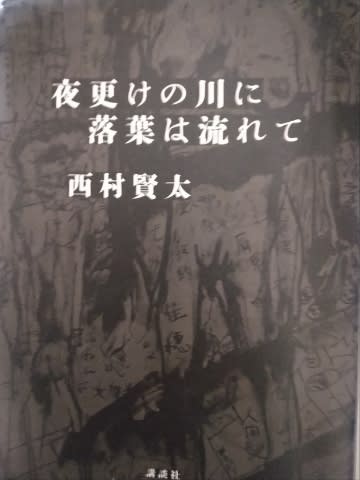小林秀雄の『感想』が、量子論の問題を中心に展開しているように、小林秀雄の関心は、相対性理論よりも量子論にあるようである。
物理学には、物質の究極の単位を突き止めるというところがあるのであろうが、量子論が明らかにしたのは、そのような究極の要素は存在しないという事実だったのではないだろうか。
ギリシャ以来の原子論では、宇宙や物質は、いくつかの要素から成ると考えられており、それは、19世紀末まで変わらない前提だったようである。
物理学は、そのような前提から究極の要素を求めて、様々な実験や思考を繰り返し、その結果、次々に、ミクロの世界の神秘が解明されてきたのかもしれない。
量子論と呼ばれる20世紀の新しい物理学は、ギリシャ以来の原子論を単純に容認し、進化させてきたのではなく、ギリシャ以来の原子論的な思考そのものに変換を迫ったように見える。
小林秀雄が、量子論にこだわる理由は、量子論が、物質の究極の要素を探求する過程で従来の認識論の基礎原理の革命を行ったからではないだろうか。
このことについて、小林秀雄は、『感想』のなかで、
「物質がアトムから成っているとい思想の歴史は、デモクリトスあるいはルクレティウスとともに古いのだが、電子論の勝利が新しいという意味は、勿論、測定技術の進歩による、その実証性にあった。
アトミズムはもはや目に見えぬ思想ではなく、確実に捕らえた実在する物質の構造となった。
ところが、ここまで来てみると、この確実な実在から逆に問われることになった。
アトミズムという考え方自体に大きな困難があるのではないか」
と述べている。
小林がここで、述べている「電子論の勝利」とは、原子の構造を明らかにしたラザフォードのことであろう。
さらに、小林は、『感想』のなかで
「物質が究極において、たった2種類のアトムに還元出来た以上、残るたった一つの問題、これらのアトムの運動を支配する厳密な法則さえ発見できるなら、アトミズムの勝利は確実なものとなるはずであった。
一歩を踏み出せばよい。
原子が太陽系の模型を示したのが夢ではないなら、天体の運動のみならず、私達周辺のあらゆる物体の運動を、あれほど見事に説明した力学の法則が、この小宇宙にも適用できないはずはない。
だが、自然は顔をそむけたのである」
と述べている。
「自然が顔をそむけた」のは、電子と原子核というふたつのアトムは、物質の究極の単位ではなかったからであり、物質の構造を、原子論的な要素から説明しようとする考え方それ自体にも無理があったからであろう。
このような原子論的な、要素論点な物質の分析を経たのちに、量子論という革命的な物理学は登場した。
そして、量子論は、物質の究極要素を探り当てるのではなくて、物質の究極要素としての素粒子は否定しないが、そこでいわれる素粒子は、「物」というよりは、ある種の状態、言ってしまえば、「場」とでも呼ぶべきものであると考えたのではないだろうか。
「物」的な物理学から、「場」的な物理学への転換が起こったのである。
ニュートン流の古典物理学は、19世紀末にその絶頂期を迎えるのだが、それは同時に崩壊期でもあったようである。
古典物理学の行き詰まりが明らかになったのもまた、19世紀末なのである。
古典物理学は、世界は「物」の集まりであり、「物」の移動や変化から成り立つというように、「物」を中心とする思考から成り立っていたようである。
そして、それを説明するのが「力学」であったようだが、19世紀になると、ファラデーやマックスウェルらによって開拓された「電磁波」の問題のように、「力学」では説明しきれない問題が出現したのである。
目に見えない光であるはずの電波が作り出され、電気火花が散ったりした結果、ファラデーとマックスウェルの「光の波動説」が、ニュートンの「光の粒子説」に取って代わることになった。
光は「粒子」であるという古典物理学的な「物」中心の考え方から、光は「波」であるという「場」への考え方へと転換したのである。
しかし、19世紀の物理学は、「光の波動説」を認めたにもかかわらず、依然として、古典物理学的な「物」中心の力学的な考え方を捨ててはいなかったようである。
「場」的な波動現象を、「物」的な力学によって説明しようとしたのである。
ここに、19世紀末の物理学者たちの直面した「矛盾」があり、「エーテル」という概念が、この矛盾を解決するものとして考え出されたのである。
しかし、「エーテル」という物的な触媒によって、電磁的な波動問題を説明するという考え方は、成功することはなかった。
この矛盾は、「エーテル」という概念を捨てたアインシュタインによって解決されるのである。
アインシュタインは、古典物理学的な考え方それ自体のなかに矛盾を発見し、その矛盾を克服するために新しい物理学、相対性理論を確立したのである。
アインシュタイン以前の力学法則は、
ガリレイの相対性原理と、マイケルソンとモーレイの光速度不変の原則と、速度の合成に関する法則、という3つの基本原則から成っていたようである。
もちろん、これらの3つの原則はともに両立することはできない。
そこで、アインシュタインは、速度の合成に関する法則を除去することによって解決したようである。
つまり、ニュートン力学の根本原則である速度の合成の原則を近似的にしか妥当しないものとみなしたのである。
たしかにニュートンの物理学は、光の速度と比較してずっと小さな速度で運動する物体には妥当するが、光の速度に近い速度で運動する物体には、妥当しないと考えたのである。
アインシュタインは、ガリレイの相対性原理とマイケルソンとモーレイの実験によって証明された光速度不変の原則というふたつの原則の上に、相対性理論という新しい物理学を打ち立てたのである。
そのとき、アインシュタインは、「時間」と「空間」という問題を提起したのである。
時間と空間という「場」の問題は、古典物理学の世界においては、あまりにも自明な、絶対的な実在であり、それらは、今更特段に考える必要のない、普遍的な実在だったのかもしれない。
ニュートン物理学の哲学的基礎づけをおこったといわれるカントの『純粋理性批判』においても、先天的なカテゴリーとして、自明の公理として容認されていたのが「時間」と「空間」である。
言ってしまえば、その「空間」と「時間」をアインシュタインは地上に引き戻したのである。
アインシュタインは、1905年「特殊相対性理論」によって、空間と時間のあいだの関係を明らかにし、1915年には「一般相対性理論」によって、物質と時間・空間の関係を明らかにした。
古典物理学は、アインシュタインの相対性理論の出現によって、その根本的な基礎概念である「時間」と「空間」の概念の改変を迫られたのである。
それは、ある意味では、ニュートン的物理学の根本原則の解体を意味したのかもしれない。
しかし、アインシュタインの相対性理論の出現によって、ニュートン的な古典物理学は、その根底からの変換を余儀なくされたのだが、「物理学の革命」はそれだけで終わったわけではなかった。
もう一段の根本的な科学革命が行われていたのである。
「量子物理学」の誕生である。
「物理学の革命」のは、単なる物理学内部の理論的深化や発展ではなく、トーマス・クーンが、
「世界観の変革としての革命」
と呼び、また、
「パラダイムの変換」と呼んだところのものであったのではないだろうか。
つまり、それは、思考の内容の問題ではなく、思考の様式の問題であったのではないだろうか。
小林秀雄が「物理学の革命」に関心を持ったのも、物理学という学問の厳密な体系的知や、その有効性のためではなくて、あたかも永久不変の真理のごとく思われる科学的真理ですら、「革命」とともに、相対化されざるを得ないのだという、物理学における思考様式の「革命」の部分ではなかったか、と思われるのである。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
見出し画像にも載せましたが、西村賢太さんの小説、やはり好きです😊
久しぶりに再読しています😊
今日も、頑張りすぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。