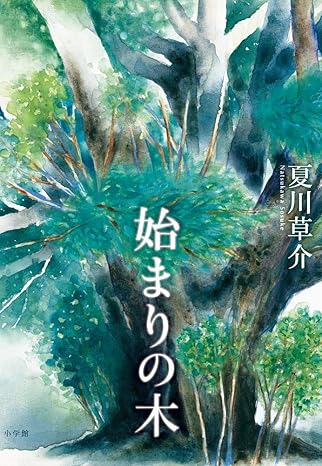君を守ろうとする猫の話の「君」って主人公の中学生ナナミちゃんのことかと思って読み始めたのですが、「君」って読んでいる私のことだった…(^^;)
いや、私ってちっぽけな話じゃなくて、私を含めて「私たち」ってことなのね…
いやいや、違うだろう!!
猫もナナミちゃんも守ろうとしたのは「本」だろう?
消されてしまう本たちを、決して消させない!!!って、消されてなるものか!!!って勇気をふりしぼって猫とともに戦ったナナミちゃん。
そうそう、守ろうとした、守ったのは確かに「本」。
でも、結果的にそれを読む私たちが守られたってことでしょ?
社会には欲がたくさん溢れていて、もっともっと便利に、もっともっと楽に、もっともっと強く、そんなもっともっとに攻め立てられているような。
本だって、もっともっと読みたいよね。
でも、限りはあって。
私の読む力にも限界があって、読みたいのに読めば面白いのもわかっているのに、でも何だか進まない…。
そんな時、その本を置いて、この「君を守ろうとした猫の話」を読み始めました。
そしたら、一気とは言えないまでもスイスイ読めて。
本って不思議ですね。
「本」のお話なので、「嵐が丘」や「ルパン全集」、「はらぺこあおむし」「フレデリック」その他たくさんの本たちが登場します。
読んだ本が登場すると誇らしいけど、読んでいない本はどこか気持ちがちくちくしてまだ読んでなくてごめんよ、、、」って思ったり、「読むからね」って気持ちになったり、そんな自分のいろんな気持ちに気づけるのも「本」の楽しさ。
「本」ってやっぱりいいよね♡
ということで、先日、図書館を旅するように隅々まで歩いてみました。
いつもは、借りる本のところくらいしか行かないのですが、奥へ奥へ入ってみたらそこにもテーブルとイスがあって。人がいたり。
いつもの窓から離れて違う窓から外を見たら、当たり前だけど違う景色が見えたり。
宇宙のこと、木や花や草のこと、いろいろな国、いろいろな学問、食べ物、職業、台所、空間、音楽、服、ありとあらゆるものがずら~~っと並んでいて
で、それで、どこにいても静かなの🎵最高じゃん🎵
その最高な場所の図書館なのですが、肝心の「図書館で読書」はなぜか、しないのです(^^;)
たぶん、突然泣いたり笑ったりできないから、、、じゃないかと自己分析しています。
百面相しながらの読書はひとりに限ります。
だいぶ脱線してしまいました…。
思うに、
さあ、みんなこの辺りで一呼吸しませんか?
という時期に入ってきたんじゃない?
それとも、このまま、もっと便利に、もっと楽に、もっと早く、もっと強く、って走り続ける?
君はどう思う?
というのが、「君を守ろうとした猫の話」ではないかしら?
後退も前進?
そういえば、ナナミちゃん、戦いに行っては戻って、行っては戻って、を繰り返していた…。
戻れるんだよね、いつだって。
で、戻れる術が「本」なのです。
<本文より>
「言葉を用いればすべてが伝わるというものではない。突き詰めれば、対話で伝えられるのは、言葉の意味ではなく、伝えようとする意志なのだと言ってもいい。心が伝われば、意味内容はあとからついてくる。そんな当たり前のことが、しかし今の世界では転倒してしまっている。心の伴わない冷たい言葉のレンガを隙間な組み上げて、それを論理的だと称し、論理的でさえあれば伝わると思っている。冷え切った論理など、一杯の温かな紅茶にも及ばない」