☆ジョンとイチコ
☆モネの一日
☆夕暮れのケイ
3篇の連作短編集。
今年も残りわずかですね。
寒さも本格的になってきて、12月は自分の気持ちもせかせかして落ち着きま
せん。
あなたはどうですか?
疲れていませんか?
無理していませんか?
時には自分を思いっきりほめてあげていますか?
我慢していませんか?
無理に笑っていませんか?
忙し過ぎていませんか?
私は先日私に投げかけられた言葉に凹んでいます。
凹んで一週間経ちました。(^^;)
でも、まだ凹みは元に戻りません。
まあ、いいや…なんて思いますが。「ふん、」なんて気持ちにも時々なりますが。
…、あの投げやりの言葉は私の痛い所だったのだろうな、と今思います。
痛い所をパンチされたらそりゃ痛いよね。
こんな時、この本の主人公たちが飲む「ミルクコーヒー」がほしくなります。
誰かが、私のために入れてくれるあたたかいミルクコーヒー。
ほんの少しの寄り道。
そこが自分好みの雰囲気で静かに座っていられて。
ぼーっと出来て、自分を忘れて、自分を取り戻す、一時の居場所。
ミルクコーヒーって、ミルクとコーヒーの割合が8対2なのだとか。
ホットミルクに少しコーヒーを混ぜたって感じですね。
そして、このミルクコーヒーを入れてくれるケイさんは隠し味的なちょっとびっくりなものをほんの少し入れます。
今、とってもきれいな夕ぐれです。
「夕暮れのケイ」さんの言葉が聴こえてきそうです。
だいじょうぶよ。
あなたたちにはいまを乗り越える力があること、
わたしは知っているの。











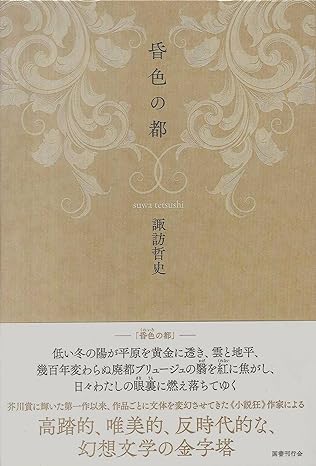

 本文より
本文より けれど、人生の選択は、振り返って正解だったのかどうかと考えることには意味がない。選択させてしまった道を進むしかないのだ。
けれど、人生の選択は、振り返って正解だったのかどうかと考えることには意味がない。選択させてしまった道を進むしかないのだ。
 本文より
本文より 「僕らは、それなくして生きられないものほど軽視したがりますから」
「僕らは、それなくして生きられないものほど軽視したがりますから」
 本文より
本文より
 夜のまっただなか
夜のまっただなか
 たくさんのよけいなことを考えて、いくつもの現実をこなさなければならない。私たちは、そういう生き物だ。
たくさんのよけいなことを考えて、いくつもの現実をこなさなければならない。私たちは、そういう生き物だ。




