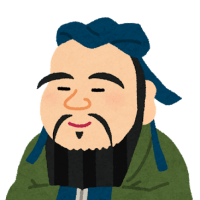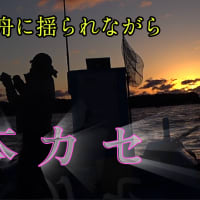論語を現代語訳してみました。
公冶長 第五
《原文》
子曰、伯夷叔齊、不念舊惡。怨是用希。
《翻訳》
子 曰〔のたま〕わく、伯夷〔はくい〕・叔斉〔しゅくせい〕は、旧悪〔きゅうあく〕を念〔おも〕わず。怨〔うら〕み是〔ここ〕を用〔もっ〕て希〔まれ〕なり。
子 曰〔のたま〕わく、伯夷〔はくい〕・叔斉〔しゅくせい〕は、旧悪〔きゅうあく〕を念〔おも〕わず。怨〔うら〕み是〔ここ〕を用〔もっ〕て希〔まれ〕なり。
《現代語訳》
孔先生が、次のように仰られました。
殷〔いん〕王朝から周〔しゅう〕王朝にかけて生きた伯夷・叔斉の兄弟は、悪事を犯した人物(たとえば殷の紂王)でさえも、ながく根に持つようなことがなかった。
だから兄弟は、他人〔ひと〕から怨〔うら〕みをかうことも少なかったのだよ、と。

〈つづく〉
《雑感コーナー》 以上、ご覧いただき有難う御座います。
当時、天子であった殷の紂王の暴政によって多くの民が苦しめられていたことを受け、武王が紂王を倒し、あらたな王朝ができたことによって、伯夷と叔斉兄弟は、「天の御心はどこにあるのか」といって、山にこもり、そこで餓死していまいました。
これは、天の御心であった紂王を、天の御心でもない武王が倒す。しかし、そのことによって多くの民が救われることになることへの、兄弟の心の葛藤といいましょうか、
ですが、兄弟は結局のところ、紂王に対しても、武王に対しても恨むことなく、その身をもって、こうした世の葛藤ともいうべきものを清算されたのだと思います。
また、こうしたところの相対性道徳(モラルジレンマ)が起こった際には、あとは自分の信じた道(正道)へと突き進んでいければいいなと思いますし、これこそが本当の意味での "自由意思" なんだろうとも思います。
伯夷・叔斉というのは、そうした意味において、己を貫いた賢人として孔子以下、史記を記した司馬遷なんかも高く評価した兄弟だったんだと思います。
※ 関連ブログ 伯夷と叔斉 「義に生きる」
※ 孔先生とは、孔子のことで、名は孔丘〔こうきゅう〕といい、子は、先生という意味
※ 原文・翻訳の出典は、加地伸行大阪大学名誉教授の『論語 増補版 全訳註』より
※ 現代語訳は、同出典本と伊與田學先生の『論語 一日一言』を主として参考