現存していない 幻の安土城 は
多くの謎を秘めた城跡だけに
石垣だけが残るその姿は
いっそう興味が湧くから不思議だ
山頂の天主跡に高さ33m地下一階地上六階の木造建築
があったなんて
信長の本能寺での自刃後13日後に誰の仕業か焼失
今や蜂やまむしが出没し
崩れしままの石垣の間から生えた樹木が一層侘しさ哀れを語り
思わず、三橋美智也の「古城」を口づさんんだ
あげく
「下天の内にくらぶれば 夢まぼろしのごとくなり」
なぁんて言っちゃってさ

山頂まで延々と続く階段


山頂の天主閣跡

多くの謎を秘めた城跡だけに
石垣だけが残るその姿は
いっそう興味が湧くから不思議だ
山頂の天主跡に高さ33m地下一階地上六階の木造建築
があったなんて

信長の本能寺での自刃後13日後に誰の仕業か焼失
今や蜂やまむしが出没し
崩れしままの石垣の間から生えた樹木が一層侘しさ哀れを語り
思わず、三橋美智也の「古城」を口づさんんだ
あげく
「下天の内にくらぶれば 夢まぼろしのごとくなり」
なぁんて言っちゃってさ


山頂まで延々と続く階段


山頂の天主閣跡











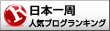











 湯量は豊富
湯量は豊富






 つづら折りの坂を登るとあちこちで温泉らしいにおいと湯けむりが立ちあがる
つづら折りの坂を登るとあちこちで温泉らしいにおいと湯けむりが立ちあがる























