<金曜は本の紹介>
 「ホンダ イノベーションの神髄(小林三郎)」の購入はコチラ
「ホンダ イノベーションの神髄(小林三郎)」の購入はコチラ
この「ホンダ イノベーションの神髄」という本は、ホンダで1987年に日本初のエアバッグの量産を成功させ、2000年にはホンダの経営企画部長に就任した小林三郎氏が、その経験を基に、ホンダが今でもイノベーションを成功させるその秘訣について、分かりやすくまとめたものです。
特に、世のため人のために「作って喜び、売って喜び、買って喜ぶ」という「3つの喜び」を大切にすることや「人間尊重(自律、平等、信頼)」という哲学と純粋な想いが、イノベーションの成功を手繰り寄せるカギとなったということはよく理解できました。
また、三日三晩の合宿で一つのテーマについて徹底的に議論するワイガヤは素晴らしいと思いましたね。
この議論を続けていると、「他人や社会のために自分やホンダは何ができるか」という気持ちに全員がなるようです。
最近、初めてホンダのクルマを買ったのですが、特にリアルタイムに各ホンダ車の情報を基に渋滞を避けるインターナビというカーナビシステムは凄いと感動しましたし、もちろんエアバッグはサイドのカーテンエアバッグも付けていてとても満足しています。
この本に書かれている努力や情熱が、こういった製品につながっているのだと納得しました。
最近だと、N-BOXやN-ONEというクルマが機能やデザインが素晴らしく、売れているようですね。
また、10年ほど前のことを思い出しましたが、S2000というクルマを試乗したときは、そのクルマの開発にかけた情熱について、かなり熱っぽく説明を受けて、そしてその走りもよくて、とても感動した記憶があります。二人乗りでなければ買いたかった・・・
ホンダはそういう情熱あふれた会社なんですね。
アップルのスティーブ・ジョブスの情熱にも似ていると思いました。
「ホンダ イノベーションの神髄」という本はとてもオススメですね!
以下はこの本のポイント等です。
・「イノベーションに挑みたい」-技術者の本能がそうささやく。イノベーションとは技術革新による新しい価値の創造であり、人々の暮らしや社会を良くする原動力となるからだ。技術者なら必ず、自らの手で成し遂げたいと思うはずである。その意味でイノベーションに取り組むことは楽しい。1987年12月10日、事故が起きてエアバッグが初めて日本で作動し、乗員を保護したと販売店から連絡を受けた。すぐに時間をつくって会いに行った相手は、群馬県の地元企業の社長さんで、「エアバッグで命拾いした。ありがとう。ありがとう」と何度も感謝の言葉を受けた。握手した時の感覚は、今も手に残っている。その後も、多くのお客様から長期間にわたってエアバッグに対する感謝の手紙をいただいた。技術者冥利に尽きるとはこのことだ。技術者としてのキャリアの大半をエアバッグの開発・量産・市販に充て、その後はホンダの経営と身近に接してきた。その間にイノベーションについて真剣に考え続けた。理想化する気は毛頭ないが、ホンダにはイノベーションを成功に導く企業文化や仕掛けがあると考えている。
・イノベーションは成長の糧である反面、それに挑戦するには漠然とした覚悟ではダメだということである。イノベーションの目的や意味について徹底的に考え、腹の底から、それこそ魂のレベルで理解する必要がある。この点、ホンダは極めてシンプルだ。イノベーションで目指すものは「絶対価値」(本質的な価値という人もいる)の実現である。ここでいう価値とは、あくまでもお客様にとっての価値である。故に、研究のための研究や、技術者の自己満足のための技術開発には見向きもしない。そして、絶対価値とは、「違い」を生む価値のことを指す。
・言いたいことはただ一つ。「他社の話なんて聞きたくない。それは相対的な話にすぎない。あんたは今、ホンダの安全の方向性を決めているんだ。そのときになぜ他社の顔色を見るのか。なぜ自分たちがこうなりたいと、絶対価値を言えないのか」ということだった。入社2年目の新米技術者に対して専務が気色ばんで真剣に怒ったのである。これが結局30分続き、具体的な報告内容まで進めず、再報告になった。相対価値ではなく、「絶対価値の実現を目指す」と話すのは簡単だが、ここまで徹底的にこだわり、実際の行動に反映させないと、その意味を腹の底から理解したとはいえない。
・以下はホンダの企業文化を著者なりにまとめたものだ。「高い自由度」「熱い議論」「本質的な高い志」が3つの柱だ。その「志」の項目の中に絶対価値の追求が含まれている。「専務とケンkしろ」というのは、「高い自由度」と「熱い議論」という2つの柱と深く関係している。以下は目新しいものではないと感じるかもしれない。ホンダの企業文化の特徴は、こうした項目だけではなく、むしろ、それを日常活動の中で、とことん考えながら愚直に実践することにある。実際ホンダでは、若手社員と取締役が役職とは関係なく、一人の人間として激論を交わすことが普通にある。
<高い自由度>
・平等(フラット組織)
・学歴無用
・ミニマムルール
<熱い議論>
・前向き
・ワイガヤ(本質議論)
<本質的な高い志>
・A00(本質的な目的・ゴール)
・自分の想い・志
・コンセプチュアル
・絶対価値の追求
・高い目標
↓
ノリのいい知的興奮集団
<自律の文化>
・一人ひとりに自ら考えさせ、自律させる(自分自身で自分を律する)
<熱気と混乱が革新の母>
・研究開発者の熱気がないと革新は生まれない
・トップが熱気に反応しないと、革新を殺す
・本格的なイノベーションの成功率は10%にも満たない。つまり、多くは失敗する。実施期間も10年以上に及ぶことが多い。長期間にわたって成功率の低い多数のプロジェクトをマネジメントすることは、論理と分析に基づいたきめ細やかな手法では無理だ。このため、「熱意や想い」といった、人間性に基づく原理でプロジェクトが運営される。ホンダは一時期、そのイノベーションにおいて、およそ20%の成功率を達成していた。通常の2倍以上である。こうして実現した絶対価値がホンダの成長の大きな原動力になったのである。さて、ここでもう一度、上司や周囲の人たちが、なぜ正しいという信念の下でイノベーションを阻害するのかを考えてみよう。その最大の理由は、オペレーションの価値観で、イノベーションを評価するからである。1年から数年の期間限定で100%の成功を求められるオペレーションの視点からは、10年以上かけて9割が失敗するイノベーションのプロジェクトは欠陥だらけに見えるのだ。加えて、オペレーションは論理と分析に基づいてプロジェクトを進めているので、これまでの取り組み内容や成果、今後の展開・見通しを理路整然と説明できる。このため、熱意や想いを推進力とするイノベーションのプロジェクトはいいかげんに見えてしまう。最後までイノベーションの本質を理解できないのだ。さらにこうした流れをダメ押しする要因がある。企業活動の95%をオペレーション業務が占めていることだ。こrは、裏を返せば、オペレーション業務で成果を上げて役員になった人が大多数を占めていることを意味する。オペレーションでの成功体験に照らすと、イノベーションの非効率さばかりが目に付くのだ。しかも多くの場合、イノベーションの現場の担い手たちは変わり者だ。イノベーションは、正規分布の中央部ではなく、端部から生まれるからである。ほとんど注目されていない領域からユニークな価値を発掘することがイノベーションである。だから必然的に、担当者はユニークな人、日本語にすれば変わり者、が多くなる。結局、多数を占めるオペレーション派が主導権を取ってイノベーションを阻害し、死に至らしめることになる。
・創業期の企業は規模がちいさく、やりたいことがあって起業したので、もともと新しいことに挑戦する気概に満ちている。イノベーションにも積極的に取り組む。しかも、創業者自らが判断するので意思決定が速い。ところが、企業が成長してオペレーションが主流を占めるようになった瞬間に熱気が失われる。すべてを理解していると勘違いしている、オペレーションが得意な経営陣が、その成功体験に基づいて深い考えもなしに、正しいことをしていると思いながらイノベーションの息の根を止めるわけだ。しばらくはそれまでの蓄積があるので、外からは順調な経営に見えるが、新たな価値が生まれないので先細りとなる。そして待っているのは、大企業病の蔓延であり、それに起因する混乱だ。多くの企業は、こうした経緯をたどって衰退していく。
・ホンダでは、目標を考える際に、必ず「A00」に落とし込んでいく。A00は「本質的な目標」のことで、「在りたい姿」や「夢」と置き換えてもよい。
・A00でもっとも重要なことは、何が本質なのかを腹の底で理解し、魂の発する言葉として表現できるまで、とことん問い詰めることだ。よく練られたA00は、もうこれ以上細分化すると手段になってしまう、ギリギリの直前であることが多い。これによって、必要となる手段(技術開発)を簡潔に統合するのである。このためA00は、適用する商品開発や技術開発といったプロジェクトごとに、内容だけではなくフェーズも変わってくる。その商品や技術に対して「顧客は何を求めているのか」「ホンダはそのニーズにどう応えられるのか」「開発を担当するあなたは何がしたいのか」を、考えなければならない。「考えてばかりで技術開発が成功するのか」という声が聞こえてきそうだが、考え抜くことはとても重要である。ここでボタンを掛け違えると、それ以降の研究開発が全て水泡に帰すことさえあるからだ。
・著者は以前、「アコード」や「レジェンド」、シビックなどの開発責任者と議論したことがある。彼らが口をそろえるのは、ぴったりはまるコンセプトができると技術は付いてくるということだ。そして、コンセプトとA00は直接つながっているのである。
・3つの喜びとは、1951年12月におやじ(本田宗一郎(創業者))が社内報で我が社のモットーとして掲げたもので、「作って喜び、売って喜び、買って喜ぶ」こと。おやじはその中で「私は全力を傾けて、この実現に努力している」と書いている。3つの喜びは、技術者、販売店・代理店、購入者の喜びを同時に実現することを目指したものだ。中でもおやじは、「買って喜ぶ」を最も重要と考えていた。「製品の価値を最もよく知り、最後の審判を与えるものはメーカーでもなければディーラーでもない。日常、製品を使用する購入者その人である。「ああ、この品を買ってよかった」という喜びこそ、製品の価値の上に置かれた栄冠である」と宣言している。これは、技術者の独り善がりに対する戒めにもなっている。「買って喜ぶ」を真剣に考えれば、技術者がイノベーションで実現すべきは顧客に喜んでもらうための価値という考えが自然と出てくる。だから、論文を買くための研究や、技術者の好奇心を満たすための技術開発には見向きもされない。そして、最後の審判はユーザーがするので、例えばユーザーに違和感がある場合は、製品や技術に問題があると考えるのである。
・おやじは「ムダなやつは一人もいない。皆に得手をやらせれば苦労をいとわず向上心が出て頑張り、本人は幸せなんだ」と語っている。「B・C級(の人材)は出て行け」と言い放った米国の経営者とは大きな違いだ。
・人間尊重は個性の重視とも重なる。異端者や変人、異能の人を排除しないで尊重する、懐の深い文化がホンダには根付いている。むしろ、イノベーションを目指すチームは変わり者だらけだ。個性がない人、言い換えれば自分の考えを持たない人に独創的な仕事ができるわけがない。人間尊重は、個性の重視を通じてイノベーションとも密接に関係しているのだ。
・ホンダは、3つの喜びと人間尊重を基本理念・哲学にしているが、哲学だけでイノベーションが実現できるわけではない。「行動(技術)なき理念(哲学)は無価値」なのだ。そこでホンダは、理念・哲学を実際の行動に結び付ける、「企業文化」と幾つもの「仕掛け」を培ってきた。人間尊重はホンダの企業文化として、3つの喜びは目指すべき目標として、ホンダ社員の体に染み付いている。こうした企業文化や仕掛けがイノベーションを強力に後押しするのだ。たとえば本質的な目標を簡潔に表現するA00や、三日三晩の合宿で一つのテーマについて徹底的に議論するワイガヤといった仕掛け、熟慮を経ていない発言に対して徹底的に叱りつける文化や学歴無用のフラットな組織という企業文化が、いわば加速装置のような役割を果たしてイノベーションを推し進める。こうした企業文化と仕掛けがホンダ独特の「熱気と混乱」を生んでいるのだ。
・仕掛けづくりに関しては、三代目社長の久米是志さんの存在が大きかったと思う。A00を導入したのは久米さんだし、ワイガヤを始める際にも久米さんが深く関わったといわれている。もともとおやじは、「技術の前に哲学がなきゃダメだ」とか「素人に分かりやすく説明できないようじゃ、おまえは分かっていない」ということを常に社員に話していた。時には「おまえたちはこれが本当にお客様の価値だと思っているのか」と涙を流しながら殴りつけることもあった。久米さんたちはそうやって直接鍛えられたが、おやじが第一線から遠ざかっていった時期、どうすればいいかを真剣に悩み、熟慮に熟慮を重ねたのだと思う。おやじは天才だから、普通の人間には同じことはできない。そして、何とかしておやじのDNAを引き継ごうとしてたどり着いたのがA00であり、ワイガヤだったのではあるまいか。
・実はもう一つ、ホンダ流イノベーションの必須条件がある。技術者が高い志と強い想いを持つことだ。ホンダでは、技術者個人の自由と裁量に任されている領域が広い。技術者のやる気がなくなったら、いくら本質に根ざした哲学があり、イノベーションの加速装置を備えていても全く役に立たない。全てが一瞬にして崩れ去ってしまう。そのため、技術者を叱咤激励して、やる気を引き出す必要がある。この役割は、経営陣が担わなければならない。これこそ、まさに人づくりなのである。財務体質が改善すれば企業がよくなったように見えるが、あくまでも短期的なものだ。中長期的に会社をよくし競争力を高めるには人づくりしかない。だから、経営者や役員は、人づくりのために時間の3~4割を使う必要がある。
・ワイガヤは社外でやる。基本は三日三晩の合宿だ。一週間の場合もあるが、1日4時間ぐらいしか寝ないから、三日三晩が限度だ。著者が所属していた安全部隊だと、一人が1年間に平均で4回くらいワイガヤに参加していた。1回3日間で、4回行うと年間で12日間にいある。年間の勤務日数は240日程度なので、約5%を通常の業務から離れてワイガヤに充てていた。参加する人数は7~8人が多い。安全部隊は著者が入社した当時は数十人で、その後人数が大きく増えた。その中から7~8人が集まるので、いつも同じメンバーというわけではない。
・実際のワイガヤはどんな雰囲気なのだろうか。何しろ三日三晩、同じテーマを延々と議論し続けるのである。そんな機会は、普通は滅多にないはずだ。当然だが、一日目はみんな元気だ。自分の意見を主張し、みんなの説得にかかる。しかし、そう簡単に説得されないから議論は白熱する。まず、それぞれが言いたいことを言わなければワイガヤは始まらない。二日目になると人の意見を理解しようとし始める。理解した上で自分の主張を深めていく。大体この頃には、ワイガヤで初めて一緒になった人の人柄も分かってくる。そして、三日目に入ると論理的な意見が出尽くして、みんな疲れてくる。そんなときに「それをホンダがやる意義は何か」なんて、議論をスタート地点に戻すような意見を言う人がいたりする。みんな「また、そこから始めるのか」という感じでドッと疲れる。しかし、これは重要で、同じ「意義」であっても、初めのころの意義と三日目の意義ではレベルが違っており、議論は確実に深まっている。こうした行きつ戻りつを繰り返しながら、議論は論理の枠を超え、創造的な領域に入っていくのだ。不思議なものでここまで来ると、自分をよく見せようとか、地位や名誉、富や権力を求める心がすっかり消えて、「他人や社会のために自分やホンダは何ができるか」という気持ちに全員がなってくる。数え切れないほどワイガヤに参加したが、それはいつも同じ。人間の本性は高貴なものだとつくづく感じる。誰もが高貴な心を持っている。これを確信して共有することが、実はワイガヤのもう一つの大きな効用かもしれない。
・三現主義は、おやじがホンダを起業して以来ずっと言い続けてきたことだ。三現とは「現場」「現物」「現実」を表す。一般には「現場で現物を見て現実を知り、現実的な対応をする」ことと説明されるが、ホンダの三現主義には、さらに「本質」という隠れたキーワードが埋め込まれている。つまり、「現場・現物・現実」を知ることで、本質をつかむ」ことがホンダの三現主義だと著者は考えている。さらに言えば、本質をとらえるためには、あれこれ考えたり議論したりする前に、まず現場・現物・現実を知らなければならないという、揺るぎない信念がホンダの三現主義には込められている。そして、三現主義は現実に軸足を置くので、机上の空論に対する戒めともなる。おやじは、この三現主義を常に実践してきた。現場に足を運び、現物をジッと見つめたり手に取ったりして、よく考え込んだ。
・三現主義というと生産現場の改善に主眼を置くことが多いが、ホンダの場合は生産現場だけではなく、開発や研究、営業や調達など全ての事業活動の現場が対象になる。
・本質は現実に根ざしている。しかし、現実をそのまま受け入れたのでは、何も変わらない。理想と現実という二つの異なった視座を行き来しながら、「何を変えるか。本当にそれを変えることができるか」を問い続け、本質を追い求めていくのがイノベーションにおける三現主義なのである。
・16年に及ぶエアバッグの開発の期間中に、しつこく聞かれ続けたことがある。直接の上司だけではなく、本田技術研究所の実質トップだった久米是志・ホンダ専務やおやじが、繰り返し繰り返し問い掛けるのだ。「エアバッグの価値は何だ?」と。これに対してはいつも、「安全です」と答えた。すると「安全の何が価値なのか?」と聞かれるので「世界で毎年10万人、毎日300人近くの人が交通事故で亡くなっています。エアバッグがあれば、この人たちの多くの命を救えます。我々がやらなければいけません。」こんなやりとりを何度も経験した。その答えを聞くと、直接の上司や久米さん、おやじたちは「そうか」と同じようにうなずいた。今になって思えば、答えた内容ではなく、答え方と目を見ていたのだと思う。それによって、開発チームがコンセプトをつかんでいるか、前向きに取り組んでいるか、そして何より、心底やりたいと思っているか、などを測っていたのではないか。質問が本質的な内容だけに、ごまかしは利かない。
・失敗したことを知って「なぜこんなことをやったのか」と聞く。そのときに「あなたがやれと言ったからじゃないですか」と答えると怒鳴り声で返ってくる。「俺がやれと言ったからやった?それなら、俺が死ねと言ったなら、おまえは死ぬのか」と。なぜ怒鳴るのか。それは、上司が言ったことを無批判にそのままやるという姿勢が許せないからだ。失敗の責任を部下に押しつけようとしているわけではない。「あなたの助言のこの点に可能性があると考えて実験してみましたが、うまくいきませんでした。」と答えれば、怒ることは絶対にない。この2つの答え方の最大の違いは、担当者自身の判断が入っているかどうかである。前者は「言われたことをそのままやる」、後者は「自分の判断によってやる」。担当者が自律しているかどうかが問われているのである。もう一つ、ここには平等の考えも入っている。上司の助言業務命令と受け止めて無批判に実施することは、そこに明確な上下関係があることを示している。一方、妥当性を判断した上で実施する場合には上下関係はない。上司の助言は幾つもある選択肢の中の一つとして平等に扱われるかrだ。ホンダには「技術の前で平等」という伝統があり、役職が高いからといって、ある特定の技術をゴリ押しすることは許されない。技術の優劣を判断する基準はただ一つだけ。すなわち、お客様に新しい価値を提供できるかどうかだ。そして、その判断を実際に行うためには、自律と平等という土壌が必要なのである。俺が死ねと言ったならうんぬんは、もともとおやじが言ったことなのだろう。何人もの先輩から、この言葉で怒鳴られた。これに限らず、多くのおやじの言葉が今もホンダの中で生きている。そして最後が信頼である。ホンダの人たちは婉曲表現を嫌う。本音と建前の使い分けもない。その方が伝えたいことを確実に伝えられ、余計なことを考えなくて済むからだ。だから「腹の探り合い」や「相手の出方をうかがう」といった”高度な話術”に出番はない。
・若い技術者でもプロジェクトの責任者になれるということを意味する。ホンダには、人が持つ、特に若手が持っているポテンシャルを信じ、大きな裁量権を与える伝統がある。こうした環境は、特にイノベーションにとっては強みになる。イノベーションは失敗に終わる可能性が高く、成功率はどんなに高くても20%前後、普通は10%に届かない。いわばハイリスク・ハイリターンのプロジェクトだ。これは、若者向けの仕事といえる。少数の例外を除けば、人は年を取るに従ってリスクを取らなくなる上、積み上げてきた専門知識も邪魔になることが多い。確かにベテランの専門家はいろいろな知識を持っているが、その知識は全て過去のもの。イノベーションは、過去の技術の改良ではなく未踏の領域に挑戦することなので、過去の知識は役に立たない。ベテランの専門家は、過去の知識が障害になって技術を素直に見ることができず、まず、できない理由を考える傾向が強い。以前にも紹介したが、エアバッグの実用化には、ホンダの技術系役員と幹部技術者はほとんど全員が反対した。イノベーションには、リスクを恐れず技術的な偏見のない若い技術者の存在が絶対に必要なのである。
・一方で、任せた以上、上司は口を出さない(支援しない)というのもホンダの伝統だ。エアバッグの開発の初期段階で、技術的な課題がなかなか解決できず、上司の主任研究員に相談したことがある。愚痴に聞こえたかもしれない。すると、「サブちゃん(著者のこと)、君は本当にラッキーな技術者だ」と、にこにこしながら肩をたたいてきた。その理由がとんでもない。「技術的な問題は、君だけが抱えているわけじゃない。たぶん、ライバルメーカーも同じだ。君がそれに挑戦して解決できたら、その技術を組み込んだすごいクルマができて、お客様に喜んでもらえる。まさに”三方一両得”だ」といった具合。正直言って「コノヤロー」と思った。こっちは真剣に悩んでいるのだから。しかし、このとんでもない答えにも不思議な効用があった。壁に突き当たっても「チャンスかもしれない」と、前向きに考えるようになったのだ。これはとても大切なことで、問題が起きたときに大変だと悩むよりもチャンスだと前向きに考えると、それだけで結果が大きく違ってくる。
・「俺はさあ、もうすぐ50歳だ。金もないけどよ。おまえの年に戻れるんだったら500億円だって払うぞ。若いというだけでそれくらいの価値があるんだ。それなのに、おまえは何をくだらないことを言っているんだ。そんな言い訳ばかりしていると、何もしないまま人生が終わってしまうぞ。そうやって生きていくのか」40年前の500億円だから相当な額だ。当時の私に500億円の価値があったわけではもちろんない。あくまでもポテンシャルの話だ。ポテンシャルをフルに生かせば500億円にもなるが、生かさなければ何もなし得ない。頭を強烈に殴られたような衝撃を受けた。くだらないことでくよくよ悩んで、時間をムダにしてはいけない。そして、できることを着実にやっていこうと心に決めた。「ラッキーな技術者」と「500億円」の話を先輩から聞かされたのは、ここで紹介したときだけではない。やはり若いときにそれぞれ何回か言われたことがある。しかも、ラッキーな技術者の話には必ず三方一両得のオチが付き、若さの価値はいつも500億円だった。だからたぶん、この2つはおやじが言ってきたことなのだろう。
・量産プロジェクトは比較的に順調に進み始めた。それには、著者が工場に対して敬意を持っていたことが大きな要因の一つだったかもしれない。敬意とは何か。当時の工場は職人気質で、理詰めの話が通じないことも多かった。酒の席に誘われたら、飲めないのだが必ず付き合うし、世話になったら心を込めてお礼を言う。こうして信頼関係を築いていった。それに加えて、相手の価値観を尊重することが特に大切だ。
・ここでは、なぜエアバッグの開発が成功したかについて考えてみたい。エアバッグの開発の道のりの中にイノベーションを成功に導く本質があると思うからだ。まず、絶対に諦めなかったことである。みなさんには月並みなことに聞こえるかもしれないが、諦めないためにはくじけない心を持つことが必要であり、それはなかなかできることではない。
・ほとんどの出席者が反対する経営会議でエアバッグの量産を決めた久米さん。必要ないと確信しながらも米国でのエアバッグの実車搭載試験を許可してくれた雨宮さん。開発中止を宣告し、権限でいえばそのまま中止にできるところを、著者の想いをくみ取って開発を継続させてくれた下島さん。そして、周囲からダメテーマといわれる中で一緒に闘ってくれた開発チームのメンバー。いろいろな曲折もあったが最終的に協力してくれたサプライヤーの皆さん。運だけでは決して乗り越えられなかったはずだ。そこにはホンダの哲学があったのである。著者が危機の際に繰り返し話した「交通事故で亡くなっている多くの人たちを、エアバッグで救いたい」という想いは、まさにホンダの哲学そのもの。この想いが、同じ哲学を魂の中に息づかせている人たちと共鳴し、彼らを突き動かしたのである。哲学とそれに基づく純粋な想いには、人を動かす、目に見えない大きな力がある。その力が大きな流れになって、エアバッグを実用化に導いた。哲学と想い、この2つこそがイノベーションの成功を手繰り寄せる最大のカギなのである。
<目次>
1章 絶対価値 さあ、未踏の技術に挑もう
2章 イノベーション包囲網 なぜ上司や周囲は反対するのか
3章 本質的な目標 良い目標がイノベーションを導く
4章 哲学と独創性の加速装置 息づく本田宗一郎氏のDNA
5章 ワイガヤ①高貴な本性 三日三晩話すと何かが起こる
6章 ワイガヤ②心の座標軸 愛について、何をしっている
7章 三現主義 まずは現場・現物・現実と心得よ
8章 現実的とは エアバッグで子供を殺すな
9章 異質性と多様性 あなたは「どう思う」、そして「何がしたい」
10章 学歴無用 答えのない問題を解く
11章 ルールとホンダのしきたり ルールは最小限に、自律する組織をつくる
12章 コンセプトと本質①五代目シビック サンバで、クルマをつくる
13章 コンセプトと本質②アポロ計画 「キミの言うことは訳が分からん」
14章 コンセプトと本質③言葉の力 技術開発を始める前にすべきこと
15章 トップと上司の眼力 久米三代目社長の、魔の40分
16章 自律、平等、信頼 俺が死ねと言ったなら
17章 若者のポテンシャル 二階に上げて、はしごを外す
18章 説得 もうホンダを辞めるしかない
19章 やる気を引き出す おまえら、ボーナスは要らないな
20章 価値の見える化 マップを描いて新しい価値を探る
21章 開発から量産への壁①連携 「エアバッグはマムシぐらい大嫌いだ」
22章 開発から量産への壁②サプライヤー 自らが動かないと何も始まらない
23章 哲学と想い 人を動かす大きな力
24章 イノベーションに挑む 天才でなくともイノベーションを達成できる
おわりに
面白かった本まとめ(2013年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。


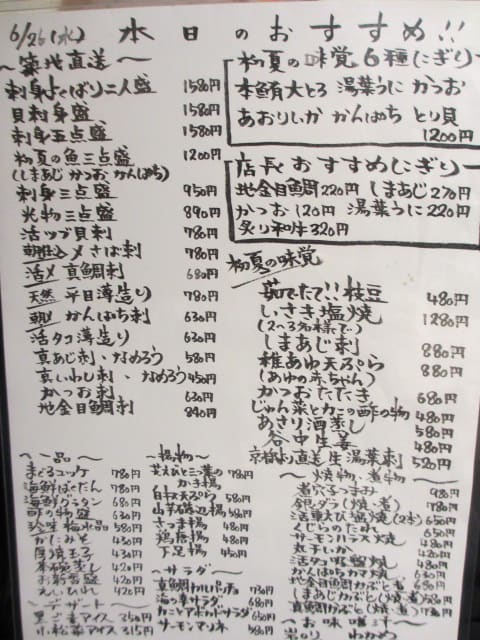






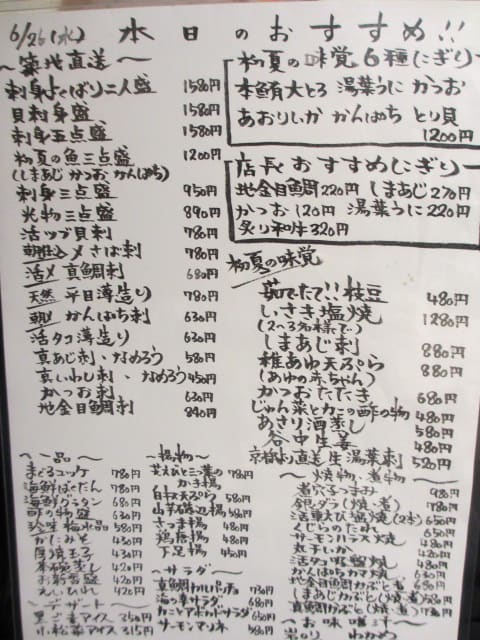
















 「ウナギ 大回遊の謎(塚本勝巳)」の購入はコチラ
「ウナギ 大回遊の謎(塚本勝巳)」の購入はコチラ 























 「世界で勝たなければ意味がない-日本ラグビー再燃のシナリオ(岩渕健輔)」の購入はコチラ
「世界で勝たなければ意味がない-日本ラグビー再燃のシナリオ(岩渕健輔)」の購入はコチラ 


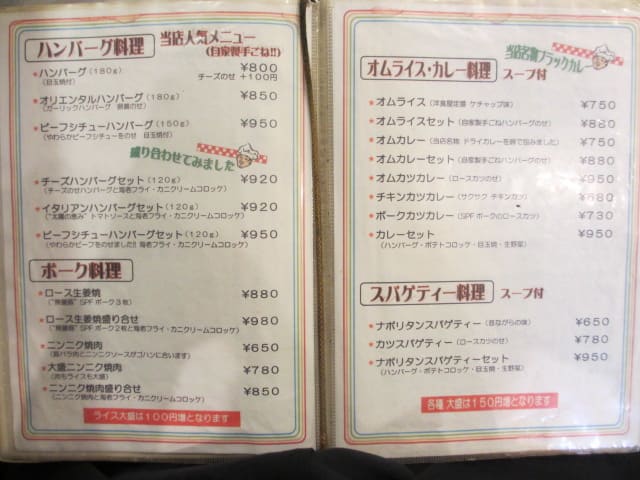


 「ホンダ イノベーションの神髄(小林三郎)」の購入はコチラ
「ホンダ イノベーションの神髄(小林三郎)」の購入はコチラ 





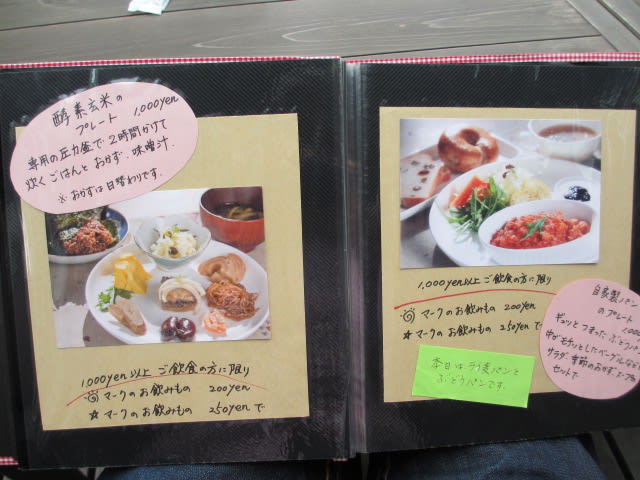

















 「生で大切なことはみんなマクドナルドで教わった(鴨頭嘉人)」の購入はコチラ
「生で大切なことはみんなマクドナルドで教わった(鴨頭嘉人)」の購入はコチラ 





























