<金曜は本の紹介>
 「「学び」を「お金」に変える技術」の購入はコチラ
「「学び」を「お金」に変える技術」の購入はコチラ
「「学び」を「お金」に変える技術」という本は、歯科医師だけでなく世界中のさまざまな自己啓発、経営プログラムなどを学び続け、現在はセミナー講師としても全国に飛び回る著者が書いたものです。
人生を確実に成功に導くものは「学び」で、この本ではその学びの方法や考え方・時間管理・人間関係・習慣などについて、とても分かりやすく説明しています。
主に以下について書かれていて、特に楽しく勉強することや、時間管理を大切にしコツコツ良い習慣をもって進めること、感謝や笑顔・スポーツ・教養が大切、周りに自分の目標などを伝えること、教えることが学びを強化、アピールすることが大切、そして勉強したことを社会に役立てればお金につながるについては共感しましたね。
・自分で仕事を天職に育てるほどのめりこむこと
・どんなセミナーを受講すべきかの答えは自分の中にある
・苦しい努力、つらい努力はせずに楽しく勉強すること
・時間管理をアップするには7つのことを守る
・計画通りコツコツと進め努力すること
・テレビによって貴重な時間を奪われないこと
・自分以外に頼めることは頼む
・学びに投資したものは損をすることはない
・勉強し続けると、追いかける人はいなくなるのでトップランナーになれる
・この世の中で起こることはすべて、自分の心の反映
・最高の人生ビジョンは社会福祉に生きること
・社会的な地位とは無関係にその人に引きつけられるかで選んで付き合うと人間関係について悩むことは減らせる
・運気の高い人とともにいること
・必死になって学びたいのならライバルの存在はこれ以上にない
・多くの人に支えられ助けられているのだから感謝することは大切
・笑顔を磨くことは大切
・達成感の喜びを味わい努力中毒になるとよい
・スポーツでがんばった人のほうが勉強でも仕事でも成果が出やすい
・本やセミナー、イベントなども出会った時が出会うべきタイミングなのでその機を絶対に逃さないこと
・本を選ぶにはTOPPOINTが参考になる
・出かけるときは最低でも3冊以上本をもつ
・一流の人材は、幅広い教養を身につけている
・努力することを通して自分を制御することを身につけることが本当の成果
・小さなことにも全力で取り組むこと
・とにかく本気になって勉強すること
・人生は毎日の生活の積み重ねだから良い習慣をつけること
・夢や目標のベクトルを自分中心から他者に役立つこと、社会に貢献することに切り替えること
・自分はどう願っているのか、どういう人物を目指すのかそれを絶えず語り続けることが大事
・学んだことを本当に身につける最高の方法は教えること
・自分の存在をいかに魅力的にアピールするかが大事
・仕事に本気に取り組み、世の中のため、人に貢献することを最大の喜びとして生きれば、その評価として必ず相応の報酬を手にすることができる
「「学び」を「お金」に変える技術」という本はとてもオススメです!
以下はこの本のポイント等です。
・1億円プレイヤーをめざす。そのために、いま、どんな仕事をしているかは大した問題ではありません。大事なのは、どんな思いで仕事をしているかです。「これこそ自分の天職だ」と確信できるぐらいいまの仕事が好きで、のめり込んでいるかどうか。それが大事なのです。私は天職は誰かに与えられるものではなく、自分で天職に育てていくものだと考えるようになりました。
・どんなセミナーがいいか。なんのセミナーを受講すべきか。私の経験が教えているように、答えは自分の中にあるのです。資格の勉強でも、語学の勉強でも懸命に学んでいくと、しだいに学びの感度が鍛えられていくのでしょう。少し学びだすと、関心がそちらに向くことから、それまで見逃していた雑誌やインターネットの広告、一度参加したセミナー主催者からのDMなど、セミナーの情報はいくらでも手に入るようになります。その中からどれを選ぶか。自分がちゃんと教えてくれるのです。数ある情報の中で、なぜか心惹かれるセミナーとか本は、自分が潜在的に求めていたもの、あるいは求めていたものに強くつながっているものです。ベストアンサーは、常に自分の中にあります。
・苦しい努力、つらい努力はしないほうがいい。いえ、してはいけない!のです。私が常に勉強をしているのは学ぶことが好きだから。楽しくてしかたがないから。勉強しているときがしあわせで、心の奥底から充足感が湧き上がってくるからです。だから、普通イメージするような苦しい努力はしませんし、したいことを我慢して勉強することもありません。その意味では「努力」は一切していません。「したいから勉強している」「楽しいから学んでいる」ので、苦労や我慢、つらい努力とはまったく無縁です。
・次の7つを守ると、「時間管理」のスキルは高水準にアップグレードできます。
①優先順位を決める
②新しいことをはじめるときは、現在、行っているものの一部を捨てる。
③できないこと、苦手なことはムリしてしに。
④したいことだけをする。本当にしたくないことは断る。
⑤取り組むときは、真剣に、集中して行う。
⑥スキ間時間をムダにしない。どんな小さな時間でも活用する。
⑦常に本気で生きる。明日はないという気持ちで取り組む。
・10代、20代、30代・・・と各段階でやるべきことをきちんと果たし、一段階ずつ積み上げていかなければ、高い頂点に到達することはりえません。私の年齢で、開業してから20年に満たない時間でここまで大きな成果を得られたのは、運がよかったからではなく、一歩一歩戦略どおり、計画どおりに私が進めてきたからです。緻密な計画と、それを実現するための真剣な努力。それを怠らずに実行してきた結果が、今日の私の姿です。
・NHK放送文化研究所の「2010年国民生活時間調査」によると、1日のテレビ視聴時間は平日平均で3時間28分。最近、テレビ離れが進んでいるといわれているにもかかわらずです。新聞は19分、雑誌・本は13分。テレビは圧倒的で、メディアの王様の座は不動です。逆に考えれば、テレビによって貴重な時間を3時間半近くも奪われてしまっていることに愕然としませんか?ながら視聴をする人もあるでしょうが、食事の後など、うっかりしていると、1時間ぐらいテレビに気をとられてしまうことはよくあります。ある知人は見たい番組は録画してしまい、基本は早送り。大事なところだけノーマルスピードで見る。この方法で1時間番組は30分以下で、十分楽しめるといっています。
・自分以外の人に頼むことができて、しかも彼らのほうがよくやってくれるとしたら、自分でやる必要はない(ヘンリー・フォード)
・最近もリーマンショックをきっかけに、ヨーロッパの金融危機と投資環境は悪化の一途をたどっています。こうした例からも、不動産や株式などの投資はいかに不確実で、時を得なければ、あっけなく無(ゼロ)に帰す、いや、大きな損失(マイナス)を招きかねないものだとわかります。それに対して、学びに投資した場合は、絶対に損をすることはないのです。学びの成果は確実に自分自身のものになり、一生、マイナスになることはありません。そのうえ、経験を重ねることによってどんどん磨きあげられていき、付加価値が加わっていくのです。
・以前、1回18万円という高額のセミナーを受講したことがあります。1年間12回で1つのコースになっていたので、参加費用はトータルで216万円。さすがに定員12名の少数精鋭主義というか、あまりに高額で参加者が少なかったのか、会場に顔をそろえた受講生は8名。比較的若いのは私ともう一人ぐらい。残りは50~60代。大手企業のトップ経営者ばかりでした。しかもこのセミナー、講義らしい講義があるのは午前中だけで、午後からはグループに分かれてフリートーク。1回18万円もとっておいて、半分はフリーディスカッションかと思ってくらいでした。でも、このディスカッションがすごくよかったのです。なんといっても、メンバーの多くは年商数百億~数千億円の大企業のトップ経営者なのです。それまで出会っていた年商数十億~100億円という経営者とはまるで格が違います。年商数十億~100億円クラスの経営者には、たたき上げの人に共通するすさまじいばかりの情熱があり、大いに刺激を受けてきました。年商100億円までなら仕組みがなくても情熱だけでなんとかいける。そんな印象をもち、私もまず、そこをめざしていこうと自身も得られました。ところがそこから1ケタ上がると、人としての器が違ってくるのです。経営者として優れているだけでなく、それぞれが人間的なオーラを放っている。親しくなって話をすると、みなすごい人格者なのです。それだけの人間力がないと大企業を引っ張っていくことはできないのだと圧倒される思いでした。
・参加者の一人、その方も大手企業の社長さんでしたが、この方から、「井上君、50歳までは勉強をしなさい。そこまで勉強を続ける人はいないから、50歳まで勉強していると、もう後を追いかけてくる人はいなくなって、まちがいなくトップランナーになれますよ」といわれた言葉はいまも脳裏に深く刻み込まれています。
・「鏡の法則」をご存じでしょうか。この世の中で起こることはすべて、自分の心の反映なのです。同じ金額を使うのでも、常に社会のため、人のために貢献できるようにと心している人にはちゃんとリターンが返ってくるのは、この法則が働くからです。
・彼らが描く最高の人生ビジョンは社会福祉に生きることなのです。カネギーもロックフェラーもビル・ゲイツも、ビジネスを大成功させると、次の生き方の軸足を社会福祉に移しています。お金はこうした使われ方をしたとき、本当の価値を発揮するのです。もともと、ビル・ゲイツの素顔はかなりの倹約家だそうです。何度も世界一の大金持ちに輝きながら、お金をじゃぶじゃぶお湯水のように使うことには関心がなく、むしろ、倹約することをゲームのように楽しんでいるというから痛快です。富は社会に還元する。こうしたことをドリームといってのける国民性は偉大です。カーネギーホールに足を踏み入れるたびに、私はその精神を胸いっぱいに吸い込むようにしています。
・その人の社会的な地位とは無関係に、その人に引きつけられるかどうか。そういう人を選んで付き合うようにしていけば、人間関係について悩むことはぐんと減らせるはずです。
・もっとも簡単に目に見えるほど確実に運気を高める方法は、運気の高い人とともにいることです。
・人付き合いと自分がなすべきことをどう選び分けるのか。群れから飛び出す。私はそう決めていたので、選択に迷うことはありませんでした。でも、要所要所の付き合いはみなと、とことん楽しみました。ただし、だらだらと長引かせない・・・。マイペースを守りながら、人間関係を最低限キープするだけの時間は確保する。自分自身の人生なのです。確信をもって自分のやり方をしていれば、周囲はちゃんと認めてくれます。付き合いが大事、人間関係が大事というのはわかります。でも、それを勉強を妨げる理由にしてはいけないし、また、その理由にはなり得ません。
・もし、何かを必死になって学びたいのなら、ライバルの存在はこれ以上ない、よき刺激となるものです。学びに疲れたり、何かに気を取られそうになったような場合も、「こうしている間もライバルは学んでいる」と思えば、怠け心に歯止めをかけられます。よきライバルがいるとかそくする。これは、大人の学びにとって、とても大きな事実だと思います。
・学べば学ぶほど、あまりにも微力であることに気づいていく。無限の可能性を秘める存在でありながら、一方で自分の非力さを完膚なきまでに知らされる。学びの行き着く先は、自分は多くの人に支えられ、助けられているというもう一つの事実への気づきです。それに報いるのは感謝しかありません。私はどんな場合も、「ありがとう」と感謝の言葉を真っ先に口にするように習慣づけています。
・アメリカのあるビジネススクールでは、全課程の最後に「笑顔」というカリキュラムが組み込まれているそうです。笑い顔を見ると、その人の品性や知性がよくわかります。私も最高の品性と、最高の知性をしのばせる笑顔を身につけることを目標に、いまも毎日、笑顔を磨き続けています。
・北海道の冬の寒さははんぱではありません。その寒さの中で卓球の朝練。放課後もあたりが真っ暗になるまでひたすらラリーやサーブの練習です。試合では強烈なスマッシュとかオーバーアクションのサーブなど華やかなプレイの応酬ですが、ふだんの練習は単調な基礎練習をうんざりするほど繰り返します。あとはランニングや筋トレ。地味でつらい努力を強いられる毎日の連続です。その甲斐あって、中学校のときには入学後はじめての大会に第1シードで出場し、優勝杯を手にすることができました。そのうれしかったことはいまでも忘れられません。目標を掲げてがんばる。結果がついてくる。最高の喜びを与えられる。この経験から、地味でつらい努力の記憶は目標を達成したその一瞬で消え去り、はかりしれない大きな喜びに変わってしまうことを身をもって知ったのです。達成感の喜びは一度知ったら忘れられません。何度でも味わいたくなり、そうなるといい意味での”努力アディクション”になってしまいます。
・スポーツで頑張った人のほうが勉強でも仕事でも、より成果が出やすい。私は自分の体験からそうした傾向を顕著に感じるのです。スポーツ経験者がなぜ、後に大きな力を発揮するようになるのか。その理由は、スポーツは肉体だけでなく、精神的にも強固なものを求められるからでしょう。スポーツは勝ち負けや記録など、誰の目にもはっきりした結果が出るので、ごまかしも言い訳も絶対にききません。自分との戦いを通じて、本質的な人間性を鍛えていくからだと思います。常に、自分自身の真の力を突きつけられる。才能不足、努力不足から目をそむけることも許されません。そうした体験から、人生は自分の力で生きていくほかはないということを強く自覚させられます。
・人との出会いと同様、本やセミナー、イベントなどとも、出会ったときが出会うべき最高のタイミングなのです。その機を絶対に逃さないこと。しばらく、読む時間が取れず”つん読”になってしまったとしても、手に入れた本はその瞬間から、潜在的な力になります。
・最近は、「できるだけたくさんの本にふれたい。それも時間をかけないで」という矛盾した思いを叶えてくれるシステムがあります。「TOPPOINT」もその一つ。「TOPPOINT」は毎月数多く出版される新刊書の中から一読の価値がある本を紹介している本のガイドブックで、1987年の創刊以来、この雑誌を手がかりに良書と出会い、効率のよい読書習慣を確立している人はかなりの数にのぼると聞きます。取り上げる本はビジネス書、ノンフィクションが中心で、中でもビジネス書のウエイトが高いようです。毎月、100冊前後の新刊書を熟読し、その中から新しい発想やアイディアが光る本など10冊を厳選。その10冊の内容が4ページ分に凝縮されて掲載されています。
・出かけるときは最低でも3冊以上の本をもって出かけます。”つん読”にしてある本や、以前読んだ本が出番となるチャンスです。移動時間は忙しい人にとって、最高の読書時間です。
・一流の人材といわれる人は、専門的な知識やスキルだけでなく、幅広い教養を身につけており、その教養が専門的な知識やスキルをさらに磨きあげ、本物の光を放つようになるのです。
・物理学やITなど、鋭い頭のよさが求められる領域でも、教養の深いことが研究成果を高めるうえで大きな力をもつと聞きます。アインシュタインはヴァイオリンの名手で、旅行にも必ずヴァイオリンを携えていき、歓迎会の席ではよくヴァイオリンの演奏を披露していたそうです。物理学を研究するときも、”よく、音楽で考える”といっています。アインシュタインにとって仕事と音楽は補完し合う関係にあり、音楽で感情が揺さぶられることが引き金になり、物理学の発想が自由にはばたくこともしばしばあったと伝えられます。
・努力の本当の成果は、努力することを通して、自分を制御することを身につけていくことではないでしょうか。人生はあまりにも誘惑に満ちています。寒い朝ならば、ベッドから起きあがるためだけでも、自分との戦いに勝たなければなりません。誘惑は仕事中にも容赦なく襲ってきます。そんなとき、誘惑に心揺れる自分をどう制御し、自分で自分に恥じない仕事をやり通すか。夜ともなれば、誘惑はさらにグレードアップするでしょう。そうしたことに次々と打ち勝って、本来、めざすものに向かって進んでいく。勝利はこうした内面との葛藤に打ち勝った者のみに与えられるのです。
・学びの成果も、まさに微差を追っていくことにより、達成されるのです。一見、小さなことに全力で取り組むことを忘れるな。小さなことを一つやり遂げるたびに人間は成長する。小さなことをきちんとこなしていけば大きいことは後からついてくる。デール・カーネギー
・私の勉強法の特徴は、「とにかく本気になって勉強する」ことに尽きます。あるテーマに絞り込み、その時期はそのテーマに関して徹底的に勉強します。徹底的に学べば、そこから必ず、成果につながる道が見えてきます。勉強してモノにならないという人が多いのは、モノにならないような学びしかしていないからです。
・人生は毎日の生活の積み重ねです。生活は習慣からつくられることが多いのですが、その習慣は性格に起因してつくられることがほとんどです。誤った生活習慣を続けていると生活習慣病になってしまうように、誤った生活習慣は人生をゆがめてしまいます。このゆがみが、運が悪い人の運命なのです。運命をよい方向に向かわせ、パワーアップするのはそれほど難しいことではありません。夢や目標のベクトルを自分中心から他者に役立つこと、社会に貢献することに切り替える。このシフトができれば運命は好転し、その後の運命はさらに上昇気流にのっていきます。
・自分はどういう自分になることを願っているのか。どういう人物をめざしているのか。それを絶えず、語り続けることが大事です。語った言葉は何よりも先に、自分の潜在意識に思いを浸透させます。「ウソも100回いえば真実になる」のです。言い切ると自信が生まれ、言い切るたびに自信が強化されていき、ついには絶対的な確信へと昇華します。その絶対的な自信はまわりの人々を動かし、潜在意識も働くようになり、夢は確実に現実のものになっていきます。
・学んだことを本当に身につける最高の方法は、教えることです。教える側に立つと、自分では理解できていたつもりのことが十分わかっていなかったと気づくことがあり、学びを徹底できるからです。
・積極的に自己アピールする姿勢がなければ、誰もその人の存在に気づいてくれません。「学び」をお金と結びつける最初の一歩は、自分の存在をいかに魅力的にアピールするか、なのです。声をかけられたら、グジグジしないで、明るい声で「やります」「やらせてください」と答えることです。
・私は、1億円プレイヤーとは、それぞれの領域の仕事に本気で取り組み、そのスキルもマインドも磨きあげられ、世の中のため、人に貢献することを最大の喜びとして生きている人だと考えています。そういう人ならば、その評価として、必ず、相応の報酬を手にすることになると確信しています。
<目次>
はじめに 学びへの投資を回収できる人、できない人
第1章 人生、すべての問題は「学び」で解決できる
学びで運命を開いていく
この世の法則を知っているか、知らないか
1億円プレイヤーになる勉強法とは?
手はじめは自分の専門分野の勉強から
成果を出すための意識を変える学び
意識が変わると行動が変わる
人間としてのステージを上げていく
潜在意識の存在を知る
原因と結果の法則はすべてにあてはまる
成功のための「学び」とは何か?
法則の活用法を間違ってはいけない
富や豊かな人間に引き寄せられる
どんな仕事も学びで天職に育てる
セミナーは最高の学びの場
何を学ぶか?答えは自分の中に!
努力はしてはいけない
第2章 時間は無限大化できる
学びの時間はこうして生み出す
人生を制する時間管理7つの法則
「いつか」ではなく「いま」との大きな差
セミナーは最優先順位で参加する
時間を2倍、3倍に増やす
速読・速聴でスピードを数倍に
時間効率を高める日常の工夫
できる人は、24時間学びつづける
同じセミナーが地元で開かれていても、東京に行く
時間は買える!けっして高くない
第3章 「学び」の成果を”お金”に結びうける
まず投資。リターンはそこから生まれる
学びはリターンが確約された最高の投資
借金もせずには成功できない
大金を投じたからこそ得られるもの
いいお金の使い方をすると人生が変わる
本当のアメリカン・ドリームとは何か?
お金をリスペクトする
素直にお金に手を伸ばす
真の豊かさを知ることは自分への先行投資
ブレない評価基準をもつ
お金を手に入れる最高のサイクル
第4章 学びと類友の法則
よくも悪くも、人間関係は引きつけ合う
人間関係では無理をしない
「この人は!」という人を見きわめる
苦手な人にはニュートラルに向き合う
運気の強い人と一緒にいるだけでもよい
人脈づくりはまったく必要ない
マイペースでも人間関係は築ける
ライバルがいる喜びと効果
ただ感謝、ひたすら感謝
笑顔も磨くことができる
第5章 1億円プレイヤーへの習慣術
毎日の習慣こそ、成功者に近づく道
達成感の喜びを体に刻む
勝ちグセをつける
安住は衰退の第一歩、常に成長
”つん読”でもいいから本を買う
「TOPPOINT」を活用する
いつも読むべき本を持参する
いざというとき、教養の底力が出る
自分を律して誘惑に勝つ
微差が大差を生む
本気で行動する
あきらめる口実を探さない
生まれもった運命を知る
そのうえで運命をつくっていく
地球儀サイズで発想する
第6章 1億円プレイヤーになる それは、明日かもしれない
1日1日、豊かさに近づいていく
自分をレアメタル化していく
「ありたい姿」を絶えず語る
積極的にカミングアウトする
学んだ結果をシェアする
学びながら、どんどん教える
したいことは口に出す
声がかかったら、イエスと即答する
お金の磁石を手に入れる
あなたは二極のどちらに属するか?
思いは叶う。それは明日かもしれない
面白かった本まとめ(2013年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
 「「学び」を「お金」に変える技術」の購入はコチラ
「「学び」を「お金」に変える技術」の購入はコチラ 「「学び」を「お金」に変える技術」という本は、歯科医師だけでなく世界中のさまざまな自己啓発、経営プログラムなどを学び続け、現在はセミナー講師としても全国に飛び回る著者が書いたものです。
人生を確実に成功に導くものは「学び」で、この本ではその学びの方法や考え方・時間管理・人間関係・習慣などについて、とても分かりやすく説明しています。
主に以下について書かれていて、特に楽しく勉強することや、時間管理を大切にしコツコツ良い習慣をもって進めること、感謝や笑顔・スポーツ・教養が大切、周りに自分の目標などを伝えること、教えることが学びを強化、アピールすることが大切、そして勉強したことを社会に役立てればお金につながるについては共感しましたね。
・自分で仕事を天職に育てるほどのめりこむこと
・どんなセミナーを受講すべきかの答えは自分の中にある
・苦しい努力、つらい努力はせずに楽しく勉強すること
・時間管理をアップするには7つのことを守る
・計画通りコツコツと進め努力すること
・テレビによって貴重な時間を奪われないこと
・自分以外に頼めることは頼む
・学びに投資したものは損をすることはない
・勉強し続けると、追いかける人はいなくなるのでトップランナーになれる
・この世の中で起こることはすべて、自分の心の反映
・最高の人生ビジョンは社会福祉に生きること
・社会的な地位とは無関係にその人に引きつけられるかで選んで付き合うと人間関係について悩むことは減らせる
・運気の高い人とともにいること
・必死になって学びたいのならライバルの存在はこれ以上にない
・多くの人に支えられ助けられているのだから感謝することは大切
・笑顔を磨くことは大切
・達成感の喜びを味わい努力中毒になるとよい
・スポーツでがんばった人のほうが勉強でも仕事でも成果が出やすい
・本やセミナー、イベントなども出会った時が出会うべきタイミングなのでその機を絶対に逃さないこと
・本を選ぶにはTOPPOINTが参考になる
・出かけるときは最低でも3冊以上本をもつ
・一流の人材は、幅広い教養を身につけている
・努力することを通して自分を制御することを身につけることが本当の成果
・小さなことにも全力で取り組むこと
・とにかく本気になって勉強すること
・人生は毎日の生活の積み重ねだから良い習慣をつけること
・夢や目標のベクトルを自分中心から他者に役立つこと、社会に貢献することに切り替えること
・自分はどう願っているのか、どういう人物を目指すのかそれを絶えず語り続けることが大事
・学んだことを本当に身につける最高の方法は教えること
・自分の存在をいかに魅力的にアピールするかが大事
・仕事に本気に取り組み、世の中のため、人に貢献することを最大の喜びとして生きれば、その評価として必ず相応の報酬を手にすることができる
「「学び」を「お金」に変える技術」という本はとてもオススメです!
以下はこの本のポイント等です。
・1億円プレイヤーをめざす。そのために、いま、どんな仕事をしているかは大した問題ではありません。大事なのは、どんな思いで仕事をしているかです。「これこそ自分の天職だ」と確信できるぐらいいまの仕事が好きで、のめり込んでいるかどうか。それが大事なのです。私は天職は誰かに与えられるものではなく、自分で天職に育てていくものだと考えるようになりました。
・どんなセミナーがいいか。なんのセミナーを受講すべきか。私の経験が教えているように、答えは自分の中にあるのです。資格の勉強でも、語学の勉強でも懸命に学んでいくと、しだいに学びの感度が鍛えられていくのでしょう。少し学びだすと、関心がそちらに向くことから、それまで見逃していた雑誌やインターネットの広告、一度参加したセミナー主催者からのDMなど、セミナーの情報はいくらでも手に入るようになります。その中からどれを選ぶか。自分がちゃんと教えてくれるのです。数ある情報の中で、なぜか心惹かれるセミナーとか本は、自分が潜在的に求めていたもの、あるいは求めていたものに強くつながっているものです。ベストアンサーは、常に自分の中にあります。
・苦しい努力、つらい努力はしないほうがいい。いえ、してはいけない!のです。私が常に勉強をしているのは学ぶことが好きだから。楽しくてしかたがないから。勉強しているときがしあわせで、心の奥底から充足感が湧き上がってくるからです。だから、普通イメージするような苦しい努力はしませんし、したいことを我慢して勉強することもありません。その意味では「努力」は一切していません。「したいから勉強している」「楽しいから学んでいる」ので、苦労や我慢、つらい努力とはまったく無縁です。
・次の7つを守ると、「時間管理」のスキルは高水準にアップグレードできます。
①優先順位を決める
②新しいことをはじめるときは、現在、行っているものの一部を捨てる。
③できないこと、苦手なことはムリしてしに。
④したいことだけをする。本当にしたくないことは断る。
⑤取り組むときは、真剣に、集中して行う。
⑥スキ間時間をムダにしない。どんな小さな時間でも活用する。
⑦常に本気で生きる。明日はないという気持ちで取り組む。
・10代、20代、30代・・・と各段階でやるべきことをきちんと果たし、一段階ずつ積み上げていかなければ、高い頂点に到達することはりえません。私の年齢で、開業してから20年に満たない時間でここまで大きな成果を得られたのは、運がよかったからではなく、一歩一歩戦略どおり、計画どおりに私が進めてきたからです。緻密な計画と、それを実現するための真剣な努力。それを怠らずに実行してきた結果が、今日の私の姿です。
・NHK放送文化研究所の「2010年国民生活時間調査」によると、1日のテレビ視聴時間は平日平均で3時間28分。最近、テレビ離れが進んでいるといわれているにもかかわらずです。新聞は19分、雑誌・本は13分。テレビは圧倒的で、メディアの王様の座は不動です。逆に考えれば、テレビによって貴重な時間を3時間半近くも奪われてしまっていることに愕然としませんか?ながら視聴をする人もあるでしょうが、食事の後など、うっかりしていると、1時間ぐらいテレビに気をとられてしまうことはよくあります。ある知人は見たい番組は録画してしまい、基本は早送り。大事なところだけノーマルスピードで見る。この方法で1時間番組は30分以下で、十分楽しめるといっています。
・自分以外の人に頼むことができて、しかも彼らのほうがよくやってくれるとしたら、自分でやる必要はない(ヘンリー・フォード)
・最近もリーマンショックをきっかけに、ヨーロッパの金融危機と投資環境は悪化の一途をたどっています。こうした例からも、不動産や株式などの投資はいかに不確実で、時を得なければ、あっけなく無(ゼロ)に帰す、いや、大きな損失(マイナス)を招きかねないものだとわかります。それに対して、学びに投資した場合は、絶対に損をすることはないのです。学びの成果は確実に自分自身のものになり、一生、マイナスになることはありません。そのうえ、経験を重ねることによってどんどん磨きあげられていき、付加価値が加わっていくのです。
・以前、1回18万円という高額のセミナーを受講したことがあります。1年間12回で1つのコースになっていたので、参加費用はトータルで216万円。さすがに定員12名の少数精鋭主義というか、あまりに高額で参加者が少なかったのか、会場に顔をそろえた受講生は8名。比較的若いのは私ともう一人ぐらい。残りは50~60代。大手企業のトップ経営者ばかりでした。しかもこのセミナー、講義らしい講義があるのは午前中だけで、午後からはグループに分かれてフリートーク。1回18万円もとっておいて、半分はフリーディスカッションかと思ってくらいでした。でも、このディスカッションがすごくよかったのです。なんといっても、メンバーの多くは年商数百億~数千億円の大企業のトップ経営者なのです。それまで出会っていた年商数十億~100億円という経営者とはまるで格が違います。年商数十億~100億円クラスの経営者には、たたき上げの人に共通するすさまじいばかりの情熱があり、大いに刺激を受けてきました。年商100億円までなら仕組みがなくても情熱だけでなんとかいける。そんな印象をもち、私もまず、そこをめざしていこうと自身も得られました。ところがそこから1ケタ上がると、人としての器が違ってくるのです。経営者として優れているだけでなく、それぞれが人間的なオーラを放っている。親しくなって話をすると、みなすごい人格者なのです。それだけの人間力がないと大企業を引っ張っていくことはできないのだと圧倒される思いでした。
・参加者の一人、その方も大手企業の社長さんでしたが、この方から、「井上君、50歳までは勉強をしなさい。そこまで勉強を続ける人はいないから、50歳まで勉強していると、もう後を追いかけてくる人はいなくなって、まちがいなくトップランナーになれますよ」といわれた言葉はいまも脳裏に深く刻み込まれています。
・「鏡の法則」をご存じでしょうか。この世の中で起こることはすべて、自分の心の反映なのです。同じ金額を使うのでも、常に社会のため、人のために貢献できるようにと心している人にはちゃんとリターンが返ってくるのは、この法則が働くからです。
・彼らが描く最高の人生ビジョンは社会福祉に生きることなのです。カネギーもロックフェラーもビル・ゲイツも、ビジネスを大成功させると、次の生き方の軸足を社会福祉に移しています。お金はこうした使われ方をしたとき、本当の価値を発揮するのです。もともと、ビル・ゲイツの素顔はかなりの倹約家だそうです。何度も世界一の大金持ちに輝きながら、お金をじゃぶじゃぶお湯水のように使うことには関心がなく、むしろ、倹約することをゲームのように楽しんでいるというから痛快です。富は社会に還元する。こうしたことをドリームといってのける国民性は偉大です。カーネギーホールに足を踏み入れるたびに、私はその精神を胸いっぱいに吸い込むようにしています。
・その人の社会的な地位とは無関係に、その人に引きつけられるかどうか。そういう人を選んで付き合うようにしていけば、人間関係について悩むことはぐんと減らせるはずです。
・もっとも簡単に目に見えるほど確実に運気を高める方法は、運気の高い人とともにいることです。
・人付き合いと自分がなすべきことをどう選び分けるのか。群れから飛び出す。私はそう決めていたので、選択に迷うことはありませんでした。でも、要所要所の付き合いはみなと、とことん楽しみました。ただし、だらだらと長引かせない・・・。マイペースを守りながら、人間関係を最低限キープするだけの時間は確保する。自分自身の人生なのです。確信をもって自分のやり方をしていれば、周囲はちゃんと認めてくれます。付き合いが大事、人間関係が大事というのはわかります。でも、それを勉強を妨げる理由にしてはいけないし、また、その理由にはなり得ません。
・もし、何かを必死になって学びたいのなら、ライバルの存在はこれ以上ない、よき刺激となるものです。学びに疲れたり、何かに気を取られそうになったような場合も、「こうしている間もライバルは学んでいる」と思えば、怠け心に歯止めをかけられます。よきライバルがいるとかそくする。これは、大人の学びにとって、とても大きな事実だと思います。
・学べば学ぶほど、あまりにも微力であることに気づいていく。無限の可能性を秘める存在でありながら、一方で自分の非力さを完膚なきまでに知らされる。学びの行き着く先は、自分は多くの人に支えられ、助けられているというもう一つの事実への気づきです。それに報いるのは感謝しかありません。私はどんな場合も、「ありがとう」と感謝の言葉を真っ先に口にするように習慣づけています。
・アメリカのあるビジネススクールでは、全課程の最後に「笑顔」というカリキュラムが組み込まれているそうです。笑い顔を見ると、その人の品性や知性がよくわかります。私も最高の品性と、最高の知性をしのばせる笑顔を身につけることを目標に、いまも毎日、笑顔を磨き続けています。
・北海道の冬の寒さははんぱではありません。その寒さの中で卓球の朝練。放課後もあたりが真っ暗になるまでひたすらラリーやサーブの練習です。試合では強烈なスマッシュとかオーバーアクションのサーブなど華やかなプレイの応酬ですが、ふだんの練習は単調な基礎練習をうんざりするほど繰り返します。あとはランニングや筋トレ。地味でつらい努力を強いられる毎日の連続です。その甲斐あって、中学校のときには入学後はじめての大会に第1シードで出場し、優勝杯を手にすることができました。そのうれしかったことはいまでも忘れられません。目標を掲げてがんばる。結果がついてくる。最高の喜びを与えられる。この経験から、地味でつらい努力の記憶は目標を達成したその一瞬で消え去り、はかりしれない大きな喜びに変わってしまうことを身をもって知ったのです。達成感の喜びは一度知ったら忘れられません。何度でも味わいたくなり、そうなるといい意味での”努力アディクション”になってしまいます。
・スポーツで頑張った人のほうが勉強でも仕事でも、より成果が出やすい。私は自分の体験からそうした傾向を顕著に感じるのです。スポーツ経験者がなぜ、後に大きな力を発揮するようになるのか。その理由は、スポーツは肉体だけでなく、精神的にも強固なものを求められるからでしょう。スポーツは勝ち負けや記録など、誰の目にもはっきりした結果が出るので、ごまかしも言い訳も絶対にききません。自分との戦いを通じて、本質的な人間性を鍛えていくからだと思います。常に、自分自身の真の力を突きつけられる。才能不足、努力不足から目をそむけることも許されません。そうした体験から、人生は自分の力で生きていくほかはないということを強く自覚させられます。
・人との出会いと同様、本やセミナー、イベントなどとも、出会ったときが出会うべき最高のタイミングなのです。その機を絶対に逃さないこと。しばらく、読む時間が取れず”つん読”になってしまったとしても、手に入れた本はその瞬間から、潜在的な力になります。
・最近は、「できるだけたくさんの本にふれたい。それも時間をかけないで」という矛盾した思いを叶えてくれるシステムがあります。「TOPPOINT」もその一つ。「TOPPOINT」は毎月数多く出版される新刊書の中から一読の価値がある本を紹介している本のガイドブックで、1987年の創刊以来、この雑誌を手がかりに良書と出会い、効率のよい読書習慣を確立している人はかなりの数にのぼると聞きます。取り上げる本はビジネス書、ノンフィクションが中心で、中でもビジネス書のウエイトが高いようです。毎月、100冊前後の新刊書を熟読し、その中から新しい発想やアイディアが光る本など10冊を厳選。その10冊の内容が4ページ分に凝縮されて掲載されています。
・出かけるときは最低でも3冊以上の本をもって出かけます。”つん読”にしてある本や、以前読んだ本が出番となるチャンスです。移動時間は忙しい人にとって、最高の読書時間です。
・一流の人材といわれる人は、専門的な知識やスキルだけでなく、幅広い教養を身につけており、その教養が専門的な知識やスキルをさらに磨きあげ、本物の光を放つようになるのです。
・物理学やITなど、鋭い頭のよさが求められる領域でも、教養の深いことが研究成果を高めるうえで大きな力をもつと聞きます。アインシュタインはヴァイオリンの名手で、旅行にも必ずヴァイオリンを携えていき、歓迎会の席ではよくヴァイオリンの演奏を披露していたそうです。物理学を研究するときも、”よく、音楽で考える”といっています。アインシュタインにとって仕事と音楽は補完し合う関係にあり、音楽で感情が揺さぶられることが引き金になり、物理学の発想が自由にはばたくこともしばしばあったと伝えられます。
・努力の本当の成果は、努力することを通して、自分を制御することを身につけていくことではないでしょうか。人生はあまりにも誘惑に満ちています。寒い朝ならば、ベッドから起きあがるためだけでも、自分との戦いに勝たなければなりません。誘惑は仕事中にも容赦なく襲ってきます。そんなとき、誘惑に心揺れる自分をどう制御し、自分で自分に恥じない仕事をやり通すか。夜ともなれば、誘惑はさらにグレードアップするでしょう。そうしたことに次々と打ち勝って、本来、めざすものに向かって進んでいく。勝利はこうした内面との葛藤に打ち勝った者のみに与えられるのです。
・学びの成果も、まさに微差を追っていくことにより、達成されるのです。一見、小さなことに全力で取り組むことを忘れるな。小さなことを一つやり遂げるたびに人間は成長する。小さなことをきちんとこなしていけば大きいことは後からついてくる。デール・カーネギー
・私の勉強法の特徴は、「とにかく本気になって勉強する」ことに尽きます。あるテーマに絞り込み、その時期はそのテーマに関して徹底的に勉強します。徹底的に学べば、そこから必ず、成果につながる道が見えてきます。勉強してモノにならないという人が多いのは、モノにならないような学びしかしていないからです。
・人生は毎日の生活の積み重ねです。生活は習慣からつくられることが多いのですが、その習慣は性格に起因してつくられることがほとんどです。誤った生活習慣を続けていると生活習慣病になってしまうように、誤った生活習慣は人生をゆがめてしまいます。このゆがみが、運が悪い人の運命なのです。運命をよい方向に向かわせ、パワーアップするのはそれほど難しいことではありません。夢や目標のベクトルを自分中心から他者に役立つこと、社会に貢献することに切り替える。このシフトができれば運命は好転し、その後の運命はさらに上昇気流にのっていきます。
・自分はどういう自分になることを願っているのか。どういう人物をめざしているのか。それを絶えず、語り続けることが大事です。語った言葉は何よりも先に、自分の潜在意識に思いを浸透させます。「ウソも100回いえば真実になる」のです。言い切ると自信が生まれ、言い切るたびに自信が強化されていき、ついには絶対的な確信へと昇華します。その絶対的な自信はまわりの人々を動かし、潜在意識も働くようになり、夢は確実に現実のものになっていきます。
・学んだことを本当に身につける最高の方法は、教えることです。教える側に立つと、自分では理解できていたつもりのことが十分わかっていなかったと気づくことがあり、学びを徹底できるからです。
・積極的に自己アピールする姿勢がなければ、誰もその人の存在に気づいてくれません。「学び」をお金と結びつける最初の一歩は、自分の存在をいかに魅力的にアピールするか、なのです。声をかけられたら、グジグジしないで、明るい声で「やります」「やらせてください」と答えることです。
・私は、1億円プレイヤーとは、それぞれの領域の仕事に本気で取り組み、そのスキルもマインドも磨きあげられ、世の中のため、人に貢献することを最大の喜びとして生きている人だと考えています。そういう人ならば、その評価として、必ず、相応の報酬を手にすることになると確信しています。
<目次>
はじめに 学びへの投資を回収できる人、できない人
第1章 人生、すべての問題は「学び」で解決できる
学びで運命を開いていく
この世の法則を知っているか、知らないか
1億円プレイヤーになる勉強法とは?
手はじめは自分の専門分野の勉強から
成果を出すための意識を変える学び
意識が変わると行動が変わる
人間としてのステージを上げていく
潜在意識の存在を知る
原因と結果の法則はすべてにあてはまる
成功のための「学び」とは何か?
法則の活用法を間違ってはいけない
富や豊かな人間に引き寄せられる
どんな仕事も学びで天職に育てる
セミナーは最高の学びの場
何を学ぶか?答えは自分の中に!
努力はしてはいけない
第2章 時間は無限大化できる
学びの時間はこうして生み出す
人生を制する時間管理7つの法則
「いつか」ではなく「いま」との大きな差
セミナーは最優先順位で参加する
時間を2倍、3倍に増やす
速読・速聴でスピードを数倍に
時間効率を高める日常の工夫
できる人は、24時間学びつづける
同じセミナーが地元で開かれていても、東京に行く
時間は買える!けっして高くない
第3章 「学び」の成果を”お金”に結びうける
まず投資。リターンはそこから生まれる
学びはリターンが確約された最高の投資
借金もせずには成功できない
大金を投じたからこそ得られるもの
いいお金の使い方をすると人生が変わる
本当のアメリカン・ドリームとは何か?
お金をリスペクトする
素直にお金に手を伸ばす
真の豊かさを知ることは自分への先行投資
ブレない評価基準をもつ
お金を手に入れる最高のサイクル
第4章 学びと類友の法則
よくも悪くも、人間関係は引きつけ合う
人間関係では無理をしない
「この人は!」という人を見きわめる
苦手な人にはニュートラルに向き合う
運気の強い人と一緒にいるだけでもよい
人脈づくりはまったく必要ない
マイペースでも人間関係は築ける
ライバルがいる喜びと効果
ただ感謝、ひたすら感謝
笑顔も磨くことができる
第5章 1億円プレイヤーへの習慣術
毎日の習慣こそ、成功者に近づく道
達成感の喜びを体に刻む
勝ちグセをつける
安住は衰退の第一歩、常に成長
”つん読”でもいいから本を買う
「TOPPOINT」を活用する
いつも読むべき本を持参する
いざというとき、教養の底力が出る
自分を律して誘惑に勝つ
微差が大差を生む
本気で行動する
あきらめる口実を探さない
生まれもった運命を知る
そのうえで運命をつくっていく
地球儀サイズで発想する
第6章 1億円プレイヤーになる それは、明日かもしれない
1日1日、豊かさに近づいていく
自分をレアメタル化していく
「ありたい姿」を絶えず語る
積極的にカミングアウトする
学んだ結果をシェアする
学びながら、どんどん教える
したいことは口に出す
声がかかったら、イエスと即答する
お金の磁石を手に入れる
あなたは二極のどちらに属するか?
思いは叶う。それは明日かもしれない
面白かった本まとめ(2013年上半期)
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。












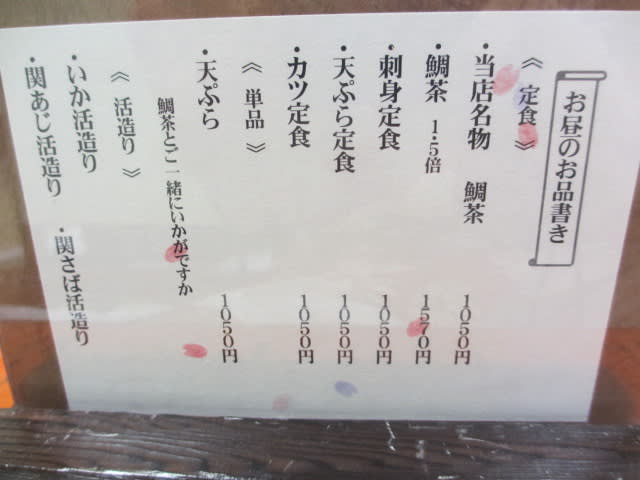










 「学び続ける力」の購入はコチラ
「学び続ける力」の購入はコチラ 






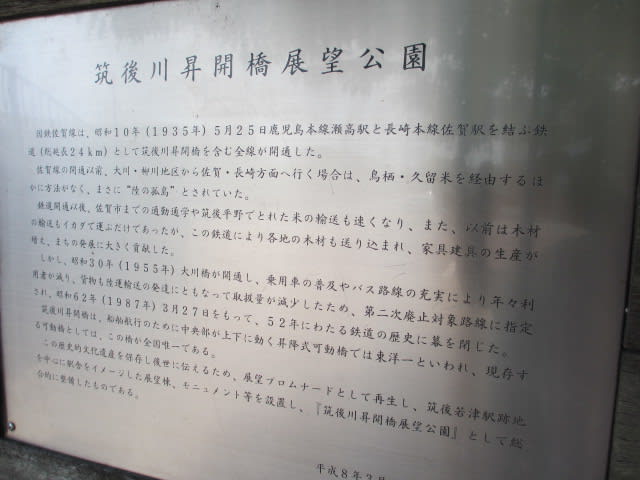


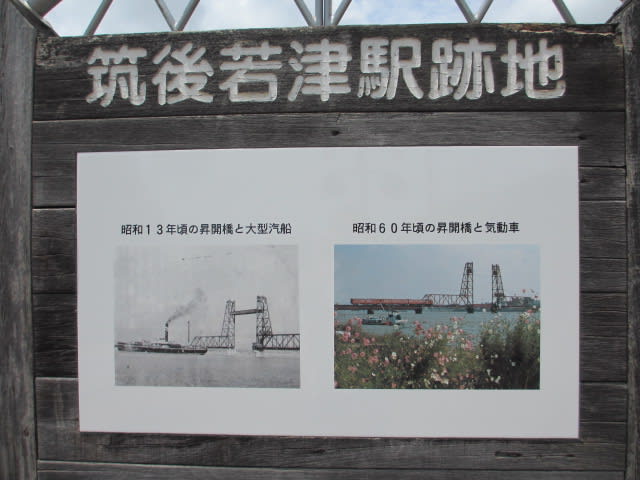
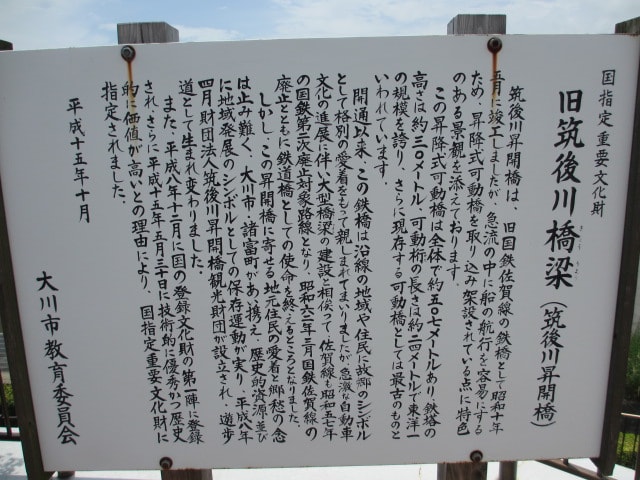















 「新幹線をつくる(早田 森)」の購入はコチラ
「新幹線をつくる(早田 森)」の購入はコチラ 




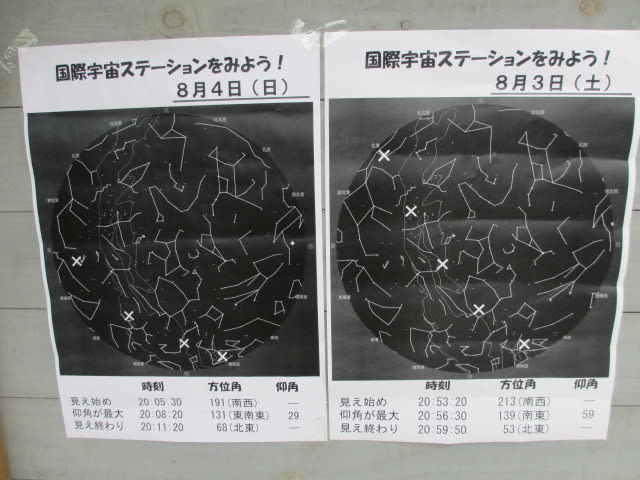
 「心を上手に操作する方法」の購入はコチラ
「心を上手に操作する方法」の購入はコチラ 






















 「ひっかかる日本語(梶原しげる)」の購入はコチラ
「ひっかかる日本語(梶原しげる)」の購入はコチラ 



